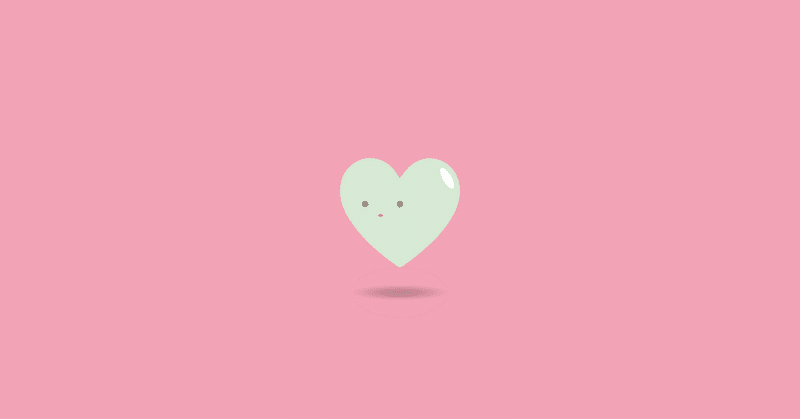
死にたい夜に効く話【3冊目】『こころの処方箋』河合隼雄著
中学生の時、「がんばれ」という言葉は呪いでしかなかった。
学校に行けなくなった時期がある。
心身ともに限界になった。
大人たちは必死になってわたしを学校に戻そうとした。
自分がやる気に満ちている時に、「無理しなくていいからね」なんて言われると、白ける。逆に「がんばれ!」と言ってもらえると背中を押されたようで嬉しくなる。
だけど、苦しい時にかけられる「がんばれ」は、まるで、溺れかけて、ようやく陸に這い上がったところを、「甘えんな」と頭を押さえつけて、また水に沈められるようなものだった。
河合隼雄先生のことを知ったのは大学生の時。
先生の本と出会ったことで、わたしのそれまでの物の見方は、ガラリと変わってしまった。
河合隼雄先生は臨床心理学者。ユング派心理学の分析家。
かの有名な箱庭療法を日本に導入したり、日本人特有の精神構造を、日本の神話や昔話の観点から研究したことでも知られている。
『こころの処方箋』は一章分がとても短い。
わたしの持ってる文庫本で一章あたり4ページ。
順番は決まってない。どこから読んでもいい。
目次から見出しを少々。
「100%正しい忠告はまず役に立たない」
「「理解ある親」をもつ子はたまらない」
「心のなかの勝負は51対49のことが多い」
「ものごとは努力によって解決しない」
「自立は依存によって裏づけられている」
「生まれ変わるためには死なねばならない」
などなど…。
思わず、どういう意味だ?とドキリとするものもある。
この本はまさに、人の「こころ」についての話だ。
実際に受けた相談や、起きた事例を交えながら、生きていくためのヒントをくれる。
河合先生の本は、どれもとても読みやすい。
書き方、と言うよりも、語り口、といった方がいいかしら。
例えば、こんな感じ。
あるとき、無理に連れて来られた高校生で、椅子を後ろに向け、私に背を向けて坐った子が居た。このようなときは、われわれはむしろ、やりやすい子が来たと思う。こんな子は会うや否や、「お前なんかに話をするものか」と対話を開始してくれている。そこで、それに応じて、こちらも「これはこれは、僕とは話す気が全然ないらしいね」などと言うと、振り向いて、「当たり前やないか。こんなことしやがって、うちの親父はけしからん…」という具合に、ちゃんと対話がはずんでゆくのである。
先生は、人間の「こころ」という目に見えないものの奥底を見ている。
どこか正解へ導いてくれる、というよりは、一緒に出口を探してくれている感じがする。
クライアント本人にすらわからない、こころの奥底へ行くのだ。
とても素人に真似できることじゃない。だって一歩間違えたら、クライアントが死んでしまうかもしれないんだから。
大人から見て理解できない行動を子供が起こした時、
「この子の性格の問題だ」「その子が異常なんだ」
そうやって、バッサリと安直に片付けられてしまうことがどれほど多いことか。
その子、本人でも気づいていないようなSOSが、外から見れば「異常」に見えるような行動として表面化してきたりする。
また、ストレスの原因になっているものだけを取り除けば解決する、という単純な話でもなく、実は予想だにしなかったところに、解決の糸口があったりする。
河合先生の本を読んで、自分がそれまで、どれだけ物事の表面しか見てこなかったかに気付かされた。
ストレスに直面したとき、「いやいや、ちょっと待てよ」と立ち止まるクセがついた。
自分の「こころ」が、どうしてこんな反応をするのか、考えてみるクセがついた。
そうやって、ある意味、練習を積み重ねていったことで、少しずつではあるけれども、昔よりは大分、生きやすい考え方ができるようになった気はする。
河合先生のカウンセリングを受けてみたかったと思う。
けれど、もう先生は故人でそれは叶わない。
今を生きるわたしたちは、河合先生や、あるいは他の誰かが遺してくれた知識や知恵を使って、自分で自分を守っていかなくちゃいけない。
「がんばれ」と言われるたび、耐えられない自分が弱いからだめなんだと自分を責め、ますます悪循環にはまっていった。
あの頃の自分に会えるものなら、「「耐える」だけが精神力ではない」のページに栞を挟んで、この本を渡してあげたいものだ。
(2023年9月10日)
