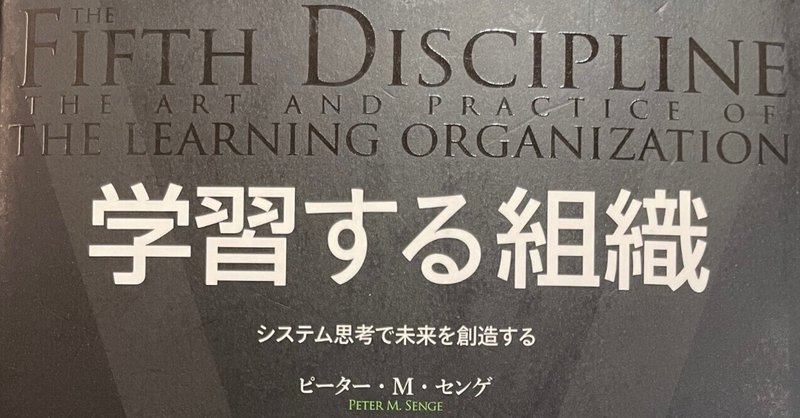
【いちごる読書note】今求められる「学習」とは~『学習する組織』を読んで~
『学習する組織』ピーター・M・センゲ
2023年の最後に読んだ本がこの『学習する組織』。
これを手にしたきっかけは、人と人との「対話」について述べたデヴィット・ボーア著『ダイアローグ』にて、序文を書いていたのがピーター・M・センゲ氏であったことから。
御多分に漏れず最初は様子見のために近所の図書館で借りて読んでいたところ、次のような一文があり、購入に踏み切った。
真の学習は、「人間であるとはどういうことか」という意味の核心に踏み込むものだ。学習を通じて、私たちは自分自身を再形成する。学習を通じて、以前には決してできなかったことができるようになる。学習を通じて、私たちは世界の認識を新たにして、世界と自分との関係をとらえ直す。
「人間であるとはどいうことか?」
複業でゴルフコーチをするようになってから早6年、いつのころからか、僕はそのようなことを漠然と考えるようになった。
目の前の一人のお客さんに、ゴルフを楽しんでもらうこと。これは、すなわち、新しいスキルの学習をしてもらうということである。最近は未経験者/初心者専門でやっていてるが、この対象者相手でさえ、単純にゴルフのスキルを伝えるだけではない、難しさがある。その難しさはまさに、相手が「人であること」に起因する。
また、この未経験者/初心者専門のメソッドを、世に広めていこうとするときに、立ちはだかる壁は一般アマチュアゴルフ業界という一つの「社会」であり、その社会はすなわち、人々が寄り集まった時に形成される(僕にとってはまだ)得体のしれないもの。人間とは何か?と同時に、人々が集まった社会とは何か?が、僕の生涯のテーマなのだ。
この本を読んで、「学習する」とはどういうことか、それがどのように人々にとって、社会にとって役に立つものであることか、ということがおぼろげながら見えてきた。その一部は僕自身が実践しようとしてきたことでもあるし、また一部は自分の中で体系化がなされず漠然としていたものであり、また、一部は今後これを組織に根付かせていくためのヒントであった。
「体系的」であるということは、すなわちその中にある要素が、単独では十分な意味を持って存在しえず、全体がつながっているということでもある。残念ながら、まだ一度や二度読んだだけでは、その全体像を腹落ちして理解、実践していける状況ではないが、現時点で書き留めておきたいことを以下に残そう。
1.「学習」とは~適応学習と生成的学習
一言に「学習」といっても、その意味するところは、個人によって異なるかもしれない。「これからの時代、生涯学習が大切ですよね? 」といった身の回りの話題にせよ、政府の主催する国家規模の会議、例えば「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」などにおいて議論される「リ・スキリング」、「学び直し」といったキーワードにせよ、「学習とは何か」ということがあいまいなまま、もしくは十分に検討されないままに単に「知識やスキルの習得」といった程度の理解で議論がなされている気がしており、ここに僕自身、違和感のようなものを感じていた。
そんな折、本書で定義される学習は以下の通りで、これこそ僕自身が実践しようとしていた学習に近しいものを感じた。
学習とは、個人として、集団として、学習者(たち) が心から創り出したい結果を実現するための能力を向上させるプロセスである
上述の一般的な用途での学習は、どちらかというと、「生き残るための学習」すなわち「適応学習」と呼ばれるものに近いと感じられる。
適応学習に関しては、例えば「これからはDX時代であるため、デジタルスキルを学び直さないといけない」という感じで、ある一定の仮定(ここでは、DX時代の到来)を前提として、それに対応していくための(でなければ生き残れない、という前提での)学習であるように思われる。
果たして、どの会社もこぞって全社的にデジタルスキルが必要なのだろうか、その前に見直すべき、ソフト面でのスキルはないのであろうか、というのが僕の抱いていた違和感である。
例えば、AIをどう活用するか(DX時代が前提)、という点で試行錯誤した結果、「議事録はAIに任せて無駄な作業を効率化しましょう! 」となったとしても、そもそも現代組織の主たる課題が、『恐れのない組織』における心理的安全性の欠如により生産的な議論が出来ていないのであれば、いくらその議事録をAI で自動化しても効果は乏しく、「DX時代に対応した施策」として、仕事を前に進めたかのように思い込んでいるだけの場合もあるだろう。
この点、上述した「学習者たちが心から創り出したい結果を実現させるための能力を向上させるプロセスとしての学習」をセンゲ氏は「生成的学習」と呼んでおり、この学習文化とむずびついてこそ、適応学習は 意味を成すと主張している。
本書ではこの「生成的学習」に個人として、組織として熟達していくための体系を示しているが、それは、センゲ氏も随所で指摘している通り、「終わりのない旅」であり、それが一面的にしか理解されない場合には、「『学習とは何か?』のような、そんな禅問答のようなことを言っていては、業務が回らないではないか! 」ということになる。(禅問答に陥ることなく生成的に学習していく体系が、この本に書いてあることなのだけれど)
トレンドに振り回されて、「リスキリング」を模索するのではなく、そもそも組織が生産的に歩みを進めていくための「学習のあり方」についても、少しは思いを馳せてもよいのではないだろうか。
2.システム思考~一般アマチュアゴルフ業界における適用例~
さて本書では、生成的学習を5つの要素(ディシプリン;「原則」みたいなもの)に分けたうえで、それらの相互依存的なつながりを全体として示すことで体系化している。これら全てのつながりを示すことは困難を極めるため、ここでは、5つのディシプリンの中でも特に全体の基盤・土台となる、「システム思考」と筆者が呼ぶものを紹介したい。
「システム思考」は、物事の因果の構造を探究する重要性を説いたものである。この因果の構造は、同書ではいくつかのパターン(これをシステム原型という)に分けられ、分かる人からすれば「またこのパターンだ」となるのだが、それでもある要因から、それを特定することが非常に難しくなっている、というのが筆者の主張である。
構造的な問題の把握は非常に難しいため、同書では、「同じシステムの中に置かれると、どれほど異なっている人たちでも、同じような結果を生み出す傾向がある(p89)」と言っているが、一般アマチュアゴルフ界がまさにその一つの実例であると思っている。
僕個人が経験したそのうちの1つのシステム原型についての「そういうことか」を以下に示そうと思う。
それは、筆者の言うところの「問題のすり替わり」という現象の一つである。その定義は以下のとおりである。
定義:問題のすり替わり
根底にある問題が、注意を引く症状を生み出す。だが、根底にあるその問題に人々が対処するのは難しい。なぜなら、その問題が漠然としているか、または取り組むことの犠牲が大きいからである。そこで、人々は、問題の負担を他の解決策-非常に効果的に思える、善意から出た簡単な応急処置ーをとることに「すり替える」。残念ながら、この、より簡単な「解決策」は症状を和らげるだけで、根底にある問題は変わらないままだ。根底にある問題は、気づかれないまま悪化する。
なぜなら、見かけ上は症状が良くなり、そのシステムは、根底にある問題を解決するためにもっていた何らかの能力を失うからだ。
一般アマチュアゴルファーの行動様式を見ていると、この「問題のすり替わり」により、その多くが「困っている」状況が説明できる。その構造は以下の通りである。

【図の説明】
①一般的にアマチュアゴルファーは、現象面( (図の真ん中のボックスのex)に着目して悩みを抱えたり、問題を把握する
②この現象の解決策をYouTubeで調べたりするので、出てくる内容は場当たり的な解決策に行き着く(上のボックス)
③しかもその方法でも多くの場合、一時的な症状の緩和が見込めるからホッとする
④と思ったら、今度は同じ症状、もしくは、正反対の症状(スライス⇒フック)に悩まされ始める
⑤④の現象を調べて、また対症療法に行き着き、程なくして、新しい(だが根本的には同じ)問題を抱える…という無限ループに陥る。
このように、図の上側のサークルをぐるぐる回ってしまうことにより、「ゴルフって楽しい! 」が、いつしか「苦しみ」に変わる・・・
この泥沼を脱出するには、図の下側のサークルに取り組む必要がある。
要は、「ゴルフの質」を向上させることだ。
ただ、そもそもこの「ゴルフの質」の向上は、一言で言い表せられるコツでもなく、また、マスターするのに時間がかかったり、特に取り組みはじめのころは、経験者程一時的な後退を感ずるものである。
これが下のサークルの左上に「=」で示された「時間的な遅れ」である。
根本的な解決策には、通常「時間的な遅れ」が伴うため、上のサークルで 何度も「一時的」「瞬間的」な疑似改善を経験した方ほど、根本的な解決策に必然的に伴う時間的な遅れに耐えられなくなる。こうして、対症療法を繰り返せば繰り返すほど下のサークルに取り組むことが出来なくなっていく副作用が生まれてしまう。
以上が、「問題のすり替わり」というシステム原型を一般アマチュアゴルフ業界に適用した事例である。
このシステム原型は、他の問題でも分析が可能であると同書では述べている。身の回りに場当たり的な対処を施すものの、繰り返し問題が再発する状況はないだろうか。
3.ココロに残ったフレーズ集
今回は少しボリュームが多くなってしまうが、ココロにとどめておきたいポイントを以下に引用しておく。
今日のマネジメントの一般的体系は、その核心において、凡庸な結果にしかつながらない。それは、チームが最高の状態で協働するときの特徴であるやる気と集合知を活用し損ねた代償として、人に「もっと働け、もっと働け」と強いるものなのだ。
☞「今日のマネジメントの一般的体系」とは、これまで慣れ親しんだ経営手法(「通常業務」や「構造改革」を含む)。個人個人は優秀なのにもかかわらず、各人がどれだけ膨大な時間を業務に費やしても、革新的な企業たりえないのは、何か根本的なところで誤りがある可能性がある。
学習する組織が、航空機やパソコンなどの工学技術のイノベーションであったなら、その要素は「技術」と呼べるだろう。人間の挙動におけるイノベーションの場合、その要素となるのはディシプリンだと考える必要がある。「ディシプリン」というのは、「強制的な命令」という意味でも「処罰の手段」という意味でもなく、実践するために勉強し、習得しなければならない理論と手法の体系である。ディシプリン(discipline:「学習する」という意味のラテン語「ディシプリナ (disciplina)」が語源)は、あるスキルや能力を手に入れるための発達上の経路である。ピアノの演奏から電気工学に至るまでのどのようなディシプリンもそうであるように、天賦の才をもつ人もいる一方、誰でも実践によって熟達度を高めることができる
☞ピーター・ドラッカーの『創造する経営者』において「体系は、常人をして成果を上げさせるための能力を与える。有能な人間に卓越性を与える」と述べていたところの「体系」と、本書でいう「ディシプリン」は同義だと思われる。
残念ながら、大半のシステム分析は、ダイナミックな複雑性ではなく、種類による複雑性に焦点を当てている。何千もの変数や、複雑多岐にわたる詳細要素を伴うシミュレーションは実のところ、私たちがパターンや主な相互関係に目を向けるのを妨げる可能性がある。実際、不幸にも、大部分の人にとって「システム思考」とは、ますます「複雑」(本当はこれを「詳細」と呼ぶべきである)化する問題に対して、ますます「複雑」化する解決法を考え出して、「複雑性をもって複雑性と格闘すること」を意味している。実は、これは真のシステム思考と正反対なのだ
☞種類の複雑性に対するアプローチと、ダイナミックな複雑性に対するアプローチは、それぞれ沼上幹著『経営戦略の思考法』における戦略思考の3パターン(カテゴリー適用法・要因列挙法・メカニズム解明法)のうち、要因列挙法とメカニズム解明法がおよそ類似した概念と言えそうだ。
(因果関係の論理の)現実は環状になっているのに、私たちが目にするのは直線である。ここに、システム思考家としての私たちの限界の始まりがある。私たちの思考にこのような分裂が起こる原因の一つは、私たちの言語だ。言語が認知を形成する。私たちに何が見えるのかは、何を見る用意ができているかによって決まる。西欧の言語は、主語ー動詞ー日的語という構造になっており、線形の考え方に偏っている。システム全体の相互関係を見たいのであれば、相互関係の言語―つまり、環状になっている言語が必要だ。
☞ここから始まるセクションだけでも、つまみ食いしていただきたい。「蛇口をひねってコップに水を入れる」という単純な具体例を用いて、因果関係が直線的(私が蛇口をひねる⇒コップに水が入る)なのではなく、環状になっているということを、分かりやすく説明している。
システム原型についての知識を深めれば、私たちの抱える最も厄介な問題の一つでありマネジャーやリーダーが絶え間なく闘っている「専門化と知識の細分化」という問題に対処するうえで役立つだろう。いろいろな意味で、システム思考に最も大きく期待できる点は、あらゆる分野にまたがる知識の統合である。こういった同じ原型が、マネジメントにおいてだけでなく、生物学や、心理学、家族療法でも起こるし、経済学や政治科学、生態学でも繰り返し起こるからだ。
☞僕自身が考えていた、一般的なアマチュアゴルファーが陥る問題として捉えていた「スイングの細分化の罠」というものと本質的には同じ。生物学、心理学、家族療法、経済学などなどに加えて、「一般アマチュアゴルフ界」を加えたい。
マネジャーの大半は、「主張者」になるための訓練を受けている。実際、多くの企業で、有能なマネジャーであるということは、問題解決能力がある―何をすべきか理解し、それをやり遂げるために必要な支援はすべて引き出せるーということだ。マネジャーたちが成功してきたのは、部分的には、説得力のある議論を戦わせ、他者を動かす能力があったからだ。
それに対し、探究のスキルは、評価されず、報われることもない。しかし、高い地位に就くにつれて、直面する問題は個人的な経験以上に複雑で多様になる。うってかわって他者の洞察を引き出すことが必要になり、学ぶことが必要になる。そうなると、主張のスキルは逆効果になり、私たちが互いから学ぶ機会を奪う可能性もある。必要なのは、主張と探求を融合させて、協力的な学習を促すことだ。
☞個人的に思っているのは、組織には「探究スキル」が相対的に優位な人材が一定数いると思われる。しかしながら、「主張者(主に組織の上に立つ人材)」はその問題解決能力を元に「成果」を出してきた人たちであり、また一般的には組織の人材評価も「成果」に焦点を当てることから、「成果を上げていない」と評価される探究者たちの意見はないがしろにされがちだと思われる。主張者たちにない観点を探究者が持ち合わせている可能性に光を当てていくには、どのようにしたらよいのだろう。一つの解決策は、仕事だけでなく、その人の多面的な要素を理解することから始まるのではないか。そして、仕事以外の要素を、「仕事には関係のない能力」だと決めつけずに、その本質と仕事とを関連付けると人財の可能性が開けるのではないか。
マネジャーは自分の今のメンタル・モデルを振り返ることを学ばねばならない。組織にはびこっている仮定を率直に話し合わない限り、メンタル・モデルの変化を期待できないし、システム思考もほとんど無意味である。マネジャーが、自分の世界観を、一連の仮定から成り立っているものではなく、事実だと「信じる」ならば、その世界観を問い直すことに対してオープンな姿勢にはなれない。また、自分の考え方、そして他者の考え方を探求するスキルが欠けていれば、新しい考え方で協力して実験することにも限界がある。
問題は、今の現実に対する私たちの受身の姿勢にある。ビジョンが生きた力になるのは、人々が自分の未来は自分が形づくることができると本当に信じているときだけだ。実は、ほとんどのマネジャーが、自分の今の現実をつくっている一因は自分にあることを体感していない。だから、その現実を変えることに自分がどれだけ寄与できるかわからないのだ。
「マネジャーたる者は何が起きているかを把握していなければならない」という信念がある。ある問題の原因を知らないかのように行動することは絶対に許されないのだ。高い地位に就いた人たちは、何が起きているかを知っているように見せる達人であり、そういう地位に就こうと余念がない人たちは、自肩をもって知っているという雰囲気を身につけることを早いうちから覚える。
私たちは、世界を単純で明白な言葉でとらえているので、単純で明白な解決策を信奉するようになる。だから、単純な「応急処置」、つまり多くのマネジャーの時間を奪う仕事を必死に探し求めることになるのだ。フォード社の「プロジェクト・アルファ」のディレクター、ジョン・マヌージアンはこう述べている。「この見つけては直すという考え方をしている限り、短期的な解決策を果てしなく繰り返すことになる。この短期的な解決策は、問題を追い払ったように見えるが、問題はまた戻ってくる。そこで、私たちは出かけていって、また直す。見つけては直す名人には、永遠に出番がある」
「物理科学の考え方が『産業時代』を支配したように、生命科学の考え方が『知識時代』を支配し始めている。生命科学の考え方は、知識や人や組織を生きているシステムとしてとらえる。それにより、着眼点が、(1)部分から全体へ、(二)分類から統合へ、(三)個人から相互作用へ、(四)観察者を外に置くシステムから観察者を内に含むシステムへと変化する」
英語の「company (企業)」の語源はフランス語の「compaigne(カンパーニュ)」であるーこれは「パンを分け合う」という意味で、「companion(仲間)」の語源でもある。興味深いことに、ビジネスを意味するスウェーデン語の古語「naringsli」は「生命の栄養」という意味であり、ビジネスを表す中国古来文字は「人生の意味」と訳される。私たちは、「組織は生きているシステムである」ということを再発見するとき、心から大切だと思う目的に向かって力を合わせて取り組むことが、人間である私たちにとって実際にどのような意味をもつかということもまた再発見するのだろう。
☞この本で度々取り上げられる言葉の語源。語源を遡ったとき、実は我々は、大昔にすでに問題の本質に気付いていたのではないだろうか。それが、いつからか(詳細に細分化して)考えすぎて、その本質を見失ってきたのではないだろうか。中世に終わりを告げたのがルネッサンス(古代復興)であったのと同様に、第2のルネッサンスが期待されてやまない。
「結局のところ、いかなる場合も組織の変容の原動力となるのは、そこで働く人たちです。組織の人たちが互いにどのようにかかわり合うかに焦点を当てることが、核となる成功理論の土台を形づくるのです。つながりの質が高まるにつれて、思考の質も向上します。チームのメンバーたちが問題のより多くの側面について考え、より多くのさまざまなものの見方を共有すると、彼らの行動の質が高まり、それによって最終的には達成できる成果が増えるのです」。
☞この文章に繰り返し登場する「○○の質」。それは必ずしも定量化できないものであり、捉えどころがないもののように思われるかもしれない。だが、分かりやすさを求めて本質を探究することを諦めるならば、組織の孕む構造的な問題は解決されず、表面的な問題が形を変えて繰り返し現出し、その場しのぎの対応を続けるだけになるだろう。
学習や開放性という文化の構築をめざす変革者は、二つの世界ー彼らが構築に取り組んでいるチームや組織のオープンな学習志向の世界と、主流の組織のより伝統的な世界に生きているように感じることがある。私たちは、企業の免疫系の壁にぶつかった変革者の問題を理解するようになったとき、息の長いイノベーションには、二つの文化を併せもち、それぞれの基本原則を尊重しながら、二つの異なる世界を効果的に行ったり来たりするリーダーが必要だということを理解し始めたのである。
細織の核となるアイデンティティと、組織の歴史上前例のない何かをつなげるための公式はない。だが、そのアプローチは、こうしたアイデンティティが存在すると言じることから始まるー「組織とは、利益を生み出すだけのものでもなければ、現在その組織が作っている製品や提供しているサービスを生み出すだけのものでもない」と。このアプローチには、真の発見の精神、心に導かれることを厭わない精神と、そして、ずっとそこにあるのに見えていなかったものを見る覚悟が必要なのである。
「人生は神聖なもの。だからそのように出会うべきだ」。(略)「それはただ私たちの身の回りにある美しさを心から味わうゆとりをもつ経験なのではないだろうか。夕空の見事な色、牛の群れの穏やかな美しさ、若木が大地から伸びる奇跡、ジンバブエの田舎の風物である巨大な花崗岩に腰をおろすという地に足のついた体験、喜びも悲しみもほかの人間と深く共感し合う不思議.....こうした一見シンプルな、創造という行為の奇跡に気づき、そのすばらしさを味わうたびに、人生は無限に豊かで不思議な力と愛に満ちているという確信と、そしてその感覚を失わないでいようとする人間はそうでない人間より豊かだという確信もまた深まる」
✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼
その他、いちごる読書noteはこちらにリスト化してます。
◆繰り返し読みたい本リスト☞LINK
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
