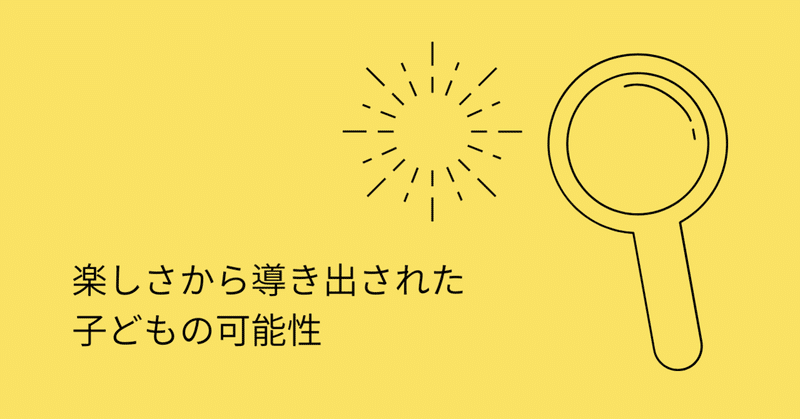
楽しさから導き出された子どもの可能性
2015年から始まったキャンプ
はじめて投稿します。
私はNPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場の代表をしている山本良子と申します。
キャンプを始めて8年。こんなに長くキャンプ事業をするとは最初は思っていませんでした。
キャンプって実施の1年前から助成金申請をして、活動場所の確保や安全管理、スタッフ集め、参加者募集等々やることが意外と多いんですね。
尚且つ、この3年はコロナ対策もしっかりしながらキャンプに挑んだわけです。
仕事量と収入を考えれば割に合わないわけですが、それ以上に得られるものがとてつもなく多いからキャンプを毎年しているわけですが・・・
今回はそのキャンプの凄さをどど~~んとお伝えしちゃいますね(^^)/
アクセス数が毎年増える
最近は、夏休みも、祝日も、平日の放課後も、子どもが公園などの屋外で遊ぶ姿をますます見なくなってきました。
16年前も危機的状態だと私自身が感じて活動を開始しましたが、今はそれ以上に危機的ではないかと感じています。
そして、そんな子どもたちの遊び環境(育つ環境)を危惧する保護者が増えてきています。
学校から帰ったら家でゲームをしてYouTubeを見て毎日過ごす子どもたち、屋外で遊ばない子どもたち、仲間と群れて遊ぶことが少ない子どもたちが増加していることは間違いないでしょうし、友達同士での遊びも学校や学童クラブ以外ではなかなかできなくなっているのが現状だと思います。
そのため保護者は子どもに少しでも夏休み中にいろいろな体験をしてもらいたい、自然の中で思いっきり遊んでほしいという想いが強くなっています。
私たちのキャンプの申込は毎年6月初めに実施します。キャンプにどれだけ興味があるのか?は保護者からの当団体のキャンプ事業へのアクセス数でも把握できます。
キャンプの募集は7月のキャンプで20名、8月のキャンプで20名の計40名です。
アクセス数は
2020年度の申込開始日400アクセス
2021年度の申込開始日600アクセス
2022年度の申込開始日2000アクセス
どんどん増えてます。
これはキャンプ事業以外でも同じ現象が起きています!!
子どもの「やってみたい!」をどう育むか?
昔から学校で実施しているキャンプというのは、活動時のプログラムが決まっていて、ご飯を作る時は班全員で作り、活動する時も基本的にみんなで参加、キャンプファイヤーのプログラムも決まっていて、歌う歌も決まっている。それを大人の指導の下で安全に楽しむキャンプでしたが、最近は様々な面白いキャンプが増えてきています。
私たちが実施しているキャンプの場合は、ご飯の時間、海遊び、釣り体験の時間は決まっていますが、プログラムごとに参加するか、しないかは子どもたちにゆだねています。
子ども一人ひとりの「やってみたい」「チャレンジしてみたい」に寄り添い、出来る限り実現していきたいという想いで、スタッフ一同全力で応援しています。
集団行動を重要視してきた時代と違い、主体性、能動性をより求められる時代となり、子どもたち自らが考え行動する力や創造力を育みチャレンジする力が求められています。
空気を読むのではなく、「やってみたい」ことを堂々と発言し、仲間を集め、チャレンジしてみる力。失敗もあるけど、それも大事。失敗なくして成功はない。悔しくてもチャレンジしてみる。あきらめない。他の方法を考える・・・。
子どもの頃の失敗体験こそ、子ども自身の経験値を上げる要因としては大きいと思っています。
子どもの「やってみたい!」をどう育むか?これは活動をする中でのキーワードではないかと思っています。

海で魚を突きたい!
漫才師よゐこの濱口さんが出演する無人島生活のように「とったど~!」がしたいという子も多くいて、時間はかかるけど、なんどもなんども海に潜り、時間を忘れて魚を捕まえる子どもたちにいつも感動しています!
魚を突いた時の笑顔が最高!!
子どもの生き生きしている姿を見ると、スタッフもワクワクします!

猫じゃらしラーメンが食べたい?
今年のキャンプで、子どもからの提案で「猫じゃらしラーメン」作りが始まりました。
「猫じゃらしからラーメンなんて作れるの?????」
・・・と思う人が多いと思いますが、どうもできるらしいのです!
猫じゃらしラーメンというのは大人気アニメ「Dr.stone」の中に出てくるもので、それを子どもたちが真剣に作りたいと考えたわけです。
「Dr.stone」の内容としては、ある日 謎の嵐に巻き込まれ、人間全員石化になってしまい、それから3000年以上経ったある日 復活をとげた主人公「石上千空」が活躍するアニメで、3000年以上も経った人類はどうなるのか?謎の石化の正体は?などとても気になりテーマがいっぱいです。
文明が無くなり、原始時代同然になった世界で出来たラーメンが「猫じゃらしラーメン」らしいのです。
「ネコじゃらし」の本当の名前は「エノコログサ」と言います。
夏から秋にかけて生える草で先端部分が犬のしっぽに似ている事から
「犬っころ草」から「エノコログサ」に変化しました。
イネ科ということでどうも食べられるらしい!
草むらから猫じゃらしを収穫して、一生懸命麺づくりにチャレンジ!
…その後はスタッフが一生懸命関わってくれて、子どもと作っていたのですが・・・結果は?
残念ながら猫じゃらしラーメンは完成しなかったのですが、な、な、なんと海水から塩を作り出しました!
Dr.stoneの主人公「石上千空」は塩を海水からとっていて、それを真似て薪で火を起こし海水を温めて2時間、塩を完成させました。
まろやかで意外に美味しい塩でした!

温泉を掘りたい!
中島サマーキャンプを実施している「ゆうきの里」には水道水は繋がっていません。井戸水をくみ上げるシステムはあるので、ドラム缶風呂ぐらいならできるけど、みんながシャワーを浴びて体をキレイにするだけの水は確保できないわけで・・・食事用の水はタンクで汲んで確保しているけど、それをシャワーに使うわけにもいかない。
で、子どもたちが考えた・・・
「温泉を掘りたい!!」
大人からしたら「できるわけないじゃないの~」と思うわけです!
でも子どもたちは、こういうときほど一致団結するのです!これホント不思議な現象ですが・・・。
そうと決まったらスコップを用意して遊ぶのを忘れて必死に掘り始めます。最初は3人ぐらいだったと思うけど、気が付くと8人ぐらいに仲間が増えていて・・・夕日が沈むのも忘れて掘る掘る・・・朝も早くから起きてきて、掘る掘る掘る掘る掘る!
でも掘っても掘っても温泉は出てこない。
次に考えたことは・・・「お風呂を作る」
海岸からタイルになりそうな平たい石を、たくさん拾ってきて掘った穴に、石を貼り付けてお風呂を作り始めました。
重たい石をみかんキャリーいっぱいに拾い、何度も何度も海岸に拾いに行き、貼り付けていました。
ある程度貼り付けたら、お風呂に水を入れるのですが・・・残念ながら水はどんどん砂の中に浸透していき、水はたまりません。
それからどうするのかな?と見ていたら、ブルーシートをお風呂の中に入れて、そこに水をためて・・・
そして最後は、元気そうなスタッフを探し、
水の入った「落とし穴」にどぼ~~ん!!

夏祭りがしたい!
コロナの影響で、この3年ぐらい夏祭りがなかったせいもあり、夏祭りをしたいという声は昨年も今年もよく子どもたちから聞かれました。
今年も7月と8月のキャンプで夏まつりを実施しました。
まず何をするか考える。
準備を始める。
材料はあるの?
お金はどうする?
お客さんはどこから集める?
子どもたち同士の話し合いからいろいろなことが決まっていきます。
スタッフも相談にのります。
言い合いやけんかもあります。
伝えたいことが伝わらなくて泣いちゃう子もいたりします。
それをフォローする子もいたりして・・・。
ここでもいろいろなドラマが起きましたが、これは次回のnoteで書きたいと思います。

キャンプでのドラマは子どもの数だけある!
子どもの「やってみたい!」は本来、毎日無限大に広がるものだと思います。
きっと、今回のキャンプでもここでは書ききれないほどの、たくさんのドラマがあったのだと思います。
私たち大人が知らない、子どもだけの世界も「リアル」にたくさん起きたことでしょう!
だから子どもの成長も感じられるし、やめられないのですが・・・。
最後に・・・
ただやはり、できれば子どもたちの日常にもっともっとワクワクを増やしてあげなくてはいけないと思っています。
地域の公園でも良いし、広場でもいい、子ども時代は大人に隠れて秘密基地を作る経験ぐらいはしないといけないし、ケンカして仲直りをする経験もたくさんしたほうがいい。
キャンプじゃないとできないという社会はおかしい!
この世に生きてきて
「生きることが楽しい!」
と、子ども時代は思っていいと思います。
子どもにとって「遊び」は生きること
子どもたちにとって「遊び」=「学び」なのです。
楽しい経験をいっぱいいっぱいするから、大人になっても「みんなを幸せにしたい!」と思えるし、「環境を良くしたい!」とか、「社会を平和にしたい!」と思う心が育まれるのだと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
