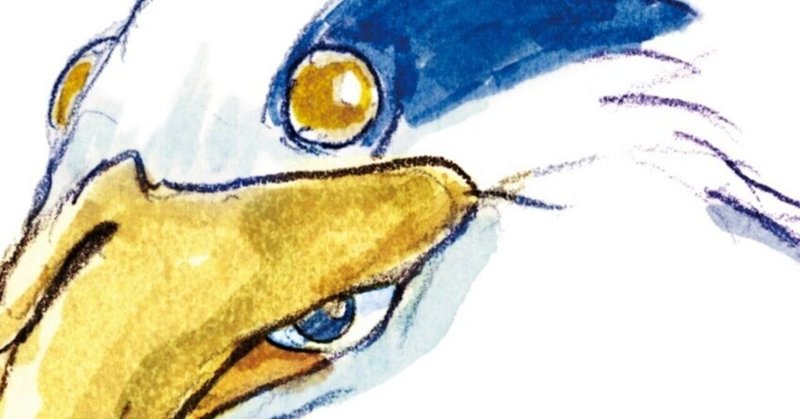
『君たちはどう生きるか』の感想をオタク特有の長文早口で述べる #2
登場人物・場面についての解釈や連想したことを書いていく。
この記事は全4篇のうちの#2である。
前回の記事は以下のとおり。
登場人物・場面についての連想篇
さて、いよいよ渾沌に目鼻をつけて遊んでみようと思う。
また、何度も同じようなことを強調するが、本記事で述べているすべての認識は、あくまで群盲の一評にすぎない。断定調で述べている部分も、すべて筆者の解釈にすぎない。客観的にみえる書き方をしていても、すべて主観である。ここに関しては、読み手の読み方にたのむところ大であるので、適宜読み替えを願いたい。
なお、それぞれの場面解釈については、章を断って義を取るようなきらいがあるが、本記事は厳密な考察ではなく、あくまで自由気ままな連想であるので、その前提でご笑覧願いたい。
『君たちはどう生きるか』という本
今作のタイトルにもなった本だが、作中ではあの短い読書シーン以外にこの本は登場しない。ただ無言で読まれるだけであり、その後この本はその書名すら再登場しない。
『君たちはどう生きるか』という本のなかでは、天動説から地動説への世界観の転回が扱われている。人間社会を生きていく上で「自分を中心に社会や他人が動いていると考えるのか」「自分は多くの人間の一員として社会に存在しているだけと考えるのか」ということは意識するに足る考え方である。そのうえでの「君たちはどう生きるか」という問いかけである。
眞人はこの本と出会い、本を読む前後で、価値観が変わったと考えられる。価値観は判断に影響を与え、行動に影響を与え、発言に影響を与える。今まで気づかなかったことにも気づくようになる。
本は作品の一場面にしか登場しなかったが、その本の影響力は作品全体に亘っている。そういう意味では、紙の束としての「本」は一瞬の登場であったものの、意識の束としての「本」は作中に何百回もあらゆる場面で登場していることになる。
不思議ノ國ノ眞人
おそらく、あの塔の内部にある不思議の国は、眞人自身の心の世界が表現されたものである。
眞人のモデルは、基本的には宮﨑駿本人であろう。場面によって別の人物や概念を代表していることもあるだろうが、全体を通してみると、どこか自伝的なものを感じる。いずれ世界的なアニメ監督となるべき人物の心の真体、アイデアの源泉が、あの不思議の国の正体なのである。
その不思議な心の塔を貴重なものとして、外から見てありがたがる者もある。不気味がる者もある。建物で覆って保護しようとする者もある。侵入してくる者もある。湧き上がるアイデアに滋養を与えて送り出そうとする者もある。それを喰って自分のものとし、生きようとする者もある。救おうとする者もある。善意から禁忌に触れ、心のざわめきを誘う者もある。嘘つきだが助けてくれる者もある。スタジオを無理に託そうとする者もある。横から口出しをして肝心なものをダメにしてしまう者もある。禁忌は、自分自身の心の禁忌であり、石のざわめきは自分自身の意志のざわめきである。
みな何かを象徴しているようでもあり、脈絡があるようでもあり、矛盾しているようでもある。一貫性はあっても、その一貫性自体が人間にとっては、不可説・不可思議のものである。まさに人間の心であるというよりほかない。
良い石
大叔父が眞人のために、良い石を選っておいてくれている場面がある。
大人が子どものために「良いもの」と「悪いもの」とを検分し、いわゆる良いものだけ、優れたものだけ、権威のあるものだけを選って薦めるようなところが、あの場面からは感じられる。大人が、大人の決めた「正しいオモチャ」だけを子どもに与えて遊ばせようとしてくるのは、よくあることではないだろうか。
子どもは、自然の中に興味のあるものを勝手にみつけて、それを勝手に拾って遊ぶものである。それを見た付き添いの大人が「汚いから捨てなさい」と言ってくるのは、もはやお決まりの光景である。
子どもが家に持って帰ってきたポケットの宝物を、大人が「くだらないもの」「素人っぽい、安っぽいもの」と論評してくるのもまた、お決まりの光景である。
大人は善意によって子どもを導こうとする。「誰にとっても、善は善であり、悪は悪である」という考えを信じ、自分の価値観と相手の価値観に違いがあることを認識しない。
子どもの感性は次第に大人の価値観に浸蝕され、そうして大きくなると、今度は自分が、幼い子どもの感性を浸蝕する立場になるのだろう。
宮﨑駿も幼いころ同じような覚えがあったのだろうか。あるいは自分の息子に同じようなことをしてしまったという自覚があるのだろうか。宮﨑駿は眞人の立場なのだろうか、大叔父の立場なのだろうか。実はどちらでもあるのかもしれない。
「おとなだって、はじめはみんな子どもだったのだから。でも、それを忘れずにいる人は、ほとんどいない。」とは、サン=テグジュペリ『星の王子さま』の中に見える言葉である。
大人はものごとの価値を、値段や数字や論理に換算しなければ認識することができない。大人は、実物よりも名義のほうをあてにする生き物だからである。しかも、その名義の優劣を評価するための尺度には一定の普遍性、妥当性があると思っているのである。その視点が天動説的(自分中心的)な考えのもとにあることを我々は自覚しなければならない。
そもそも善悪とは、どこに根拠がある概念なのだろうか。大人たちが言うように、普遍的のあるものなのだろうか。
机の上の墓石を善とし、ポケットの中の宝石を悪とするような考えが、本当に宇宙の真理として存在しているのだろうか。
ワラワラのために命ある魚を殺すのは善で、逆にペリカンがワラワラを食べるのは悪であるとするような考えが、本当に誰にとっても普遍性のある善悪であるといえるのだろうか。
自分の目には善意に映るものが、他人にとっては悪意となることだって往々にしてある。「往々にしてある」どころではない。地動説的な視点に立てば、善悪の基準は人によって皆違うという捉え方の方がむしろ普通だともいえるのである。
自分の信じる善=世界共通の善だと思い込んでいるうちは、善悪の本質を知ることはできない。自分も他人も、ひとしく同じ天地の間に起居する個々の人間である。誰か1人の善をもって、ほか全員の善を代表することなどできないはずである。
では、今まで存在すると信じてきた世界共通の善とは何だろうか。
何に書かれているものだろうか。もし何かに書かれているとしたら、それは書いた人の考える善にすぎない。
みんなで相談して決めるものだろうか。みんなの善悪の考えがバラバラだったときに、どうすればよいかわからない。どんなに絶対悪と思えるものでも、相手にとっては絶対善であることもあるのである。
自然の法則のなかにあるのだろうか。自分の考えを去って自然をみつめてみる。しかし、いくらみつめても、自然には善悪の差別がない。自然には意志が存在しないのである。自然は清濁を併せ飲み、なるようにしかならない存在である。
畢竟、世界共通の善などないのだ。自分がかつて信じていた善悪、倫理、道徳というものが、いまや普遍性を失い、根幹から崩れていく。すべての善悪の掟は、属人的な個人意見に出自をもつ仮初めの代表選手にすぎないのである。
世界共通の善というものが幻想であるならば、自分の信じる善悪を一方的に万人に適用し、その善悪に基づいて万人を裁こうなどという考えもまた説得力のない話である。善意の押し付けも悪意の押し付けも、ひとしく精神暴力的、自己中心的、天動説的な考えであることを認めなければならない。
自分も他人も、ともに同じ天地の間にある人間Aと人間Bである。人間Aである自分に善悪を設定する権利があるのなら、人間Bである他人にだってその権利があることにある。
大叔父が選んだ「悪意のない石」は、あくまで大叔父の目から見た個人的な善である。眞人の考える善とは違う。インコの考える善とも違う。ペリカンの考える善とも違う。誰かの取り分を大きくすれば、誰かの取り分が小さくなる。不思議の国の統治者としての責任は重い。
眞人は、大叔父が決めた善悪の石の引継ぎを拒否する。自分はほかのだれでもなく、自分自身の善にしたがって生きる。また、自分一人が世界を統治する特権を保有し、自分の善を万人に押し付けるような態度はもはや取るべきでないと思慮してのことであろう。
一方、そばで見ていたインコの王は、石のチョイスが自分の正義と一致しないことに気付いて腹を立て、あっけなく世界を壊してしまったのであった。
ヒミ
ヒミの正体は、眞人の母の若い頃の姿であろう。持物として火が用いられているのも、暗示的である。
作中に、眞人の母は若い頃に塔の中で神隠しに遭い、1年後に出てきたという話があったが、それは最後の場面でヒミが元の世界に帰っていったことと関連づけて説明することができる。また、「母に会える」と唆されて入っていった世界なのだから、そこで母にあたる人物に会うのは不自然ではない。
宮﨑駿は母をはやくに失っており、今までの作品のなかにも、母へのあこがれのような表現が散見される。あの不思議の国が宮﨑駿の心の世界だとすると、そこで大きな存在感をもっているあの少女は、まさしく母である。
最後にヒミは「眞人を産めるんだから幸せ」というフレーズを述べる場面がある。眞人はヒミを母だと知っており、ヒミは眞人が自分の子どもであると知っている。物語上、二人がなぜお互いに親子であると気付いたのかはよく分からなかったが、おそらく『千と千尋の神隠し』で千尋が親を見抜いたのと同じようなもので、「親子は以心伝心ようなところがあるはずだ」という宮﨑駿の考えの表れでもあるのではないだろうか。
筆者の世代ではかなり廃れてしまっている視点だが、昔ながらの日本思想を持った人たちには、人間を精神と肉体とに分けて捉える視点がよく見られる。似たようなものとして、物事を無形と有形とに分けて捉える考え方もよく見られる。ここで、精神と無形とは同根の概念である。また、肉体と有形とは同根の概念である。年配の人の話を聞いたり文を読んだりしていると、彼らは、精神と肉体、無形と有形について非常に強い概念的区別を感じているらしく、この両者が合一して完全体となるという思想がたびたび現れる。
たとえば『千と千尋の神隠し』において、湯婆婆は肉体的なものの権化であり、銭婆婆は精神的なものの権化であるといえる。銭婆婆の「わたしたち、二人で一人前なのに」というセリフは、精神と肉体の合一について言及しているものであろう。
湯婆婆は大きな店を構え、儲けを喜び、名を奪って労働者を支配し、ハンコを盗んで利を得ようとするが、これらは肉体的なもの(物質的なもの)への崇拝心の表れである。鼠に姿を変えられた自分の大事な子どもが目の前にいても全く気づかなかったのは、湯婆婆が肉体的なものしか見ないからである。
銭婆婆は、質素な家に住み、真心を込めて仕事をし、千尋に心理的なアドバイスをするが、これらは精神的なものへの崇拝心の表れである。千尋は、精神を司る銭婆婆との出会いより、記録ではなく記憶でハクの正体を見抜き、肉眼ではなく心眼で親の正体を区別できるようになる力を得た。息子を肉体で見分ける湯婆婆と、親を精神で見分ける千尋が、ここではうまく対比されている。
ところで、銭婆婆は「沼の底」という場所に住んでいる。精神とは心の異名である。心の権化である銭婆婆が「沼の底」を宿としていることから、宮﨑思想には心の世界=沼の底というメタファがあるのではないかということが推測できる。今作において眞人が落ちていった世界は、地獄の沼の底である。沼の底ということは、つまり、あの世界はやはり主人公の心の世界である。
眞人は青鷺に導かれ、「肉体」として再現された母の姿を見せられる。しかし、それは抜け殻のようなもので「精神」としての母はいない。その後、不思議の世界において、「肉体」としては母の姿をとっていないが、「精神」としては母であるともいえる少女ヒミに出会うのである。時間を共に過ごし、絆によって結ばれた眞人とヒミは、本当は親子であることを、心を以て心に伝えられるような状態になったのであろう。千尋と同じように、「目で見る」ではなく「心で見る」の境地に至ったのである。千尋は銭婆婆から啓発を受けてその境地に至ったわけだが、眞人は長い時間をかけた自分の心との対話によってその境地に至ったといえる。
ここで、サン=テグジュペリ『星の王子さま』の思想が思い出される。『星の王子さま』の話では「心で見ることの大切さ」が大きなテーマとなっており、その思想は全編をつらぬいている。
宮﨑駿はサン=テグジュペリ(『星の王子さま』の作者)の作品群の愛読者である。新潮文庫から出ているサン=テグジュペリ『夜間飛行』『人間の土地』の表紙カバー絵は、ともに宮﨑駿の描いたものである。
ちなみに「君をのせて」(『天空の城ラピュタ』の主題歌)にある以下の歌詞は、『星の王子さま』に出てくる「砂漠が美しいのは、どこかに井戸を、ひとつかくしているから」「きみが星空を見あげると、そのどれかひとつに僕が住んでいるから」というセリフを本歌取りしたものであろう。
あの地平線 輝くのは
どこかに君を かくしているから
たくさんの灯が なつかしいのは
あのどれかひとつに 君かいるから
サン=テグジュペリ作品が宮﨑思想に与えた影響力の大きさがうかがえる。
『星の王子さま』の思想では、心の絆によって結ばれることを重視する。
作中の王子さまは、たった1本の大切な薔薇を星に残し、はるか離れた地球にやってくるのだが、地球には同じような見た目の薔薇が大量に生えており、星で大切にしていた自分の薔薇が実は特別でもなんでもなかったのだと気付き、泣いてしまう。その後、あるキツネとの出会いがあり、時間を共に過ごし、絆によって結ばれ、そして別れ際に、本当に大切なのは「目で見る」ではなく「心で見る」ということなのだと教わる。そこで、王子さまが再び大量の薔薇たちに会いに行ってみると、そこにいる大量の薔薇たちが自分の薔薇とは全然似ていないことに気付く。外見はよく似ていても中身は違うのだという一番大切なことに気付けるようになっていたのである。これは王子さまが「目で見る」ではなく「心で見る」の境地に至ったことを示す象徴的な場面である。王子さまは砂漠で出会ったパイロットと仲良くなるのだが、愛する薔薇のために星に帰ることを決意する。星に帰るという方法が死であることに気付いたパイロットは、必死に王子さまを引き留めようとするものの、王子さまは死んだ身体を抜け殻であるとし、思い出の中にある心こそが本物であると告げる。そして、最終的に王子さまは死の道を選ぶのである。
眞人が最初に青鷺に見せられた母は、まさしく魂の抜けた抜け殻であった。星の王子さまが愛する薔薇と同じ外見を持った薔薇に惑わされたように、眞人も母と同じ外見をもつ模型に惑わされてしまったのである。しかし、最終的には、眞人は心の中に少女を見つけ、見た目は違っても、彼女こそが本当の母なのだと気付く。元の世界に帰ろうとする母に対して、眞人は母がいずれ火事で死んでしまうことを心配する。しかし、母は生まれてくる眞人に会うため、笑顔で死の道を選ぶのである。星の王子さまが、愛する一輪の薔薇と再び会うために、死の道を選んだ場面と重なる。眞人と母との絆は、目に見えるものにとらわれず、強い心のつながりへと育っていたのである。
冒頭、眞人はナツコのことを母に似ていると言っていた。愛する母と別人のナツコが似ているからこそ、眞人はナツコに心を開くことをためらっていたのだろう。星の王子さまが愛する薔薇と別の薔薇の見た目が似ていることに戸惑ったのと同様である。
しかし、星の王子さまが薔薇の違いを「心で見る」ことができるようになったのと同様に、眞人もまた母とナツコの違いを「心で見る」ことができるようになったのである。
かくして、眞人はナツコに以前の母の影を見ることはなくなり、新しい母として受け入れられるようになった。また、以前の母の影を遠くに追い求めることはなくなり、自分の心の中に認められるようになった。
眞人の母、宮﨑駿の母は、どこか彼方ではなく、自分自身の心の中にいたのである。
海の彼方には もう探さない
輝くものは いつもここに
わたしのなかに 見つけられたから
青鷺
青鷺は高畑勲だろうか。腐れ縁のようなものを感じる。
眞人はどうしても青鷺が気になって仕方ない。表面的には争っているようにみえるが、実際には眞人を時に導き、時に見捨てるようなそぶりをみせ、時にピンチを助け、最終的には戦友のような関係を築いている。
面白いのは、眞人が青鷺の嘴修理の細かい注文に対して甲斐甲斐しく応じるところである。高畑勲の指摘を受けてブツブツと文句を言いながら作画を直す宮﨑駿の姿に重なる。
「風の谷のナウシカ』映画化の際の話として知られる「宮﨑駿がいままで尽くしてきた高畑勲に対して、ぜひ自分のプロデューサーになってほしいと依頼したところ、高畑勲はこれをきっぱり断り、なぜ自分がプロデューサーに向いていないかということを説明したノートまで作ってきた」という逸話は、お世話をした青鷺が突然冷たいことを言って見捨ててこようとするところに重なる。実際、宮﨑駿は高畑勲からプロデューサー謝絶の辞を受け取ったとき、見捨てられたと感じたそうである。しかし結局なんとか説得に成功し、最後までジブリで2人一緒に働いたところなどは、まさしく眞人と青鷺の関係そのものである。
青鷺が高畑勲でないとすれば、あるいは宮﨑駿自身の想像力の権化かもしれない。つまり、擬人化された想像力である。青鷺は「嘘つき」として出てくるが、嘘とは想像力(フィクションやファンタジーを生む力)の異名でもある。想像力というものは、うまく付き合えば役に立ち、時に助けられることもあるが、しばしば制御が難しく、得体の知れない働きをするところがある。
中島敦の小説に『狐憑』というのがある。家族の死を境に、とんでもない想像力によって妙なことを口走るようになった男が、次第に人々からストーリーテラーとして面白がられるようになる話である。『狐憑』においては、この想像力の源泉は憑き物のせいであるとされているが、今作の青鷺はちょうど宮﨑駿に憑いた憑き物のようなものであるとみなすことができる。
ワラワラ
天に昇れば人間として生まれるという説明が作中にあるが、象徴的な意味としては、宮﨑駿の心の中に浮かんだアイデアの種を表しているように思う。大量のアイデアの種に滋養を与えて養う者もいれば、それを食い荒らす者もいる。一方ではそれを救おうとする者もいる。
あの不思議の国が宮﨑駿の心の世界を表しているならば、わらわらと湧いて浮き上がり、やがて表の世界に出ていく無数の玉は、アイデアの赤ちゃんといえるだろう。それを喰わなければ生きていけない者たちとは、何を象徴しているのだろうか。
キリコ
作中にはキリコという名前の人物が2人出てくる。1人は一緒に不思議の国に吸い込まれたお婆さんであり、もう1人は不思議の国で出会った若い女性である。2人は同一人物だろうか。
若いほうは『千と千尋の神隠し』のリンに似ており、お婆さんのほうは『崖の上のポニョ』のトキに似ている感じがする。モデルがいそうな気がするが、実在の人物のうち誰を指しているのかは、宮﨑駿の人間関係に詳しくないのでよく分からない。
世界の跡継ぎ
大叔父が世界の跡継ぎを求めている描写がある。
世界の跡継ぎとは、スタジオジブリの後継者の隠喩かもしれない。スタジオジブリには、宮﨑駿の心を引き継ぐものが必要だという焦りがある。大叔父が宮﨑駿で、眞人が宮﨑吾郎であろうか。
横から様子を見ていたインコの王は、肝心なところに余計な喙を容れてくる誰か(鈴木プロデューサー?)を表している可能性がある。
ちなみに「大叔父が宮﨑駿で、眞人が宮﨑吾郎」との説は、さきに述べた「眞人は宮﨑駿」という説と矛盾していると思うかもしれないが、これは問題視するに及ばない。たしかにデザイン的な見地からいえば、「AはB」で通ってきたものが突然「AはC」に変わるのは一般に推奨されない。一度シニフィアンとシニフィエの関係を定義したならば、なるべく変えないでおくのが観客フレンドリーな設計であるといえる。しかし、それは工業デザインの話であって、アートの話ではない。アートは工業デザインと違って、そのような制約を必ずしも受けないものである。
この矛盾が気になる人は、掛詞というものを思い出してみればよい。小野小町の「わがみよにふる ながめせしまに」の「ふる」という単語は「経る」という意味なのか「降る」という意味なのか。仮に「経る」を正しいとすれば「わがみ世に経る ながめせしまに」と解釈できる。逆に「降る」を正しいとすれば「わがみよに降る 長雨せしまに」と解釈できる。これはどちらか1つの解釈を採らなければならないようなものではなく、注目する部分に応じて2重の解釈を採ってよいものである。
歌人の「大いなる心」を31文字という「小さな空間」に籠めるための工夫として、掛詞は、我が国で長く愛されてきた。同様に、宮﨑駿の「大いなる心」を2時間4分という「小さな空間」に籠めるための工夫として、宮﨑駿は映画の中で掛詞をしたと考えることもできるのである。
気と意思
積み木の材質が木でなく石であることを眞人が気にする場面がある。なぜかは分からない。木を渡すのは気の配り、石を渡すのは意志の押し付けという洒落だろうか。眞人が石で頭を打つ場面があることから、石は人を傷つけることのメタファなのだろうか。
インコの思う天国
庭園を訪れたインコが、口々に「ここは天国だ」「ご先祖様!」と讃嘆する場面がある。もとはインコは南国産の鳥なので、ジャングルこそが夢にまで見た見も知らぬ美しき故郷の風景なのであり、心に響くものがあったにちがいない(実際には、野生のセキセイインコの生息地は熱帯雨林のようなジャングルではないのだが、論旨には関係ないので今回はジャングルということにしておく)。人工物の中で育ったインコにとって、あの庭園は極楽、原始的な自然そのものなのである。
しかし、どうしても引っかかるのは、あれは原始的な意味での「自然」ではないということである。
インコたちは、ひょっとするとあれを「自然」だと信じているようであるが、あえていえば、あれは「仮の自然」または「人工」である。
筆者は上京して気付いたのだが、都会では、草木でありさえすれば人工的に維持されているものであっても「自然」と呼ぶ例がかなり多い。たとえば、商業ビルの建物内の花壇にある観葉植物を見て「自然があっていいね」と言うような人までいる。筆者が個人的に「自然」と言われて最初に思い出すものは、温室で管理されている園芸植物ではなく、刈ってもまた生えてくるようなススキやクズの藪である。これは植物の種類の違いに注目しているのではない。人為によって維持されているものか、勝手にそうなっているものかという違いに注目しているのである。『風の谷のナウシカ』でいえば、ナウシカが地下に作った小庭ではなく、腐海のイメージのほうが「自然」のニュアンスに近い。地下の小庭の植物は、もとは腐海から採ったものであるとはいえ、どちらかというと人工物の中で箱庭風に再現された疑似的な自然である。
よく「自然がある」というような言い方をするが、ものの順序を考えると、自然を見て「自然がある」と思うよりも、人工を見て「人工がある」と思うような意識を持ったほうが正確である。地球のデフォルト状態はあくまで自然である。そこに人間がアスファルトを敷いて住んでいるだけなのである。逆であるわけがない。
「あ、自然がある!」という言い方は、あたかも地面の上にレジャーシートを敷き、そのレジャーシートの上に乗り、それから外周にある本来の地面を見て「大地がある!」と驚くようなものである。
レジャーシートの上で生まれ育った子どもは、レジャーシートこそがもともとの地面だと思いがちであり、「レジャーシートは大地に敷かれた敷物にすぎない」ということを知らない。大地ならレジャーシートの裏にもあるのだが、そのようなことは思いもよらない。そのような環境において、レジャーシートの上に人為的に乗せた少量の砂をもって「美しい大地」と呼ぶような文化が生まれる。さらに極まって、観賞用に磨かれた砂1粒を「大地」と呼ぶようになる。レジャーシートの外に出てたびたび遊んだ経験のある子どもは「その粒は、砂というものであって、大地とは少し意味が違うのではないか」と感じるだろう。しかし、その感覚は、レジャーシート上に並べられた砂粒を「偉大なる大地」だと思って育った子どもにはなかなか伝わらない。
今作における不思議の世界のインコは、本物のジャングル(外の世界)を見たことがなかった。ご先祖様の故郷たるジャングルを、おそらく話には聞いていても、実際に見たことがないのである。ただ、ジャングルというものに感動する感性は、ずっと代を重ねても心の奥底に眠っていた。
そこに思いがけず現れたジャングルである。感動するに、なお余りある感動が、眼前に広がっているのである。内陸県で育った子どもは、はじめて海を見たときに大変な感動を覚えるらしいが、おそらくそれと同じ感動である。天の川を見たことがない子どもが初めて天の川を見たときにも、富士山を見たことがない子どもが初めて富士山を見たときにも、東京タワーを見たことがない子どもが初めて東京タワーを見たときにも、おそらく同じ種類の感動があるのではないだろうか。
ところが、このときインコが見たものは、本当のジャングルではない。インコたちがジャングルだと思って感動しているものは、温室庭園的に再現された仮のジャングルなのである。この残酷さが分かるだろうか。
たとえば、眞人が青鷺に導かれ、母の姿を示される場面がある。
眞人は顔を確認する。それが本当に母だと分かったときの感動は、どんなに素晴らしいものだったであろう。そして、それが本物の母ではなく、ただの模型だと知ったときの心情は、どんなに複雑なものだったであろう。
眞人はすぐに種明かしを受けたので、まだ幸せである。まだ信じ切らないうちに、偽物だと分かったからである。もし偽物であるということが観客のみに知らされていたとして、作中の眞人があれを本当の母だと思い込み、無邪気に飛び上がって喜び、最後まで信じて心の支えとしていたとしたら、我々観客は要所要所で眞人の幸せそうな顔を見るたびに、その残酷性を意識せざるを得なかっただろう。
作中のインコはみな生きる場所を追い求め、苦しんでいる。眞人にとって本当の母を思う心が切実であるように、インコにとっては本当の自然を思う心が切実なのである。現実世界の自然(非人工)を知る観客として、塔の中の庭園を天国と思って感動するインコの無邪気な姿、純粋な心をおもうと、あの場面が非常に残酷に見えてくる。
次回(似た作品についての連想)
今作と似ていると思った既存の作品について述べていく。
『不思議の国のアリス』『草枕』『MOTHER2』を挙げる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
