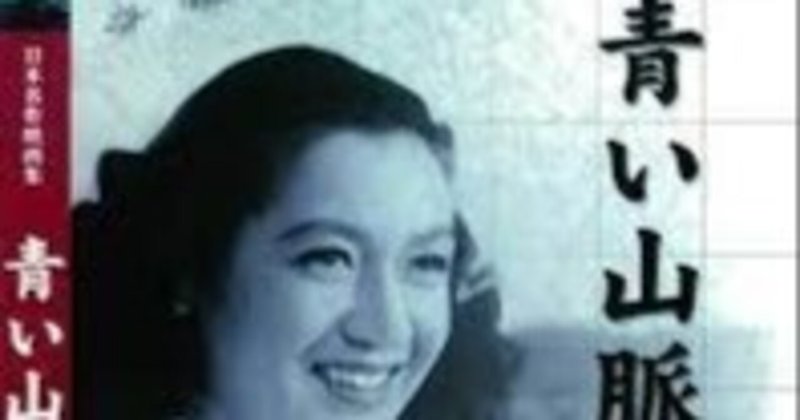
「青い山脈」(1949)が名作とされてるのはおかしくないか論
バンコクから帰国しまして一週間が経過しました。
仕事は基本リモートなのに職場へのコミットを求められるレベルが半端なく、週末はグッタリしています。
リーマン人生の出口戦略が急務で、色々とアイデアを漁ってます。
正月に現地で高熱で寝込んでからいまだに咳が残っており、日々良くなってはいるのですが、治りが遅いのも気になります。
これコロナだったかもしれないですね・・泣
帰国してから、念願の映画生活に復帰。
40年代の映画をひととおり見るのは去年で終わるはずだったのに、まだ数本課題作が残ってしまいました。
今週見た映画は下記3本。
・戦中の1943年に制作され政府に検閲されまくったらしい黒澤明のデビュー作「姿三四郎」
・1949年キネマ旬報ベスト10の第二位の「青い山脈」
・アマプラでベン・アフレック+マット・デイモンの「AIR」
「AIR」は80年代にパッとしなかったNIKEがマイケル・ジョーダンと提携してエア・ジョーダンを開発し、大儲けするまでの経緯を描いた内容。
面白くなくはなかったんですが、敢えてマイケル・ジョーダン役を映さない演出も微妙でしたし、よくあるドキュメンタリー映画の手法の枠から出ない凡庸さが気になりました。
ベン・アフレックとマット・デイモンの共演で言うとかの有名な「グッドウィル・ハンティング」の画期性を思い出し、どうしても比較してしまうのが宿命というか、残念なポイントですね。
さて、本題の「青い山脈」ですが、久々にイライラしっぱなしの映画体験となってしまいました。
あらすじは、男女が人前でイチャコラしたことが学校で問題になり、その是非について延々と議論が展開されます。それを原節子演じる芯の強い教諭が庇う、という内容なのですが、この議論がくだらなすぎて、今の感覚で見ると、とてもついていけない。この映画の尺は3時間もあるのですが、本当に拷問のようでした。
男女間の恋愛でさえ自由にできない戦前の文化のことを「封建的」と呼ぶようなのですが、第二次世界大戦後の「民主化」により、ようやく開放的に恋愛ができるようになったと。その象徴がこの映画で、評価ポイントもそこにあるようです。
ただ、戦前の世界の映画を同時代で見ていくと分かるのですが、アメリカもヨーロッパも自由に恋愛ができない、という文化がいっさい見て取れない。
日本映画も、あまり恋愛を題材にしたものがなさそうです。恋愛映画に検閲が入っていたのかもしれませんが、ここまで恋愛自体がタブーとなっていたとは、逆に新鮮な発見でした。
「戦後の民主化」以前の日本の社会ってどんな感じだったんでしょうね。大人になり、そんなことに関心を持つ頃には祖父母もいなくなっており、知る術がないのが皮肉です。
上記の戦前日本社会の特異性には普遍性がなく、その特異な因習からの解放というテーマは全く共感を呼ばないものに筆者には思えます。あるいは、違ったアプローチであれば、まだ見れるものになるかもしれません。
前述のキネマ旬報のランキングはリアルタイムで選出されたものだとは思うのですが、今改めて選出するとすれば本作品はまったく引っ掛からない気がします。映画は時を経ても普遍的に理解されることが大事だと思っているので、その意味ではこの映画が成功しているとは思えないです。
「青い山脈」は何度もリメイクされた名作とされてるのですが、今後リメイクを検証していく価値があるか悩んでしまいます。
1949年のキネマ旬報ベストテンの1位は、これまた原節子主演の小津安二郎監督「晩春」です。
この作品も昨年鑑賞し、その名作ぶりは理解したつもりなのですが、「青い山脈」と同様の問題を抱えているように思えます。
原節子演じる20代後半の主人公は、愛する父の面倒を見ることに生き甲斐を感じており、嫁ぐ気持ちがサラサラない。それを問題視する父親は何とか娘を結婚をさせようと奮闘し、親離れを促す、という内容です。
父親を恋愛対象であるかのように振る舞う娘の価値観も理解しがたいものなのですが、その娘が20代後半なことを理由に無理矢理嫁がせるようとする父親像というのも、まったく共感できませんでした。
筆者の存命な母親が、結婚することが人生の至上命題のような価値観を押し付けてくることにそもそも嫌悪感があるので、個人的に反発してしまうのかもしれませんが、このような価値観ってメチャクチャ独特に思えます。
神道なのか、仏教なのか、儒教なのか、どこからくる価値観なのか、今後の考察対象にしたいと思っています。
最近の旧統一教会と特定政党の癒着もそうですが、戦後の「民主化」以前の価値観や、そこに戻ろうとする勢力って本当に気持ち悪いな、と思ってしまいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
