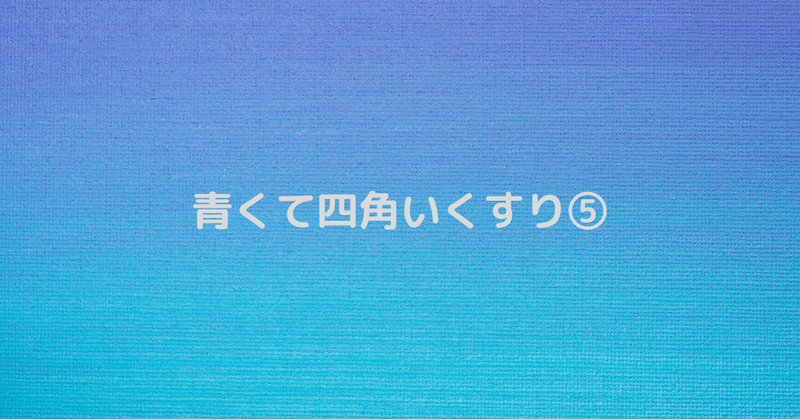
青くて四角いくすり⑤
ほんとうにハンバーグを作ってくるか試してみよう。
そんな気分にさせられて、また、夏菜子に会いに行った。
夏菜子は開口一番、
「ごめん、ハンバーグ無理だった。これで許して」
と、小さな花柄の紙袋を、私の目の前に差し出した。
中を覗いてみると、小さなカップケーキが5つ、アルミ箔に包まれて、こちらに顔を向けている。
「食べてみて」
夏菜子は、私がどんな反応をするか興味深げに見つめている。
アルミ箔を少しめくって、一口かじってみると、ほのかにミルクの風味を感じたが、少しパサついているのが気になった。
「おいしい?」
夏菜子は、無理にでも、おいしいと言わせたいらしい。
「おいしいよ。さすが、夏菜ちゃん。お菓子が作り上手だね」
と、笑顔で答えると、アルミ箔を全開にして、おむすびをかじるように、がぶり、がぶりと平らげてみせた。
また、いつもと同じことを済ませた。
二人で天井を眺めていると、夏菜子から話しかけてきた。
「私ね、奨学金もらって、大学に行ってるの。親は二人とも高卒なんだけど、どうしても大学に行ってみたかったんだ。こう見えても、高校の成績はよかったんだよ。大学に行って、下宿もしてみたかった。でもね、奨学金もらっただけじゃ、お金足りないの。親に下宿代を少しは負担してもらってるんだけれど、食費や服にもお金がいるし、親にこれ以上迷惑かけられないから、たくさんバイトしてきたんだ。でも、もう疲れちゃった」
夏菜子はすべてを言い終えると、小さくため息をついた。
「そうなんだ」
私は、ぽつりと呟くと、自分の学生時代のことを思い出していた。
家に金がなく、奨学金をもらって大学に行ったものの、周りの学生が遊び呆けているのを横目に、バイトばかりで明け暮れた学生時代。
夏菜子も昔の私と同じ境遇にいて、つらい目にあってるのだと思うと、急に抱きしめてやりたくなった。
すると、それより早く、夏菜子が私の手を握りしめてきた。私は、応えるようにさらに強く夏菜子の手を握りかえした。
夏菜子は、振り切ったような明るい声で、
「私、居酒屋でバイトしてるんだ。このバイトはね、ずっと続けているの。こういうお仕事してるけど、普通にバイトしてるんだよ。夏菜子の居酒屋さん姿、見てみたいでしょう。今度、お客さんで来てみてよ」
と、彼女が勤める駅前の居酒屋に誘ってくれた。
鉄道が複雑に交錯するこのターミナル駅の周りには、ホテルや百貨店、オフィスビルなどの高層建築が建ち並ぶ。
付近には、高級クラブや料亭が林立する歓楽街があるのだが、夏菜子が働く居酒屋は、そこから程遠い私鉄の高架下を利用した飲み屋街の一角にある。
こんな居酒屋に一人で来るのは何年ぶりだろう。同僚や部下と、たまに居酒屋でひと息つくことはあったが、一人で飲みに出るとなると、何だか落ちぶれた感じがして嫌だった。
でも、課長職を解かれた今となっては、お似合いかもしれないなと思いながら、お店の古びた暖簾をめくると、店の内は白熱球に照らされて、温かみを帯びた光に包まれていた。
手前に3席、奥に7席のカウンターと、通路を挟んで反対側には、6卓のテーブル席がある。
場所柄か、サラリーマン風の客が多いようだ。スーツを脱ぎ、ネクタイを弛めて、枝豆をつまんだり、焼き鳥にかじりついたりしながら、ジョッキを傾け、二人、三人で何かしら熱心に語り合っている。
私にも、こんな時代があったなと感慨に浸っていると、私を見つけた夏菜子が、客の合間をすり抜けて、私の前にやって来た。髪を後ろで束ねて、黒のTシャツとジーンズの上に、お店のハッピを羽織っている。
「いらっしゃいませ。お一人様ですか、こちらへどうぞ」
夏菜子は、マニュアルどおりの台詞を、元気いっぱい私に掛けると、無邪気に笑って見せた。
私は、夏菜子に、家の玄関で「お帰りなさい」と迎えられたように思った。なんと言っても、いま目の前にいる夏菜子が一番気に入った。この姿は一生脳裏に焼き付いて離れないと思う。
夏菜子は、カウンターの奥から2番目の席に私を案内すると、店の奥に入り、おしぼりとつきだしを持ってきた。
「何になさいますか」
居酒屋姿がすっかり板についた感じの夏菜子に見惚れていると、
「ここは、つくねが美味しいんだよ」
と、小声で教えてくれたので、
「とりあえず、生中とつくね、それにカンパチをお願い」
と注文した後、夏菜子にそっと「ありがとう」と目配せをした。
カウンターの奥では、ハッピにはちまき姿の大将が忙しそうに立ち回っている。
しばらくすると、夏菜子が料理を運んできた。
「ゆっくりしていってね」
という言葉を残して、夏菜子が立ち去ると、私は一人きりになってしまった。
仕方なく、まずは、ジョッキに口を付けた。
店の騒がしさの中で、一人、酒を飲んでいると、いろんな思いが頭をよぎる。
「学生時代に、夏菜子と出会ってたら。きっと、彼女に惚れ込んで、猛烈にアタックしただろう。」
まあ、結果は見えてる。でも、そんな恋に落ちることさえなかった寂しい学生時代だった。恋といえる恋をした覚えはない。
結婚は、会社に入ってだいぶ経ってから、叔父が薦めた見合い相手と、相性というよりも、双方待ったなしということで決まったものだった。だから、熱烈な恋というものをまったく知らないのだ。
そんな妻とも、今まで何とかやってきたのだが、愛情というものは、わからないままでいる。
そういえば、夏菜子が何気なく、
「奥さんと、一緒に寝てるの?」
と、聞いたことがある。
「昔は、娘を真ん中に寝かせて川の字になって寝てたけど、今は、妻がくまのぬいぐるみを抱っこして寝ているよ」
と、答えたら、
「くまちゃんに代わってもらって、奥さんを抱っこしなくちゃ」
と、笑ってたのを思い出した。
そんなことを思い出しながら、酒を進めていると、不意に、夏菜子がやってきて、
「ほい、何考えてたの。お酒まだ進んでないよ」
と、テンポよく話しかけてきた。
「あんまり強い方じゃないんだ」
と、ジョッキを回しながら答えると、
「そう、ほどほどにね。これ、私からのサービス、熱々だから気を付けてね」
といって、鉄皿に乗った豆腐ハンバーグを置いていった。
(つづく)
サポート代は、くまのハルコが大好きなあんぱんを買うために使わせていただきます。
