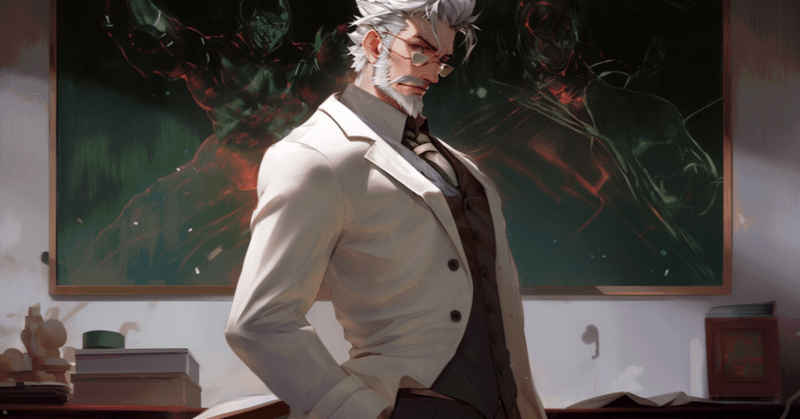
総論01 ベンゾジアゼピン離脱症状
ベンゾジアゼピンの離脱症状について定義しておきましょう。
毎日服用していたベンゾジアゼピン系の睡眠薬を中止したら眠れなくなった。
これは、必ずしも離脱症状ではありません。
睡眠薬ですから、不眠に対して処方されていたはずです。睡眠薬は対症療法に過ぎませんから、服用を中止すれば、服用開始前と同レベルの不眠が現われます。これを離脱症状とは呼びません。
服薬中止によって、服薬開始前よりも強い不眠が現われることもあります。これは反跳性不眠(リバウンド)と呼ばれ、狭義の離脱症状とは解釈されません。
一部でベンゾジアゼピン減断薬のバイブル視され、しばしば参照される「アシュトン・マニュアル」では、易刺激性や知覚刺激といった精神症状、筋肉の凝りやめまいといった身体症状がベンゾジアゼピン離脱症状として挙げられています。
アシュトン・マニュアルにリストアップされている離脱症状は多種多様に及びます。それは恐らくベンゾジアゼピンが脳内で直接的・間接的に多種多様な神経系・神経伝達物質に影響を及ぼす薬物であることの裏返しだと言えるでしょう。
ベンゾジアゼピンは脳内のGABA(γ-アミノ酪酸)作動性神経のGABA受容体上のベンゾジアゼピン受容体に結合することでその効果を発揮します。GABA作動性神経は脳内の他の神経系を鎮静する方向に働きますが、ベンゾジアゼピンにはこのGABA作動性神経の働きを増強する作用があります。それにより、催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用といった多彩な効果が発現します。
ベンゾジアゼピンの服用によって脳に広範な機能的変化が起こるわけですが、これが長期に渡ると、脳はホメオスターシスを保つべく、脳神経細胞の可塑性を発揮して、その変化を均衡しようとします。例えばGABA受容体のダウンレギュレーションが起こる。ベンゾジアゼピンの助けで過活動を起こすようになったGABA受容体の数を減らすことで、GABA作動性神経全体の興奮を抑えようとするのです。
脳内では神経伝達物質による伝言ゲームによって情報伝達が行われています。GABA作動性神経からの「伝言」を受け取っている多くの神経系でも、二次的に変化が起こりえます。その変化は、ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、グルタミン酸作動性の神経系に及ぶと考えられており、その変化はさらに、これらの神経系とシナプスを形成するニューロンにも影響を及ぼします。
ベンゾジアゼピンが起こす機能的な変化を、脳はニューロンに微小な器質的変化を起こすことで代償します。ベンゾジアゼピンは服用を中止すれば比較的速やかに脳内から消失しますが、ベンゾジアゼピンが消失したからといって、脳の器質的変化はすぐには元に戻りません。コンスタントにベンゾジアゼピンが取り込まれる前提で均衡が保たれるように変化をきたした脳が、ベンゾジアゼピンというハシゴを外されることで複数箇所で連鎖的にバランスを崩す――これが離脱症状です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
