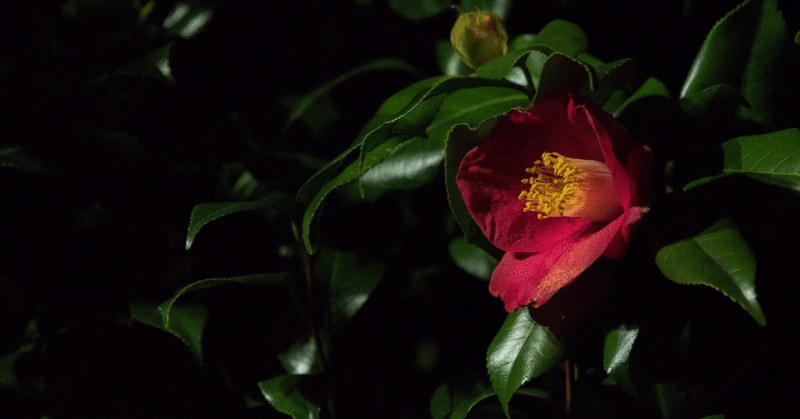
令和源氏物語 宇治の恋華 第百四十八話
第百四十八話 浮舟(十二)
探し続けた浮舟がすぐそこにあると思うと匂宮の心はもう抑えることは出来なくなっておりました。
姫のおられる部屋の格子をほとほとと叩くと、目を覚ました右近の君が誰何する。
「どなたでございましょう」
「右近か、私だ」
声を低く抑えて薫に似せることなどはこの宮にとって造作もない。
右近はてっきり薫が忍びで訪れたと思い込んで急いで格子を開け、すぐに灯を差そうとするのを宮は言葉巧みに遮りました。
「実は山で狼藉に遭ってしまった。見苦しい形をしているので灯は点してくれるなよ。そっと浮舟の元へ案内しておくれ」
「まぁ、そんなことが。かしこまりました」
漆黒の闇にほんのりと高雅な香が漂うのをやはり薫と疑わぬ右近は言われた通りに匂宮を女主人の元へと導いてしまったのです。
夢うつつの状態で物音に気付いた浮舟は薫が訪れたのかと身を起こすと強い男の腕に抱かれてそのまま唇を塞がれました。
これは、薫君ではない。
そう気付くと力の限り逃れようともがきましたが、か弱い女人ではどうにもなりません。
「やっとあなたとお会いできた。片時も忘れたことはなかったよ」
その囁く声に浮舟はそれが姉の夫であると悟ったのです。
「どうかお赦しくださいまし」
誰も見咎めぬ闇の中では匂宮の情熱を留める術はありません。
耳元で愛を囁く言葉は熱を帯び、初心な姫はそれだけで頭の芯が溶けてゆくようにぼうっとのぼせてしまいます。
心の中で薫に助けを求めながら男の為すが儘になるしかないのでした。
情事の後の女人の汗ばんだ肌の香りはどのような香にもかなわぬ。
ましてや背徳の添うたものほど魅惑的で甘美なものはない。
「あなたは私の物だ」
恋しい姫は首筋に口づけるも死んだように身動きもせず、ただただ涙を流すばかりで宮を振り返ることはありません。
「その涙は薫の為に流しているものか。憎らしいことよ」
そうして宮はまた浮舟を抱きしめる。
浮舟は薫に対する申し訳なさと姉に対する罪悪感にまみれて呆然と突然降りかかってきたこの事態を把握できず、せめて夢であればと願わずにはいられません。
「あなたの為に危険を顧みず山を分け入ってやって来たのにだんまりとは情けない」
念願を果たした男は満ち足りて女の心裡を斟酌できなるはずもなく、すでに我が物としたからには遠慮も無い。あまりにも一方的でそこには愛し愛されるという本来の形が欠如してしまっているのです。
なんとも情けないことよ、と浮舟はまた涙を流しました。
「ねぇ、これは運命であったとは思いませんか。物語などでもあるでしょう。どんなに互いを恋い慕っている男女でも宿縁が無ければ結ばれぬということもあるし、まさかと思われるような二人が結ばれたりと。私達が出逢ったのは前世の宿世としか考えられないのですよ。もう朝が来てしまうとは恨めしい」
落ち着きを取り戻した宮は浮舟の絹のようになめらかな肌に指を滑らせながら優しく囁きました。
ですが女の耳にはいまだに男の声は届きません。
萎れたようにうつむく横顔が艶めかしく、そんな姿がことさらに可憐に思われてこの人と離れたくないという気持ちばかりが込み上げる。
浮舟はたしかに美しい姫ではありますが、中君の気品の前では物足りず、左大臣の六の姫の華やかな美貌を前にすれば色褪せて見えることでしょう。しかしながら険しい山を越えて遥々やって来た達成感と異界の如き宇治という遮蔽された空間では、夢うつつの心地で浮舟を眺める宮の目を塞ぐのです。
姫があまりにも恋しくてなまじ逢わぬ方がこれほどの物思いを味あわずに済んだやもしれぬ、と考えるだけでも宮の目からは涙が流れるのです。
はたり、はたりとこぼれる涙に女は男が泣いているのだと気付きました。
「なぜお泣きになっていらっしゃるのですか?」
「あなたと離れるのが辛いのだ。私は身分がらそうそう気軽に出歩くことは許されない。しかしあなたと逢えぬでは恋死にしてしまいそうだよ」
恋しいあまりに死んでしまう、などという甘い言葉はあの生真面目な薫ならばけして口にはしない言葉でしょう。
浮舟はこの時初めて匂宮をしっかりと見ました。
端正に整った美青年が自分を恋するがゆえに涙を流す姿は胸が締め付けられるようにせつなくも甘やかなときめきを覚え、浮舟は頬を赤らめました。
「きっと京では私の行方が知れぬと大騒ぎになっているであろう。だが、このままあなたと離れることはできまい」
そうして受ける接吻は情熱的で優しく、先刻まで憎いとばかりに思っていた女の心は妖しく揺れ動くのです。
匂宮はやはりこのまま今日はここで過ごそうと右近の君を近くへ呼びました。
浮舟の側にいるのがてっきり薫だとばかり思っていた右近は顔も隠さずにしどけない姿でくつろぐ匂宮の姿を見て愕然としたことは言うまでもありません。
なんということをしでかしてしまったのだろう。
浮舟さまは傷ついていられるに違いない。
ようよう確認もしなかった自分の落ち度であると右近は顔を青くして己を責めました。
「右近、謀って申し訳なかった。私は二条院で会ってからやはりこの人が諦めきれずにずっと探し回っていたのだよ。この人を見つけるまではと妄執に駆られて亡霊のように生きてはいなかったといってもいい。ようやく今生き返ったところなのだ。無分別といわれても今日このまま帰ることなどできまいよ」
右近は勝手な言い分にあきれ果てて呆然と物も考えられませんでしたが、今更嘆いても起こってしまったことは詮無きことと、ここで事を大きくしても姫の御為にもならず宮へも失礼にあたると気を鎮めました。
こうしたことはまさに宿縁としか言いようがなく、これも浮舟君の逃れられぬ運命で、誰が悪いわけではあるまい、と思われるのです。
「本日は姫の母君から迎えが参ります。この期に及んでは宿世ととやかく申し上げることは致しませんが、折が悪うございます。今日のところはお戻りいただき、御志があればまた日を改めてごゆるりと」
なんとか宮を追い払おうとする右近の分別くさい言い分を宮は鼻であしらいました。
「無粋なことを言うではないか、右近よ。お前も一人前の女ならば恋心を知らぬわけではあるまいに。母君には物忌みだとでも言えば済む。それよりも身分を顧みず山を踏み分けてきた私の気持ちをわかっておくれ。何と言われてもここからは動かぬよ」
姫君が恥ずかしさにうつ伏せる姿も痛ましく、右近の君は、大変なことになった、と頭を抱えました。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
