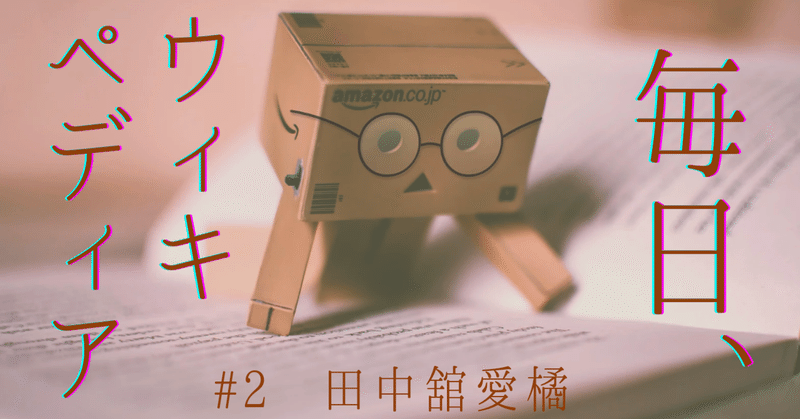
毎日、Wikipedia #2「田中舘 愛橘」
みなさんこんにちは、結城です。
「毎日、Wikipedia」2日目の今回は、田中舘愛橘(※敬称略)についての項目を読んでみました。念のために言っておくと人名です。
え、なにこれ?という初めての方は以下の記事をお読みください。
この人の名前、いったい何て読むの?という単純な興味から読み始めましたが、様々なことを行った偉大な人物だということがわかりました。
それではまとめていきます!
「聞かれた相手に直ちに答えようと思ったら、テニヲハなどにかまっておられるか。今やらなければ殺されると思え」
「地球には2つの衛星がある。1つはもちろん月であるが、もう1つは日本の田中舘博士である。彼は毎年1回地球を回ってやってくるのだ」
田中舘愛橘とは
読み方は「たなかだて あいきつ」です。隠館厄介みたいな感じでしょうか。
愛橘というあまり聞き慣れない名前は、中国で元の時代に編纂された「二十四孝」という書物内の故事が由来です。
生きていたのは1856〜1952年なので、日米和親条約からサンフランシスコ平和条約くらいまでを過ごしたということになります。
行年がなんと95歳。スリランカ人もびっくりの長生きっぷりですね。
職業は地球物理学者ですが、地球物理学に収まらないほどの功績を残しています。
今回はその中でも主な4つの功績を紹介しようと思います。
1.日本式ローマ字の考案
東京大学に通っていた頃、愛橘はヘボン式ローマ字の表記法に疑問を持つようになります。
そして1885年(32歳)、五十音表に基づいた日本式つづりを対案として学会に提出し、「日本式ローマ字」と名付けられました。
ここからがヘボン式と日本式の対立の始まりです。
愛橘はその後も日本式ローマ字の普及活動を続け、さらに日本語をローマ字で表記するべきだというローマ字論を唱えました。konnakanjidesyōka?
そんな中の1937年(81歳)、政府はヘボン式と日本式の2つを合体させた「訓令式」のローマ字を採用するという令を出します(ローマ字論はもちろん採用せず)。
ローマ字に関する問題はとりあえずここで一段落ついたように思われましたが、戦後になるとGHQのマッカーサーの命令によってヘボン式が復活して使われることになりました。
2.根尾谷断層の発見
根尾谷断層は日本最大の地震断層です。
時は1891年(35歳)、マグニチュード8.0もの日本最大の直下型地震、濃尾地震が濃尾地方で発生します。
大学の命令で調査に向かった愛橘は、岐阜県にある根尾谷断層を発見。世界に発表し、大反響を巻き起こしました。
弱冠35歳にも関わらず凄い功績ですね。
3.日本におけるメートル法の推進
1907年(51歳)、国際度量衡委員会に日本が加盟し、最初のアジア代表常設委員に愛橘が任命されます。
その頃の日本では尺貫法が使われていてメートル法がメジャーではありませんでしたが、1921年(65歳)に議会で度量衡法の改正法案が通過し、メートル法が基本の単位となります。
これも愛橘の啓蒙的な講演活動の賜物です。
ただ一部では尺貫法が使われ続けていたようで、完全な施行は1959年(没後)となっています。
4.東京大学航空研究所の創設
1918年(62歳)、東京大学航空研究所が作られ、愛橘は顧問に就任して航空研究をしていきます。本当に生涯現役のような人ですね。
第一次世界大戦が起こり、航空機が戦争に使えるとわかると、政府の支援もあって施設が拡充されました。
またその頃に皇族が相次いで研究所に訪れていたことからも、国家から期待をされていたことがわかります。
おわりに
以上が4つの功績でした。
田中舘愛橘、生涯に渡って多彩な活躍をされていて本当に凄いと思います。
それでは、最後まで読んでくれた皆さん、ありがとうございました!
あなたのお金で募金をします
