
私がどうしても海外勤務にこだわる3つの理由
将来、海外で仕事をしてみたいけど、治安が不安だしホームシックになりそうだなぁ。
でも、若いうちに海外勤務を経験しておいたら役に立つんじゃないかなぁ。
他に海外で働きたい人ってどのような理由で海外で働きたいんだろう。
今回はこのような疑問にお答えいたします。
みなさんは海外で働くことにどのようなイメージをお持ちでしょうか。
治安が心配。ホームシックになりそう。など様々なイメージを持っているはずです。
私も治安に関しては不安ですが、それでも海外で働くことにこだわる理由があります。
純粋に、海外という場所が好きで憧れを持っているというのも1つの理由ですが、それだけではありません。
私の場合は、海外勤務自体にこだわっているのではなく、海外において外国人をマネジメントすることにこだわっています。
英語が使いたいなら日本でも使える仕事に就けば良いのでは?と思われるかもしれませんが、それだけの理由ではありません。
今回は、私がなぜ海外勤務にこだわるのかについて詳しくご説明いたします。
※こちらの記事を書いたころ(こちらの記事はもともとブログに記載していたものをnoteに転載しました)はまだ日本にいましたが、現在は海外のITベンチャー企業でCOOとして従事しています。同時に日本で起業をして、インバウンド向けの事業の立ち上げも同時に行なっています。こういった経験も踏まえて、こちらの記事を追記していきます。
上記に記載してあるマネジメント部分に関しては、実際に海外でマネジメントを体感した上での学びを以下の記事で記載しているので、ぜひ海外で働くことに興味がある方は参考にしてみてください。
>>「マネジメント」とは何かを考察した結果、得た気づきをまとめてみた
海外勤務にこだわる理由
私が海外勤務にこだわる理由は、大きく分けると下記の3つあります。
海外勤務にこだわる理由
1. 外国人をマネジメントするため
2. ビジネスレベルで英語を習得するため
3. 環境適応能力を身につけるため
外国人をマネジメントすることと、ビジネスレベルで英語を習得することは関連性がありますが、私は両者を切り分けて考えています。
それでは、1つ1つご説明いたします。
海外勤務を希望する理由は外国人をマネジメントするため
外国人をマネジメントしたいのであれば、日本の会社でも出来ると思います。
確かに、”外国人をマネジメント”という言葉を聞くと日本でも出来そうですが、それは私が求めていることとは少し違います。
日本で外国人をマネジメントすることと海外で外国人をマネジメントすることでは以下の違いがあると考えています。
日本で外国人をマネジメントする場合
・日本の企業で働くので、外国人がマイノリティとなる
・つまり、外国人側が日本の企業に合わせた働き方・文化に適応する必要がある
海外で外国人をマネジメントする場合
・日本人が海外の企業で働くため、日本人がマイノリティとなる
・つまり、日本人側が相手国の文化・働き方に合ったマネジメントを提供する必要がある
最近では、ダイバーシティという考え方(以下引用参照)が広がっており、他国の文化と共存しようという動きが盛んになってきています。
ダイバーシティ
市場の要求の多様化に応じ、企業側も人種、性別、年齢、信仰などにこだわらずに多様な人材を生かし、最大限の能力を発揮させようという考え方。1990年代のアメリカで浸透し、旧日経連、日本経団連などで研究が重ねられていますが、一般にはいまだ単なる人材の多様化と理解されている場合が多いようです。
日本の人事部より引用
マネジメントの仕方も企業ごとに決めるものではなく、外国人の割合によって変わるマネジメントになり、よりパーソナライズされたマネジメントが求められるようになるのではないかと考えています。
このパーソナライズされたマネジメントを作り出すことが、私が海外勤務を希望している理由の1つです。
海外勤務を希望する理由はビジネスレベルで英語を身につけるため
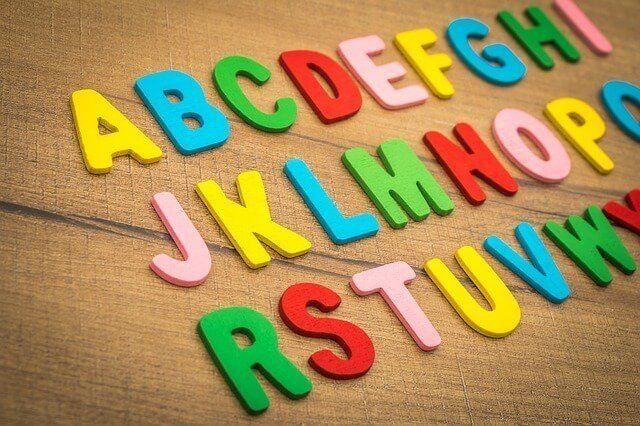
ご存知の通り、この世はどんどんグローバル化しています。
当たり前のようにどこでも英語が飛び交っており、日本の企業もビジネスを日本で完結することは難しくなって来ています。
グローバル化が進むにつれて、日本企業においても外国人が数多く働くようになって来ています。
社内公用語が英語である企業はまだ多くはありませんが、この先更に増えると考えられます。
それを考慮すると、その時に英語を身につければいいのでは?という考え方もあると思いますが、私自身はそれでは遅いと考えています。
社会人のみなさんなら、よく考えてみるとわかることですが、年配の方より若者の方が英語が出来る方は多いですよね。
若者の方が英語を話すことができる人が多いという事実は、ほとんどの企業で共通して言えることです。
これから10年後を考えみると、よりグローバル化が進み、もっと英語が出来る若者が会社に入って来ることになります。
それによって、〝英語が出来る〟こと自体に価値がなくなっていきます。
そのため、なるべく早く英語をビジネスレベルで習得することを目標としています。
確かに、ビジネスレベルの英語を身につけたいだけであれば、日本でも出来るかもしれません。
しかし、実際に海外で英語を使って仕事をすることと、日本で1人で英語を勉強することとでは習得度合いが変わってくると考えています。
使える英語を身につけるためには、現地で働いてみるのが1番早いのではないかと思います。
環境適応能力を身につけるため
環境適応能力は軽視されがちですが、私はとても重要なものであると捉えています。
留学をしたことがある方であれば共感していただけると思いますが、環境が変化するとストレスが溜まります。
企業に入社して海外勤務を希望した場合、発展途上国での駐在になる可能性が非常に高いです。
発展途上国は、まだまだ犯罪は多いですし、感染症などの危険もあります。
※私はフィリピンに1年ちょっと留学していたのですが、デング熱とアメーバ赤痢にかかりました。
様々なことに気を使いながら生活を続けるとストレスを感じてしまうのが人間です。
しかし、不思議なことに環境に慣れてしまうとストレスなくなっていきます。
住めば都という言葉があるように、ある程度長い間住んでいれば問題ありません。
仕事でのストレスを抱えながら環境にも適応するという経験は今までないので、海外勤務を通して適応能力を身につけられればと考えています。
番外編:社会人と学生のリーダーシップは別物

この記事を通して学生の方に伝えたいことがあります。
それは、リーダーシップについてです。
リーダーシップがある人間が日本企業には求められますが、学生時代のリーダーシップは社会人で求められるリーダーシップとは別物ではないかと考えられます。
それぞれのリーダーシップに関して説明すると以下のような違いがあります。
学生時代のリーダーシップ
・学生時代のリーダーシップとは、とにかく率先して先導を突き進んでいくタイプ。みんな仲良くゴールすることを最終目的と捉えるリーダー
・登山に例えるところの、全員が仲良く手を繋いで辛いことを乗り越えることを目的とするリーダー
社会人で求められるリーダーシップ
・社会人のリーダーシップとは、時に誰かを切り捨ててでも、最終目的地にたどり着くことを目的とするリーダー
・登山で例えるところの、登山中に誰かが怪我をしたら、その人を置いてけぼりにしてでも頂上までたどり着こうとするリーダー
私たちからみたら前者のリーダーの方がありがたいです。
ですが、社会では後者のリーダーの存在が求められています。
日本において、終身雇用制度が破綻しようとしている現在、みんな仲良く定年まで仕事をしよう。とはいかなくなってきているからです。
リーダーシップの身につけ方
そのリーダーシップはどうやって得るのかと考えたところ、海外でのマネジメント経験という答えにたどり着きました。
海外ではとにかく結果が全てと考える人間がたくさんいます。
すなわち、結果が出ないやつは置いていくぜ!と思ってる人々をマネジメントするのは並大抵なことではないと思います。
こういう人々を束ねる経験は今現在、日本ではなかなか出来ません。
日本でも将来的には結果主義が拡がっていくことを見越して、早めにそういう人々を束ねることができる力をつけておきたいなと感じています。
英語も使えてマネジメント力も上がって一石二鳥ですね。
諸国の人々をマネジメントする経験は、日本ではチャンスが回ってくる可能性は海外勤務に比べて限りなく少ないです。
こういった理由により、海外で働くことにこだわりを持ち始めました。
もちろん、この考えが正しいか否かはわかりませんが、少なくとも損する結果にはならないのではないかなと考えています。
海外でマネジメントを経験してみた結果
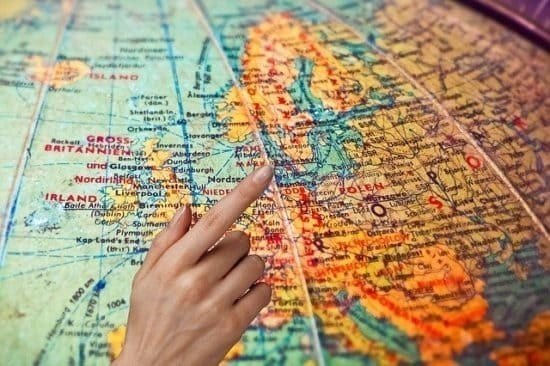
こちらの記事を書いた頃からは、だいぶ時が過ぎ、現在は海外でマネジメント業務に従事しています。
20代半ばで、30名程度の規模とはいえCOOというポジションをやらせていただいていることは非常に光栄に感じています。
まさにこの記事を書いた頃に描いていたキャリアプランを現在進行形で突き進んでいることになります。
もちろん、楽しいことばかりではなく、この立場だからこそ考えなければならないことも次々と襲いかかってきます。
こちらの記事では、以下2点について追記していきたいと考えています。
追記内容
・実際に海外で働いく前と後で何かしらのギャップがあったか?
・享受したメリットとデメリットは具体的にどのようなものか?
海外で働くとは?働く前と後のギャップは?
昔から海外で働くことに対する憧れは強く持っていました。
もちろん、現にこちらの記事を読んでいただいている方には、いかに私が海外で働きたがっていたかは感じてもらえているのではないかと思います。
とはいえ、実際に働く前とのギャップがなかったとは言い切れないので、働く前と後の印象を整理していきます。
海外で働く前と後のギャップ
海外で働く前に感じていたことは大きく分けると2つあります。
1 ある程度(TOEIC700点レベル)の英語力があれば問題なく働くことができる
2 ゴリゴリの成果主義で年齢は全く関係なく風通しの良い文化
1つ目に関しては、「全然そんなことはありません」というのが正直な感想です。
業種にもよるかもしれませんが、海外でマネジメント業務に従事したい方、IT系の会社に勤めたい方はTOEICレベルで最低900点レベルは持っておくことを推奨します。
※もしくは、その業界の知識を十分以上に保有している。
辛辣なことをいうかもしれませんが、コミュニケーションができなければプロジェクトの進捗も正しく把握することができませんし、細かいレベルの指示をすることができません。
特に今回のようにコロナウイルスの影響でリモートワークが強制されるような場合は、完全にオンラインかつ英語でやりとりをする必要性が出てきます。
よくある記事では、「TOEIC700点以上あれば海外で働けますよ」と書いてありますが、鵜呑みにしない方が良いです。
もし、これから海外で働きたいと考えている方は、いますぐに海外に飛び込んでも、英語を使ったコミュニケーションでは全く苦労しないレベルまでは上げてから行った方が良いでしょう。
留学期間も含めたら2年以上海外で過ごしている私ですら、未だに理解できないことが稀にあります。
もちろん、英語があれば良いということでもありません。
少なくとも英語を使えるということは、スタートラインに立っただけに過ぎません。
なぜなら、「あなたでなければいけない理由がない」からです。
それゆえ、
前職や自己学習によって得たスキルを使って、他の社員といかに差別化を図ることができるのか
という点が非常に重要になります。
そのためには、毎日欠かさず本を読んだり、新規ビジネスモデルに考えを巡らしたりする必要があります。
※どのような本を読めば良いのかわからないという方は、以下の記事にてオススメの本をご紹介しているので参考にしてみてください。
>>社会人が読むべき本をジャンル別でご紹介します!【本当に役に立つものだけ厳選】
次に
ゴリゴリの成果主義で年齢は全く関係なく風通しの良い文化かどうか
に関してですが、こちらは間違いなくその通りだと言えます。
基本的に海外にある企業だけあって、年功序列なんてものはなく、しっかりと成果を出せば評価してくれます。
現に私自身も日本ならまだ若手社員扱いですし…。
「言いたいことが言えない」なんてことは皆無です。
時には、バチバチすることもありますが、それはそれで楽しめるという方にはぜひ海外で働くことをオススメします。
日本にいる頃ではできないような体験が次から次へとできることは事実ですし、若いうちからチャンスを掴むことによって、今後の人生においてもプラスの影響を与えるということを声を大にして伝えたいです。
まとめ
今回は、私が海外勤務にこだわる理由に関してお伝えいたしました。
海外で働くことでしか手に入らない能力・気づきは必ずあると思っています。
大学生の頃に留学に行かなかったことを後悔している社会人の方は結構いるのではないでしょうか。
その後悔を海外勤務という形で取り戻せば良いのではないかなと思います。
最後まで読んでくださった方はありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
