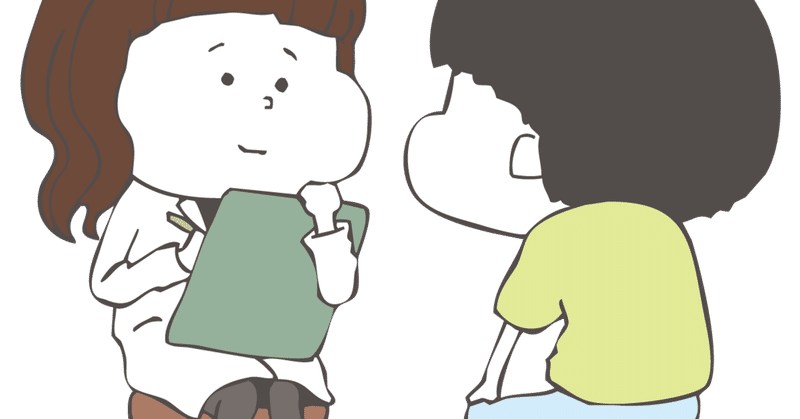
【心理学】カウンセリングとか心理療法って実際どんな感じなの?
それでは、仏教心理学どんどんやっていきましょー!
(^~^)
まず、心理学、カウンセリング、心理療法の基礎知識から整理します。その中で、仏教ととっても共通点の多い「論理療法」というものがどういうものか、浮き彫りにしますね。
使うテキストは、この本です。
もし自分がカウンセリングを受けたいと思ったらどうやって選ぶかを考えてみると良い
心理学、心理療法っていうのは、前回の記事で紹介した認知行動療法や、論理療法の他にもいっぱいあります。
有名な治療法だけでもこんなにあります。

カテゴリ一覧
なんだか、最初から目が回りそうですが、自分が心理カウンセリングをやってもらいたい、と考えた場合、医者、カウンセラーがどんなテクニックを持っているのかを、ウェブサイトなどで事前にチェックすることは必須になってきます。
つまり、一口に外食と言っても、イタリアン、フレンチ、和食、といろいろありますよね。自分は論理療法が良いと言っても、どこでもやっているわけではないのです。マインドフルネス療法をやって欲しいと言っても、マインドフルネスは名前は有名ですが、心理療法としてやっているところの方が少なかったります。
でも、食事であれば、イタリアン、フレンチ、和食とイメージが付きますが、心理療法は普段馴染みがないので、分かりませんよね。
そういう時はこれをまず判断基準にして絞ります。
心理療法はディレクティブとノンディレクティブに2分される
ここでこのシリーズのテキスト『唯識と心理療法』から引用してみます。
心理療法には、大きく分けて「非指示的(non-directive)」「指示的(directive)」ということばで表現される二つの大きな流れがあります。
分かりやすく言うと、セラピストがクライアントに対して、「ああしなさい、こうしなさい」とか、「あああるべきです、こうあるべきです」といったことを一切言わないのが、非指示的アプローチです。
それに対して、「こうした方がいいのではないですか」「ああしたほうがいいですよ」といったことを指示してくれるのが、まさに指示的なアプローチです。
そういう分類でいうと、仏教は、本来、法を解くものですから、もともと指示的です。
太字はみこちゃん
ちょっと専門的になってしまったので、図を使います。

カウンセリングは非指示的で、心理療法は指示的
「傾聴」ということばを聞いたことがあるかも知れません。傾聴というのは、とにかく、じっくりと悩みを持つ人の話を聞くやり方で、これが非指示的方法です。一般的にはカウンセリングというとこっちですね。
それに対して、もちろん傾聴から始まるのですが、話を聞いた後、「こうした方がいいのではないですか」と、方向性を与えるのが、指示的アプローチということになります。
前回の既読スルーの例で挙げた、認知行動療法も論理療法もこちら、指示的アプローチということになります。
非指示的アプローチで有名なのは、ロジャースの「来談者中心療法」というものです。
来談者中心療法では、「人はみんな、自らを成長させるための力を持っている」という考えを前提としています。来談者自身が自分の生き方について主体的に語り、真剣に向き合う中で、来談者は自らを成長させることができると考えます。
そのため、この療法は「非指示的な関与」を特徴とします。カウンセラーがクライエントに対してあれこれとアドバイスしたり、解決策を提示することはありません。カウンセラーは、悩みを抱える人の話を受容的に傾聴していきます。
そうして非指示的なかかわりを継続した結果として、必然的に、クライエント自身に洞察や気づきがもたらされるとしています。
太字はみこちゃん
このnoteでも取り上げている、マインドフルネスをベースとした心理療法、マインドフルネス療法も、非指示的ですね。
マインドフルネス瞑想の特徴は「いまこの瞬間」に意識を向け、知覚、思考、感情、行動を観察することに重点を置いています。これらの感覚をながめ、良い、悪いの価値判断をしないことを大事にするのです。
太字はみこちゃん
指示的アプローチは本やネット記事で自分でやることもできる
では、今この記事を読んでいるみなさんのように、いますぐカウンセリングを受けにどこか駅前のクリニックなどに行きたい、というわけではなく、興味がある、自分でも試しにやってみたい、というひとはどっちがいいのでしょうか。
それは、当然、指示的アプローチになります。
なんでかというと、非指示的アプローチは、とにかく聞いてもらうことがメインですから、聞いてくれる人がいないとそもそも話にならないからです。
指示的アプローチの場合には、本やネット記事に質問事項が書いてあって、それを自分の頭で考えたり、ことばにしてノートに書き出したりします。そして、こういう場合だったら、とうことで、ケースに当てはまりそうな著者の言葉を拾って自分に当てはめて考えてみるということができるわけですね。
というわけで、認知行動療法には、題名にズバリ『自分でできる認知行動療法 うつ・パニック症・強迫症のやさしい治し方 ココロの健康シリーズ 』といったように、「自分でできる」と書いてある書籍もあるわけです。
"自分でできる論理療法"という題名の本はなさそうだ
そこで、アマゾンで自分でできる論理療法というズバリの本はないかなと探したのですが、とりあえずありませんでした。
でも、論理療法も指示的アプローチですので、自分でできる本にできないことはないのです。
多分、認知行動療法よりも多少難しいからでしょう。
でも、大丈夫。
次回より、みこちゃんがテキストを中心にいくつかの参考書を読みながら、自分でもできるやり方で、さらに「論理療法」の中身を解説してきます。
お楽しみに(^-^)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
