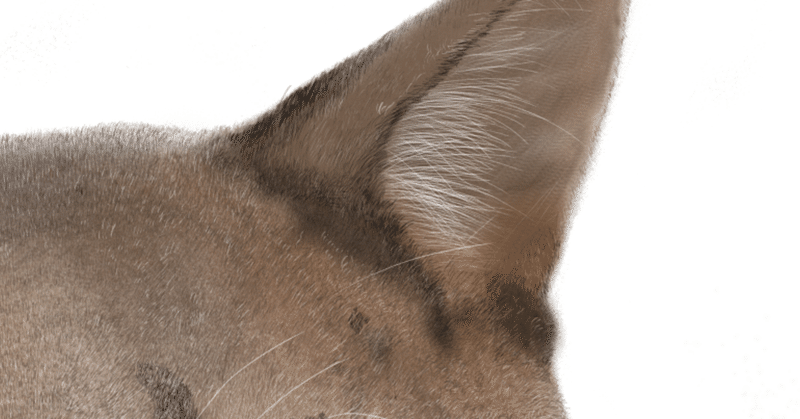
【短編小説】 幸せを願う
タクシーをヒッチハイクしたら、止まる。止まるし乗せる。でも金を取る。
その当たり前のシステムがいまいち理解できない面倒な客を乗せたのは、午後九時過ぎだった。今年も今日で終わりだというのに、奇妙な客を乗せてしまった不運を、少し呪った。
中肉中背中年。頭頂部では、砂漠のオアシスように一部だけ生い茂った髪の毛がゆさゆさと揺れて未練たらしい。真っ赤なジャケットを着たそんなおっさんが、
「なんで金払わなあかんねん!ちょっと乗せてもろうただけやないか!ヒッチハイク知らんのか!」
と喚いている。見苦しい。
俺は返事するのも馬鹿馬鹿しくなり、ただ黙ってそのおっさんを眺めた。
「いつからそない世知辛い世の中なったんや。俺の若い頃は困っとる人見たら助けたもんや。ええか、親切っちゅうもんはうちからにじみ出るもんなんや。誰の為でもない。強いて言うなら、自分の成長の為にするもんなんや。それを金取るてアンタ・・・」
おっさんは呆れたように俺を見ているが、呆れたいのは俺の方だ。
しばらく無言の問答が続いたあと、おっさんは深いため息をつき、呟いた。
「分かった。あんたがどういう人間か、よう分かったわ」
そう。タクシー運転手という人間だ。そして、分かって頂いたのなら料金二八四○円を支払って欲しい。
「分かった上で、頼みがある」
「なんですか」
「連れていってほしい所があんねん」
「お客さん、こっちも仕事ですし、お金払ってもらわないと」
「払う。払うがな。払うから頼むわ」
「今までの分もですよ」
「・・・・・・細かい男やな」
かなりおかしな客だが、年の瀬にこんな客を乗せるのも一興かもしれないと思った。どうせ年が明けても、憂鬱な日々の繰り返しなのだ。
車を走らせて十五分、目的地はまだまだ先のようだ。長距離の客は上客だが、本当に金は持っているのだろうか。
心配していると、ふいに、おっさんが口を開いた。
「わしな、座敷わらしやねん」
やっぱりやっかいな客だ。年の瀬に妖怪を自称するような輩が、まともな訳がない。酒の臭いもしないから、普段からこれなのだろう。「わしな、妖怪やねん」などと言って、おざなりにも対応してくれるのはキャバクラ嬢だけだ。
「ジブン、疑ってるやろ」
「そんなことないですよ」
「それ、絶対疑ってる目ェやん」
疑ってはいないが、確信はしている。妖怪ではなく、ただの変人だ。ある意味、妖怪よりも質の悪いやつだ。
「まあ、ええわ」
このまま妖怪話を続けられてもたまらないので、俺は会話を変えることにした。
「で、どちらに行かれるんです?」
言われるまま車を進めてはいたが、俺は行く先を知らない。おっさんは前を見ながら答えた。
「ああ、うん。長嶋君の家や」
「そのお友達の家はどちらなんですか?」
すると、自称座敷わらしのおっさんは急にこちらを向いて、でかい声で言った。
「なんでわしが長嶋君と友達やねん!そう見えるっちゅうんかい!」
妙に嬉しそうだ。下手に刺激しても面倒臭いだけだろう。
「見える?なあ、そう見える?」
見えるもなにも、俺は長嶋君なる人を知らない。だが、とりあえずここは話を合わせておいた方がよさそうだ。
「まあ、見えますよ。それはもう」
「ほんまかい!ほんまに言うてるんかいな!」
おっさんは一人でなにやら照れたあと、俺を見て呟いた。
「まあな。わし、結構そういうとこあるねん」
もう相手にしないと決めた。
「でもお客さん、その方の住所を教えて頂かないと、お連れできませんが」
「住所はちょっと分からんねんけど、大丈夫。ここからやったら場所分かるから、口で言うわ。それでええ?」
「ええ、問題ないですよ」
「あと、着いたらちょっとだけ待っててほしいんやけど、そういうのも大丈夫?」
「そういうのも、大丈夫です」
「おおきに。おしるこ買うたるわ」
ちょっと欲しい。
「まあ、すぐ済むし」
年越しの挨拶だろうか。いや、このおっさんがそんな律儀なことをするわけがない。出会ってまだ数十分程度しか経っていないが、このおっさんが裏表など全くなさそうで傍若無人な人物であることはよく分かる。
それでも、客の用事に口出しするのはご法度だし、そもそも俺は他人に興味などない。俺は無言で車を進めた。
十分ほど進むと、おっさんが言った。
「ああ、そこ。そのアパート。あの二階の端っこんとこが長嶋君の家」
見ると、そこにはあまりキレイとは言えないアパートが立っている。年の瀬だからだろうか、ほとんどの部屋は明かりがついているが、長嶋くんの部屋の電気は消えている。留守だろうか。それとも、もう寝たのだろうか。
「おお、おらんな。寝てんのかな。ちょうどええ。入りやすいわ」
なんと、このおっさんは空き巣だったか。いくら他人に興味がない俺でも、さすがに空き巣の送り迎えをできる程の無関心ではない。それに、知っていて見逃すと警察に捕まりそうな気がする。
「ちょっとお客さん。それ空き巣じゃないですか」
「空き巣ちゃうよ、縁起でもない。ちょっと入るだけや。今チャンスやんか」
「それを空き巣って言うんです。警察呼びますよ」
暴れられるかと思ったが、おっさんは意外と冷静に答えた。
「どないな道理で、座敷わらしを警察に突き出すっちゅうねん」
「不法侵入です。道理じゃなくて法律です」
「わしが不法侵入やったら、にいちゃんは何やねん」
「通報者ですよ」
おっさんは、へへへと笑った。
「座敷わらしが玄関からこんにちは言うて入っていったら、そら筋通らんやろ」
他人の家にこっそり入っても歓迎されるのは、サンタクロースくらいのものである。そう言うと、「なんや自分、西洋かぶれか」と言われた。「日本人やったら日本のええとこ、もっとよう見たれや」とのことだ。そして「まあ、あのじいさんも大概日本びいきやけどな」と続けた。どうやらお知り合いのようだ。
おっさんはドアを開けて降りようとしたので、俺は慌てておっさんのジャケットの裾を引っ張った。おっさんは恨みがましそうな顔で俺を見た。
「いやほら、わし、座敷わらしやし?家に入り込んでなんぼやし?」
悪い顔をしている。
「ダメです」
するとおっさんはシートに腰を下ろした。
「頼むわ。行かせてくれや。あと一人、こいつだけは幸せにしなあかんねん。こいつだけは、幸せにならなあかんねん」
「幸せにしたいなら、せめて不法侵入はやめましょうよ」
「せやから!」
おっさんは語気を強めたが、すぐに俯き、呟いた。
「せやから、妖怪は、そういうもんやねん。いくら座敷わらしや言うても、人ひとり幸せにするんも影からやないとあかんのや。陰日向に支えるんが、わしらの矜持や。にいちゃんも、応援団やったら分かるやろ」
「俺、応援団じゃないですよ」
「ここは応援団やいうことにしときや。まあええわ。いくら矜持やいうても、堂々と行動できへんのは辛いもんや。な?応援団やったら分かるやろ?」
どうしても、俺を応援団にしたいようだ。
「応援団も、スタンドで堂々と応援していますよ」
「ええねん、応援団はどうでも。今そんな話してへん」
無茶苦茶なおっさんだ。
しかし、このおっさんが真剣だということはなんとなく感じ取った。妖怪を自称している頭のおかしいおっさんではあるが、人の人生を幸せにしたいという想いに嘘偽りはないようだ。しかしなんだか気持ち悪い。
「妖怪はな、今のご時世、堂々とは生きられへんのや。あんたには分からんやろうけどな。ただでさえ化学や技術や言うて、わしら妖怪のことなんか忘れてしもうてる。わしらは異形のもんや。そんなもんが堂々と出歩いてみい。どうなる?」
さきほど堂々と「わしな、座敷わらしやねん」などとのたまったのはどの口だ。
おっさんが、ポツリと言った。
「にいちゃん、ボクシングの長嶋康介て知らんか」
「長嶋くんて、ボクシングの長嶋康介なんですか?俺、ファンだったんですよ」
俺が好きだったボクシング選手だった。彼は昔、OPBF、つまり東洋太平洋チャンピオンだった男だ。
「ファンだった・・・か。まあええわ。知ってるんやったら話も早いわ」
おっさんによると、長嶋康介は幼い頃に両親を失い、祖母一人に育てられたらしい。貧しい家庭環境からいじめに遭い、強くなる為にボクシングを始めたのだという。持前のディフェンステクニックと強打を武器にKOの山を築き、デビュー戦から一度もダウンを喫することもなく、OPBF、つまり東洋太平洋のチャンピオンの座についた。
しかし、世界に最も近い男と期待されて挑んだ世界戦で、彼は全てを失った。最強の座をほしいままにしていたメキシコ人チャンピオンの前に手も足も出ず、三度のダウンを奪われ、七ラウンド終了のゴングと共にセコンドからタオルが投げられた。完敗だった。
勝負の世界だ。真っ向勝負で負けたのだから、仕方のないことかもしれない。しかし、長嶋を追い詰めたのは敗戦ではなかった。打ちひしがれて帰国した長嶋は、その日のうちに祖母の死を知った。心臓発作だったらしい。
それでもなんとか再起はしたのだが、どうやら拳を壊してしまっていたらしい。かつてのキレはなく、復帰二戦目で若いフィリピン人ボクサーにKO負けを喫すると、彼の周りからは人がいなくなったのだという。
「ひどいとか可愛そうとか言う権利、にいちゃんにはないよ。あんたさっき、ファンだった、言うたやろ。だったて、過去形で。にいちゃんも、長嶋くんが負けたら途端に消えた人間の一人なんや」
そうなのかもしれない。無名のボクサーにKO負けを喫し、テレビでも取り上げられなくなった長嶋から、俺もいつしか興味を失った。プロとはそういうものだとは言うが、去られる側の心情は想像したこともない。昨日まで仲間だ親友だと言っていた人たちが、急に掌を返していなくなる絶望感など、考えたこともない。どこか現実ではない、別の世界の物語だったかのように、みんな彼のことを忘れ去っていったのだ。俺も世間も、その後出てきた日本人世界チャンピオンに目移りし、長嶋のことは存在しないように扱ってしまっていた。
「まあ、結局、残ったのは飼うてる犬だけやったっちゅうこっちゃ。世間は冷たいもんやの」
おっさんはそう言うと、俺の顔を覗き込んだ。
「犬はええよ。まっすぐ芯通ってる飼い主なら、貧しかろうが何やろうが、裏切るような事はせえへんから。にいちゃん、飼うなら犬やで。オススメはレトリーバーや。下手したら人間より賢い。俺の次くらい」
おっさんは笑った。犬と比べて一歩リードなら、おっさんも大したことはないような気がする。
「とにかく、これだけ人に裏切られても愚痴も言わん。残ってくれたもんは犬でも精一杯面倒みる。精一杯、幸せにしようとする。そんな長嶋くんは、もっと幸せになってもいいと思わんか?」
怪しいおっさんだが、なんだか信じてもいいような気がしてきた。犬のことはよく分からないし、このおっさんが妖怪であることを信じることはできないが、しかしこのおっさんが他人の幸せを願い、他人の幸せの為に行動していることは間違いなさそうだ。行動は問題ありだが、善人なのだろう。
「なんで長嶋康介なんですか?」
「何がや」
「いや、大した疑問じゃないんですけど。確かに長嶋は負けた途端にみんなに手のひらを返され裏切られましたけど、犬を大事にするいい人かもしれないですけど、でも不幸な人はいっぱいいるんだし」
俺も含めて、と言いかけたが、なんとか言い止まった。このおっさんと話しているうち、俺には自分が不幸だと言う資格がないように思えた。不幸なのは、俺じゃない。
「わしな」
おっさんが言った。
「犬派やねん」
「それだけでなんですか」
「人の幸せを望むのに、大層な理由なんかいらんわい」
そう言うと、おっさんはガハハと笑った。
「じゃあ、犬を飼っていたら、座敷わらしが来てくれるんですか」
「猫派の座敷童もおるで。ちなみに人気動物ランキング三位は意外と牛やねん。びっくりやろ?せやからか、北海道が一番座敷わらしが多いねん。綺麗なとこやし、何食うてもうまいからなあ」
「座敷わらしって、そんなにいるんですか」
「まあな。全国座敷わらし連盟に加盟してるんは大体五百人ほどやけど、モグリもおる。まあ、違法やねんけどな。結構、罰金取られんねんで」
白タクみたいなものか。
「みんなに裏切られても愚痴も言わず、自分のもとに残ってくれた犬の幸せだけでも守ろうとしてんねや。犬好きとしては、なんとかしたい思うやろ」
結構適当なんだと思った。でも、確かに言う通りだ。幸せを願うのに、大層な理由がある方がおかしいのかもしれない。
その時、俺はふと口を開いた。
「ねえ、お客さん」
「ん?」
「俺、家に母親がいるんですよ」
どうしてだろうか。言葉は、意識の外からやってくるように、自然に口から出た。冷静に考えると、年の瀬に妖怪を自称して他人の家に乗り込もうとするこのおっさんは怪しいはずなのに、俺はこのおっさんなら自分の悩みを聞いてくれる気がしたのだ。
「おお、そうか。それやったらはよう家に帰ったらなあかんな。今日くらいはちゃっちゃと・・・・・・」
「家に帰るの、嫌なんですよ」
「・・・・・・なんでや。年の瀬に息子が母親のところに帰る。世の道理やろうがい」
「認知症で、しかも寝たきりで。もう五年になります」
「それやったら、余計にはよう帰らなあかんやろ」
「・・・・・・」
さっきから胸ポケットの中で震える携帯電話は、おそらく同居している姉からの電話だ。出ないわけにもいかなかったが、仕事中だからと自分に言い訳し、画面すら見ていない。
帰るのが怖い。毎日タクシーを運転し客を乗せ、家に帰ると息子の名前すら思い出せない寝たきりの母と、介護と仕事に疲れた姉がいる。毎日この繰り返しだ。この現実を見るのが嫌でたまらない。
逃げているのだ。それは分かっている。姉よりも多くの介護費を出していることを言い訳に、姉に介護を押し付けて、小さくなってゆく母親から目をそらし続けているのだ。父が病気で他界し、七十を過ぎて認知症が進んだ母を、俺は重荷に感じているのだ。
「それやったら、絶対に帰らないかんなあ。にいちゃんの事情はあんまり分かったれへんけどな、でも帰らないかんいうのは分かるわ」
俺は黙った。何を言うべきか、分からない。
「わしも妖怪や。寿命は人間の比やあらへん。せやからいろんな親子見てきたわ。もちろん、認知症の親持った子供もな。顔が分からん、名前が思い出せん。子供からしたらショックやろ。せやけど、いくら呆けても、一番大事なことは忘れられへん。頭やのうて、心のどっかで覚えとるもんなんや。お腹痛めて生んだ母親やったらなおさらやで。生んだことないから、そこらへんよう分からんけどな。でもたぶん、そうや」
そういえば母親は、俺が帰宅すると必ず体を起こしている。俺の名前もどうせ分からないのに、いちいち起きてきて面倒だと思っていたが、ひょっとして出迎えてくれていたのだろうか。唐突に昔の話をすることがある。脈絡がなく、うるさいと思っていたらが、ひょっとして子供たちが小さい頃を必死で思い出そうとしているのではないだろうか。姉は、気付いているのだろうか。
俺も、おそらく姉も、認知症の母親を重荷に感じている。子供たちの名前を忘れてしまった母親を、どこか他人行儀で眺めている。母親を、邪魔だと感じている。
見えていなかったのだ、何も。本当に辛いのは、子供の記憶を失っていく母親に違いないのだ。結局、俺はただの馬鹿な親不孝者で、自分の不幸など、つまらない思い込みに過ぎなかったのだ。
「とりあえずここはわしを信じたらええんや」
おっさんは言った。
「にいちゃんな、認知症のおかん持って、家帰ったら疲れ切った姉ちゃんおって、自分の人生は何やねんやろ、ええことなんか何もあらへんて思てるかもしれへんけどな、自分のことしか考えんようやったら、一生このままやで。姉ちゃんやおかんの幸せは何か、考えたことあるか?長嶋くんの人生はにいちゃんの生活には何も関係ない。せやけど、他人の幸せを願って、他人を幸せにしたい言うもんを信じてみ。自分の損得はなしにや。そっからやで」
きっとこのおっさんの言っていることは正しい。親の幸せさえ願えず、願うことさえ忘れ、それどころか自分の不幸のように思ってきた俺が、今さら他人の幸せを願ってもいいのか分からなかったが、おっさんの言うとおり、まずはここからなのだ。
「長嶋さん、幸せになれますか」
「だから、幸せにするて言うてるやないか」
おっさんは笑った。
「俺、母親を幸せにできますかね。今からでも、遅くないですかね」
「遅いことなんかあるかい。息子が自分の幸せを願ってくれる。それだけでも親は幸せなんや。あとは、精一杯やりや。一歩踏み出せたら、あとはホイホイ進めるわ。そういうもんや」
おっさんは、ガハハと豪快に笑い、俺の肩を叩いた。
「ほな、送ってくれてありがとうな。なんぼや?」
「いえ、あの・・・。六五七○円です」
すると、おっさんは三万円を俺に渡して言った。
「釣りはええ。その金でおふくろさんに何か買うて帰ったってや」
何と言えばいいのか分からず、俺はただ頭を下げた。それしかできない自分が、もどかしかった。
「ほなな。寄り道はええけど、家帰りや」
「ええ、そうします」
おっさんはタクシーのドアを開けて外に出た。
アパートに向かって歩き出すおっさんを、なんともなしに見ていると、アパートからコバルトブルーのコートを着た、派手なおばさんが出てきた。おっさんは片手を上げてそのおばさんに挨拶すると、俺のタクシーを指差した。車内の俺にまで聞こえる大きな声で「おおきに!」と言ったかと思うと、そのおばさんはそのままタクシーに乗り込んできた。
「あのおっちゃんとバトンタッチな。大丈夫、話はついてるし」
ひょっとして、座敷わらしのおっさんの友達だろうか。
「え?ああ、はい。どちらまで行きましょう」
「近くに、まだ開いてるデパートかなんかある?」
「ありますよ」
「じゃあそこ寄ってくれる?」
「かしこまりました。その後は?」
「にいちゃんのタクシー会社まで、かな。退勤の時間やろ?今日は絶対家帰らないかんねやろしな」
俺は驚いておばさんの顔を見た。いかにも関西風な風貌で、固定資産税を取られそうなほど顔がでかいこのおばさんは、俺の肩をバシバシと叩きながら、大きな声で言った。
「私も座敷わらしやねん。そんな感じするやろ?」
まったくそんな感じはしないが、なんとなく事情は飲み込めた。「母さん、か」と、おばさんには聞こえないように、口の中で呟いてみた。なんだか、初めて早く家に帰りたいと思った。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
