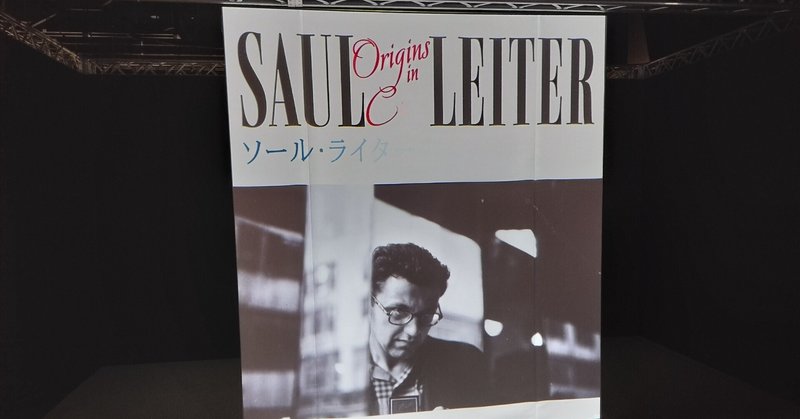
時折、見逃してしまうんだ。大切なことが、今、起きているという事実を。
今月もなにかと忙殺されてnoteが書けていない。noteは空き時間に勝手気ままに書いているから、それは仕方がない。しばらくあくとちょっとそわそわしてしまう。それが理由ではないのだけど、ネタにもなるしと気になっていた展覧会に足を運んだ。
その展覧会は「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」。
またまたソール・ライターが渋谷にやってきた。3年ぶり。ということはわたしのnote活動もそろそろ3年になるということだ。かなり初期(2本目)に書いたのが前回のソール・ライター展についてだったのを思い出した。
Bunkamuraが改修工事で長期休館中なので渋谷ヒカリエが会場になっている。9階のヒカリエホール。もともとここはイベント会場なので仮設感は否めないけど、最近の会場らしく巨大な展示空間がある。休館中の仮設会場ならではの佳処はあるはずだ。
◆
会期の残りがわずか数日だったからか結構な人混みだった。3年前の前回はコロナ禍で完全予約制だったこともあって、わりとゆったり観られた。今回はそうした制限もなかったのでちょっと落ち着かない。しかしここまでの人気だとは。とくに6年前の初回顧展を知っているとその違いには驚くばかり。それだけ人びとの心を惹きつけるなにかがソール・ライターの写真にはあるのだろう。
最近の展覧会らしく写真撮影が可能だった。しかもすべての展示が対象だった。常に誰かがシャッター音を鳴らしている。写真展のバックグラウンド音声としての演出を来場者に委ねたのかなんて思えるぐらい、シャッター音が聴こえ続ける。
ちょっと脱線するけど、展覧会での撮影には賛否両論がある。
わたしは展覧会の写真撮影には手放しで賛成ではない。来館者としての自分の経験を振り返ると、撮影に頼ってしまってしっかり観られないのではないかと思ってしまう。それに会場での撮影はガラスへの映りこみなんかがあって思うように撮影するのはむつかしい。撮影したところで見返すのはそれほど多くはなく、だいたい大量の写真に埋もれてしまって探し出すことすら億劫になる。
展示する側の立場を想像すると、撮影の可・不可を明示するために目障りなカメラマークを作品のすぐそばに置くことになる。これはまことに無粋で展示を白けさせてしまう(今回のソール・ライター展はすべて撮影可だから目障りなマークはなかったけど)。それにせっかくの図録販売の機会損失になる可能性があるんだから、撮影可にすることにはあまりメリットはないのではないか。
わたしのすぐ近くにいた客は、作品すべてに加えてキャプションから各章の導入文までことごとく撮影していた。よもや図録をつくるつもりなのかと思えるぐらいだった。その手間を考えれば、図録を買う方が写真の質も良いし読み物として得られる情報も多いのだから、馬鹿馬鹿しくなりそうなものだ。その人にはどういう目的があったのだろうと不思議だった。
作品の画像は図録のほうがクオリティが良いのは当然だし、展示風景を撮りたくても混み合っていればかならず他の来館者が写ってしまう。聴こえ続けるシャッター音を背景に、わたしは今回はなるべく撮影はしないでおいて図録を買おうと決めた。
◆◇◆
この展覧会は4部構成になっていた。
はじめの「ニューヨーク 1950–60年代」では、ソールが単身ニューヨークで写真を撮り始めたころの作品がならぶ。ストリートのスナップ写真ばかりの印象だ。ソールは歩きながらシャッターを切っていたのだろう、作品にはそんな臨場感がある。そう、ニューヨークは歩いて歩いて歩きまくる街なのだ。わたしもニューヨークに出張したおり、毎日やたらと歩いたのを思い出した。
ここでは抽象表現主義が台頭する当時の美術界について触れられていた。この章の後半では数々のポートレートが並んでいる。駆け出しのアンディ・ウォーホル(しかも母親とのツーショットまで!)やマルセル・デュシャン、ウィレム・デ・クーニング、写真家ではユージン・スミスやアンリ・カルティエ=ブレッソン(後ろ姿を隠し撮り!)、さらにはセロニアス・モンクなど 音楽分野の人物まで撮影していて、いやはやニューヨーク恐るべしという凄みを感じた。“アート”界がニューヨーク中心だったことがうかがい知れる。
◇
その次は「ソール・ライターとファッション写真」。
壁面と展示ケースを活用したファッション雑誌『ハーパーズ・バザー』の展示が圧巻だった。ソールの写真は編集者ヘンリー・ウルフとの縁で表紙と誌面を飾りはじめる。
当時はフィルムそのものが出版社にわたってしまって残されないことが多かったらしく、雑誌そのものやそのカラーコピーの展示が中心だった。ソール・ライターらしい不意打ちのような構図や鏡やガラスへの写り込みを多用した“キュビスム”作品が目立っている。
雑誌の紙面の芸術性は今よりもずっと高かった。この種のファッション雑誌は、つい映画『プラダを着た悪魔』を思い出してしまう。しかし、あの映画の世界の商業性よりもずっと誌面づくりの美意識が勝っていたのを感じた。50年代後半から60年代の米国文化は豊かだった。今のようにビジネス優位ではなかった。
◆
続いて「カラーの源泉—画家ソール・ライター」。
もちろんカラー写真もあるのだけど、このセクションの大半がソールの絵画作品だ。ボナールやヴュイヤールなどのナビ派の影響が説明されていた。ナビ派だけでなく、直前のポートレイトのセクションにあったウィレム・デ・クーニングを彷彿させる作品が並んでいる。以前のソール・ライター展ではおもに写真に絵の具で彩色を施したものが多かったので、絵画はあくまで写真作品の延長といった印象だった。今回は紙に描かれた絵画ばかりだった。
「絵画は創造であり、写真は発見だ」
との彼の言葉が紹介されていた。彼は写真家である以前に画家でありたかったらしい。たしかに過去の2回の回顧展でもそう説明されていたっけ。
展示作品にはさまざまな紙に不透明水彩などで描いたものが多かった。なかには紙に印字された文字が透けて見えるものがあり、わたしの悪い癖でつい解読を試みてしまう。先に書いたようになるべく撮影はしないつもりだったけど、後になって忘れてしまいそうだったので撮影しておいた作品がある。それが下の写真。

そこにはうっすらと「AWARD TO Saul Leiter」「FIRST HONORABLE MENTION」の文字列が見える。下部には「THE LIFE CONTEST FOR YOUNG PHOTOGRAPH(ERS)」と読める (カッコ内は推測)。おそらくソールが受賞した新人賞かなにかだ。その賞状を絵の具で塗りつぶしている。完全に塗りつぶすのではなく、その紙が何なのかが分かる程度にとどめている。これにはどうも意味がありそうだと深読みしてしまう。
展示解説には一言もそれに触れられていない。タイトルは《無題》。制作年不詳。要するになにもわかっていない。没後に発見された大量の未発表作品のひとつだろう。作者の意図がわからぬ以上どうにも解説しようがないというところか。
写真で発見し、絵画で創造するというソールの言葉を思い出す。写真の新人賞の賞状を塗りつぶしたこの絵画はなんとも象徴的ではないか。
◇
「カラーの源泉」セクションのあと、「終の棲家」としてEast 10th Streetのアパートが再現されていた。これがなかなかに興味深かった。
現代のデジタル化された生活とは異なり、やはりアナログだ。フィルムやスライドを確認するスタンドが鎮座していたのが象徴的。すぐに写真を確認できる現代と違って、ひとつの写真に向き合うエネルギーが違う。画家を志したソールは、それはそれは丹念にフィルムやスライドをチェックしていたことだろう。

スライド確認用のテーブルから数歩あるくぐらいの距離に描きさしの抽象画があった。フィルムを確認し、画架に向かいなおすまでのこの距離は作品にどう影響したのか。わたしは具象絵画を描くからモチーフや取材したものはすぐ近くに置きたくなるけれど、もしや抽象画にはこの距離が必要なのかもしれない・・・などと想像した。
◆
4番目は「カラースライド・プロジェクション」。
ソール・ライターが生前にプリントした写真はかなり限られていたそうだ。解説には「わずか200点あまり」とあった。では膨大な写真の大半はどうしていたのか。それは再現されたアパートに置かれていたスライドのスタンドや、壁面に投影したスライドの形で確認していたという。
なるほど。さっきデジタル化された現代とちがってアナログだったと書いた。それは確かにそうなのだけど、プリントではなくスライドで確認していたのなら、それは色を光として知覚していたことになる。それって、現代のデジタル撮影した写真データをモニタ越しに観るのと同じではないか。減法混色ではなく加法混色。現像しないとわからないタイムラグはあったにせよ、発色という点では現代のデジタル写真を観るのに近かった。
ソール・ライターはニューヨークの光を観て、それを表現していた。写真では、反射や写り込み、曇りガラス越しの滲み効果を多用した。そして米国の抽象表現主義に通じる抽象画を描いていた。スライドの展示を観ていると、それらがつながってくる。

円形の拡散ライトの台に扇型に並べられたとても小さなスライドたち。そのなかには見慣れたソール・ライター作品があった。逆光のなか浮かびあがる、ひとつひとつのスライド写真の光景。小さな長方形を凝視していると、自分が小さくなって没入するかのような不思議な感覚になる。そこには実際にその場面を観たかのような臨場感があった。
小さな小さなスライドを覗き込んで感じた世界の光景は、展示室の仕切りを越えると空間自体を包み込むスケールで迫ってきた。
次の大規模プロジェクションの展示のことだ。それはヒカリエホールの大空間だからこその迫力だった。以前のBunkamuraザ・ミュージアムではできなかった展示だ。
左に5面。

右に5面。

両面の中央に腰掛けが設置されていて、眼前でスライド写真が次々と切り替わる演出に浸ることができる。ちょっとした映画館なみの空間だ。この10面の大型スクリーンに、約250点の作品が投影される。文字どおりのスライドショー。それまでの混雑した会場にはちょっと疲れはじめていたけれど、おしまいのこの演出ですべての疲れが吹き飛んだ。
◇◆◇
暗室のように暗い会場を出ると、そこはショップになっていた。いつものように図録を探すも、見当たらない。そのかわり、「会場限定」と書かれた小ぶりの冊子のようなものが眼に入った。
そうか、この展覧会は図録が用意されていなかったのか。だからまるで図録をつくるつもりなのかと思えるぐらい片っ端から撮影していた来館者がいたのか。
ショップまで来てしまったので、もう会場には戻れない。どこかに図録がないことは書かれていたんだろうか。わたしはそれを見落としていたのかもしれない。このnoteに載せたわずかな写真だけでも撮っておいてよかったと思った。
過去2回のソール・ライター展の図録はすでにかなりの作品が網羅されている。今回の展示との重複もそれなりにある。それに過去の図録は書籍として一般書店で販売されている。たしかに3冊目の図録は必要ないとの判断もあり得そうだ。
会場限定の小ぶりの冊子のようなものは、小冊子ではなくポスターブックとある。そして円形のステッカーが貼られている。

“時折、見逃してしまうんだ。大切なことが、今、起きているという事実を。”
円形のステッカーには、こう書かれていた。ソール・ライターの言葉だ。いやはや、これには苦笑いしかない。まるで図録を買えばよいと考えてほとんど写真を撮らなかったわたしに対する皮肉ではないか。図録なし・撮影可との“大切なことが起きている”のを見逃してしまっていた。
もちろん図録の代わりにその開催記念ポスターブックを購入した。
ところでこのポスターブックとはなんなのか。ビニールから出して開こうとすると予想外の向きに表紙が開き、巨大な“ポスター”が現れた。


これはあの大型スクリーンのスライドショーを思わせる。ソールの代表作と生涯については、前回・前々回のソール・ライター展の分厚い図録でじゅうぶん。ならば今回はインパクトある大型展示の記録に的をしぼろう、そういうことなのかと理解した。
展覧会の記録資料としての図録とはちょっと違ったポスターブック。表紙以外に文字がないシンプルさと潔さがソール・ライターらしい。
ソール・ライターが感じ表現しようとしたニューヨークの光と色、それを通して感じられるなにか、それらをどこかでふと思い出したときに、またこのポスターブックを開くことになるかもな・・・という気がする。それがインスピレーションにつながれば、「図録なし・撮影可」を見逃したことの怪我の功名、つまりセレンディピティだなぁなんて思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
