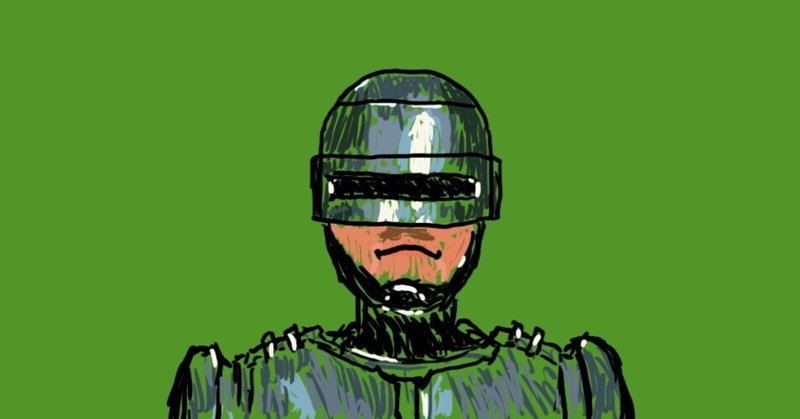
瞑想は、スポーツ選手のように毎日続けるもの- マインドフルネス日報
どうも。
マインドフルネス警察のゼンコップ(@zencyborg)です。
最近知ったのですが『サピエンス全史』の著者ユヴァル・ノア・ハラリ氏も、毎日2時間ほど瞑想に取り組んでいます(驚)。
彼に限らず、Googleをはじめ世界中のハイパフォーマーに「瞑想」は大人気。
わたしは社会人になって仕事のストレスに悩まされていましたが、瞑想によって不安が減りました。
その経験をもとに社会のストレスを減らすべく、マインドフルネスを広めています。
NOTEでは毎日、名著『マインドフルネスストレス低減法』からの学びと、シンプルライフ本の抜き書きを少しずつ発信していきます。
また、誰でもすぐに始めれる「3分瞑想」のやり方と「食べる瞑想」のやり方についても簡単に説明。
コロナで不安が続きますが、自分と向き合う機会でもありますので、マインドフルネスを全力で広めていきます🍵
【瞑想】毎日続けることの重要性『マインドフルネスストレス低減法』より
【毎日続けるという意思】
瞑想に積極的に取り組むように努力し、そのプロセスに耐えられるように十分な自己トレーニングを行うことが、高度な集中力を養い、瞑想の効果を高める上で非常に重要な要素。瞑想を継続して続けるためには動機付けが必要で、病気を治すことや、ストレスをなくすことなど、なんでも良い。
【瞑想する人はスポーツ選手と同じマインドが必要】
・自分の気が向いた時だけ、やりたいときだけ練習するのではない
・天気が良くて、一緒にやってくれる仲間がいて、時間の都合がつく時だけ練習するのではない
・毎日毎日、規則正しく、雨であろうと晴れであろうと、体調が良くても悪くても練習を続ける
・練習の成果が上がろうと、上がるまいと、とにかくひたすら練習する
【ただひたすら続けることが重要】
瞑想を好きになる必要ない、ただ、ひたすら続ける。ためになったか、ならなかったかは、8週間が過ぎてから考えましょう。
【続けれる環境を整える】
瞑想トレーニングを行うための45分という時間を毎日捻出するために、ライフスタイルを大幅に変える必要があります。45分と言う時間は、魔法のように湧き出てくるわけではないので、自分のスケジュールを調整して、トレーニングを行う時間を作り出さなければいけません。
【読書】『ワン・シング 一点集中がもたらす驚きの効果』vol. 11
やることが多すぎて、結局自分は何がしたいのだろう?
「なんでも挑戦すること」は組織の中で称賛される場合があります。
わたしが以前勤めていた会社も「なんでも挑戦すること=善」という考えで、わたしもありとあらゆることに手を出していました。
しかし、手をつけた全てに関して残ったものは、そこそこの結果。
やることが多く忙しい日々を送る中で、結局自分は何をしたいのかを問い直した時に出会ったのが『ワン・シング』という本です。
この本では何かに一点集中して取り組むことが大成功の秘訣であることが解説されます。
以下、本から学んだ重要箇所をいくつか紹介します。
ーーーーーーーーーー
【答えの3つのレベル】
優れた質問の次は、優れた答えを見つける必要がある。その答えには3つのレベルがある。
①すぐにできるもの
②背伸びしなければできないもの
③可能性があるもの
→②か③を選ぶ。
②はやりがいがあり、自分の能力の限界を目指すことになり精一杯力尽くさなければ達成できない。最高なのは③。変革を成し遂げる会社はここで勝負している。
【先人の研究】
先人の研究は、最高の答えを探すときの最良のスタート地点。今自分が進んでいる道をすでに踏み超えた人たちを探しましょう。ほとんどの場合に先人がいる。彼らの経歴・経験を調べ、自分の指標、向かう方向性になるか考える。
【最高の目標は、大きくて具体的なもの】
大きさとは、すぐにできることや、背伸びしなければできないものではなく、可能性があるもの。具体的とは、期限を決めること。
ーーーーーーーーーー
明日も引き続き、本からの学びを紹介していきます。
【初心者向け】3分瞑想、食べる瞑想のやり方
瞑想に興味があるけど、瞑想のやり方が分からなくて始めれないならば3分瞑想がオススメ。
3分だけなので、すぐに始めることができます。
3分瞑想に興味がわかなければ「食べる瞑想」というものがあります。
これは言葉どおり、食べることを通じて意識を集中する方法を学ぶもの。
瞬間瞬間を体験しながら食べることによって、今まで何となく食べていたものでも思わぬ発見があります。
また食べる瞑想は、瞑想が「何か普通ではないもの」や「神秘的なもの」という誤解を解くのにも使われるトレーニングです。
\【3分間瞑想のやり方】/
・3分だけでいい
・座ったまま
・目を閉じて
・力を抜く
・背筋を伸ばす
・呼吸は自然に任せる
・どんなふうに感じているかを感じる
・呼吸を観察する(呼吸に注意を集中する)
\【食べる瞑想のやり方】/
・3粒のレーズンを用意する(アーモンドなどでもOK)
・レーズンを初めて見るようなつもりで観察する
・指でつまんだ感触、色や表面の状態に注意をはらう
・そこでわきあがる思いに気がつく(好きとか嫌いな思いや、感じなど)
・しばらくレーズンの匂いを嗅ぐ
・口にはこぶために、腕が手を持ち上げるのを意識する
・心と体が食べ物を予期して、唾液をだすのを意識し、唇にレーズンをのせる
・そのまま口にいれて、1粒のレーズンの本当の味をたしかめながら、ゆっくりとかみしめる
・十分にかんだら、飲みくだすときの感触を確かめながら飲みこむ
・自分の体がレーズン1粒分おもくなったような気がするか確認
参考図書『マインドフルネスストレス低減法』
わたしが毎日少しずつ読み進め、瞑想のガイドとして使っているのが『マインドフルネスストレス低減法』です。
わたしがこの本を使う理由は以下の3つ。
・著者のJ.ジョンカバットジンがMasterClassで講師を務めている。
(MasterClassは世界レベルの著名人が講師を務める、アメリカの有料オンラインクラス)
・メンタリストDaiGoさんもオススメしていた本。
・妻がすでに持っており大絶賛している。
(つまり家にあったので、買わなくても良かったわけです。)
普通の本と比べると本書は390pもあり大著ですが、毎日少しずつ読み進めて実践することによって、確実にマインドフルネスの基礎が身につきます。
本日の瞑想記録
今日は心が過去のできごとにとらわれ、追いやろうとしていると気づきました。
具体的にいうと、以前読んだ本に、主人公が激怒して部下たちを叱責するシーンがあり、その場面に自分がいたら嫌だな〜と考えていました。
自分がその記憶にとらわれている「感じ」を観察すると、何かにしがみつこうとしていてギュッと窮屈なもの。
自分がとらわれていくのを積極的に観察すると、最終的に全く正反対の、とらわれないということが分かります。
わたしはまだその境地にいたっていませんが、積極的に事態を観察しようという心構えを持ち続け、とらわれないことを体得したいと思います。
とらわれないことに関して昨日、良い眠りはなにごとにも心と体をとらわれないことが重要、ということを学びました。
早速眠るときに、浮かんでくる考えを手放してみると、すぐに寝付くことができ、効果を実感しました。
この手放すという感覚を、起きているときにも実践できるように学んでいこうと思います。
それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
