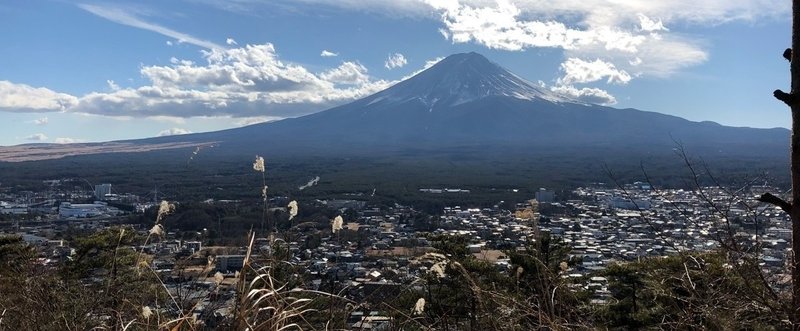
21世紀以降はキリスト・ユダヤに仏教やヒンドゥー入れてこうぜ、と薄々感じていた話
このエントリー書いたきっかけは
【落合陽一徹底解説】「サピエンス全史」続編から見える日本の勝ち筋 ──前編(Forbes)を読んで、色々思い出したからです。
※本エントリーは
・ユヴァル ノア ハラリ著「サピエンス全史」を既に読破orざっくり知ってる
・20世紀のIT技術がどうやって生まれて発達したかを漠然と知ってる
の2つに当てはまった方は特に読んで欲しいやつです。
知人が本出した時の話
もう2年前ですけど、前職で一緒だった児玉君が本を出して、その時色々と協力した時のことをここに書いてます。
で、読み返したら当時のブログにも書いてた。
「AIの先にあるものは、決して西洋だけでなく、人類が知と意識の研鑽の途中で見つけていたものと繋がる多様性とか?」
相当丸めて書いてたな。実際僕が言った意見はこんな感じです
シンギュラリティがなんか最後の審判っぽく横行してる感じあるじゃん。
21世紀入ってからキリスト主体でありつつ、他の宗教や倫理観が入り乱れてくる多様性を含めて、むしろそれを売りにするというか、そうすると仏教や禅はあれど宗教的文化が薄い「日本人」が書いた本として、独自のポジションにおけるんじゃない?
個人的に不満なんだけどさ、全編通じて聖書的・欧米的じゃん。20世紀のIT歴史振り返る場合はOKなんだけど、こっから未来をなぞるなら他の宗教も入ってきた方が自然だし「今後起こること」じゃない?だってもうAI自体インドと中国無視できないじゃん。
※上の引用が初稿を読ませてもらった時に「海外でもこの本売れると思う?」的な話題で僕が言った発言
※下の引用は、完パケが出来上がってもう発売待つだけの時点で「強いて不満があるとすればさ」って話題における僕の発言
当時2016年だったけど、なんか「西洋!西洋!!西洋!!!」なのがずっと引っかかってた。もちろん超いい本だし、実際売れたみたいだけど。
2016年9月、サピエンス全史 邦訳発売
で、そんなやりとりした半年後ですよ。
読んだ人には説明不要だろうし、読んでない人には「どんな年齢やバックボーン、職業の人にとっても絶対損しないし面白いから読んで!」としか言いようがない(語彙力)
僕がサピエンス全史好きな点
・ユヴァル ノア ハラリが歴史学者の観点として書いていること
(歴史大好き人間として、歴史学者のプレゼンスが上がること自体嬉しい)
・太古の時代から丁寧に分厚く歴史をなぞり、未来まで突き抜けるのだけど、富や資本主義、技術の発達を「まあ、共通の神話だってことで支持されてさ」で片付けちゃっている痛快さ(本当はもっと深い。ここも語彙力・・)
で、同時に引っかかっていたのが「お前、イスラエル出身ユダヤなのに、ちょーっと西洋側に傾き強くない?」って。
もちろん東洋にも触れてるんだけど、全編通じて西洋で一本道が見えていた気が(読んだ当時)していた。
そしてサピエンス全史の続編を落合さんが解説した冒頭の記事に繋がる。
Forbesの落合さんの記事から、僕が「!!!」と感じた部分抜粋
ハラリは大多数の集合的な協働能力が人類と他の生物を分かつと主張しています。だとすれば、ネットワーク化されたアルゴリズムが僕らの認知的な限界を突破したとき、導かれるべきは「ネイチャー(僕はよく“計算機自然”と表現します)になるはずでしょう。それにもかかわらず、ハラリが結論として導出するのは「超人(Homo Deus=神の人)」なのです。
こういったコンピューターテクノロジーによったエコシステムやビオトープを考えたときに、西洋的思想の持つ厳格性やキリスト教的一神教価値観は自然と調和をモチーフにする東洋思想よりも齟齬が出やすい。
ハラリ自身、本の随所で三人称を志向しつつも、結論部では一人称「ホモ・デウス」に固執しています。どうしても、西洋観の一本筋を通そうとする葛藤が見え隠れするのです。
・・・と3か所引用したのですが。
まさにこれ。っつうか2つ目に引用したやつは本当にそのまんま過ぎて鼻血出る。
2016年にいまからタイムスリップして、当時の俺に「おい、そこの知的好奇心と嗅覚だけが取り柄の語彙力の無いやつめ、お前がいいたいのはこれじゃないか?」って言ってやりたいよ。めっちゃ言いたい。あるある言いたい。バービーボーイズの目を閉じておいでよに乗せてあるある言いたい。
語彙力。
ハラリのサピエンス全史に感じていた違和感もわかった、というか落合さんの解説が解らせてくれた。
歴史好きにはおなじみのやつだ。
歴史学者ってどんなに高名な方でもやらかす特性があって「自分の論(説)を貫こうとすればするほど、どんどんロジックの脆弱性が高まる」
行き過ぎるとトンデモ説を展開して学会からシカトされんだけど、ハラリはさすがにねじ伏せた、でもちょっとやっぱ歴史学者なんだなあと。
ホモデウス、邦訳楽しみだなー。記事の締めにこんなの書かれたら期待しちゃうよ。↓
内面的な自然と一体化して無目的な平穏を求めようとすることを目的とする……この大いなる矛盾は、死と幸福の概念でパラダイム設定を試みるハラリの議論にも通底しているのです。この矛盾に向かい合いながら西洋個人の更新を目指す論は力技を感じますし、ハラリにしか書けないのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
