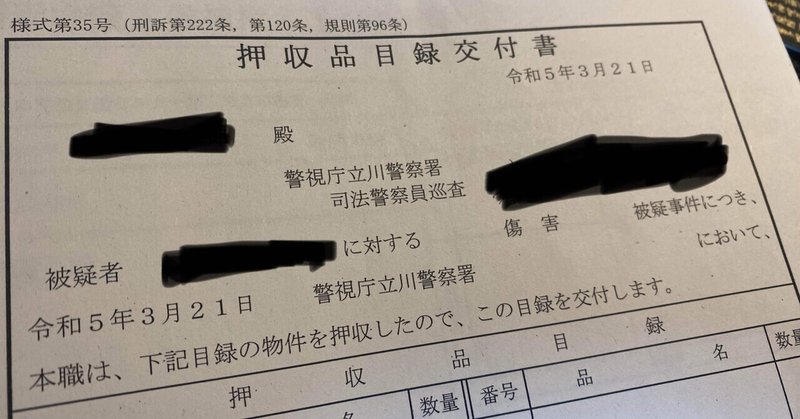
音楽のパッション
酒を飲んだ帰り道、中央線の車内で口論になり、男の顔を思い切り殴った。
男は警察に連れて行くと喚いた。T駅のプラットフォームに降りた中年の背中を蹴り上げると、取っ組み合いになり、私から二、三発殴り、頭突きを入れた。男の口もとに鮮血が滲んだ。
なにか大声で抗議して、私に血を飛ばしてくる。喚くなと言うと、腹いせに血の混ざった唾を吹き掛けてきた。私のシャツに粘度のある、赤いまだら模様が浮かんだ。黒い背広の汚れは目立たなかった。
駅員が駆け付け、間に割って入り、トイレットペーパーを持ってきて男に血を拭わせた。気がかりなのだろうか、通行人が散乱した屑を拾おうとする。
「下がってろ」私は二、三歩前に出て怒鳴った。「人の血に触るな」
通行人は目を丸くして、気まずそうに後退していった。駅員はその間で困惑していた。
それから、警官が来た。たくさん来た。十三人ほどやって来た。
現場のプラットフォームから改札前に連行され、代わるがわる同じような質問をされた。
私は露骨に血まみれで通行人の目を引き、野次馬の学生たちが騒いでいた。知ったことではなかった。衆目を気にする神経があるなら、電車のなかで人など殴りはしない。署まで同行することになった。
警官たちに付き添われ、こちらを一瞥しては目線を外す人々のなか、駅の構内を歩く気分はいやに穏やかだった。
この状況とはなんの関係もなく「人生は幾何学ではない」という言葉が浮かんで、すぐに消えた。どこかで耳にした、安いキャッチコピーだった。
パトカーから眺める夜の町は、窓ガラスのスモークでより一層うす暗かった。街並みは俗悪だった。鋳造された星々のような外灯が輝いていた。灯りはパトカーの速度で後ろに尾を引いて、暗がりに吸い込まれていった。
事件を起こした時、刑事の質問というものは、恐ろしく平板である。
大声でなにか説教するでもない。便宜をはかったと言われかねないので、かつ丼を出す訳でもない。そういう無感覚が私をもっとも苦しめた。
恰幅の良い中年の刑事は、ぼそぼそ決まった項目を聞いてから、身分証を出すように言った。私の返答は、出さぬだった。妙な沈黙のあとで、刑事が交代した。柔道世界チャンピオンのような刑事が取調室に入ってきた。
刑事が早く出せと怒鳴り散らした。やはり私の返答は、あくまで出さぬだった。なぜ出さぬのかと刑事が聞いたので、なぜ出さなければならぬのかと応じた。
三人目の刑事が入った。どうやら今度は、良い刑事のようだった。
「言い合いになって喧嘩になったのは分かってる。みんなで楽しく飲んだ帰りなんだし、ここは素直に応じて一見落着にしましょうよ」
大体こういうことをジェントルに言われた。出さぬと即答した。取調室の外で刑事が額を集めている。身分証を出すべきか、出さざるべきか、それが問題だった。
あまり長い間、取り調べは出来ないと言われ、中断となった。中断する旨が書かれた書類にサインを頼まれ、ここまで暴力的なサインがあるものか、いや、これで自由の身かと考えていると、待合室に通された。入り口のパイプ椅子に、制服の警官が坐って見張っている。
逃げも隠れもしないぞと考え、ベンチで横になり、鞄に入れてあったギッシングの『ヘンリ・ライクロフトの私記』を読んだ。ギッシングの描いた英国の田園は美しかった。寝転んで読んでいると、気分も落ち着いてきた。
「煙草が吸いたい」
そう呟くと、見張りの警官に、俺も吸いたいよと言い返され、お互いに苦笑いしてしまった。
コーヒーを買わせてくれと頼むと、警官二人に付き添われて、署内の自販機を使わせて貰った。もっと煙草が恋しくなる。ニコチンが切れて、意地悪というか、反官的な気持ちが芽生えた。
「二人で煙草を吸いにいきましょう」
「吸うなら一人で吸うよ」
「しばらく吸えそうにないですね」
軽口を叩いてやると、答えがないままに見張りが交代した。今度の警官は無口だった。気怠そうに白髪を掻いて、座席から脚を投げ出して坐っている。空き缶が灰皿にしか見えなくなった頃、部屋の外でひそひそと声がした。
「あいつ一睡もしてないぞ」
「コーヒーは飲んでたよ」
「そんなもん飲ませるな。頭が冴えてくるだろう」
やや人権侵害のきらいがある台詞をよそに、鉄格子の窓の群青に、だんだんと明るみが差した。貧血に陥った女の顔色のように、微妙な色合いだった。
今は何時だと聞くと、朝が来たよ、と言われた。被疑者に余計な情報を与えたくないのだろう。そんなことは分かっている。自分が置かれている状況も、意地を通せば不利に向うことも、全て分かっている。
「眠くなってきましたね」
「俺も眠いよ」
「この時間は書類の関係ですか?」
「うん。裁判所も暇じゃないからね」
「こんな時間に裁判官は動くんですか」
「二十四時間で動いてるよ。もう令状がくるよ」
どうやら裁判所は、ヨドバシカメラの通販より仕事が早いらしい。
「早く、捕まえて欲しいですね」
「俺も早く、捕まって欲しいね」
遠くで自動車のエンジンの音が聞かれ、窓硝子は朝の輝きだった。ドライアイを揉みほぐすようにやさしい光だった。モザイクの窓に、あわい影がゆっくりと揺れている。どうやら桜の枝だった。満開ではなかった。やさしくお辞儀するように、風にそよいでいる——ごきげんよう、ごきげんよう、罪人さま。悩ましい春のおとずれだった。
部屋の外が騒がしく、もう書類が仕上がったらしい。どたばた刑事が部屋になだれ込み、待合室から、取調室に連行された。身分証を出さぬ代償に、捜査令状を突き出された。刑事の説明は続き、不眠も手伝って、やはり要点が分からなかった。
「確認なんですけど、身ぐるみを剥がす権限があるということですか」
「そうです。身分証を出して下さい」
柔道世界チャンピオンにお触りされるより、この手で身分証を白日の下にさらした。ポケットの中のマネークリップに身分証が挟んであった。
朝まで守り抜こうとした、なにかしらの感性がそこにあった。てのひらのマネークリップの感触を、ずっと忘れることはなかった。哀しみがてのひらのうちに、結晶していた。
マネークリップは押収され、形だけだから、と刑事がささやいた。この両手首に手錠がのし掛かった。私は深いため息を吐いた。捕まったことよりも、私のようにギルティな人物を捕まえるのに、これほど時間が掛かることがショッキングだった。
警官が逮捕の瞬間をデジカメで撮り、どういうポーズをしたら良いのか悩んだ。手錠が掛かっているとなれば、なおさら。
すぐに手錠は外された。逃亡できる見込みなど、初めからない。
身元が割れて、私という人間の実在が確認された。取り調べは仕切り直しとなり、全く同じ質問が繰り返された。
残念ながら、同じような出来事を書きつらねる余白はない。ひとまず刑事との雑談、そして犯罪者の食事について描写しよう。
長い論争により、私と警察の双方は疲れ切っていた。刑事は眠いと口走り、取り調べが終わってまもなく、あろうことか居眠りし始めた。決して故意ではないのだけれど、手錠の金属が軋むと、刑事がはっと覚醒した。
「逃げようとしたら、どうするのですか」
「手錠が椅子につながっていますから」
「椅子を持ち上げれば移動できないこともないですが」
刑事は力なく笑った。私と同世代で、議論を挑むとやたらと早口で応じてくる男だった。こういう男にはユーモアが利くという目論見があったが、その破顔はなんだか空しかった。公務員によく見られる、安定はしているが向上も無いというニヒルな感じだろうか。
「このあと仕事があるんでね。警察なんで、定時で帰れるわけじゃないんです」
「被疑者の僕にも、このあと仕事があったんですよ」
相手が疲れていると見込み、やり返した。
「おかげさまで無断欠勤ですよ」
「あまり仕事に執着していないように見えます」
執着という言葉づかいは、なかなか面白かったと思う。
「まだ取り調べがあるわけだ」
「変死体を見なきゃいけない。変死体ってわかりますか」
「つまり、変な死体ですね」
若い刑事はまた笑った。
「そういうことです。死体が届いてるんですよ」
「届いているという表現は斬新ですね」
「ひどい匂いなんです。素人じゃ耐えられない」
この刑事、俺よりもサイコだなと考え、なんだか可笑しかった。さきほどから二人でへらへらしているものの、これは取り調べである。刑事の怪談はまだ終わらなかった。
「季節によっては、ドロドロになってる時もあるんですよ。じつはさっきも死体を見てきたんですよ。匂いませんか」
「いや。被害者の血の匂いしかしませんね」
「よかった。ファブリーズを掛けてきたんです」
怪談が一区切りして、シームレスに被疑者の昼食に移行していった。弁当が取調室に運ばれてくる。オムレツと白米、添えられた漬物という、素朴な食事である。オムレツなどはなかなか可愛らしく、ハローキティのキッチンに付属するおまけのようだった。警官がお茶を持ってきてくれたので、感謝の気持ちを伝えた。
「わざわざ犯罪者にすいません」
「大したお茶じゃないよ」
出された飯に文句を付けるのは無礼と考え、黙々と食った。空腹は最高の料理人ですからね、などと刑事が野次ったけれど、知ったことではない。ひどく飢えていたせいもあり、旨かった。
飯を食い、うとうとしていると、取調室の外で刑事が大騒ぎしている。ワールド・ベースボール・クラシックの決勝に日本代表が挑んでいるそうだ。人が逮捕されているのに、無神経である。
「昼間の警察署ってのは、あんなもんです」
申し訳なさそうな弁だった。彼も体育会系ではないかもしれず、二人とも静かに眠りたかった。
なんだか空しさを感じ、二日後にデートの約束をしていると私は口走った。その日には会えないかもしれないと刑事は言った。日本のバッターがヒットを打ったのだろうか、外で乾いた歓声が鳴った。
「こういう仕事をしていると、女性と予定が合わせづらいんですよ。それに僕はメンクイなんです。なかなか相手がみつからない」
この刑事は公権力の末端で、休日は女に困っている青年でもあった。二人して、茶を濁すように笑った。良い友人にはなれないだろう。
「彼女が見つかるといいですね」
そう私は言った。皮肉ではない、むしろ、ささやかな祈りだった。
留置所は、受け入れの準備を終えた。若い刑事にお別れするタイミングを逃したまま、手錠にくくられた紐を引かれ、連行されていった。鉄のドアを何枚か隔てた、地下へ。
私物はすべてリストに記録にされ、口内と金玉の裏に武器を隠していないか、セキュリティチェックが入った。初老の看守は私をまっすぐ見据え、注意事項を話した。彫刻のような皺の入った老人なのに、瞳ばかりが真っ直ぐに澄んでいた。
「これから留置所に入ってもらいます。私はあなたの世話係で、中の生活を心配する必要はありません。とは言っても三十人の人間が生活しています。いろいろな人間がいることでしょう。『なにやったの』と聞かれることもあります。お喋りをすることは構いませんが、彼らとはたまたま同じ場所に行き着いただけです。友だちではありません。住所や名前、仕事を聞かれるかもしれません。喋って後悔しないように」
振り返ってみると、この看守の弁には、大事な教訓があった。半分は正解で、もう半分は不正解という話ではない。必要な息を吸い、余分な大気を吐くように、同時に行わければならない矛盾についての教訓だった。
与えられたのは教訓と、古ぼけたスウェットとズボン、サンダルだけだった。手錠とサンダルは窮屈で、スキー初心者のように廊下を歩いた。サンダルに番号の書かれたシールが貼ってある。二九という番号が私の新しい名前だった。
看守にエスコートされ、灰色の廊下を歩くと、床から一段高くなった所に、鉄格子をはめ込んだ部屋があった。目線の高さに半透明のセロハンが貼ってあり、中は覗けない。キーチェーンで看守が扉を開けた。
人間はいなかった。六畳ほどの空間に、緑のカーペットが敷かれて、窓の付いた小部屋が見えた。小部屋は便所であると説明され、私はサンダルを脱いで部屋に入った。
看守は去り、ああ独房で良かったと考えて、一眠りしようと横になった。急に点呼が始まった。
そうか、点呼かと思い、ごろりとしていると、格子の外から、坐れ、と怒鳴り声が飛んできた。点呼の時は坐りなおして、手のひらを開いて待機しなければならなかった。
看守が大声で番号を叫んでいく。二九番と呼ばれ、返事をする。最初の点呼だった。通常であれば一日に三回ほど点呼は行われた。
鉄格子から壁に掛かった時計が見えて、しばらく経ったと思っていたが、入ってから十分も経っていなかった。
腕を組み、秒針をにらむと、緩慢なリズムの暗示で、デートに間に合わない予感が強まった。
無念を嗅ぎつけるように、看守がやってきた。部屋を移動すると言い出した。廊下を歩くと、義務教育の現場でよく見るような水飲み場があった。なぜかアルミの上に、血が漂っている。整列する牢屋の前で、看守が立ち止まった。
扉を開けると、中に三人の囚人が坐っている。サンダルを脱ぎ、そっと房に入って、カーペットに坐った。ごきげんようと挨拶する者もなければ、背景にモーツァルトが流れているのでもない。
最初に口を開いたのは、手前の大男だった。タンクトップからせり出した腕に、粗い光沢の刺青を入れている。一体何の柄なのかは、よく分からない。しかし、三〇〇メートル先から見てもヤクザである。
「なにやったの?」
「傷害です」
「だいぶやったのか?」
「そうですね」
「飲んでたのか」
「飲んでました。相手も酔っ払っていたと思います」
「別に心配することじゃないな。ヨンパチで出られる」
「ヨンパチ?」
「四十八時間で留置は終わるよ」
「そんなもんですか」
「うん」
大男は、俺なんかは詐欺で捕まった、俺じゃなくて先がやったんだけどな、と言い訳した。奥に坐り込んでいる老人が、上目遣いで相槌を打っている。この男は、無免許運転で捕まったと告白した。もう一人の罪状は不明だった。小柄で若くもないが、目つきが悪く、急に人を殴りそうな雰囲気があった。
新しい同居人たちは、口々に検察官を罵倒している。一方の私はごねることもなく、ただ待っていようと考えていた。私の犯罪をたしなめる者は一人もいなかったからだ。出会うべき人に出会えたことを悦んでいた。
──牢獄を出た後、再会した知人たちに、なぜ暴力を振るったのかと問われた。動機など述べようがない。一回の犯罪は、一度の人生の、圧縮された抽象画だった。色づかいや筆のほとばしりに、どういう作為があったのか、そいつを説明できるなら表現する必要はない。つまり完璧に弁解が出来る者は、そもそも罪を犯しはしない。
牢獄の仲間と、ランチの時間だった。
コッペパン二つと、マーガリン、ピーナッツバター、飲むヨーグルトだった。牢獄のランチは必ず、コッペパン二つだった(愛着を込めて、以後はこのパンを「犯罪パン」と呼ぶことにする)
一心不乱に、犯罪パンを食った。一切れのパンにも滋味があり、文句なしに旨かった。
廊下に響いていた囚人の話し声は、午睡で静かになった。私も犯罪パンを完食し、ようやく横になった。
私の父は、ひどい飲んだくれだった。
酔って帰ってくると、ふらふらになっていて、家の鍵を開けることが出来ない。
子どもの私は、もう夢を見ている。父が扉を思い切り叩くと、いとも簡単に夢がはじけた。母が玄関に駆けて行った。
いきおい余った夜などは、サイレンを鳴らすパトカーで帰ってきた。どうやら上司の首を絞めて、通報されてしまったらしい。こういうことが何日も続くと、まだ赤ん坊だった妹は寝不足に苦しんだ。
内省してみると、私は血統書付きの飲んだくれに過ぎなかった。
もっとも私の一族は、血を遡るのが到底かなわないほどに、勘当による分裂と、養子による同化を繰り返していた。
一族の者は思い付いたように婚姻し、子どもを作って、また新しい伴侶を探した。そのような子どもたちは、未成年のまま家を飛び出して、二度と帰って来なかった——同情と金を求めている場合は別として。
父方の祖父は、東京大空襲で同級生をほとんど失った。川に飛び込んで生き残ったものの、空襲で亭主を失った曾祖母は再婚するしかなかった。
祖父はその家庭になじまなかった。戸籍の上で身内であるという、建前にも従わなかった。古い姓のまま育って、夜学を出てから、造幣局で働いた。私の抱える坐りの悪い感じは、祖父の体験から流れ込んだものと思われる。
相槌よりほかに会話することがなかった祖父が、どうやって祖母を口説いたのか。大いなる謎ではあるけれど、私の父は誕生した。
戦争体験か、造幣局で得た職業病か、祖父はケチだった。出来心で父が消しゴムをちぎったりすると、祖父は靴べらを振りかざして何度も殴った。
祖母にかばわれて、いくらか人間的な情を持った父は、芸術家くずれだった。
高校の美術教師から、彫刻とデッサンを褒められて、父はいたく悦んだ。正当な評価なのか、たんなる憐れみなのか、私には知る由もないけれど、父はベラスケスの絵画に心を奪われ、身の回りのものを熱心にデッサンした。美大の入試を受けると、本人に自覚できないような微妙な色盲と診断され、不合格となった。
同情の余地はない。父が酔って暴れるのは、いわば敗北した芸術家なりの、世の中への復讐だった。
父にとってはラーゲリと言って差し支えない職場で、上司の首を絞めるのも、無理もなかったのだろうか。同じオフィスで両親は出会い、この物語の語り手であるところの私が誕生する。
母の家系は恥ずかしい百姓ばかりで、勤勉ではあるものの、絶望的に学がなかった。正月などに親戚のつどいに寄ると、文盲の爺さんが騒いでいる。
顔付きの違わない三兄弟の爺さんがみな文盲だった。焼酎の瓶を咥え、兄弟で肩を組んで、東京音頭を歌っている。
母は私を遠ざけた。人差し指でじぶんの頭を差して、これなのよ、と母は説明した。確かに生まれつきの気狂いがたくさん出てきた。わが国の識字率が一〇〇パーセントを記録しないのは、おそらく私の家系のせいだろう。
安いカクテルのような血筋に置いて、私は初めて散文に向き合った末裔だった。
私の育った家庭には、書物などというものは、一冊も落ちていなかった。こういう家庭に産み落とされた子どもが散文に関心を持つまでに、どれほど分裂を経験しなければならないか……
そんなことはどうでも良い。私の教育が失敗するまでの経緯を書こう。
少年時代、心を入れ替えて学校に行くと宣誓し、その足どりのまま通学路を逆走した。定期券を使うと足が付くと考え、隣町の図書館まで歩き、書架の影に坐りこんだ。
日が暮れるまで小難しい本に向き合うのに疲れると、その姿勢のまま居眠りした。
閉館の時刻まで、同じ姿勢でいた。子どもの頃の私は退屈で、大人が考えるよりも卑屈だった。
ある社会科の教師と、授業中に言い合いになった風景が思い出される。
何かを語ろうとすると、先生はね、という枕詞を付けてしまう、鬱陶しい教師だった。私が寝坊して教室に入った瞬間に、要領を得ない質問をしてきた。
「うるせぇよ」
教室中の生徒が笑い、教師は激昂した。着席した生徒たちを挟んで、二人で十分ほど口論した。出て行けと言われて、そのまま図書館に戻った。後日、廊下ですれ違った時に、この間は悪かったと謝罪されたが、僕はあなたと喧嘩したつもりはありませんと返事した。
その社会科の教師がポルシェを買ったなどと自慢するようになった。誰も聞いていないのだが、先生のポルシェは時速二〇〇キロも出ると、方々の教室で触れ回っている。
自慢のポルシェは校舎のわきの駐車場に停めてあった。スーパーマーケットで買い物するには不便そうな、小ぢんまりとした赤いポルシェだった。確かに美しい車だった。
私は廊下の窓を開け、ポルシェの屋根に椅子を落とした。
ただでさえも狭そうな車内なのに、屋根が思い切り凹んでしまった。見下ろすと、踏み潰されたトマトのようだった。
朝礼に社会科の教師が出て来て、開口一番に泣き出しそうな声で、先生は悲しいと演説した。学校中の生徒が笑った。
ポルシェ破壊事件の容疑を掛けられ、知らないものは知らないとシラを切った。図書室の司書や一部の国語教師から、彼がそんなことをやる訳はないと擁護された。
確かに不良のように悪事を自慢したい気持ちはなかった。
学校関係者たちが事件を耳にして驚いたり、義憤や哀れみを表明するなかで、私はもっとも冷静だった。この私が手を下さずとも、いずれあのポルシェはクラッシュするものと確信していた。
この世界は、クラッシュの総体として成り立っている。
両親はクラッシュしたことによって私という子を設けた。行く先の違う人々がクラッシュして都会が出来る。無数の岩石がクラッシュしてこの星が誕生した。私はクラッシュすべき何かに出会うことを待ち望んでいた。退屈が高じて、老後の楽しみのように本を読みふけっていた。
ある分野の書物は、クラッシュを事細かに記述しているが、クラッシュが私にどのような影響を与えるかを決して説明しようとしない。どれほど示唆深く、美しい文章に直面しようとも、その言葉によって椅子ごと蹴倒される者はいない。不服だった。私は散文に出会い、その抽象性を心の底から憎んでいた。
さて、悪い噂が立った上、私の逃亡癖も改善しなかった為、両親は知らせもせずにカトリックの高等学校への転入手続きを始めていた。
この頭に聖水を注ぎ、改心させようという魂胆だろうが、知ったことではないと考えながら、山の上の学校行きのバスから、さんざめく木々を眺めていた。
冬の訪れに野山は沈んだ色に染まり、何かしらの理由で転校する生徒の顔色や、バスのエンジン音にも活気が宿っていない。アーメン、この鼓動の打ち方がもっとも弱々しかったけれども。
どこにも行きたくない、居たくないと願いながら、十七歳の冬を越そうとしていた。
転入してすぐに同級生と喧嘩になり、椅子を投げ付けてしまった。
シスターに呼び出され、礼拝堂の準備室に出向いた。
「あなたが自分を傷付けるようなことをして、とても悲しい」
こういう説き起こしで、静かに諭された。
鶯色のセーターに、細かい花柄のスカートを身に付けたシスターは、やさしい眼差しで私を見据えている。子どものように短い亜麻色の髪を微動だにせず、一言ひとことを大事そうに喋った。
彼女が本当に聖職者なのか、シスターとは通り名に過ぎないのか判然としない。こういう叱責を受けた試しがなくて、裸電球のやさしい灯りの下で、私は反抗的になれなかった。
「あなたは本が好きなんですね」
「好きじゃないですよ」
「なにが好きなの」
「そんなものはないですよ」
なぜかシスターは目を細め、私にはどこか居心地が悪かった。
「作文を出してください」
「まあ、やってきます」
「なんでもいいから、読んだ本の感想を書いてきて」
「分かりました」
「N君という子を知っていますか?」
「知りません」
「きっとあなたと気が合うと思う」
「悪いやつですか?」
にこにこしながら、シスターは肯いた。
それから数日して、美術の課外授業で、自然の風景をスケッチすることになった。校舎の外に出ると、木枯らしは肌をちくちく刺すようだった。生徒に運動をうながす校風に文句を言っていると、シスターは野山を案内した。
木々の枝葉はみな枯れて、けもの道には萎れた草花がうつむいている。淋しいばかりではなくて、雲間から日射しがこぼれて自然の明暗は美しい。眩しい緑の主張より、パステルカラーの山道は気分を落ち着かせてくれた。
足どりに応じて、段々と道は高くなって、この息づかいが少し乱れ、真冬なのに額に汗が滲んだ。木々の根っこが道の上で波打っている。私がつまずくと、シスターは手を差し伸べてこの体を支えてくれた。枯れた山にも、力強い生命があった。
山を駆け上がった先に、林をスプーンでくり抜いたような小さい休憩場があった。丸太のベンチにNが坐っていた。スケッチボードを膝に置いて、リラックスしながらも上品な姿勢だった。
シスターの紹介の後、私の目を覗きながら、Nはゆっくりと喋った。どことなくいけ好かない奴だった。今日は天気が良いですね、と挨拶すると、Nとシスターは顔を見合わせて笑い出した。心外だった。
Nはトーマス・マンを読んでいると言い出した。『ワイマルのロッテ』はなかなか面白いなどと話すくらいで、なかなか嫌味な趣味だった。
「そんなもん読んでる場合じゃない。ここは『魔の山』みたいだ」
「トーマス・マンなんて読むのね」
シスターは教師らしく感心していた。
「でも『魔の山』ってどういう話なの」
「少年が山の病院で暮らす話です」
三人で笑ってしまった。時刻だった。スケッチに戻るようシスターに言われ、Nと木陰の下をぶらぶらした。彼は課題を終えていて、歪曲した二本の木を見事にデッサンしていた。私と言えば、信心深い老婆でも描こうかと考えている途中だった。
「なにがシスターなんだ。ただのおばさんじゃないか」
Nは礼儀正しく相槌を打った。
「あの人はめんどうくさい。目をつけられたんだよ」
「どうでもいいよ。『ワイマルのロッテ』は退屈だった。トーマス・マンは説教でしかない」
「岩波文庫から出てるけど、絶版だったね。あれを読もうと思った時点でえらいよ」
「暇なんだよ。教養小説はつまらない」
「そうかな。まあ時代を進めるといいよ。ヘルマン・ブロッホの『ウェルギリウスの死』は気に入ると思う」
やはり、癪な奴だった。放課後、帰りに立ち寄った図書館で、『ウェルギリウスの死』を検索に掛けると、世界文学全集に収録されていた。かびの生えた小説だろうと踏んだ。
——ああ、これほど文章に圧を感じる、外国の小説を読んだことはなかった。
畳み掛けるような文章にみな意識がみなぎり、大詩人が自身に訪れる死を内省している。冒頭を読んでいる時などは、うるさい文章だなと考えたけれど、構成が素晴らしかった。だいぶ消耗を強いられた感じもあったが……
今すぐにでも、Nに感想を話したかった。推薦する本のページに、彼の知性が匂っていた。
乗馬の授業の時、Nは女の子と連れ立っていた。
その女の子は、黒いワンピースの立ち姿で、エナメルのローファーを履いている。手綱を握る姿ではない。線が細く、端正だったけれど、どこか陰のある横顔だった。二人の談笑する仕ぐさを見ていて、立ち入る気にはなれなかった。
馬場に面した小屋の影で、昼食を待ちかねて息を荒くした馬を撫でていると、Nと目線が重なった。女の子を置いてNはこちらに歩み寄り、礼儀正しく挨拶した。
「ブロッホを読んだよ」
「馬に触らないほうが良い。指がなくなることはないけど、骨折するかもしれないよ」
私は鳶色の馬を撫で続けていた。暗い馬小屋の明るい方に、Nは立ち尽くした。私とNの間で、正しいテンポを刻むメトロノームのように、馬が頭を揺らしている。
「『ウェルギリスの死』だね」
「そうだね」
「どうだった」
「文章がくどい。息継ぎの暇がない」
Nは怪訝そうな顔をして、私の目を覗き込んだ。顔は良いけれど、小柄な奴で、私を上目で見ている。長い、二、三秒だった。Nは苦笑いをして、足元の小石をかるく蹴った。
「ほんとうは良かったんだ?」
「あの子と付き合ってるのか」
「まあ、そうだね」
「ローファーで乗馬しようとしてる女と」
「馬が怖いって言ってて。初めから乗馬するつもりがないんだよ」
「じゃあ、馬糞でも拾わせてろ」
「君も馬の世話をしてる」
「アニマルセラピーは効果がないよ。教師だって動物だろう」
放課後になり、Nとそのガールフレンドと、夕暮れのセピアに染まった自習室に集まり、気まずい雰囲気に浸りながらお喋りした。
Nのガールフレンドは、可愛らしいけれど、人間の顔に焦点を合わせるのが苦手なようだった。私とNは子どもらしくない、背伸びした話題ばかりで、きっと彼女には退屈だったろう。思い切って、刺激的な話を切り出した。
「君はなにやったの?」
突然尋ねられ、彼女は戸惑っていたけれど、別に私は神父ではない。懺悔を求めているのではなかった。
「僕はシンプルに不登校だった」
私に比べて、Nは不躾ではなかった。
「複雑な不登校もあるからね」
彼は茶を濁した。Nのガールフレンドは、ようやく私の目を見据えた。
「ぼや騒ぎを起こしました」
反射的に私は吹き出してしまっていた。Nは口を噤んだけれど、ガールフレンドの方が先に笑ってしまった。山の上に来てから、私は初めて自然に笑った。自習室が戸締まりになるまで、三人でへらへらしていた。
我が強いのだろうか、Nのガールフレンドの話は長すぎた。脈絡もなく、私は眠気を覚える。山の向こうに陽が落ちて、自習室は段々と青ざめていった。
結局、なぜ彼女が放火に魅せられたのか、あるいは苦しい決断に走らなければならなかったのか、分からずじまいだった。
それでもガールズトークは続いて、陽が落ちた野山を散歩している間に、私たちは最後のバスを逃してしまった。
ゆっくりと坂道を下ると、痩せた女のような木々が密生する林の中だった。
深まった暗がりは、景色のシルエットをみな隠してしまい、三人で携帯電話のライトを点して、一歩ずつ、確かめて歩いた。
いっぽん腐った木がもたれ掛かり、ふもとへの道に横たわっている。呪われた木だった。おびただしい羽虫が幹のうえで這い回っていた。
私たちは黙り込み、どうやって通過しようかと議論する前に、阿吽の呼吸で制汗剤を吹き掛けた。羽虫の群れは一切動じなかった。
Nのガールフレンドは、学生鞄からライターオイルを出し、幹にふり掛けた。挙句の果てに、マッチまで出てくる。私とNは唖然とするしかなかった。
女の子がマッチを擦り、腐った木に投げつけると、耳を刺すような音と共に燃え上がった。羽虫は一斉に飛び上がり、羽ばたきながら火花を散らし、次々に墜落していった。
辺りはほんのり明るく、一層静かになった。腐った木は燃え続けている。三人はそれぞれの姿勢で坐り込み、季節はずれのクリスマスをずっと眺めていた。
山のさんざめきがまだ響いている。目が覚めると、牢獄の中だった。
入浴は五日に一度。再生を祝う祭典のような行事だった。私にとっては二日目の監獄生活の始まりだった。
脱衣所と浴場は地続きで、もう濃い湯気が立ち込めている。罪人のファッションの甲斐もあり、浴場は刺青のデパートのようだった。
たらいで頭を洗う窃盗犯を通りすぎると、奥の湯船から極道が立ち上がった。若くはないし、苦労してきた顔付きだった。しかし、体は締まっている。水面から脇腹をよじるように上がると、背中いっぱいの鯉が、活発に撥ねた。
代わるがわる湯船に入ると、両端に中国人が坐っていて、私に挨拶をした。発音がつたなく、中国語で良いと返事すると、ニーハオ、ニーハオと口々にお辞儀した。片方は偽札を刷って捕まり、もう一方は容疑、不明。
どやどやと爺さんが浴場に入った。どのくらい牢屋に居るのか知ったことではないが、余命が五分もなさそうな歩き方だった。
たらいにお湯を注いで、思い切り禿げ頭に掛けた。熱湯に巻き込まれ、周囲の輩がふざけんなよと洩らした。その割に、若造がシャワーを使うと怒鳴り散らした。
爺さんがシャンプーを流す時、輩は看守の目を盗んで、死角からシャンプーをふり掛けた。いくら爺さんが頭を擦っても、泡が取れない。中国人二人と一緒になって私は笑った。安い海老をさっと湯通しするような入浴だった。風呂を出ても、湯気は肌をはなれなかった。
脱衣所を出ると、看守が待っている。一人いっぽんと定められた綿棒で耳を清掃する。看守は綿棒がすべて返却されるまで、立ち通していた。
運動場に案内されると、四方をアスファルトに囲われた狭い空間だった。ヤクザ映画でひと悶着あるような、風通しの良い景色ではない。壁に据えられた鏡を利用して、囚人たちは髭を剃っている。
電気剃刀が貸し出され、文句を言い合う呼吸の中で、私もシェービングのスイッチを入れる。話し声がよく通り、思わず見上げてみると、つつ抜けの天井から四角四面の青空が見えた。そうか、俺は牢獄に落ちたんだなと考えた。
案外さっぱり仕上がったな満足した時、髪を後ろで束ねた小男に話をふられた。チンピラらしく肩を揺らして近づいてきた。
「なにやったの」
私は返事に困ってしまう。小男のにやつきは悪意によるものか、好奇心の働きか、あるいは両方か判断できなかった。
「まあ、ちょっと」
「ちょっとって言う人はピンだな」
ピンとはどういう意味かと考え、廊下を歩いていると、余罪の有無かもしれないと気づいた。廊下の端に台車が停まり、本が収納されていた。二日目から、読書が許される。ラインナップは素晴らしかった。
掘り出しものの『和英対照仏教聖典』を素早く抜いた。馬鹿に立派な装丁なので、いざとなった時に強い武器になる。残りは『村上春樹 雑文集』とカズオ・イシグロの『日の名残』を借りた。
牢屋に坐り、ニベアを塗って、カズオ・イシグロを読み始めると、
「二九番、二九番」
と看守に叫び出された。
検察庁で調べがあるという。これ以上、私の犯行に究明すべき事実があるなら、退屈しないで済むのだが……
身体検察と手錠での拘束を終えて、紐でつながった罪人たちが歩き出した。
階段を上がらなければならず、足並みをそろえないと、半グレの踵を踏んでしまう危険な行進だった。我々は、地上の階に出た。
廊下の先はぼんやり明るく、こちらに冷気を流し込み、囚人たちが外に出ると、署の裏口にバスが横付けされている。冷やかすような時雨が渡っていた。四、五人の警官が囚人を濡らさないように、検察庁行きのランウェイに傘を添えた。
山の上の学校に、初めて登校した時も、こんな気分だったかと考える間に、囚人たちが決められた座席に坐り、バスは滑るような無音で走り出した。
高反発な木のベンチに一時間ほど坐らされ、図らずもうんこ座りの私である。堪え難いのは、斜向かいの黒人だった。
小声でラップを歌っている。
「うるせえ」
と看守に怒鳴られようとも、また歌い出す。怒鳴ってやろうかと考えたが、検察庁では私にも無駄口を利く権利がない。なによりうずくまった獣みたいに巨躯な黒人だった。タランティーノの映画の用心棒にしか見えなかった。
二、三時間待たされ、検事と話すチャンスが訪れた。ゲシュタルト崩壊するほどに韻を踏むラップから解放されて、安心した。
手錠を締めなおし、腰を紐で巻かれて、看守と二人でエレベーターに乗った。「めちゃくちゃ混んでいて、大変ですね」とねぎらうと、「喋るな。壁の方を向け」と、銃殺される五秒前のようなことを言われた。これには傷付いた。
エレベーターは上昇した。何階層に向かったか、はっきりしなかった。おそらく天に召されるほどには高くなかったろうが。
小ぎれいな廊下の先の、無機質な扉を開けると、私と検事の間がアクリルで仕切ってあった。
女が奥に坐っている。小綺麗で、よく喋れそうな女だった。
待遇の面ではやや不満があるものの、この職業は自分に合っている、隙のない仕事をしなければと考えていそうだった。法学部時代に恋人を二人ほど変えはしたが、落ち着いた恋愛をして所帯を持った感じと言えば良いのか、私のような男には手厳しそうだった。
検事のそばに記録係らしい男も付き添っている。お勉強は出来るに違いない、しかしながら冴えない顔だった。
黒縁眼鏡で知的に決めたつもりだろうか。ダイソーの老眼鏡にしか見えない。スーツのサイズは合っていないし、なんの冗談だろうか、ピンクのネクタイを締めている。私を縛る紐のほうがまだお洒落だろう。以後この男については一切、描写しない。
検事は、言いたくないことは言わなくて良い、ただ嘘を吐いても良いということではないと説明してから、被害者をどう殴ったのかと質問した。
記憶がはっきりしないと前置きして、ばちんばちん殴ったと答えると、検事は、ばちんばちん、と復唱して苦笑いした。
モダンバレエの振り付けではあるまいし、手足をどう出したかなど覚えているはずがない。前科者の男と付き合ったことがないのだろうか?
「拘留は十日までと決まっていますが、何度でも延長することができます」
検事がばちんばちん説明した。
「拘留が決まった場合、資力が四十万円以下であるなら国選弁護人を付ける権利があります。希望しますか?」
「そうですね」
そうして部屋から退出した。久しぶりに女と喋ったのに楽しくなかった。黒人ラッパーの斜向かいにまた坐った。特殊詐欺をやったヤクザの言うヨンパチの内、半分の時間が経とうとしていた。
翌日、検察庁にまた出向くと、裁判官から拘留質問をされた。検事と同じ質問をするばかりで、跳ねかえる気力はもうない。
格子戸ごしに、看守が書類を提示した。十日間の拘留が決まった。
理由の欄には、一に虚偽の供述の疑い、二に証拠隠滅、逃亡の恐れがあると書かれていた。ああ、デートに間に合わないなと考えた。
「逆走、逆走」
留置所よりシリアスな看守が叫び、縄の行進が始まった。
帰りのバスに乗ると、網目状の窓から、緑を織り込んだ町の風景が広がっている。イケアの青い建築の下で、人びとが行き交うのが見える。濡れたアスファルトは、不思議とグラマラスだった。
桜は雨にあおられて、黒い光沢の路地に、ぱあっと花びらを散らした。満開には早かったのに、花もようだけ残して、散ってしまった。うす暗い護送車の窓辺から、この町に住みはじめて、やっと美しい風景を見つけた。
しかし窓ガラスのスモークに遮られ、通行人は罪人の姿を見ることがない。
留置所に帰ると、おい、長い社会科見学だなあ、と特殊詐欺にからかわれてしまった。どうやら被害届が出ている嫌いがある。無免許じいさんは、お前も被害届を出せと騒いでいる。牢獄から被害届を出すとは、斬新な捜査妨害だろうが、まもなく国選弁護人が来た。
初めて入った面会室に、女の弁護人が坐っていた。やはり若くはない。パンツスーツに、襟の広いグリーンのシャツを合わせている。マッチングアプリで初めて会った男女のように、うやうやしく挨拶し、ひとまず事件の話になった。
「殴ったの?」
「うっかり殴ってしまいました」
「何回うっかり殴ったの?」
「顔を三、四回殴って、蹴りを二回、頭突きを一回ですね」
「二人、殴ったんだって?」
「いや。殴ったのは一人です」
「やっちゃったね」
「そうですね。検事はどうしたら釈放してくれるんでしょうか」
「それがわかんないから相談しに来てるわけ」
「そうか」
「示談するのがいちばん手っ取り早いと思う。相手はお金なさそうなおじさんだった?」
「そうですね。だから、殴ったってのはあります」
弁護人は笑っている。村上春樹の小説に登場するエネルギッシュな女みたいだった。少なくとも、検事よりはタイプだった。
「ねえ、お金はあるの?」
「払いたくない。服を汚されたし」
「だって、相手は暴行だけど、ボクは傷害をやったのよ。分が悪いってこと。抵抗すると罰金刑になるし、再拘留になると思う。示談しちゃったほうがいいと思う」
「いけすかないけど、給料日を過ぎてるから、多少はあると思います。いくらが相場ですか」
「初めてなら、人を殴った時の相場は二十万円くらい」
久しぶりに声を出して笑ってしまった。
「高い勉強料だね。キャッシュカードは持ってる? 宅下げしてくれれば、わたしが引き出して被害者と話してみる」
「じゃあ、お預けします」
「二十万円とキャッシュカードを弁護人様にお預けするって一筆ちょうだい」
「それはいいけど、被害者様に謝罪文でも書くべきですか」
「いちおう書いたほうがいい。染みないものでも食べて下さいって」
「あんなに痛みつけたのだから、何を食っても染みるでしょうね。キャッシュカードは預けます。あと一つお願いがあります」
「はい」
「本を差し入れて貰えませんか。代金はお支払いしますので。『死に至る病』という本です」
「ちょっとメモさせて。タイトルはなんだっけ?」
「ですから、『死に至る病』という本です」
「著者は」
「キェルケゴール」
「は」
「キェルケゴール」
「ゆっくり言って」
「キェ、ル、ケ、ゴール」
「ケ、ル、ケ……」
「ゴール」
「ケルケゴール?」
「カキクケコの『キ』が頭文字です。その次が捨て仮名の『ェ』です」
「キェ、ル、ケ、ゴール?」
「その通りです。キェルケゴールはデンマーク人です。僕もデンマーク語は正確に発音で出来ませんが、それで良いと思います。『死に至る病』は、岩波文庫から出ているはずです。お手隙の時があれば、差し入れて頂きたい。二千円あれば買えますので」
「本はアマゾンでしか買わないから、届いたらそっちに転送する。二十万と二千円を引き出していいのね」
「良いですよ」
「ほかに不安なことは」
「留置中にデートをすっぽかしてしまいました」
「それは罪が重いね」
「ちなみに『死に至る病』とは絶望のことです。僕も絶望しないようにします」
「大丈夫よ。死刑に至る罪じゃないから」
なかなか心強い人で、お喋りしていても楽しかったものの、「進展があったらくる」と言い残して、国選弁護人は素早く部屋を出て行った。
『死に至る病』を本当に送ってくれるか、ひどく心配する日々だった。いま読まねばという想いは強まるばかりで、大学時代に教師が言ったフレーズが頭をよぎった。
「研究職につかないなら、思想をやる時間は限られているんだよ。まず学生時代、次に老後だね」
私の弁で訂正するなら、もう一つ、精読にむいた時間がある。牢獄の時間だ。
二日が経ち、なかばふて腐れていると、ようやくデンマークの待ち人が来て、私は大はしゃぎして受領書にサインした。
デンマーク語の独訳を重訳しているせいか、表現が硬い。もっとも、キェルケゴールの筆致かもしれない。でたらめな翻訳とも思えなかった。
しかし、丁寧に読んでいけば、筋は通っている。ドイツ語の長文は、一文いちぶんを前後させ、入れ子構造を取りながら、美しい知恵の輪をなしている。
この輪の繋がりこそが論理そのものであり、論理は私に静かな活気を与えた。朝から晩まで、牢でロンリーな論理を弄していた。
学校の図書室に篭もり、小説を書くのに疲れると、三人で遊んだ夏がリフレインした。
私の育った町は草木がおびただしく、駅から歩いて間もない所に、小川の流れる自然公園が広がっている。
日射しの強い時期を過ぎて、枝葉に覆われた川辺はさびしげだった。
川の流れは澄んでいるけれど、水面に明るい反射はなく、真夏には耳を聾する地虫の声も、蛙の入水する音も響かなかった。
浅瀬に鯉が打ち上がって、小蝿をはべらせて死んでいる。ふるさとの案内はうまくいかなった。
もはや二人の関心は、小川を辿った先にあるという、洞窟状の防空壕にしかなかった。幼い頃、散歩に連れられ、祖父から聞いた怪談だった。下町で空襲に遭った祖父。この片田舎の防空壕に隠れたことがあるのか、私のもっとも古い記憶といっても差し支えない一場面で、はっきりしなかった。
三人で防空壕へと歩いていくと、川辺の舗装された道は途切れ、ひたひた流れる水面を渡るうちに、藪蚊の羽音が高くなる。日傘をおともにするNのガールフレンドには辛く、二、三十分ほど歩いてから、彼女は引き返そうと言った。
案内役の私はどちらでも構わず、恋人同士で、もう少し歩こう、引き返そうという応酬になり、彼女は大泣きしてしまった。
「あいつ、生意気だろう」笑いながらNが言った。「今度、三人でセックスしよう」
「そいつは、理性的じゃないな」
「理性か。聞きたいのだけれど、人体を解剖したら、理性という器官が出てくるのかい。理性なんて迷信なんだよ。だって、世界は残酷なことで溢れかえっているじゃないか」
私は黙り込み、Nと肩をならべて、彼女が小川を渡るのを見つめ──、
図書室での居眠りは禁じられている。そっと司書が私の肩に手を置いた。私に訪れたのは、進路を放り出したことからくる空虚な感じだった。Nたちは特進コースのカリキュラムで、受験勉強にいそがしい。
そろそろ図書室を出ようとした時、Nのガールフレンドが入ってきた。こちらに気付いていないのか、書架のすき間に入り、見えなくなってしまった。この頃、受験勉強で忙しいのか、あまり登校していなかった。おどかしてやろうと思い、後を追うと歴史の書架の前だった。
「勉強しなくていいの?」
背中から話し掛けても、Nのガールフレンドは驚かなかった。振り返ってぼんやり私を見つめている。どこにも焦点の合わない、真っ黒な瞳だった。
「Nは国立に行くのかな。缶詰だな」
「どうでもいい、そんなこと」
「今日はサボってるのか」
「あなたに言われたくないよ。特進じゃないからって、余裕ぶっこいて」
「大人は焦ってるみたいだ」
「とくに用事があってきたわけじゃないよ、わたしは」
不思議な奴だなと改めて考えた。二人でNとどういう会話をしているのか、想像もつかなかった。
「おもしろい本をおしえてよ」
「そんな本、ここにはない」
「Nみたいなこと言う」
「うるせえよ」
「ここってCDは置いてあるの?」
二人で視聴覚のコーナーに入り、古ぼけたジャケットを一枚いちまい拾い上げ、すき間に戻した。Nのガールフレンドは、ライナーノーツを眺めていた。
「ベンジャミン・ブリテン」
彼女が呟いた。私はクラシックなど小耳に挟んだこともない。窓辺に面した小さな机に、オーディオコンポが据えつけてあった。
二人でイヤホンを分け合い、慣れた手つきで彼女が再生ボタンを押した。
ロストロポーヴィチが演奏するブリテンのチェロ組曲だった。ボリュームが高すぎて、最初の重音奏法に二人でのけぞってしまう。彼女の笑顔を見たのは、多分、初めてだったと思う。
「聞いていて、不安になるな」
「そうかな。とてもいいと思うけど」
「こんなのをずっと聞いてるのか」
「チェロはいいよ。人間とおんなじ音域で奏でるの」
「これが人間と同じ音域?」
「クラシックは聞かないの?」
「育ちが悪いから、聞かない」
「でも、いま聞いてる」
「なにも響かないよ。家庭になかった音だから」
「わたしは小さい頃、ピアノを習っていました」
彼女は急に背筋を伸ばし、よそよしい口調を取った。
「練習は辛かったけれど、音楽はわたしに耳がついていることを教えてくれました。手先がふるえるようになってやめました」
「そっか。気の毒だったね」
「ありがとう」
「Nとは会ってるの?」
「もともと、そんなに会わなかったかな。もう帰らなきゃ」
それから、二人と会うことは二度となかった。彼女からメールが届いて、妊娠したと知らされ——、
久しぶりです。元気にしていますか。わたしはあまり元気ではないです。
学校に行けていないのは、彼の子どもがお腹にいるからです。世間体というものがあるそうなのです。
歩き方を覚えた時くらいから、母のご機嫌を取っていました。
親戚の子どもたちのなかで、わたしがいちばん可愛らしくて、賢かったのです。母はじぶんの夢とか希望を、わたしに託していたのだと思います。
はじめて小学校に行った日、綺麗なレースの飾りがついたワンピースに、頭に大きなリボンをつけていました。男の子から好かれたのですが、女の子からはいじめられました。でも、嫌じゃなかった気がします。
ランドセルの中に大きな石を詰められた時もありました。石を大事に取っておきました。うちにかえって、引き出しのなかから石を出して、学習机に置いてずっと眺めていました。
表面が滑らかで、丸々とした、うすい緑いろの石でした。嫉妬がそこに結晶していました。うっとりするように、美しい石でした。その石がわたしの重みそのものだと気づくまでは。
男の子とお付き合いするようになって、いやがらせはもっとひどくなりました。中学三年生のときには、大学生とデートしたりしていました。みんな顔が良くて、汚れの一つもないシャツとスニーカーを身に着けた男の子たちでした。
男の子たちはみんな親切で、けれど一度体を重ねたあとでは、なにかがそれまでと決定的に違っていました。
わたしはなんでも知っていたのです。たくさん本を読んで、ピアノの難しい曲を初見で弾いたりしました。両親とか、先生が、目配せ一つで、わたしを良い子だと勘違いすることも。
でも、わたしをわたしにしてくれるものを見つけることが出来ませんでした。どんなに難しい本も、女の扱いに慣れている男の子も、そんなことは教えてくれませんでした。
だから、わたしという壁をぶち破るために、たくさんの男の子たちと寝ました。体とか心に悪いことばかりしました。わたしは、背伸びして、ひねこびて、駄目になってしまいました。
高校二年生のころ、そそのかされてたばこを吸いました。ほんとうは発覚するはずなんてなかったと思います。でも、もらった煙草を、あの石とか、手ひどく振った男の子たちの恋文と一緒に、引き出しのなかにしまっていたのです。
期待を一心に背負ったわたしは、母から監視されていました。煙草を見つけて、母はわたしのほっぺたをみみずばれが出来るくらい、強くぶちました。
あなたと同じ学校にきて、N君と出会いました。かれが、かれだけが、わたしの汚らしい部分を、そのまま愛してくれました。お腹にいる赤ちゃんは、わたしがやっと見つけた個性です。それを手放したら、またわたしは空っぽになってしまいます。そんなに邪悪でも、命なのです。
こんど、会えませんか? 赤ちゃんを産むと言ったら、両親に出ていけと言われました。別の男の人のおうちで過ごしているから、暇なのです。これで良かったのか、じぶんでもよくわかりません。
でも、はっきりしたことがあります。
わたし、わたし、女なんかに産まれてくるんじゃなかった。
この文面が私を悲しみの底に突き落としたのならば、どれだけ良かっただろうか。私は恐ろしい無感覚に陥った。どういう言葉を掛けたら良いのか棚上げにしたまま、ただ月日が過ぎていった。
会いに行こうと考えて、最後に聞いた彼女の声色が押しとどめる。私は決して二人の理解者ではなく、重い慰めであったり、考えなしの助言によって、二人の情が萎れてしまうことを恐れた。ある側面から考えれば、彼女が求めていたのは、Nの不安な表情だったのかもしれない。
──少年を卒業した私に懺悔が許されるなら、一時の好意と、自己犠牲による支えとの間には、深い川のような幅が広がっていた。この時の私は、彼女の不安げな表情に、自身の弱さを見出したに過ぎなかった。思慮深いことばで慰めることが叶わなくとも、ただ悲しみを共有することは出来た。
二人を見失ってから、この足を支えてくれる場を探して、さして勉強するつもりのない学科を進路に選んだ。目眩のように山は赤く色づき、枯れ果てて、降り積もった雪がため息を白くした。
少年の感性からして、余りに長いギャップイヤーが過ぎて、Nから電話が掛かってきたのは、卒業までわずかとなった時期だった。
「悪かった」
長い沈黙が続いて、私はため息にも似た深呼吸をした。
「なにも謝ることはないよ。不安だっただけだ」
「そっか」
「恋人は元気にしてるの」
「してない」
迷いのない、短い返事だった。
「きっとそうだろうと思った」
「どうして」
「君の声を聞いても、そこにあるべき何かがなかったから」
「なにがなかったんだろう」
「こんな言葉は使いたくないけど、愛かもしれない」
「愛なんてものを信じているとは、意外だったな」
私はほとんど絶望して、そのために落ち着き払ってこう話した。
「愛は信じてないよ。でも、愛という言葉を口にしてしまう、ナイーブな人間は信じるよ」
「そうか。君をそこまで不安にしてしまったんだね」
「不安になる感性があってよかったと思う。君には信仰があったっけ」
「ないよ。芽生えることもないよ」
Nはしおらしく、私のニュアンスが伝わったのかもしれない。関係を修復するには、もう遅かった。
「山の上で、信心が芽生えたよ。この僕をいじめて、仲間はずれにする神さまを、主として崇めることにしたよ。主は与え、主は奪うと聖書に書いてあるだろう。君たちとのお別れは、素晴らしい恩寵だった。ありがとう」
「皮肉なのか、本音なのか、よくわからないな」
「僕にもわからないな」
二人は長い間、黙り込んだ。最後にNから聞いたのは、ただの皮肉だった。
「いつか君も恋愛をすれば、こういう状況のやるせなさが分かるよ」
「その時はいい友人をなじったことを、精一杯、後悔したいと思う。それじゃあ、元気で」
どちらから電話を切ったのか、思い出せない。これが最後の会話だった。
シスターには塞ぎ込んだ私が気がかりに違いなく、すれ違った廊下で何度も声を掛けられた。
話すべきことがないと言うより、浮かばなかった。親切な教師に、三人は友だちだったじゃないかと、決して言わせたくはなかった。ときどき会って、尻尾を踏まないうちに撤退し、握手も喧嘩もなかったけれど、悪くない関係だったと思う。
辛口の恩寵だったけれど、険しい道を歩く二人のしあわせを祈った。ハレルヤ、私はまた一人だった。
昼食が終わり、牢獄の外で、そっと雨が降り始めた。
どこかの房で揉めごとがあった。もうすぐルームメイトをシャッフルするそうだが、正確なところは分からない。寝そべりながら、聖書を開いた——『キリストは地上に生を受けた時、激しい叫びと涙によって、ご自身を死からお救いになるように、あの方へと祈りを捧げました。そして強い信仰によって恐れから自由になったのです』
犯罪パンで腹が一杯になり、私は煙草が吸いたいと口走った。同じ房のリピーターは昔は朝に吸えたんだけどなと言った。煙草が吸いたいあまり、もっと早く生を受け、もっと早く捕まっていたら、煙草が吸えたのにと考える。つまり、煙草が吸いたかった。
苛立っているのは私だけではない。特殊詐欺も、私選弁護人のくる時刻になると、落ち着きがなくなる。看守に呼ばれると、尻尾をふって面会室に歩いていく。無免許じいさんと罪状不明のおっさんも気疲れした。
「あのぶんじゃ、検事がネタを握ってるんだろうな」
無免許じいさんはあぐらを掻いて、ちり紙を畳んでいる。
「有罪になったら長くなる。詐欺だし」
「どのくらいですか」
「知らんけど、ヤクザもんは長いから」
「終身刑にしたらいい」
罪状不明の男が久しぶりに喋った。彼はルームメイトの特殊詐欺と仲が芳しくない。
「いびきがうるせぇとか言ってきやがって。自分がいちばんうるせぇじゃねぇか」
「僕はうるさいかな」
「お前は獄死したみたいに寝てるよ」
「まあ、部屋が代わったら、よく眠れますよ」
「お前さ、あんな奴と話すなよ。あんまり仲良くなると、出てからもつるむことになるぞ。また捕まるかもしれんぞ。ヤクザだから」
十分後に帰ってきた特殊詐欺はへらへらしていた。ヤケになっているようだった。
呆然として眺めていると、私の肩をぱんぱん小突いてきた。みな気味悪がったが、飯の時間だった。
カーペットの上にござを敷き、夕食を待つと、中身がよくわからない揚げ物が配膳された。無免許じいさんはみそ汁にしょう油を注ぎ、ずるずる音を立てて啜った。上の歯がほとんどなかった。
夕食を終えて、よその房の若い衆が相撲を取って大騒ぎしている。思わず、うるせえなと私はつぶやいた。全員が、苛立っていた。
その晩、特殊詐欺は食後の運動として、私にマス・ボクシングを申し込んできた。ルームメイトはうんざりした顔である。
特殊詐欺は年寄りではないけれど、頭髪は禿げ上がり、運転手付きを自慢するだけあって肥っていた。
当て身を抜きにしてしまえば、腕に速度も出なければ、足運びも上等ではない。息を荒くして、額に汗がほとばしっている。タンクトップを脱ぎ、彫り物を出しても、こうなってしまえば威圧感はない。段々と相手は苛立ちを覚えているようだった。
「お前、腕が細いな。殴ってこいよ」
「いやですよ」
「いいから、殴れよ」
「なんで」
手のひらでミットを形づくり、特殊詐欺は青筋を立て、本気の一撃を待っている。遠慮がちに殴ると、乾いた音がぱんと鳴った。
「本気で殴れ」
と怒鳴ってきた。腰をひねり、拳をねじ込むと、特殊詐欺の手首に当たり、骨どうしがぶつかる音がした。腕の筋張ったところへと痛みが走り、彼は腰を曲げてうめいた。
「てめえ、痛ぇんだよ、馬鹿」
「もうやめとけ」
無免許じいさんが口を出した時、就寝の時刻が近づいて、看守が本を返却するよう遠くで叫び出した。
消灯の時刻を過ぎても、特殊詐欺は寝付きが悪く、寝返りを打ちながら悪態をついた。冬眠に入れなかった熊のようだった。巨体が転がり、こちらと目が合った。餓鬼は早く寝ろ、と特殊詐欺は言った。
「寝るのがもったいなんですよ」
「修学旅行みたいだな」
「まあ、そうかもしれない。一つ、聞いてもいいですか」
「あ」
「あなたが詐欺を指示したんですか」
「文句あるのか」
「ないですよ。僕は暴力を否定したことがないんですから」
「だから捕ったんだよ。お前、更生の見込みがないな」
「みんな、暴力とはなにかという問いから逃げたいだけなんですよ」
特殊詐欺はうなるような声で笑い出した。
「なにか、おかしいですか」
「お前は頭がおかしいんだよ」
「そうかもしれない」
「頭おかしいけど、根性あるよ、お前。ちょっと見直したよ」
「そうですか」
「お前の言う通りだよ。なにが良くて、なにが悪いなんて、やったあとじゃなきゃ分からないんだ。結果がどうであれ、俺は反省しない。反省なんて子どものするもんだ。男は犯罪だぜ。反省じゃない」
最後の台詞は夢うつつで、何を言っているのか理解出来なかったけれど、このヤクザ者からなにか詩的な力を感じてしまった。救われたような気がしていた。ゆっくりと寝返りを打ち、男は大きないびきをかき始めた。私も安心して深い眠りに落ちていった。
翌朝、噂通りに部屋替えが行われ、分かれる前に、特殊詐欺はなにかあったら俺に言えと親しげな口調で言った。こちらが下手に出れば、面倒見が良い男なのかもしれないが、その目つきは穏やかではなかった。
「じゃあ、うざいやつがいたらボコボコにしてください」
「再逮捕になるだろうが」
「まあ」
「お前、舐めてるのか」
「舐めてないですよ」
沈黙が流れ、特殊詐欺は表情を崩して、まぶたが蕩けるように目を細めた。
前科九犯などと偉そうなこと言っている。そこまで下手を打てば、チンピラとしても使い物にならないだろう。ヤクザになって日が浅いのか、金が足りないのか、背中の彫り物は未完成だった。図体が馬鹿でかい、お人好しなヤクザだった。
なにをやったのか知ったことではないが、次の房で一緒になった連中を好きになれなかった。
怖じ気づいて口を利かない子どもと、豚箱で二ヶ月飼われただけで、先輩面のおっさんだった。
このおっさんは小言が、うるさい。ティッシュはこう使うと良い、マスクを付けていれば反省していると思われるなどと、お節介を働こうとする。気色悪かった。
布団の敷く位置を指示されて、ついに私は我慢できずに、枕を寝床に叩きつけた。二人とも見て見ないふりをして、毛布を広げている。また因縁を付けてきたら、殴ってやろうと決心して就寝した。
房は三つに別れている。キェルケゴールに向き合い、疲れるとスティーブン・キングでお口直しする翌日だった。
もはや時間は無為に、よどみなく流れていった。かつて時間は書物にあられた時制と、激流のように過ぎていく時刻とに別れていた。牢獄の時間は、たった一つだった。
なにも迷うこともなく、ルームメイトとの諍いをのぞけば、気分は穏やかだった。
誰かしらの機嫌を取らなくて良かった。ごみの収集時間を気にする必要もなければ、残業もない。好きなだけものを考える余裕があるという点で、牢獄は世間よりも自由だった。被害者に手紙を書くと言って、あり金で便箋を買い、ボールペンを借りて、この小説を書いた。
ものを読んだり、執筆に集中出来たのはありがたかったが、たった一つの時間はまもなく砕けちった。看守に面会の予定が入ったと言われ、どこの野次馬かといぶかしむと、母が申し込んでいた。職場から、ご子息が無断欠勤を続けていると、連絡があったらしい。
面会室の母の面差しには、世話を焼いてもかまわない、しかし腹に一物あり、目上の者として説教しようという雰囲気があった。
となりの父は、もともと子どものしつけに無頓着で、尻の持って行き場がないようだった。まるで黄昏どきの農夫のようだった。極道とじゃれ合った緊張から一転して、私としても、両親との面会にはリアリティがなかった。
「なかの生活はどんな感じ?」
「別に大丈夫ですよ。娑婆より健全ですから」
この返事が神経を逆撫でし、母は怒濤のようにまくし立てた。
「なにが大丈夫なんだ。これが大丈夫だから、お前は馬鹿息子なんだよ。いっぺんカマでも掘られたらいい」
こちら側につき添った看守が笑いを堪えていた。こうなってしまえば、好きに言わせておくしかなく、私からの質問は一つだけだった。
「妹は元気ですか」
両親は急所を突かれたような顔をした。心外だった。身重である妹に、兄貴が捕まった話が出来るわけもなかったけれども。そのあと、母が連れてきた私選弁護人がやってきたが、被疑者の権利として断った。
面会を終えて、去勢された猫のようにカーペットに横たわった。ルームメイトと喧嘩して、再拘留も良いかもしれないと考えていると、普段からうるさいおっさん静かに読書していた。表紙からして、学校のテキストのようだった。
素直な人だと感心していると、彼と目が合った。そのままの姿勢で、お互いに微動だにしなかった。相手のまなざしは子どものようで、反応に困っているようだった。思い切って、なにを読んでいるのかと聞くと、彼は恥ずかしそうに口ごもった。
「どうしてそんなものを。ここで学ぼうとするなんて、偉いですね」
「いえ。分からないことばかりです」
「僕だってそうです。分かりたくないんですから」
私の返事を聞いて、二一番と命名された囚人は不思議そうな顔をした。テキストを大事そうに抱え込んだ。
「二九番さんは、勉強が出来ますか?」
「出来ません。不登校でした」
「文系ですか、理系ですか」
「あえていえば、文系かもしれない」
二一番はテキストをそっと開き、ページに顔を寄せて朗読をはじめた。
「織田信長の家臣である明智光秀が、謀反を起こしたのは、その、」
「本能寺の変ですか」
「うん。そうだ。本能寺の変ですね」
「一五八二年ですね」
「ええ、なんでわかるんですか」
「いい覚え方があるんです」
「なんですか、教えてくださいよ」
彼はやや憤っていた。私は悪意を働かせたのではなかった。
「本能寺の変の図は付いていますか」
「付いてます」
「光秀のパンツの柄は?」
「光秀が見つかりませんよ」
「苺のパンツを履いてます」
「うそですよ、そんなの」
「一五八二、苺のパンツ」
私が吹き出してしまうと、相手の囚人はしてやられたといった風に頭を掻き、部屋のすみの少年は黙り込んだままだった。いろいろ教えてくださいと二一番に頼まれたが、そんなことは出来ないと返事した。夜中まで歴史のクイズは続いて、二一番は寂しそうに出す問題がなくなったと言った。
彼はぼちぼち事件のことを語り出した。あいまいな言い方で逮捕された気持ちを説明するので、相変わらずなにをやったのか不明だけれど、どうやら痴情のもつれのようなニュアンスがあった。
「人を殺したんですか?」
二一番は苦笑いした。
「勘弁して下さいよ」
彼の興味は英語にうつり、自動詞と他動詞を説明するのになかなか苦労した——「捕まるは自動詞で、殴るは他動詞なんです」
大学を三年で中退するのだから、母が泣き叫んでもしかたないと腹を括っていたのに、台所をナプキンで拭きながら、そう、分かった、とだけ言われた。
呆れ返っているというより、涙や憤りを見せるだけの、生命力を涸らしてしまったのかもしれない。台所の前に置かれた円卓で、私は頬杖を着いて叱責を待っている。
「なにかやりたいことはないの」
母は静かにささやいた。釣り針を落とす音にしか聞こえなかった。
「わかるように言ってほしいの。手伝えるかどうか、考えてみたいから」
「なにもないですよ。本当に」
「そう、しかたないね。夕飯は食べていったら。チキンカレーにしたの」
「ハンバーガーを食べにいきます」
「そんなものばっかり食べてちゃ駄目だよ。美味しいんだろうけど」
「別に、旨くないです。もう帰ってもいいですか」
「あんた、父親に似てきたね」
「ありがとう」
「どういたしまして」
生まれ育った町を卑屈な気持ちで歩いた。快速でT駅まではこばれる間に、奇妙な夢を見た。
やわらかい土を指先でつかみ、墓を掘る。夢中で掘り進めていたら、墓穴から抜け出せなくなった。なぜ墓穴を掘ったのか、思い出せないまま掘り進めていると、私の肌は蠟が溶けたように汗ばんだ。墓穴が暑いのは、地球の核心に近づいたからだろう。
土のなかに、固いものを見つけた。灰色の棺だった。
棺のふたを開けてみる。ふしぎな生きものが、からだを横たえていた。
シルエットは人間のたぐいだった。全身をクリーム色の粘膜で覆っている。呼吸のリズムで膜を伸縮させて、大気をひゅうひゅうと鳴らしている。
触れると、ふいに膜は千切れた。紅い液がにじんだ。
指でこすって、膜を剥がしていく。生きものは保護を失った。とろけそうな筋肉は、白い繊維をまだらに織り込んで、呼吸するたびに、肉の凝集をゆるめた。羽のようなあばらや、胸や腹部に埋まった核心が見えかくれする。
好奇心にほだされて、顔のヴェールを剥がすと、女が眠っていた。見覚えのある顔だったけれど、名前は思い出せなかった。彼女の表面に、まるまるとした滴が浮かび始めて、棺の底に液が溜まっていく。そのうち気化して失われてしまうに違いない。
棺に入って内側から、ふたを閉めた。
私も、彼女も、棺すらもみんな溶けてしまって、地層の一部になり、草花として生まれ変わった。
草花は大人しい獣に食まれ、獣もほかの獣に食べられた。
獣は死に、虫や土の肥やしになった。そうやって、また私は地下にもぐっていく。あちこちを循環するのはたのしかった。この世界は、どこまでも私の領土だった──、
目が覚めるとT駅に、電車は停まっていた。ドアが締まる直前に、プラットフォームへ飛び出した。チンピラにぶつかりそうになり、悪態を吐かれた。改札を過ぎてから、いやな気持ちを振り切って、夜の街を走って行った。
寝つきが悪く、昼ごろに目覚めた。
放ったらかしにしていたRに電話を掛け、大学を辞めると告げた。中退に関してはなにも言われなかった。声色から、彼女の憤りがひりひり伝わってきた。
十五分、経ってから、Rが訪ねてきた。インターホンのモニター越しに、彼女の無表情が写っていた。居留守を使おうと考えたけれど、彼女は身じろぎしなかった。モニターが暗転し、ちょっと安心した直後に、もう一度ベルが鳴った。
重たい腰を上げて、ドアを開けると、思い切り顎をなぐられた。
Rは立ち尽くしたまま口をつぐみ、濁った目で私を睨みつけている。お互いに視線を逸らさず、私からすれば激怒した顔もチャーミングだったが、そんなことを言っている場合ではない。廊下に響くような大声をRは上げた。
「あんたと話してると、どうしようもなくいらいらする」
恐ろしい早口で、彼女が言った。
「なんであんたが母親に見捨てられてるのか、あたしには分かるよ。人間的な感情がないし、可愛くなかったんだろうね」
「そうかもしれない」
「なんなの、その握り拳は。やりかえせばいいんじゃないの」
「君は殴られたら言うことを聞くのか」
「やり返す」
「わかったから、とりあえず入れよ」
二人でリビングに入り、ラジオに耳を澄ました。目は合わせなかった。彼女は林檎の皮を果物ナイフで剥いて口に運び、口の端を舐めて、最悪、とつぶやいた。
電話が鳴った。Rに戦慄が走った。ガラステーブルの上でバイブレーションする携帯電話はやかましかった。私の父からの電話で、思い切って電源を切ってしまった。
「ごめん」
「別に。ちょっとびっくりしただけ。静かだったから」
「ほっぺたに林檎の皮がついてるよ」
意表を突かれて、恥じらいつつ、Rは頬をこすった。いたいけな気分で眺めていると、彼女は取ってよと言って苛立っていた。膝を立て、テーブルを回り、屑を払ってあげると、すぐそばのRにじっと見つめられた。
「あなたの顎も赤くなってる」
吐息に果実の香りが含まれていて、私は落ち着かなかった。
「これくらい何でもないよ。前はもっと腫れたしね」
「お母さんのこととか、言わなきゃよかった。ごめんなさい」
「気にしてねぇよ」
潤った女の顔が浮かんでいる。ほそい指がそっと傷に触れた。鈍い痛みにではなく、となり合わせになったのは久しぶりな気がして緊張した。
さりげなく離れて、Rは正座の足を組み直した。しおらしくしているけれど、すぐ調子に乗るに違いない。
彼女はひらめくような知性が働いて、揚げ足を取ることが趣味だった。一体何を食ったらそういうことを思いつくのか、不思議で、面白いことを口走り、自分を芸術家であると思い込んでいた。このような心理は、精神病と紙一重だった。病んでいて、思わせぶりだった。
「ねぇ、台所から糞みたいな匂いがするんだけど」
私は思わず笑ってしまった。見事な緩急だと思った。
「台所で糞はしないよ」
台所にはおびただしいボトルが積み上がっている。大掃除が始まった。二人でドアーズの『ソウル・キッチン』を歌いながら、ごみを分別し、食べかすを掃除機で吸引した。確かに台所に異臭が立ち込めており、酔った勢いで糞をしたのかといぶかしんだ。彼女とのいざこざと同時に、水に流してしまおうと考えた。
「ひどい英語だね」
掃除機に負けじと、Rが大声を出した。
「せっかく歌詞がいいのに。ジム・モリソンが化けて出るよ」
掃除が終わると、深夜の二時になっていた。二人でピルスナーを飲みながら、冷や奴に林檎をしぼった。
「よく噛んで、食べて」
言われた通りにすると、林檎の香りが鼻の奥ではじけた。旨くて、切なくなり——、
久しぶりに会って、狭いベッドで寄りそったのに、セックスはしなかった。
不眠のまま寝返りを打つと、ゆっくりRが目を覚ました。カーテン越しに、街の灯りが潰れている。眠ったふりをするには、あまりに夜は長かった。眠れないのかいと聞くと、彼女は力なくうなずいた。ほんのり、濡れた髪の匂いがした。髪は黒々とつやめいて、暗い雰囲気に白い顔が埋まっているようだった。
「勉強したことをぜんぶ返すから、ねむれるようにしてほしい」
「ねむれるように、奇蹟を起こすよ」
Rの手をにぎると、自動車の遠ざかる音に合わせて、彼女の顔に青い影がすべった。痩せ衰えて死んだ祖父を思い出した。
「これからどうするつもりなの」
目を閉じたまま彼女がささやく。
「一生ベッドの上で這い回ってすごすの」
「君はどうするんだ」
「あたしは、まだ大学院にいる」
「キューバに亡命しようと思う。農夫になりたい。野菜を有機栽培したいな」
「亡命なんだ。罪状は」
「思考罪」
「いかがわしいことを考えた罪ってこと?」
「まあ、そうだね」
「スペイン語を喋ってみて」
「グラシャス、アミーゴ。チョート」
「どういう意味」
「感謝する、友よ。ちんこ」
私の胸に顔をうずめて、Rは笑い出した。
そのまま抱き合っていると、からだを小刻みに震わせて、彼女は泣きはじめた。
朝がおとずれるまで、おなじ姿勢を保ち続けていた。この抱擁にどういう意味があるのか悩みつつも、抱きしめる力を弱めなかった。
自意識の重みでベッドの表面が沈んでいき、二人で深い場所へと落ちていった。
夜を通してどんな話をしたのか思い出せないけれど、気障な話題を選ぶようにした。どうして世間はここまで偏狭なのかと、二人でいぶかしんだ。
そうやってお互いの孤独を持ち寄り、複数形の孤独にした。観念に立てこもり、世間に降伏する夢を見てから、また真っ白な朝を迎えた。
お茶をする金はない。芸術的な情熱もありはせず、女性への敬意などそもそも知らない。ぶらぶらと、二人で公園を散歩した。
気の利いたお世辞も、ハミングを交えたスキップもない。これをデートと呼ぶなら、つがいの鳥獣の社会性が強調されるべきだろう。私の半生のなかで、まあまあ幸福な時期だった。
歩きすぎてRの足にサンダルのストラップが食い込み、血がにじんだ。そうか、サンダルを履く季節かといぶかしんだら、もう夏だった。晴れ、ときどき出血、二人の心理は不安定だった。
ごちゃごちゃ軽口を叩かれ、木陰のベンチに坐ると、目の前に陽光をたたえた湖が広がっている。
水面の反射は明るいというより、あらゆる影を曝くようで、お天道様に顔向け出来ない、救われない魂には眩しすぎた。
「むかし、あの湖からバラバラ死体が出たらしいね」
私のトリヴィアを聞いて、あたしの足首もちぎれそう、とRは返事した。
「次はどこにいこうか」
「あなたに決めてほしいんだけど」
墓参りしようと提案すると、嫌がるに違いないという予想に反して、Rは二つ返事で了承した。どの故人を弔うのか、墓所がどこにあるのか、そんな質問はしなかった。
二人ともスイカのチャージが残っていたので、バスに乗った。さきほどまでの不機嫌はどこに行ったのか、Rは鼻歌を歌っていた。おそらくバッハの曲で、彼女らしいなと笑ってしまった。
「作曲はしてるの?」
「いつもしてますよ」
鼻につく声でRが答えた。
「小説は書いてるの?」
私は黙り込み、気に障ることだったかと、Rは気まずそうだった。
「君の鼻歌を聞いてるほうがいいよ。なにも考えなくていいから」
「そう言われちゃうと、すこし心外な気がする。あたしは音楽が専門なんだけど」
初めて会った時、Rは作曲していると恥ずかしそうに語った。出てくる話は芸術のことばかりで、何だかひねくれた女だなと考えた。
しばらく経ってからまた会うと、アリス・紗良・オットというピアニストの録音を聞いて欲しいと言われた。ムソルグスキーの『展覧会の絵』だった。素直に良かったと感想を伝えると、Rは勧めたことを忘れていた。
いつも早口で喋り、短く切りそろえた黒髪を揺らした。小柄なのに声が通り、怒り出すと手が付けられない女の子だった。
「気分を害したなら、いちおう謝るよ」
「いちおう謝ってるだけ進歩があるから、許します」
Rはケイト・スペードの鞄から、文庫本を取り出した。ユルスナールの『とどめの一撃』だった。
出会った頃のように彼女は快活で、もう一発殴られることはないだろう。もっとも、私の母を持ち出して罵倒してしまった罪悪感から、寛容になっているのかもしれないと考えた。
二人とも身内の話題を出す時は、最大限の注意を払うようにしていた。Rにとって最大のこじれは、彼女の兄との関係性だった。私のような人間にも冷やかすことが出来ず、こちらの妹の話題も出せなかった。
昨晩の口論には、聖域に踏み込みかねない危うさがあった。このデートには、戦後処理の緊張感があった。かき氷でも奢ってあげたら、すこし和むだろうか。しかし、そんな金はない。
墓所のずっと手前にバスは停まり、二人で山の道を歩いて行く。坂道を上がりながらも、Rは文句を言わなかった。私の引け目を感じ取っているに違いない。
テンポを合わせて歩いた。彼女は息をはずませた。手を差し出すと、赤ん坊のように濡れたてのひらが握り返した。黒いワンピースが陽光を反射させた。青筋の浮くうなじに、黒髪が張りつき、足は血まみれだった。
山を巻くカーブが終わり、目の前がひらくと、ビリヤード台のような土地に墓石がならんでいた。祖父の墓まで迷わずに向かい、火をつけた煙草で弔った。お盆の時期で、墓所は花々にあふれ、かえって人生の終着駅は寂しげだった。
彼女はしゃがみ込んで拝んだ。私は周囲をぶらぶらしながら煙草を吹かしていた。よその墓石から、お花を一輪ずつ盗んで束ねると、色とりどりの奇麗なブーケになった。
「なんでそういうことするの」
Rはあきれて果ててしまった。墓所でデートしたことはあるかと聞いても、そっぽを向いている。私は自分の顔をブーケで隠した。
「ボードレールみたいだろう」
なにがなんだか分からないようで、怪訝な顔をされてしまった。
「悪の華」
私が呟くと、彼女はうつむいて笑いを堪えた。
「困った爺さんだったよ」
私はブーケを振り回しながら話した。
「晩年は自転車で転んで、車椅子生活だった。ボケてたんだよ。それでも、人に世話されたくなかったから、うちでも、病院でも、手当たり次第に暴れて、最期は眠るように死んだ。火葬したら、デカい金属の部品が出てきた」
「部品」
「手術で大腿骨にボルトを入れたからね。ネジみたいなものだろうと思ってたら、『ターミネーター』の部品みたいな塊だったよ。あれは美しかったな。葬儀屋に処分させちゃったんだけど、持って帰れば良かった」
Rはそっと私の手を握った。悪の華を手向けてしまうと、私たちはバスの時刻を気にしはじめた。
彼女とは長続きしなかったというより、二人の関係性をうまく説明できないままで、別れ話をする必要もなかった。
夏の終わりに呼び出されカフェに出向くと、Rは張り詰めた表情で私を待っていた。気持ちが不安定なのか、別れ話なのか、どちらかだろうと考えたながら、まずいコーヒーを飲んだ。どうでもいい話題ばかりだった。
「なにかあったのか」
そう聞くと、Rは泣きそうな顔をした。堰を切ったように、兄さんのことを話し始めた。
「恋人じゃなくて、お兄ちゃんを探してたの」
「そうだったんだ。でも、それは無理だよ」
迷うことなく返事をすると、彼女は北国のほんとうのお兄ちゃんのもとに帰ってしまった。大学を辞めてからというもの、毎晩のようだった通話は、その日を境にして途絶えた。
それから、親の金で、色々な女と遊んでまわった。名前すら思い出せない女たちは、こちらの一方的な感傷で別れ話をしたのに、私を励まして去っていった。
クレジットカードの残債が積もり、仕送りが来なくなった。
それから、リクルートスーツで過ごす秋が始まった。
早朝のうすもやの中で、プラットフォームの時刻表はぼんやりしている。電車の窓辺から、墓石のような街並みを眺めていた。
彼女とまた会う理由ばかりを考えて、実際は会えずにいた。女が代わるたびにRの印象は薄れていく。しかし、彼女の顔立ちを忘却しても、忘却した事実は決して忘却しなかった。
かつて私がもっとも嫌悪していたはずの、世間に溢れる人間が目を覚ます。
洗面台の前でシェービング・フォームを立てると、スプレー缶が情けない音を立てた。あまり泡が立たないまま、剃刀を当てると、一センチほど首を切ってしまった。
Yシャツに血が付かないように、ティッシュで抑えながら、家を出て行った。玄関から三歩飛び出して、帰りたいと思った。
私は電車に駆け込み、誰かが線路に飛び込んだ。電車が停まったのは私のせいではないのに、遅延証明書を差し出すと、上司は迷惑そうな顔をした。
年の近い上司たちとランチに行き、ハワイアンカレーを食った。オフィスの女の子のなかで、誰がいちばん可愛いかと議論している。私はにこにこしながら、適切なタイミングで相槌を打った。
窓辺に疲れた顔が反射していた。クレーマーの電話を切り、ため息まじりに顔を上げると夜景が広がっていた。残業に追われながら、待ちぼうけになっているに違いない女を、もうしばらく待たせて置こうと考えた。
部屋のはしにいる上司を呼ぼうとすると、悪いんだけど、手が離せない。こっちに来てくれないかと大声で返事された。
ああやって自身で動こうとしなから、上司は肥っているのだろう。遠くの席からでも、スターバックスの容器がポーンのように並んでいるのが見えた。あの甘ったるい匂いを、嗅ぎたくなかった。私は電源を長押しして、ラップトップを強制的にシャットダウンして退勤した。
電車を乗り継いで、三十分も遅れて会いに行った女の子は不機嫌ではなかった。むしろ私の方が苛立っていた。
言葉を交わさずに街を歩いて、落ち着いて話せる酒場に二人で入った。奥の席に入って、立ったままビールを飲んでいると、騒がしいサラリーマンたちが近くに陣取った。夜になっても明るい街なのだから、これくらい酔っ払っていても、喧嘩の種にはならないだろうけれども。
彼女は、私の苛立ちに気づいている。七歳年上で、気を遣いすぎる女の子だった。なんの段差もないのによく転んで、穴だらけになった部屋を養生テープで補修する女の子だった。
リフレッシュしようと考えたのか、養生テープさんは映画の話を始めた。ニコラス・ウィンディング・レフンの『ドライブ』という映画だった。話が弾むかもしれないと思ったが、彼女はあなたに教えられたから観たと言い出した。落胆してしまった。
──気を引くこうとして放火する女の子や、その子の面影を追って付き合った音大生の子は良かった。二人とも神経質だったけれど、対応に追われている間は充実していた。
相槌を打つ年上のガールフレンドはあまりに常識的だった。付き合いだして半年が経っているのに、スカッシュが上手くて、カルバン・クラインの下着が似合うという印象しかなかった。
話題を絞り出そうとすればするほど気まずくなった。近くのテーブルにジョッキを置いた男が唐突に声を上げた。
「久しぶり」
養生テープさんは戸惑いつつも、愛想の良い声で男に挨拶した。相手はやはり仕事帰りらしいスーツの二人組で、片方の男は彼女の知り合いらしい。ぺらぺらとため口を利いている。なかなか仲が良かったのだろうと察した。
「デートですか?」
相手の男がつまらないことを聞いてきて、そう、と簡潔に返した。私の感じの悪い返事で、場は急に気まずくなった。間を置いて、彼女はお手洗いに行った。
「彼氏ですか?」
相手の男に質問されて、私はまた雑な返事をした。なにかのロックが大音量で流れていた。相手が大声で同じ質問をする。ほとんど怒鳴るように、そうだよと言い返した。相手の男は、不機嫌そうな顔をした。喋り方からすると、何軒かはしごしているのだろうが、知ったことではない。連れの臆病そうな男はうつむいてしまっている。
「付き合ってるのか。よかった」
小声で男が呟いた。この台詞は聞き逃さなかった。
「お前、喧嘩売ってるのか」
私から詰め寄っても、相手は引き下がろうとせずに、売ってねぇだろうと言い返した。相手の胸倉を掴むと、周りで立ち飲みしていた客が遠ざかった。養生テープさんがお手洗いから帰った。
「なにしてるのッ」
「喧嘩買ってる」
「喧嘩売ってねぇだろ」
「殺すぞ」
「やれるもんなら、やってみろよ」
彼女が私の腕を押さえ、やめてッと叫ぶのと同時に、私は男に頭突きを叩き込んだ。近くのサラリーマンがあッと声を洩らすのを皮切りに、そのまま揉み合いになった。
彼女が間に割って入り、女の重みに耐えられず三人で床に倒れ込んだ。相手の男はあおむけの姿勢から蹴りを放ち、私は狭い店内の壁まで吹っ飛んだ。
壁にならんだ酒瓶が、はげしい風鈴のような音を鳴らした。
相手の男が立ち上がり、血走った顔で、罵倒しながら迫ってくる。ジャックダニエルのボトルをキープし、私も正面から応じると、ふたたび彼女が間に入った。
楽しく飲んでいた女子大生のグループが一斉に泣き出し、店員が止めに入った。ジャックダニエルを弾き飛ばされ、指に鈍い痛みが走った。大乱闘の最中に、相手の顔を一発殴ってやった。
その後、ずらかろうとしたものの、相手の男と店員からすればそうは問屋が卸さない。パトカーで署に連行された。
警官と話しているうちに、やはり相手は元彼であると発覚し、彼女の弁明によってだろうか、喧嘩両成敗で帰っても良いということになった。
ただし、後日、聴取があるかもしれないと前置きされ、身分証を求められた。なんで見せなきゃならないんだ、と言い返した。取調室で養生テープさんが号泣してしまっていた。健康保険証を見せ、早口で電話番号を告げて、彼女と帰り道を歩いた。
手が血まみれになっていることに気づいた。七五〇ミリのジャックダニエルを弾き飛ばされた時、人差しの爪が縦に真っ二つに割れ、親指の爪などは半分くらいまで剥がれてしまった。
「悪かったよ」
謝っても、養生テープさんは返事をしなかった。溶けたマスカラで、黒いなみだの跡を残した横顔は、まっすぐ前を見据えていた。せめて喧嘩した理由を聞いて欲しかった。
「駅まで送るよ」
「あなたといるほうが危ない。指は大丈夫なの」
指先の痛みが段々とひどくなっていき、消毒液を求めて二人でコンビニに入った。トリスのハイボールをかごに入れると、彼女は苦笑いした。
「なんか飲まないのか」
「高いビールを買って」
コンビニの前でプルタブにを開けようして、親指が痛んだ。ハイボールを開けて貰って消毒も頼んだ。爪の剥がれた指先に消毒液が掛かり、思わずうめいた。
「痛むでしょ」
「しばらくスペースキーが打てないと思う」
なかなか面白い冗談のつもりだったけれど、彼女は笑わなかった。
「あの人とは長かったんだよ」
パイン味のビールをすすりながら、彼女が言った。
「二年も同棲してた」
「結婚したかったのか」
「そのつもりだった」
「どうせ向こうから、別れたいって言ったんだろう」
「うん。夜職の女とは結婚するなって、親に言われたみたい」
「クソガキが。そんな奴、殴られて当然だ」
「あなたもわたしの次の恋人に殴られることになるよ」
「なんで」
「あなたはわたしのことなんてどうでもよかったんだよ。きっとあなたにとってはなにもかもどうでもいいんでしょうね」
「なんの話なんだ」
「さよなら」
彼女はすたすた夜の道へと歩いていった。棒立ちして見送ると、こんな時に限って養生テープさんは転んでくれなかった。寂しかった。
行き場を失い、彼女の影を追いかけるように、あてもなく街を歩き続けた。交差点で立ち止まる。ガラスケースのような建築が立ちならび、信号機の赤を反射させている。
通りの端々には、高級ウィッグのキャベツ畑のように、街娼たちが等間隔で立ち通していた。
信号機が青になった瞬間、群集は同じステップで横断歩道へ踏み出した。人々と街並みは完璧なプランで整列しているのに、私だけが同情すら求めずにさ迷っていた。
コンビニでストロングゼロを買って、流し込みながらまた歩き出す。なにか名状し難い怒りに突き動かされ、ふらふら曲がり角に入ると、女と肩がぶつかった。お互いに謝罪もなく、女はうすら笑いを浮かべ、汚らしい誘い文句をならべた。
「やらねえよ」
「ケチだね」
「病気になるだろうが。死に至るヤリマンか、お前は」
女の子は少し面白がっているような顔をした。
「ラーメン食いに行こう」
「そうやってプライベートに持ち込まれるの困るんだけど」
「誰がお前とつるむって言ったんだ」
「でもラーメンは食べに行きたいんでしょう?」
「うん」
「いいラーメン、期待してもいいですか?」
「殺すぞ」
怯えるどころか女は大声で笑い出した。
ラーメンなどというものは文化のない食事と決め込んでいたのに、今夜だけは体に悪いものを食いたくなった。屋台の良し悪しの区別などつく訳もなく、女の案内で煮干しラーメンを売りにしている店に入った。麺が茹で上がるのを待ちながら、明るい場所で眺めてみると、可愛くもなんともない女だった。
「手はどうしたの」
「ジャカルに噛まれた」
「ジャッカルがいるの?」
「うるせえ」
「怖くて話ができないよ」
街娼は膨れっ面になり、さすがに罵倒し過ぎたと反省した。チャーシュが沢山盛られたラーメンが出てくると、きゃあきゃあ騒ぎながら写真を撮り始めた。
椅子に真っ直ぐ坐ることの出来ない私はやっとのことで胡椒を掛けようとする。ラーメンに爪楊枝を撒いてしまった。思わず雄叫びを上げると、静かに食べて下さいと店主に怒られた。彼女は何食わない顔で、ずるずる啜っていた。
「なにをそんなに怒ってるの」
「あるいは悲しいんだよ」
「何が悲しいの」
「なにが悲しいのか分からないことが悲しい」
「わたしも悲しいよ。ホテル代別途で一万五千円の女なんだから。社長さんも、主婦も、子どたちも、みんな悲しいの。生きるってことは悲しいことだよ」
「悲しい仕事なのか」
「いいえ。体を売ったから悲しいんじゃないの。悲しいから体を売ったの」
「そうか、そういうことか」
我々のとなりに坐ったカップルが死んだような顔でラーメンを啜っていた。勘定を払って立ち去ろうとすると、女に袖を引かれた。行きつけのバーに行きたいと言い出した。
この女が私を嵌めようとしていることにようやく気づいた。その先を見てみたいという欲望が浮かんだ。よこしまな考えだと思うほどに、好奇心は強くなっていった。
街娼と肩を組んで、掃き溜めとしか言いようのない、雑居ビルのエレベーターに乗った。
予想、的中。飲み放題なのにビールばかりが出てきて、頼んだウイスキーは来ない。隙を見て逃げようかと考えながら、便所に入った。
悪戯彫りを入れた店員たちが入り口にたむろしていた。油ぎったラーメンを食ったばかりなのに、女はチキンの盛り合わせを頼んだ。次々に注文する。携帯電話を取り出すと、圏外になっていた。
外で電話をさせてくれと頼んだ。関取みたいに馬鹿でかい店員に付き添われて、地上まで降りた。電話を耳に当て、取引先の相手をヘッドハンティングする振りをして、そのまま夜の街へ駆け出した。
裏路地に飛び込み、撒いてやったぜと安心していたら、正面から通行人が躍り出た。てめえは関係ねえだろうと怒鳴りつけたら、馬鹿、俺は店員だ、と言い返された。後ろから追っ手も来て挟み撃ちになった。逃げることを察知されて、待ち伏せしていたようだ。壁際に押さえつけられて、派手に往復ビンタされた。気持ちの込もったサービスだった。
「金払えよ。十万出せよ」
「そんなに持ち歩いてるわけねえだろ」
「じゃあ降ろしてこいよ」
「そんな貯金は、ない」
「無銭飲食なんかしやがって、どうなるか分かってんのか」
羽交締めにされて腹を何発か殴られ、飲み食いしたものを返品するところだった。寸前で堪えたせいで、口の中で苦い味がした。顔を押された姿勢で、私は相手を思い切り蹴った。何人か通行人が駆け寄って様子を伺いだすと、相手は焦ったのか、さらに大声を上げた。
「五万でいいから払え」
「ごねると半額になるのか。どんな商売してんだ」
「とりあえず一万だけ出せよ、締めるぞ」
「もう締めてんだろうが」
「くそが。払わなくていいから帰れ」
大の男三人が路上で乳繰り合ったせいで、なかなかの観客動員数を記録していた。腹いせに私の顔を殴り、店員二人はその場を去ろうとした。二人は野次馬を言葉にならない言葉で、怒鳴り散らした。
「ごちそうさま」
後ろから罵倒を浴びせても、二人が振り返ることはなかった。
——爪が剥がれた状態で取っ組み合ったせいか、手から肘にかけては血まみれだった。帰宅してから発覚したことではあるが、顔に数箇所の青あざが浮かんでいた。血管が切れたのだろうか、目の端が異常に血走っていた。呼吸するたびに肋が軋んで、寝返りが打てなくなった。
満身創痍に違いないだろう。しかし、プラットフォームで次の電車を待つ間、フルセットのテニスをやり切ったような清々しい気持ちだった。
私の生活に足りなかったものが、ようやく明確になった。
鍵つきの部屋でもの思いにふけって少年時代を過ごした。それなりの定職に就いて、金曜日に泊まりにくる彼女もいて、歯ならびが悪い訳でも、偏頭痛に苦しんでいるのでもない。
これまでの半生で唯一見出せなかったのは、いまこの時、この場で生存しているという手触りだった。指先と腹に鈍痛が走る。最高の気分だった。痛みは、音楽だった。
私は牢獄に行き着いた。正確にいえば、警察署の地下の留置所にいる。拘置所や刑務所に行く見込みはないと気づいて、落胆していた。
房には正面の格子のほかに、裏手の窓のような格子が備わっている。裏手から、二九番と呼ばれ、若い看守が顔を覗かせている。悪い予兆に思えて、駆け寄った。
「もうすぐ出られそうか」
「わかりません。弁護人が被害者と話せているのかすら、わかりません」
二一番が自分のことを聞かれたのかと心配し始め、寝る前にシャドーボクシングをしたり、天井の羽虫を必死になって殺そうとした。相部屋の子どもの囚人を抱きかかえれば、虫に手が届くなどと、看守も黙っていないことを言う。
面倒になり、看守とのやり取りを白状すると、珍しいことですね、と急に落ち着きを取り戻した。私の出所が近いと考えたようで、落ち込んでいる。悪いことをした気がして、先に出たら差し入れをする、なにが欲しいかと聞くと、彼はもごもごした。
「辞書がいいです」
翌日になり、警察署での調べがあった。調書を書いた刑事がまた出てきて、さすがに出たいでしょうと聞いた。柔道世界チャンピオンがにこにこしていた。
立て続けに弁護人も来て、示談が取れたと話した。
「雨の日なのに釣りにいくなんていって、変なおっさんだった」
彼女は楽しそうだった。私選弁護人のことを聞いて、わたしで十分よ、と勝ち誇った顔をしている。勝ったのはあんただけだよ、と思った。
「もう面倒を起こしちゃだめよ」
「面倒ですが、勉強にはなりました」
「そうなの?」
「身銭を切らなきゃ、勉強できない類いのことです」
「出たら、とりあえず事務所に電話ちょうだいね」
「そうですね。フランス料理でも食いにいきますか」
国選弁護人が大笑いしたが、私には何もかも笑えなかった。
房に戻ると二一番は落ち込んでいた。
「そろそろ出所ですね。退屈になりそうです」
ほとんどの人間と同じように、出所しても彼には行く当てがなかった。またクイズをしようと言っても、浮かない表情のままだった。その晩の彼は寝ごとが激しく、便所と寝床を行き来した。
翌日、看守に呼び出され、外界に通じる扉の前に立たされた。他の囚人に配慮したのだろうか、重いシャッターが閉ざされて、牢獄への帰り道は閉ざされた。看守は出所が許された旨を告げ、この件がどう扱われるか、我々にも分からないと説明した。
小窓から私を呼んだ看守に付きそわれ、警察署の玄関まで歩いた。留置所とは打って変わり、看守は気さくに手を振って見送った。
一体、何がめでたいのだろうか。人生より、長い懲役があるだろうか。この十日間、世間という広い房から、留置所という狭い房に映されたに過ぎなかった。いっそのこと絶望を突き詰めてみたいと思った。それならば私に出来ることは——、
とは言っても、あまりにも人生は忙しく、私には息抜きが必要だった。無性に甘いものが食いたくなり、31アイスクリームに入った。
店のスピーカーから、宇多田ヒカルが流れていた。音楽とはこういうものかと思い出して、懐かしかった。
おそらく世間は休日だった。若い母親が子どもをあやしている。口もとに付いたチョコレートをハンカチで拭うと、泣き出しそうな女の子は聞き取れない言葉を叫んだ。
マスクメロンのアイスクリームに齧りついた時、若い母親と視線が重なった。若い母親は、体のラインに沿った赤いセーターに、シンプルな金色のネックレスを合わせていた。こんな昼間に一人でアイスクリームを頬張る男を面白そうに眺めて、すぐに視線を外した。マスクメロンの香りがふわりと立ち上がった。店を出てから、三歩進んで、腹に熱いものを感じてとめどなく吐いた。
気分がすっきりして、街の色彩にも違和感がなくなった。行き交う人々から気を逸らすように顔を上げると、夕暮れの空がひび割れていた。桜の枝が無造作に伸びていた。ほとばしった血潮のように、見事な咲きっぷりだった。
桜を見上げていると、携帯電話が鳴り出した。電話の取り方がよく分からず、画面におびただしい通知が届いていた。職場、両親、そして女の子からの失意のメッセージ。
やっと電話を取ると、心配そうな上司の声が聞こえた。私はなんの迷いもなく、事件を起こしたと明かした。
「なにをやったの」
涙声で問いただされた。そいつを説明する言葉を持ち合わせていなかった。重たい無言が続いた。桜は一層つやめき、色盲の父に、この色彩をどう説明しようかと考えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
