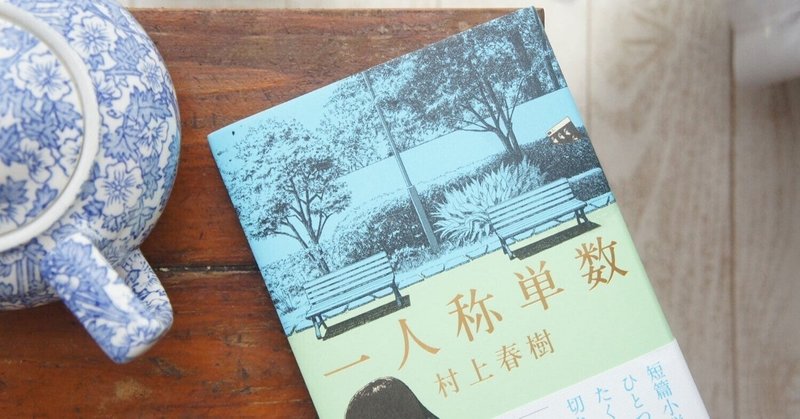
自作小説行商人。
郷里の九州に舞い戻ってからは滅多にお目にかからなくなったが、東京に住んでいた頃はよく駅前で露天商を目にしたものだった。占い師や似顔絵描き、ハンドメイドのアクセサリー売り、ネットメディアで「闇が深い」と言われているフルーツ売りの若者等々。
その頃の俺は大学院生を経て無職というカネの無い身分だったから、そんな所でモノを買う余裕などほとんど無かった。そもそも露天商や路上販売という商売には多かれ少なかれ胡散臭さがつきまとう。仮にカネがあったとしても其処で進んでモノを買おうという人の方が少ないのではないか。
だが、俺はその露天商という存在を何とはなしに好いていた。もうすぐ三十路を迎えようというのに未だに職歴が無い男、まっとうな社会の枠組みからはみ出した慮外者として、真夏の熱帯夜だろうと真冬の寒空の下だろうと地べたで商売をする彼ら彼女らに何かしらの親近感を抱いていた。働いていない自分と働いている彼ら彼女らとでは実のところ天地の開きがあるのだが、当時の俺は自分とあの人達が似たもの同士の存在だと至極勝手に決めつけていた。
多少カネに余裕があるとき、そして気が向いたときには、そういう露天商の商品を覗いてみるのが習慣だった。向こうのセールストークは聞き流しつつ商品を眺め、これはと思ったものだけ手にとってみる。実際に買うことは少なかったが、それでもこれは良いと思ったものは本当に買っていた。
ある時、西瓜を一玉買ったはいいがバス代が足りなくてそのまま歩いて帰った事がある。持ち帰るのは重かったが、冷やして食ってみると汁が詰まっていて美味かった。それ以上に、買い上げたときの行商の兄ちゃんの嬉しそうな笑顔が印象に残っていた。今にして思うと、モノを買うというより社会とのコミュニケーションを買っていたのかもしれない。そういう形で必死に社会とつながろうとしていたのだと思う。
そういう具合に、俺は露天商という存在を好ましく思っていた。
その露天商たちの中でも、ひときわ印象に残っている男が一人いる。
― ― ―
十年近くも前の事だったと思う。季節は秋で夕暮れの頃だった。
友人達と遊びに出掛けた帰り、電車に乗ろうと俺たちが向かった駅前の石畳。そこに一人の男が腰を下ろしていた。
青と黒のチェックのネルシャツに色褪せたジーンズ。若者と呼んでいい風体だが、歳かさは当時の俺よりも上の三十代と思われた。顔つきもそうだが、はしゃいだところの無い落ち着いた物腰は二十代前半までのそれとは思えなかった。
男の目の前に並べられているのは八冊の小冊子。色付きの模造紙にタイトルを書きなぐった表紙、その内側に何枚かのペーパーが綴られているのが見える。”冊子”と呼んだがその実そう呼ぶのが憚られるほどの安っぽい装丁だった。
男の傍らにはこれまたなぐり書きの売り文句が書かれた小さな置き看板。曰く「自作小説売ります。一冊百円」。
男の視線は目の前の雑踏に向けられているが、行き交う人々を注視しているわけではない。其処に視線を置いている、ただそれだけの事。
俺は大いに興味を惹かれた。売り物の小説というよりも、小説売りの男そのものに対して。
どういう経緯があってこんな事をやっているのかは知らない。だが少なくとも、自作の書き物を”小説”と銘打って、あまつさえ駅前でそれを手ずから売るという行為は勇気と行動力の要るものだろう。やろうと思いさえすれば誰でも出来る事だが、リターンや損得勘定の合わなさ故、ほとんどの人間がやらない事でもある。
そういう合理的な勘定をすっ飛ばして、自作の小説を二束三文で売る男。実際に有り得そうでその実有り得なさそうな、現実と虚構の間そのもののような存在。
熟れた柿色の日差しに照らされた小説売りの男は虚空を見つめて佇んでいる。
駅に向かおうとする友人を引き留めて、俺は男の前にしゃがみ込んだ。
「・・・ああ、どうぞ見てってください。小説売ってますんで」
挨拶の口上としては無難だが、とっくのとうに知れきった内容。行動の突飛さとは裏腹に常識的な男のようだった。
「何で、こんな事してるんですか?」
恐らくはすでに多くの人が同じ質問をしているのだろう。出し抜けかつ不躾な俺の問いに動じる事無く、男は微笑みを浮かべて返答する。
「別に深い理由は無いんですよ。する事なくてヒマだったし、何か自分で作ってみて、それで色んな人に見てもらいたいなあって。そう思ってやってるだけなんです」
成程、聞く限りは真っ当な理由だ。だがそれでも、こうして己と己の作品を衆目に晒すという行為に至るにはもっと深いところでの理由があるに違いない。
出来る事ならもう少しこの男のパーソナリティを深堀りしてみたいと思ったが、所詮俺は通りすがりのただの客。一期一会の者として、そういう質問を相手にぶつける事は流石に憚られた。
男の返答に頷きつつ、目の前の冊子を手に取り表紙をめくる。ペーパーに印刷された文字の群れに目を通した。
正直に言う。つまらなかった。
”小説”と銘打たれているがエッセイと呼んだ方が良いだろう。男の身の回りの由無し事が綴られている内容だ。断っておくと、俺は文芸作品として小説が格上でエッセイが格下という意識は持ち合わせていない。小説だろうとエッセイだろうと面白ければそれで良いと思っている。
だが、男の作品はそもそもエッセイとしてよろしくない品質のものだった。文章は平易と言うより拙劣で、無闇な改行や空白の多さばかりが目につく代物。ハッとするような気付きがあるわけでもない鈍らな着眼点。
いかに安価とは言え、これを小説として売り物にしているという事実に心底驚いた。当時の俺は特段書き物をしていなかったが、それでも俺の方がまだマシな物を書けると思ったものだ。
一冊目を元あった場所に置き、二冊目、三冊目と手に取ってみる。やはり一様につまらない。
「おい、もう良いだろ。そろそろ行こうぜ」と友人の一人が背中越しに声を掛ける。その声で我に返り、小説売りの男の方に視線を向けた。
男は俺を見ていた。先程の虚空を見つめる視線とは明らかに違う、目の前の客を意識した眼差し。
ただ、冊子を買ってくれる事へのねばつくような熱い期待はその眼差しには欠片も込められていない。ただただ澄み切った眼差し、透き通るような瞳を以て俺を見つめていた。
「――買います。全部」
咄嗟に声が口を衝いて出た。
「え、マジで!?それ全部買うの!?」
小説売りの男より先に友人の方が驚いて声を上げた。
男の方も目を丸くしている。
「え、良いんですか?本当に?」
「ええ。一冊百円だから全部で八百円ですよね。お釣りをお願いします」
驚く友人と小説売りに構う事無く、俺は財布から千円札を取り出して男に手渡す。そのまま目の前の冊子をすべてかき集めたら手元で束ねて右手で持つ。八冊すべて揃えても片手で掴めるほどの小ささと薄さだった。
「・・・その、売ってる僕が言うのも何ですけど。そんなに面白かったですか、僕の本?」
お釣りの二百円を手渡しながら男が俺に問い掛ける。
一瞬答えに窮したが、すぐに言葉が湧いてきた。
「モノの良し悪しはよく分かりません。ただ、これを自分で作って駅前で売ってる兄さんが面白いって思ったんです。面白い人が作ったモノなら面白いと思うんで、とりあえず全部買います。後でじっくり読ませてもらいます」
返答を受けた小説売りの男は、激しい喜びや感動を示す事は無かった。
ただにっこりと、目の前のおかしな客に微笑みを浮かべていた。相変わらず澄み切ったままの、その両の瞳を細めて。
「ありがとうございました。また何処かで会ったら宜しくお願いします」
柿色の夕暮れに照らされた小説売りは深々と頭を下げた。男の礼に会釈して、俺は友人たちの方へと踵を返す。
「おいそんなもんにカネ使うなよ今のでタバコ二箱は買えたぜ」という友人の言葉を聞き流しつつ駅へと向かう足取りは、自然とテンポが上がっていった。
― ― ―
あの時買った冊子は一冊も手元に残っていない。あの後帰って友人達と一緒に読んだが、やはりどれもつまらなかった。詳しい内容もとっくの昔に忘れている。「だから言ったじゃねえかメシなりタバコなりに使えば良かったってよお」という呆れかえった友人の声だけが記憶に残っている。
それから十年近く経った今、俺はこうして書き物を嗜んでいる。カネを取っているわけでは無いが、時間と労力と経験と、己のすべてを駆使して作品をつくり衆目に公開している点ではあの小説売りと全く同じ地平に立っている。
だからと言って、あの小説売りが何故あのような行為に及んでいたのか、その理由や気持ちが分かるという事はあり得ない。むしろ何かをつくって発表する理由など百人いれば百通りだと思う。よしんばそれが似通った理由やエモーションの動きであったとしても、その本当の在処はそいつ自身にしか分かり得ないものだろう。それも、本人ですら言語化し得ない漠たるかたちでしか感じ取れないものとして。
そういう意味では、あの小説売りの男は俺にとってある種の指標なのかもしれない。
自分の身の回りの出来事を時間をかけて綴り、それを”小説”と銘打って衆目に公開し、自分自身の姿も晒した上で手ずから売ろうとした男。恥も採算も度外視して、ただただ自分のなかの何かに衝き動かされていた男。
作品はつまらなかったし内容も忘れてしまった。
だが、あの男の創作者としての芯の通った姿勢と澄み切った眼差し。
それだけは、十年経っても忘れられない。
