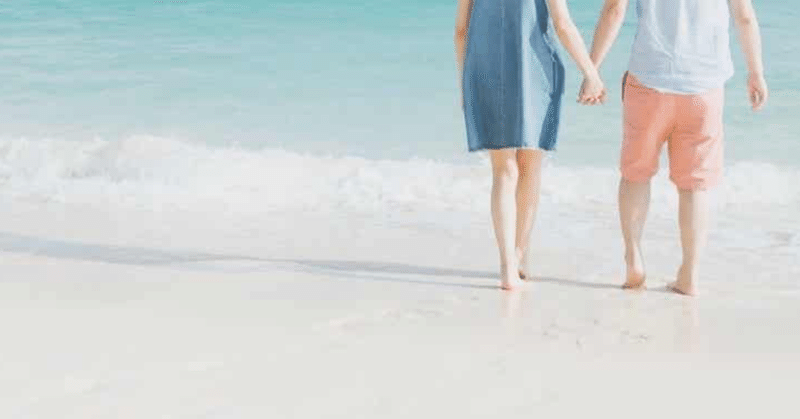
小説「透明でまっとうな新しい日々」
昨年の夏に書いた掌編小説を加筆修正のうえ、再掲致します。
主人公の2人はそれぞれにハンデやコンプレックスを持っていますが、彼らなりにコミュニケーションを駆使して、優しくも満たされた生活を送ってゆく物語です。
「ちょっとの工夫で困難は回避できる」という言葉は私の小説のベースとなる考えであり、私自身が生きる上でのモットーでもあります。
もし、いまあなたの目の前に救いようのない障害があったのなら、形容しがたい悲しさに溢れているのなら、この小説があなたが生きる上での小さなヒントになったら幸いです。
そんなことを書いている作者自身も小さなヒントを探している最中です。
あなたも、私もアラタや透子のように透明でまっとうな一点の曇りもない新たな日々をこれから送ることができますように。
「透明でまっとうな新しい日々」
岩波アラタの綺麗な弧を描く後頭部が私は好きだ。
彼の髪は重たくて黒い。
部屋でふたりソファーに並んで眠たい映画のDVDを観ている時、私はおもむろに彼の髪を優しく撫でる。寝たい、の合図。それから彼のコットン100%のシャツをゆっくり脱がしていく。
アラタの体はいたる所にアトピー性皮膚炎が広がっている。関節の内側や耳などの皮膚の柔らかな部分はもちろん顔面も湿疹でかぶれている。
乳幼児の頃から患っているのだと言っていた。現在はステロイドでの治療をしているけれど、ある程度炎症が引いても引っ掻いてしまったりしてまたぶり返すのだと言う。
初めてアラタと出会ったとき、外見から年齢がまったく予想できなかった。私より年下にも見えるし反対にずっと年上にも見えた。アラタに年齢を聞くと
「俺、今年、年男なんです」
と、少しはにかんで教えてくれた。スクエア型のメガネの奥に笑い皺が見える。36歳。
そうか私と同い年なのね。同い年と聞くだけでどことなく親近感が湧いて嬉しい。
「そうなんだ、箕島(みのしま)さんと俺、同い年なんだね。なんか嬉しいな。年男、年女って神のご加護が受けられるって聞いたけどほんとかな。今年、俺たちいい年になるといいね」
ふふとアラタが笑う。彼の話し方はふうわりとしていて耳に優しい。
まるで紙風船が畳にハラリと落ちる様のようだ。天井から落下するそれら紙風船の空気ごと、取り零すことなく、べしゃりと潰すことなく受け止めたい。
できるならそれら一式丸ごと飲んじゃいたい。初対面でそう思った。
アラタとの出会いは春分の日にふらりと一人で出かけた高田馬場にある名画座の劇場内でだった。 邦画を鑑賞し、身の毛がよだつラストに震えた。
劇場に照明が灯り、人もまばらになった頃、隣を見るとひとり戦慄している男性がいた。アラタである。きっと彼も私も同じような面をしていたに違いない。
私の顔を見て、アラタは同士を発見したかのように顔を綻ばせて言った。
「この映画、むちゃくちゃ怖くありませんでした?予告じゃそんなの全然だったのに」
映画館での出会いをきっかけに意気投合し、それからというもの仕事帰りや休日に我々は待ち合わせをしては水族館を巡り、東京スカイツリーに登り、新宿御苑を散歩し、ビリヤードをして、ダーツバーに行って、それから正式なお付き合いを始めた。
随分と男女のあれこれが何も起こらないデートを重ねたものだ。彼は付き合うまで手すら握ってこなかった。昭和の歌謡曲の世界か。その間じりじりとして、もうそろそろいいでしょという頃、みどりの日に映画を観に行ったあと、アラタが言った。
「箕島さん、俺、こんな体してるから、彼氏として付き合うの嫌でしょ?周りの目とかあるし」
最初こんな体、と言われたときにどのことだと思った。私振られてるの?
「ほら、アトピーがさ。顔にも出てるし」
目線を逸らさずに顔に指をさしてアラタが言う。
そんなの、いやそんなのって言い方は変か。アトピーとか全然気にならないよ。
伝え方が偽善的にならないように気をつけて、まっすぐアラタに届くように努めた。
「ほんとうに付き合ってもらえるの?ああ、よかった。俺、今日でもう箕島さんと会えなくなっちゃうのかなって思った。俺のこと、どう思ってるんだろうって不安だったんだよね」
彼は両目を両手のひらで瞑ってから少しずつ上を向いた。肩が小刻みに震えている。泣いているの?
彼の顎のラインがすうっとして線が細い。白く長い指、でも指の節ははっきりとした凹凸を感じる。その節のところどころにある湿疹からチラリとのぞく血が、ハッとするほど美しい。
人はその感想を不謹慎だと罵るだろうか。
血液の綺麗さをぼんやり見つめていると、アラタは涙を拭き取って言う。
「昔さ、友だちに陰で言われたんだ。アラタは顔とか体がガサガサで気持ち悪いよなって。湿疹を移されたくないから近寄ってほしくないって。
そいつ、友だちだと思ってたからショックでさ。それからあんまり深く人と付き合わなくなっちゃったんだよね。
俺、箕島さんとはもっと深く関わりたくって」
私も彼が所有する傷ひっくるめて、もっと正しくアラタのことを知りたい。彼の過去をなぞりたい。
ねえアラタ、箕島さんじゃなくて名前で呼んでよ。もう一歩前に踏み込んでほしい。
アラタの指を私の首筋に当て、薄い唇を開く。
私の、名前を、呼んで。
唇をゆっくり大きく動かして、一文字ずつ丁寧にアラタに伝える。
「透子ちゃん」
やっと呼んでもらえた。私はにっこりと微笑む。
透子ちゃんだって。ちゃんづけってなんだか甘やかされているみたいでこそばゆいけど、悪くない。もっと沢山私だけに名前を発してほしい。
けれども私は声を失っているためアラタの名前を呼ぶことができない。
返事をする代わりに心込めて大きく頷いた。
私が罹患した失声症は前職で勤務していた際に突然発症した。
海産物を扱う小さな商社の営業事務職だったが、女性の上司から理不尽なお叱りを毎日のように受けていた。致命的な仕事のミスは特段していないのに何かと難癖をつけられる。
職場で鳴った電話の呼び出し音1回目で出られないとクドクドと怒鳴られる。動作が緩慢だ、社会人としてなっていない。日付が全角で入力されていた。注意力が散漫すぎる、社会人としてなっていない。スカートの丈が短い、社会人としての常識がなっていない。
はいはい私が悪いでいいですよ、と流していたつもりだが、私の心身はそうは捕らえておらずストレスが日々蓄積していったようで、昨年末を境に、突然発声ができなくなった。
失声症がその後2ヶ月ほど継続したため、元の会社は退職し、現在はリサーチ業務会社でデータ入力の仕事に就いている。7月に入っても私の声は喉に戻らない。
箱庭療法なんかも試したけれどいまひとつ効果が見られず、何度かで通院もやめてしまった。人間声が出なくても必要最低限の生活はできるものだ。
職場をはじめ、人と会話をするときはメモ用紙やスマートフォン片手に意思疎通を行う。
映画館で初めてアラタに話しかけられたときも、
『私、声が出ないのですが、もう少し感想を伺いたいです』
とメモ用紙に書いて見せたら、彼はあっと驚いて、そのあとにっと笑って、もちろんです、ぜひお話しましょうよと続けてくれた。まさかそのまま2時間もカフェで筆談が続くなんて思わなかった。
初めてアラタと寝るにあたって私は少し躊躇した。
彼の肌を舐めたり噛んだりしたら痛くならないのだろうか。舐めても平気?そんなことを訊ねたら失礼だろうか。
暗闇の中で衣服を脱いだアラタの体に目が慣れてくると、体中に炎症を起こしているのがわかる。
「透子ちゃん、俺の体、気持ち悪い?」
まったくそう思わないが、アラタにそんなことを言わせたことが悲しい。
私は首を振って、スマートフォンのメモ画面に文字を入力する。液晶の光がアラタを肌を照らす。
触られて嫌なところはあるの?
舐められるのは嫌?
もうこればっかりは彼を不快にさせないためにも聞いて確かめるしかないと思った。
スマートフォンを見てアラタが苦笑いする。
「透子ちゃんありがとうね。そうね、最初に言っとかないとだよね。気を遣わせてごめん。俺、首と関節の内側は舐められると痒くなっちゃうかも。あとは普通の人と同じで大丈夫だよ」
普通の人と同じ、の言葉が重く響いた。
俺、普通とちょっと違うからというのはアラタの口癖になっている。自虐。そんな風に言わないでほしい。
あなたもわたしもたいして変わらない。
皮膚が荒れようが、発声不能だろうが、まっとうな五体と五感を持って我々は生きている。
と思いたい。いや、恥じることなくまっとうな人間として我々は生きている。ちょっとした不利な条件も工夫次第で回避できる頭を私たちは持っているんだよ。
私の長い髪が彼の皮膚を刺激しないように髪を結った。アラタの炎症部分を避け、迷路を進むように舌を這わせた。アラタの芯に私の気持ちが到達するよう願いを込めて丁寧に這わせた。
行為の後、アラタの皮膚に刺激を与えないように浴室にぬるい温度で湯を張った。
浴室内にはバスソルトの袋がいくつかあり、裏面の注意事項には「炎症、湿疹等のある方のご使用はお控え下さい」と記載があった。
バスソルトはいずれも会社の同僚や親戚に土産物として貰ったものだ。なんだか社会全般に否定された気持ちになり、ふんと鼻を鳴らしてそれらをキッチンのゴミ箱に全部まとめて捨ててやった。
「透子ちゃん、8月に伊豆に泳ぎに行かない?」
ふたりで湯船に浸かっているとアラタが言った。四角く折りたたまれた水玉ソーダ色のタオルがちょんと乗っていてとても可愛らしい。
体、しみないの?
すんごいしみるみたいだけど、海水療法で劇的に改善したっていうひともいるんだよね。この前医者に聞いたら試してみたらって言われたんだ。俺、ちゃんと治したくてさ。透子ちゃん付き合ってくれる?」
うんと頷いてから、水着買いに行く?と鏡の端に書くと、今度の休みに水着買いに行こうよ。俺、宿予約するねと笑い、伊豆かあ。何年振りだろう。金目鯛の煮付けが有名だよなあと早くも嬉しそうだ。
アラタはよく泣き、よく笑う。私よりずっと表情が豊かで魅力的だ。
こうして私のスケジュール帳にアラタとの日々が埋まっていく喜びを感じた。
山の日、西伊豆の海水浴場に訪れた我々は、ラジオ体操第1を初めからお終いまで真面目にこなし、いっせいのおせえっの彼の合図で海にザブザブと勢いよく入って行った。
肩まで浸かると、隣にいるアラタがひぃひぃ声を上げて痛がった。
「痛い…痛い、いや痛くない!!痛くな…痛い!!」
見ていられなくなった私は慌てて浜に上がろうよと彼の腕を引っ張るが、もうちょっと頑張ると粘って泣き顔で踏ん張っている。
波が押し寄せる度に今にも泣きそうな顔になるが、そこまで彼を奮い立たせるものは何なのか。
結局、何度か浜と海を行ったり来たりして30分も持たず浜辺に撤退した我々だった。
いや、全身に響く激痛に耐え30分近く海水を浴びることができたのだ。アラタの大健闘を称えるべきだ。
我々は海の家のちろちろと水圧の低いでシャワーを浴び、バスタオルで優しく体を拭いて、浜に敷いたレジャーシートの上でカキ氷を食べることにした。
アラタも私もブルーハワイシロップ一択だった。
カキ氷を食べている途中でアラタの肩を叩いて私が舌を出して見せると、アラタも青に着色された舌を出す。まるでバケモノのようなベロ。
あははと笑ってからアラタが言った。
「透子ちゃん、ベロ、真っ青でゾンビみたい」 「アラタこそ。ねえゾンビのベロって青かったっけ?」
「……あれ、透子ちゃん、声」
アラタが目を丸くして私の瞳と喉のあたりを交互に見比べる。私は改めてあーあーあー、と試しに発声をしてみる。青巻紙赤巻紙黄巻紙!バスガス爆発ブスバスガイド!……すごい全部噛まずに言えた。
半年以上喪失していた声が戻ってきた。何でこんな簡単に発声できたんだろう。何でこんな簡単なことができなかったんだろう。早くアラタとたくさんの話がしたい。ねえ、私の声ちゃんと聞こえている?
「透子ちゃんの声聞けて嬉しい。意外とハスキーだから少しびっくりした。いい声してるね」
「やだなあ、照れるよ。ねえ、声が出るようになったのアラタのおかげな気がする。ありがとう」
声が出なかった時にはアラタの表情を逃すまいと必死で瞳を覗き込んでいたが、いざ発声できるとなると、面と向かってアラタの顔を見つめるのが 少し照れてしまう。一方のアラタは以前と変わらずまっすぐに私の顔を覗き込んでお話をしてくれる。
「そんなそんな、俺こそ、海に肩まで入ったの今日が生まれて初めてなんだ。学校のイベントとかで海水浴に来ても俺だけ入らなかったし。
でも透子ちゃんと会って、体質改善したいって思ったし、普通の恋人みたいに海に行きたかったんだよね」
アラタはカキ氷のカップに唇をつけ、残りのカキ氷を一気にかき込んだ。
「そう、せっかく学校行事で海に来たのに入れないのはちょっと……いやけっこうさみしいね。私もアラタと海に来れて嬉しかったよ。じゃあ、思い出作りってことで一緒に写真撮ろうよ」
私はレジャーシートの上にあるビニール袋の中からコンパクトデジタルカメラを取り出した。
アラタはシャッターボタンを下に向けたカメラを握り、右腕を伸ばす。カメラのレンズをこちらに向けたのを確認してから、私たちはふたり舌をべえーと思いきり伸ばした。
ハイチーズ!
真っ青な舌の画像が液晶画面に表示されて、酷い写真と言って私たちは笑った。
「俺、実は写真もすごい苦手だったんだ。やっぱり体にコンプレックス持ってて」
そんなことないのに、と言いたいけど、外野にそんな気持ちはわからないと言われるのが怖くて完全否定ができず、曖昧に首を振った。
「でも、透子ちゃんと付き合ってから、ちゃんとふたりの記録も残したいって思ったんだ。
透子ちゃん、新しい気持ちにさせてくれてありがとう」
「新しい気持ち?」
「うん、前向きな気持ちっていうより新しい気持ち。
今まで悩んでたことが全部まっさらになって、いちから始めてみようっていう気持ち。そういうのって大人になるとだんだん薄れていくでしょ?俺、透子ちゃんといると新しい気持ちになるんだ」
「アラタ、買い被りすぎだよ。でも新しい気持ちっていいね。私はアラタと付き合ってからちょっとした困難があってもいくらでも回避できるって思えたよ」
ほんと?と言ってアラタの顔がぱっと明るくなる。ねえ知ってる?アラタはホラー映画もコメディに変えてしまう力を持っているんだよ。
アラタはビーチパラソルで日陰になった砂を手のひらで集め山を作り、その頂上にカキ氷のストローをさした。
「新しい気持ちと困難回避か」
そういってアラタが納得したようにうんうんと頷いた。
「透子ちゃん、ね、棒倒ししよう」
うんと頷けば彼は砂山を指でポンポン叩いて固めた。透子ちゃん、はいどうぞ。
「じゃあ僭越ながらわたくしから」
ストローを倒さないように指で砂の山を奥から手前に寄せる。まったく動くことのないストロー。
「透子ちゃん、あとで岩場も行こうよ。それからさ海の家でラーメンも食べよう。あ、おでんもいいよね、カレーもありだな」
「うんうん、あとでいろいろ悩んで決めよう。はい、次はアラタの番」
彼も砂を手前に寄せるがまだまだストローは挿さったまま動じない。
「それにしてもさ、最初に一緒に観た映画、怖かったよねえ」
「そう、ほんと慄いたよ。アラタもすごいビビってたし」
「透子ちゃんだってまあまあ顔が青かったよ。さっきのブルーハワイくらい」
私たちはにんまりしながら愛情を持ってお互いを冷やかす。こうしてお互いを冷やかしたり愛したりできることも、いくつもの偶然が折り重なりあって成立したことを私たちは身をもって知っている。
後ろ向きだった過去、希望に満ちた今日、だけど明日はどうなるかなんて誰にも予測することはできない。
もしかしたら明日は足がなくなっているかもしれない、ベッドから動けない状態になっているかもしれない。
そういったハンデや危機の可能性から抜け出すことは一生できない。生きている以上、絶対にできない。
だけれども。五体五感の一部が欠損したり、破損、不足していたとしても工夫と塾考をもってすれば、最低限生きていく上での困難を回避することは可能だ。
そう、私やアラタのようにいろんな道具を使って、あらゆるコミュニケーションを図ってお互いを知って、ハンデもコンプレックスも乗り越えていくことが絶対にできる。
強い気持ちを持って、前を向いて、自身にレッテルを貼らずに透明な新しい気持ちで、今日もあなたと共に私を生きていく。(了)
頂いたサポートはやすたにの血となり肉となるでしょう🍖( ‘༥’ )ŧ‹”ŧ‹”
