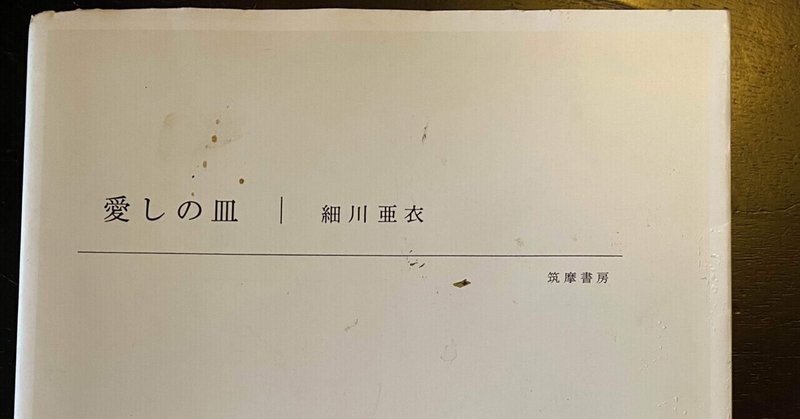
11代目伝蔵の書評100本勝負4本目
①食べたくなる本(三浦哲哉 著 みすず書房)
②愛しの皿(細川亜衣 著 筑摩書房)
大枚を叩いて作った図書館用の書棚が書斎の大半を占めています。約5000冊以上の本が鎮座しています。文字通り鎮座していて、愛書家?としてはささやかな蔵書数でしょう。そして大きな声では言えないけれど、読了したのは多く見積もっても2割くらいです。生きているうちに全てを読了できる可能性は非常に低く、そういう観点からすれば、もう1冊も新たな本を買う必要はないような気がします。気がするだけですけど。
昔から料理関係の本は好きでした。本を買うために書店に行くとレシピ本だけでなく、調理人や料理研究家のエッセイを手に取ることも少なくありません。「柴谷博士の世界の料理」(柴谷篤弘 著 径書房)や「私の洋風料理ノート」(佐藤雅子 著 復刊ドットコム)などはお気に入りの料理本です。レシピだけでなく、その料理にまつわる物語が垣間見える本が伝蔵の好みのようです。
①はレシピ本や料理研究家を批評した本です。著者の本業?は映画批評で、大学に籍を置く学究肌の人です。しかしながら本書は学術的な内容では決してなく、具体的なレシピは紹介されていないのに、時に口の中が唾で一杯になったりしました。それは記述が必ずしも批評的でなく、取り上げている料理研究家に寄り添っているからでしょう。と同時著者自身も日常的に料理を実践していてレシピ本を好意的に取り上げているからでしょう。いずれにせよ料理好きならば、そして食通を自認される方には自信を持ってお勧めできます。「みすず書房」は硬い本?を出版する版元ですが、「みすず」デビューにも最適な1冊となることでしょう。
②は①が取り上げていた料理研究家のひとり。本の帯には「それは五感に染み渡る レシピとエッセイ」とあり、読了後「その通りだ!」と声をあげさせていただきました。ただレシピは巻末に比較的簡略に記述される。料理に慣れてない人なら戸惑うかもしれません。しかし著者は肥後熊本藩主だった細川家に連なるお方ですからその辺りは「ヨキにハカラエ」ということなのかもしれません。少なくとも簡略なレシピは本書の欠点ではないと思います。なんと言っても紹介された料理の写真の美しさは特筆すべき点で前述した「五感に染み渡る」決して羊頭狗肉ではありません。(因みに撮影は著者ではなくカメラマンの邑京一郎)
本書の一番最後のレシピは「素うどん」です。レシピには「極上のだしをとる」とありますがそのためのレシピはなしです。エッセイの中で著者は書きます。
”私にとって、季節の移ろいを1番感じる食べ物といえば素うどんだ。〟
そこで僕も早速作ってみることにしました。何はともあれ問題は「極上のだし」です。手持ちの利尻昆布と焼津産の厚削りカツオ節で時間をかけゆっくりだしを取ります。


「だしをとる時にはは沸騰させないこと」という玄人はだしの料理好きである友人、大ちゃんの言葉を思い出しながら小一時間かけてだしをとりました。そしてうどんは北海道産の細乾麺。レシピにあるようにだしは「酒と塩」で味を整えました。
そして実食。

本文に
〃上手にだしが取れた時は心を鬼にして具を入れないようにする〟
とあったので上手にだしが取れたか心もとなかったけれど、従ってみました。
確かに著者が言うように「染み渡る」という表現がぴったりの一杯でした。
ただ、意志の弱い僕は途中妻の作った海苔の佃煮と七味を加えたことを白状致します。どちらが美味しいというわけではなく、別物という気がしました。
春を感じる季節になったら著者を見習って素うどんを作ってみようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
