
朗読「羅生門」芥川龍之介
朗読 「羅生門」 芥川龍之介
羅生門
羅生門は芥川龍之介が東京帝国大学在学中、まだ無名作家だった1915年(大正4年)に雑誌「帝国文学」へ発表された作品です。
そして羅生門には元になった物語がありました。
画像 手書きイラスト(綿棒)筆 原図トレース
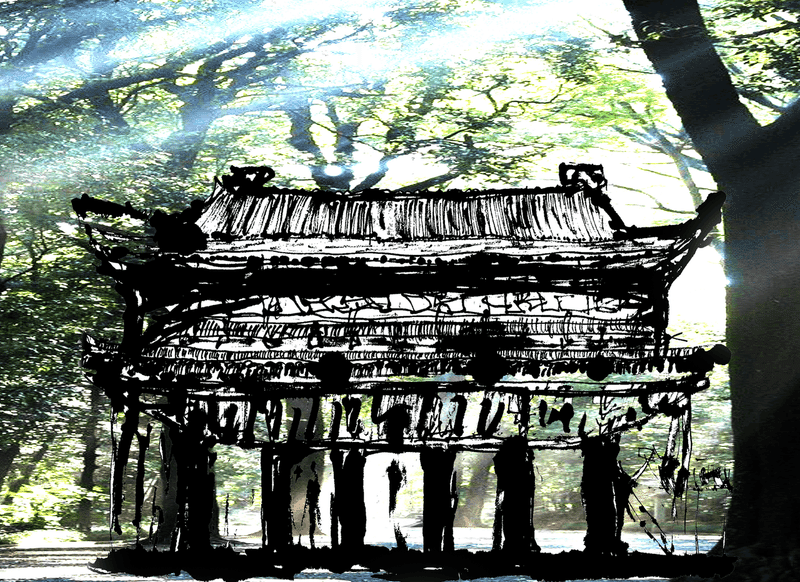
それは平安時代の末期に作られた「今昔物語集」という説話集の中の物語で、これを元に羅生門という作品は生まれたのです。
(今昔物語集の「羅城門登上層見死人盗人語」と「太刀帯陣売魚姫語」の内容を交える形で書かれた)
羅生門の主な登場人物は、主人に暇を出された下人と、盗みを働く老婆の2人です。作品の舞台は平安時代の京都にあった羅生門。
羅生門は朱雀大路の南端にあった大門で、羅城門とも表記されます。
この高さ70尺(約21m)、幅10丈6尺(約32m)もあった羅生門ですが、地震や辻風、火事や飢饉などの災いが続いて荒れ果てており、鬼が住むといわれるほどでした。
■そんな羅生門が舞台の物語です。
【羅生門のあらすじ】
ある日の暮れ方、主人から暇を出されて途方にくれる下人が、荒廃した羅生門の下で雨やみを待っていた。彼が門の楼上に登ると、女の死体の髪を抜く老婆がいた。
憎悪を抱き、力で老婆を押さえつけた下人だったが、老婆から生きる為の悪事を正当化する言葉を聞く。
下人の心に悪を肯定する勇気が湧き「自分もそうしなければ餓死する体なのだ」といい、老婆の衣服を剥ぎ取って夜の中に駆け去ってしまう。
作品の冒頭は、主人に暇を出されて(仕事をクビになって)羅生門で途方に暮れている下人から始まります。
どうにもならないことを、どうにかするためには、手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、築土の下か、道端の土の上で、飢え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。
選ばないとすれば__下人の考えは、何度も同じ道を低徊したあげくに、やっとこの局所へ逢着した。
しかしこの「すれば」は、いつまでたっても、結局「すれば」であった。
下人は、手段を選ばないということを肯定しながらも、この「すれば」のかたをつけるために、当然、その後に来るべき「盗人になるより外にしかたがない。」ということを、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたのである。
このままここに居ても、飢え死にするだけ。
手段を選んでいる場合ではないが、盗人になる勇気が出ない、という状態でした。
ともかく寝る場所を探そうと門の楼へ登ると、女の死体の髪を抜く老婆の姿を見ます。
その髪の毛が、一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは、恐怖が少しずつ消えていった。
そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が、少しずつ動いてきた。
__いや、この老婆に対すると言っては、語弊があるかもしれない。
むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分ごとに強さを増してきたのである。
この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか盗人になるかという問題を、改めて持ち出したら、おそらく下人は、なんの未練もなく、飢え死にを選んだことであろう。それほど、この男の悪を憎む心は、老婆の床に挿した松の木切れのように、勢いよく燃え上がりだしていたのである。
下人には、もちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。
したがって、合理的には、それを善悪のいずれかにかたづけてよいか知らなかった。
しかし下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。
もちろん、下人は、さっきまで、自分が、盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れているのである。
盗みを働く老婆、そしてあらゆる悪に対して激しい憎悪を抱く下人。
さっきまで自分も盗人になる気でいた事を忘れ、老婆を捕まえて理由を問い詰めます。
けれども、老婆は黙っている。
両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を、眼球がまぶたの外へ出そうになるほど、見開いて、おしのように執拗く黙っている。
これを見ると、下人は明白に、この老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されているということを意識した。
そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。
後に残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足とがあるばかりである。
その時、その喉から、からすの鳴くような声が、あえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。
「この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしょうと思うたのじゃ。」
下人は、老婆の答えが存外、平凡なのに失望した。
そうして失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな侮蔑と一緒に、心の中へ入ってきた。
捕まえた老婆の生死が自分の意志に支配されていると意識した下人は、憎悪の心を冷まします。
しかし老婆の平凡な答えに失望し、侮蔑に加えてまた憎悪を抱くようになります。
その気色を感じた老婆は話を続け、この死人も生前に生活の為の悪事を働いていたこと、だからこの死人も大目にみてくれるはずだ、という事などを話します。
その話を聞いた下人の心には、悪事を働く勇気が生まれてきます。
しかし、これを聞いているうちに、下人の心には、ある勇気が生まれてきた。それは、さっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。
そうして、またさっきこの門の上へ上がって、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気である。
下人は、飢え死にをするか盗人になるかに、迷わなかったばかりではない。その時の、この男の心持ちから言えば、飢え死になどということは、ほとんど、考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。
「きっと、そうか。」
老婆の話が終わると、下人は嘲るような声で念を押した。
そうして、一歩前へ出ると、不意に右の手をにきびから話して、老婆の襟髪をつかみながら、かみつくようにこういった。
「では、おれが引剥をしようと恨むまいな。おれもそうしなければ、飢え死にをする体なのだ。」
老婆を捕らえた時の勇気とは反対の勇気を得た下人は、老婆の着物を剥ぎ取り、夜の闇に逃げ去っていきました。下人の心理推移をまとめると、下記のようになります。
門の下
羅生門で雨宿りをしていた下人は、仕事もなくなった事でこの先を案じ、「盗みを働くしかない」と考えますが決心が付きません。
老婆を捕まえる
盗みを働く老婆を発見し、老婆と罪に対する憎悪から捕まえた下人。
「安らかな得意と満足」を得ますが、老婆の平凡な答えに失望し再び憎悪を抱きます。
老婆の話を聞く
更に老婆の話を聞いた下人には、「さっき門の下で、この男には欠けていた勇気」「この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気」が生まれます。
そして、飢え死にするか盗人になるか、という迷いも消え、老婆から着物を剥ぎ取って逃げ去りました。迷い→老婆と罪への憎悪→安らかな得意と満足→再びの憎悪→盗人になる、という心理推移を辿った下人。この心理の変化についての問題が出題されやすいので、よく理解しておくと良いでしょう。
底本:「芥川龍之介全集1」ちくま文庫、筑摩書房
1986(昭和61)年9月24日第1刷発行
1997(平成9)年4月15日第14刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚 芥川龍之介全集第一巻」筑摩書房
1971(昭和46)年3月5日初版第1刷発行
初出:「帝国文学」 1915(大正4)年11月号
※底本の編者による脚注は省略しました。
入力:平山誠、野口英司
校正:もりみつじゅんじ
1997年10月29日公開
2022年7月16日修正
青空文庫作成ファイル:青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/)
voice.リンク 羅生門1

voice.リンク 羅生門2

朗読 青空文庫
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/127_15260.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/card127.html 朗読
映画の解説
『羅生門』(らしょうもん)は、1950年の日本の映画である。監督は黒澤明、三船敏郎、京マチ子、森雅之などが出演した。
芥川龍之介の短編小説『藪の中』を原作とし、タイトルや設定などは同じく芥川の短編小説『羅生門』が元になっている。
平安時代を舞台に、ある武士の殺害事件の目撃者や関係者がそれぞれ食い違った証言をする姿をそれぞれの視点から描き、人間のエゴイズムを鋭く追及しているが、ラストで人間信頼のメッセージを訴えた。
同じ出来事を複数の登場人物の視点から描く手法は、本作により映画の物語手法の1つとなり、国内外の映画で何度も用いられた。海外では羅生門効果などの学術用語も成立した。
撮影担当の宮川一夫による、サイレント映画の美しさを意識した視覚的な映像表現が特徴的で、光と影の強いコントラストによる映像美、太陽に直接カメラを向けるという当時タブーだった手法など、斬新な撮影テクニックでモノクロ映像の美しさを引き出している。 ウイキペディア
YouTube
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
