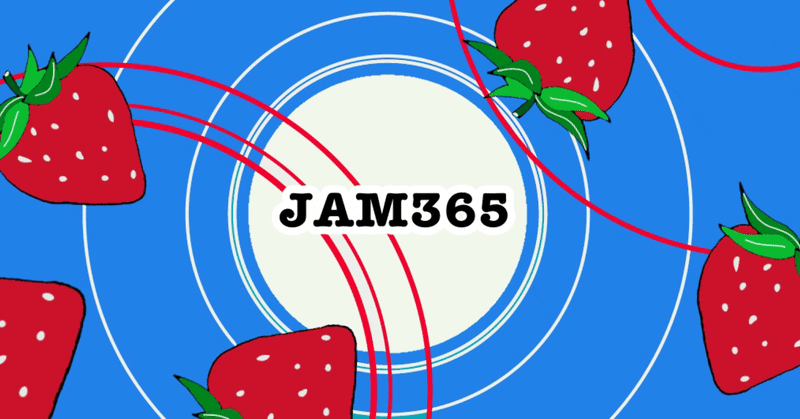
7.16 虹の日
傘をさして出かけた憂鬱の水曜日。
近所の人にもお化けと呼ばれているホーリーは、暗い部屋に飾る花を買いに出た。
雨の日はいい。
皆が薄暗さの中で、わずらわしい水の粒と足元の水たまりに靴が嵌まらないかばかりを気にしている。
それぞれが顔を覆うほどに傘を下しているので、すれ違う人の顔など見ない。
ホーリーにとっては晴れた日ほど外出が苦痛であり、曇りで普通、雨の日は絶好のお出かけ日和だった。
美容院に行くのが恥ずかしくて自らで切っている髪はちりちりの天然パーマのために使い古した竹ぼうきのようになっている。
雨の日ほどその癖が強く出てしまうが、傘があれば問題ない。
ホーリーは自分の見た目を直視しなくて済むように、いつも食器棚を鏡がわりに使っていた。
もう何年も自分の姿をしっかりと見たことはない。
それでも、ぼんやりと映る自分の姿は確かに生気が無くお化けのようで、真夜中には自分の陰に驚くこともある。
ホーリーが探しているのは、道端の花売りだ。
花屋の中に入れば、それこそ色とりどりの季節を問わない花で溢れかえっているだろうが、室内だとどうしても傘は閉じなければいけない。
それくらいなら、道端の花売りから季節の花を買う方が良いと思っている。
どうやらこの日は通り雨のようで、強い雨脚が段々と弱くなってきた。
「大変、急がなくちゃ」
花売りは手押し車を押して移動しているので、同じ場所には留まらない。
ホーリーは早足で慣れた街中を歩き回り、そしてようやく老婆の花売りを見つけた。
「すみません、お花をください」
老婆の白髪も雨粒を受けてうねり、無数の蛇が住むようだ。
顔は灰色でしわくちゃ、花を選ぶ手の甲もしわくちゃでしみだらけだった。
ホーリーは心の中で安心した。
そしてすぐに、このおばあさんになら負けていないかも知れないと思った自分を恥じた。
「あの、ちょっと急いでいただけますか?」
雨がかなり弱くなってきて、焦ったホーリーは出来るだけ丁寧にそうお願いしてみた。
すると老婆は首を傾げて笑う。
「おかしなお嬢さんだね。なに、もうすぐやむから焦らん方がいいさ」
老婆はわざわざ新品の新聞紙を丁寧に丸めて、それをまた丁寧に広げ直している。
「雨が上がらないうちに帰りたいんです。そのままでもいいのでいただけませんか」
雲間から日が差して来て、辺りがうっすらと明るくなった。
「お願いです。私、傘が無いと、ああ…」
願い虚しく、最後は霧と化した雨が止んで、街並みは足元から順に光に照らされた。
ホーリーはまるで日光に当たると死んでしまう吸血鬼のように、傘をさしたまま顔を覆ってしゃがみこんだ。
「お嬢さん、大丈夫だよ。どうせみんな最後はこんなしわくちゃになるんさ。それにあんたの儚げな姿も私はいいと思うけどね。ほら、顔上げてごらん。良いものが見えるよ」
老婆がしきりに肩を叩くので、ホーリーは仕方なく涙目のまま半分顔を上げた。
老婆はホーリーを見ておらず、どこか高いところを指差している。
「あっちだ、あっち。見事なもんだ」
水たまりに目を伏せたが、そこに映っていたものに驚いて顔を上げた。
「すごい…」
空に架かる二本の虹の煌めきが、ホーリーの胸まで真っ直ぐに届いた。
あまりの大きさに、辺りでも通行人の感嘆の声が漏れ聞こえた。
「生きててこんな立派な虹に出会ったことがない。お嬢さん、やっぱり雨上がりまでいて良かったろう」
ホーリーの真っ黒な瞳に、何色もの光りが集まって揺らめく。
こんなに美しく、たくさんの彩りを目にするのは久しぶりのことだった。
老婆は放心しているホーリーの膝に白ばかりの季節の花束を置いて手押し車を押しはじめた。
我に返ったホーリーが支払いをしようとすると、老婆は「今日は気分がいいからプレゼントさ。あんたもその花束分の優しさを誰かに分けてやってくれりゃいいから」
ホーリーは目尻の涙を拭って、深々と老婆にお辞儀をして見送った。
街を見渡して、傘を閉じて歩き出す。
人々は虹に夢中で、すれ違う人々の顔など気にしていない。
ホーリーは帰り道、街角に設置されている募金箱に花代を入れた。
隣に立っていた係員が「ありがとう」と笑ってくれたので、ホーリーも何年ぶりかの笑顔を返した。
晴れた光が充満した部屋の中央に、ホーリーは老婆のくれた花を飾った。
虹が消えると、いつの間にかその花びらは七色に色づいて、少し温い初夏の風に応えるように揺れたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
