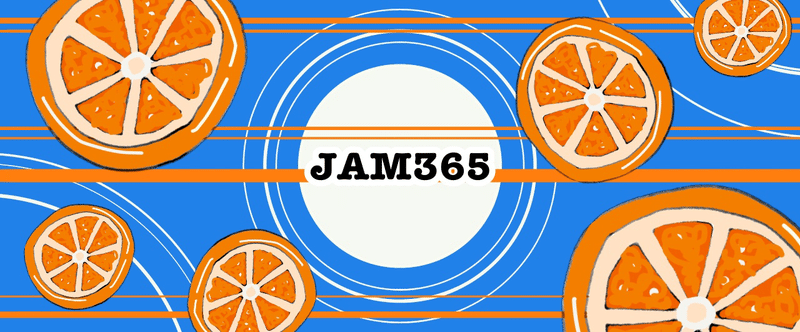
3.29 作業服の日・マリモの日
寒の戻り、というやつだろうか。
突然また寒くなった。もう四月の足音が数百メートル後ろくらいに聞こえているというのに。
健太郎は冷え切った体で現場の帰りに寄ったコンビニの空のおでんのケースを見て、眉毛をハの字に下げた。
もう春の用意をしているのだ。俺はこんなに冬の只中にいるというのに。
作業服の上に着たジャンパーのポケットに手を突っ込み、現金の数を確認する。あまり心強いとは言えない額だ。
仕方なく、健太郎はあったか〜いの段にあるペットボトルの焙じ茶と、カップの味噌汁、おにぎり三つを温めてもらったものを買いもとめ、胸に抱えて店を出た。
寒い夜道を歩き、寒いアパートに帰る。
息は白く、空からは雪が落ちてきそうだ。
ささりの悪い鍵穴に鍵を突っ込み、力ずくで回すと金属の擦れる音がして扉が開いた。
「ただーいまー」
狭い玄関に汚れたスニーカーを脱ぎ捨て、手探りで暗い部屋の電気をつける。
流しには朝ごはんの洗い物が溜まっているが、畳敷きの六畳一間はきれいに片付いている。
健太郎はちゃぶ台の上にコンビニの袋を置くと、折り畳んだ布団の隣の背の低い書棚の前に正座した。
「ただいま帰りましたー」
自前で作った赤い水玉柄の小さな座布団の上に置いた、小さな瓶に挨拶をする。
健太郎が指先でそっとつつけば、おかえりと返すようにふわふわと緑のマリモが揺れる。
「今日も可愛いなぁ。寒かっただろう?暖房が無くて悪いね」
健太郎は、部屋の隅にある白くなった四角い畳の跡を見て言った。
現場で知り合い仲良くなった中年の男に娘が産まれたというので、石油ストーブを出産祝いにあげた。
男の家には暖房器具が無く、家が寒くて娘が可哀想だと男が嘆いていたからだ。
中古で悪いけど、と言うと男は何度も頭を下げて礼を言った。
健太郎は、もう春が来るだろうし男一人くらいなら暖房器具が無くても何とかなるだろうとたかを括っていたところもあった。まさかまだこんなに寒い日があろうとは。
「お前のことだけは心配だな。今夜は一緒の布団で寝よう」
健太郎はコンロで湯を沸かし、カップの味噌汁を作って簡単な夕飯を始めた。
寒いのでジャンパーは着たまま、作業服の上にマリモの瓶を入れてやる。
身寄りの無い一人暮らしの健太郎の心を日々支えるのは、この祖母から送られてきたマリモだけだ。
健太郎は幼少期から北海道で祖母と暮らしていたが、成人すると同時に上京した。
都会暮らしのなかで彼女がいたこともあったが、人と暮らすのはあまり向いていなかった。
土木作業員として懸命に働き、毎月祖母に仕送りをするのが健太郎の幸せだった。
祖母は少ない年金から健太郎の好きなお菓子や缶詰などを送ってくれていたが、ある日突然マリモの入った瓶を送ってきた。
そして、その宅配便が祖母からの最期の贈り物となった。
マリモは大きくなる様子もなく、生きているかどうかも実は分からない。
それでも健太郎は、祖母から譲り受けたこのマリモを家族の一部として大切にしていた。
「はあ。やっぱりあったかい味噌汁は沁みるわ。早く春にならないかなあ。な、マリモ」
息をするたびに腹の上でちゃぷちゃぷと揺れるマリモを見ながら、健太郎は気の抜けた顔でそう言った。
「ま、北海道の冬よりはマシか。…ん?もしかしてお前寒い方が得意?」
腹が満ちて畳に崩れながら、健太郎はマリモの瓶を腹から出して顔の横に置いた。丸々としたその姿を眺めながら、幸せな気持ちでうたた寝を始める。
くしゃみをして起きるまで、健太郎は祖母とマリモと一緒に春の野原の上で遊ぶ夢を見た。
寝ぼけまなこを擦る健太郎の姿を、ころころと揺れるマリモが見ていた。
寒い三月の終わりの夜だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
