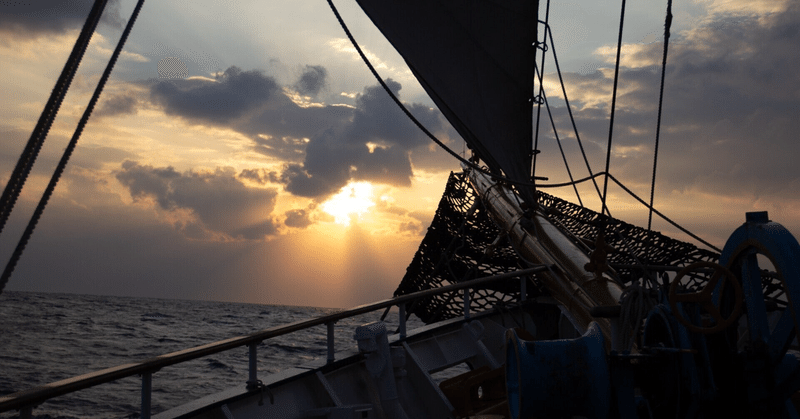
「トライアングル」その9
連載ファンタジー小説 わたしはだれ?
第二三章 すべてそろった
翌朝、ランダムで教会の塔へ降り立つと、まず、ここがかなり傾斜していることがわかった。
「ここにもしっかり砂が積もってる。とにかくこの砂を捨てないと、どうなっているのか調べられないよ。
しかたない、みんなで手分けして始めるとしようかね」
ばぁばにこういわれても、砂をすくう物などだれも持ってきていない。
そこで、すべり落ちないように四つんばいになりながら手で砂を捨てる作業が始まった。
一人で捨てられる量は少なくても、さすがに九人もの手があると着実に作業は進み、午前中には、砂の下からきらきら光る粒がまじった白い石が現れた。
「外壁は茶色い石を使っているのに、ここだけは光る白石を使ったんだね」
白い石は平らではなく、複雑に凹凸をつけて敷き詰められていた。
「すげえなぁ。石と石の間には、かみそりの刃一枚だって入らないぞ」
トンデンじいさんが感心しながらうなっている。
「それはすごいけどな、石が変なふうに敷いてあるだけで、光を集める仕掛けなんてないよね」
カンタンがいったように、ここにはなにもなかった。
「一体どうやって光を集めるんだろう?アルドたちは、なにかわかるかい?」
ばぁばがきいたが、アルドたちも首を横にふった。
このとき、フレイがばぁばの手を握った。
「ばぁば・・・」
ばぁばがアルドを見る。
「ちっ、もうきやがったか」
なにもわからないうちに、また洞窟にもどらなければいけなくなった。
「くそっ、なんの成果もなしだ」
洞窟にもどるやいなや、カンタンが悪態をついた。
「ねえアルド、ここにいるのがあなたちだけのときは、あの風は夜にしかこなかったんでしょ?」
サラダッテがきくと、アルドはうなずいた。
「おれたちは、あいつに対してなんの手もうてなかったから、夜だけ吹いて脅
すだけで十分だったんだろうよ。けどフレイが来たから・・・、風の声を聴く者が現れたからな」
「新しい風が吹くかもしれないと恐れてるの?」
「そうかもしれないな。だとすると、あいつは、もうじきに、おれたちを一歩も外に出さなくなるかもしれない」
これをきいて、ばぁばはすぐに決めた。
「もうほんとうに時間がないね。こうなったら、一つ一つみんなで調べるなんて悠長なことはしてられない。
明日は、手分けして残りの三つの塔を調べるんだよ。カンタンはブレンド、ハメドといっしょに交易人の塔に、トンデンじいさん、サラダッテ、シラードの三人は長フォラードたちが塩とをしていた塔を調べてくれるかい?アルドとフレイと私はもう一度風聴塔を調べるからね」
ばぁばがこういったとたん、今まで古い毛布の上で丸くなっていたミラクルが飛び出してきて、しきりにニャアニャアと鳴き始めた。
「おやおや、ミラクルもいっしょに行きたいみたいね。はいはい、サスーラにきいてあげますよ」
サラダッテが、ばぁばを見た。
「ネコはじゃまになるだけだよ」
「ランダムに乗るときは、私がちゃんと抱くし、それにミラクルはとてもお利口だから、きっとじゃまなんかしないわ。
だからお願い、連れていっていいでしょ?」
すぐにフレイがいったので、こまったばぁばが、今度はアルドを見た。
「おれはかまわないぜ」
これで決まった。
次の日、一番最初に出発したカンタンたちは、交易人の塔にランダムをつけ
るやいなや持ってきたバケツを使ってすぐに砂をかきだしはじめた。
この作業を一時間も続けるうちに、この塔の上も昨日の教会と同じように傾斜していて、光る石の粒がはいった石が凹凸をつけて複雑に敷き詰められていた。
カンタンたちは、石一つ一つを叩いたり、なでたりしながら調べてみたが、こちらの方も昨日と同じように何の仕掛けや仕組みもでてこなかった。
そして、それはサラダッテたちも同じだった。
「おいおい、こんなに調べても何一つ出てこないなんてよぉ、本当にここが大なるトライアングルの一つなのか?」
傾斜した塔の上で、トンデンじいさんは、すべらないように両手をついてしゃがんでいたが、敷き詰められた石を一心不乱に見ていたサラダッテには、そんな愚痴はまったくきこえていない。
頭をかしげてなにか考え込んでいるサラダッテを見て、シラードがきいた。
「なにか気になることがあるんですか?」
「ねえシラード、このきらきら光る粒が入った石って、ほかの所でも使ってるの?」
「いや、こんな石は、ほかの所で見たことありません。ぼく、教会にも、それにこの塔の中にも何度も入ったことはありますが、床も壁もみんな茶色っぽい石でしたよ」
「そう、やっぱりね。ねえ、もう一つききたいけれど、フラリアではよく大雨が降ったの?」
「雨ですか?ここは大雨が降るっていう地形ではないと思うけど・・・」
「おいサラダッテ、おまえなにか気がついたな。なにがわかったんだ?早く教えろよ」
トンデンじいさんが、サラダッテにつめよった。
「ここの屋根は街の中心に向かって傾斜しているでしょ。昨日の教会はどうだったかしら?」
「おい、おれは、おまえが何を知ってるのか教えて欲しいんだって」
「今から話すわ。でもそのためには教会はどうだったか知る必要があるの」
「ここと同じ、街の中心に向かって傾いていましたよ」
シラードが答えた。
「やっぱり。じゃあカンタンたちが調べているもう一つの塔も、きっと同じね」
「だから、それがなんだっていうんだ?」
トンデンじいさんが、じれったそうにきいた。
「私はね、最初屋根をこんなに傾斜させるのは、ここは大雨が多いからだと思ったのよ。ほら、傾斜していると雨がたまらずに下に流れやすいでしょ?でもシラードにきいたら、ここでは大雨が降らないっていったわ。
だったらなんのために、こんなに傾斜させたの?それに、どうしてここだけこんなに光る石を使ったのかしら?」
サラダッテは、トンデンじいさんを見てきいた。
「お、おれに、そんなことをきいたって知るわけないだろ」
「あの・・・もしかしたら、この屋根を反射板みたいに使いたかったから?」
おずおずとシラードが答えた。
「そう、私も三つの塔は、太陽のあたり具合から、それぞれ傾斜角度を変えて光をどこか一ヶ所に集める役目をしてると思うのよ。
じゃあ、どこに光を集めるのだと思う?」
「それは、あそこですよね」
シラードが風聴塔を指さしたころ、その風聴塔では、ばぁばとアルド、そしてフレイが塔の一番上にのぼり、フラリアの街を見下ろしていた。
「ここと、あの三つの塔は、見たところずいぶん昔に建てられたみたいだね」
「いい伝えによると、はるか昔、フラリア人が国を興すとき、まずこの四つの塔を建てて、よき風を吹かせたらしいんだ」
「ふーん、そんな言われがあるんだったら、塔に仕掛けがあってもおかしくないね。
さてさて、いわくつきのこの塔が小なるトライアングルなら、ここに光が入るはずだけど、一体どういう仕組みがあるのか見当もつかないねえ」
「光が入ってくるとしたら、柱と柱のあの開いたところからだよな?」
「そうとしか考えられないよね。だったらもう一度下の階を調べたほうがよさそうだ。フレイ、下におりるよ」
フレイは座って、じっとフラリアの街を見ていた。
「私、まだここにいたいの」
ミラクルも、フレイの横に座って動こうとしない。
「じゃあ、そこにいてもいいよ。けどね、落ちないように気をつけるんだよ」
そういい残して、ばぁばとアルドは下におりていった。
フレイが座っている風聴塔にも細かい砂が厚く積もっており、砂の上には花の形をしたミラクルの足跡がいくつもついていた。
フレイは砂の上に座って、そっとミラクルを抱いた。
「ミラクル、ミラクル、私ね、風のうなり声をきくと気が狂いそうになるから、本当はちょっと恐いのよ。
あんなに恐ろしい声の中から、喜びの声なんてきけるわけない。
でも・・・でもね、こんなことは誰にもいえないの」
声もださずに泣き始めたフレイの頬を、ミラクルはざらざらの舌で何度もなめた。
「ふふ、ミラクルったら、いたいよ」
ミラクルは泣いているフレイの目をじっと見つめてから、トンと砂の上に降りた。そして塔の中央まで行くと、今度は厚く積もった砂を一心不乱に掘り始めたのだ。
「ミラクルったら、どうしたの?こっちにおいで」
フレイが呼んでもミラクルは砂を掘りつづけた。
掘られた砂の穴がしだいに大きくなっていく。しばらくすると、ミラクルの爪がガリッと何かをひっかく音がした。
「どうしたのミラクル?」
フレイが見てみると、ミラクルの掘った穴の底にガラスのようなものがあった。
「これ、なに?」
フレイは両手で穴の周りの砂を取り除いてみと、それは大きな厚いガラスで、一番凹んだ中央にむかって複雑なカット模様がほどこされていた。
このガラスが風聴塔の天井にはめ込まれていたのだ。
「ばぁば」
と、フレイは叫ぼうとしたが声がでない。
「フレイ、この光はなんだい?なにをしたんだい?」
ばぁばが下から叫び、フレイは息を吸い込んでから、大声をあげた。
「ばぁば、すぐ来て。私、窓を見つけたの」
すぐにかけあがってきたアルドとばぁばは、この大きなガラス板を見て息をのんだ。
「砂がガラスを隠してたんだな。だから下には光が入らなかったんだ」
「こんなガラスがはめ込まれていたなんて気がつかなかったよ」
アルドはガラスの一番くぼんだ箇所を指さした。
「上から見ると大きなガラス板だが、見ろ、先端はこんなに細い。
この細い先が三階の天井部分に出てるんだ。あの石の天井から、こんなに小さな穴を見つけるのは至難のワザだな」
「もしかして、これが真実の窓かい?」
「そうだとしたら、三つの塔から、ここに光が集まるはずだ」
アルドは手をかざして空を見た。
「あと少しで陽が真上に来る。そのときがきたら、これが真実の窓かどうかわかるはずだ。見ろ、塔の上が光ってる」
三つの塔の上はまぶしく光り、その光が風聴塔に向かって伸びている。
「下に行くんだ!」
そう叫んだアルド、ばぁば、フレイが階段をかけおりると、天井の小さな穴から、ブルーフェアリーの花が彫られた石に向かって光が注がれていた。
まばゆく輝く光は、次々と色を変えながら花を照らしている。
この光を、ばぁばとアルドは、放心したように見ていたが、やがて太陽の位置がすれ、光がすぅーと消えてしまうと、ハッと我にかえった。
そしてようやく、床に座り込んでガクガクとふるえているフレイに気がついたのだ。
「フレイ、フレイ、大丈夫かい?」
ばぁばはフレイをかたく抱きしめた。
「ばぁば」
フレイは、ばぁばの胸に顔をうずめて泣き始めた。
「ああ、ああ、かわいそうに、おまえは、あの光が恐かったんだね」
「ちがうの、ちがうの。恐かったのは、あの光を見る前まで。でも・・・、でも今はもう大丈夫。ばぁば、私、光の下に立つわ」
泣きながらいい放ったフレイの目には、強い決意が満ちていた。
そしてこの目を見たばぁばは、もうなにもいえなくなってしまった。
アルドもつらそうな顔をしてフレイを見ている。
「とにかく、今はまず洞窟に帰ったほうがいい。ほかの連中にももどるようにいうから、話はそのあとだ」
アルドはピィーッ鋭い口笛を吹いてから、ばぁばとフレイをランダムに乗せて、洞窟にもどっていった。
第二四章 光の下へ
アルドたちが洞窟に帰ると、そこには、もうサラダッテやカンタンたちがいたので、ばぁばはみんなに、風聴塔での出来事を話したのだった。
この話をきいて、トンデンじいさんやハメドたちは一旦は喜んで歓声をあげたものの、すぐにだまりこんでしまった。
なぜなら長フォラードの詞の謎をといたものの、これから先になにがあるのかだれもわからなかったからだ。
ただ一つ、これからおこることに、フレイはたった一人で立ち向かわなければいけないことだけは明らかだった。
トンデンじいさんは、なんの手助けもできないもどかしさを紛らわすかのように、壊れたモーターをガチャガチャと音をたてて直そうとしていた。
だれもがだまりこんでいる中で、サラダッテが低い声で子守り歌を歌い始めると、フレイはそっとその場から離れた。
「外に出たいか?」
ひとりで洞窟の入り口に立つフレイに、アルドがきいた。
「扉を開けてもいいの?」
「今はあいつの気配がないから大丈夫だ」
アルドが、やっと人ひとり通れるぐらいの幅に扉を開けると、フレイはその間をすっと通り抜けて、洞窟の外に出てみた。
誰もいない街が、月の銀色に照らされている。
「フレイ、おまえは本当にもう恐くないのか?」
フレイはうなずいた。
「おれは、おまえを犠牲にするようで・・・」
「アルド、私はあの光の下に立つと自分で決めたの、だから犠牲なんかじゃないのよ」
「これから先、なにがおこるのかわからないんだぞ。もしおまえがやめたいのなら・・・」
「アルド」
フレイはアルドのことばをさえぎった。
「私ね、ばぁばといっしょに暮らしていて、とっても楽しかったのよ。毎月変わる花の名前も大好きだった。でも心の奥では自分がだれで、どこで生まれたのか知りたかったの。
そんな時にフラリアのことを知って、ここに来て、アルドたちに出会って、そしてわたしの本当の名前が、自分がだれなのかわかった。
でもわたしの故郷のフラリアはこんな悲しいことになっていた。
あの詞をきいて・・・、私にしかフラリアを助けられないってきいて、最初は恐かったわ。でもね、今日、あの虹色に輝く光を見たら、どうしてだかわからないけれど、恐いっていう気持ちがどこかに飛んでいってしまったの。長フォラードがいった光は闇を吸い、って本当ね」
フレイはアルドを見上げてほほ笑んだ。
「もしかしたら、死んでしまうかもしれないんだぞ」
吐き捨てるようにいって、顔をそむけたアルドの手をフレイはぎゅっと握った。
「もしそうなっても、悲しんだりしないでね、苦しんだりしないでね。
純粋なフラリア人はいなくなっても、きっとフラリアの国がよみがえるから」
だれも眠ることができない夜が明けると、ハメドは炉に火をおこし、固いパンと干し肉の朝食を用意した。
「風聴塔には、いつ行くの?」
フレイはアルドにきいた。
「太陽が真上にくる少し前だ」
「じゃあ、まだ時間はあるのね。ねえアルド、ランダムで街の上を一周したいの。連れてってくれる?」
ニャーオとミラクルが、フレイの足元にすり寄ってきた。
「ふふ、ミラクルも行きたいって。ね、いいでしょ?」
「ああ」
まだ冷たい空気が残る朝日の中、フレイとミラクルを乗せてアルドはランダムを飛ばした。
「アルド、ブルーフェアリーの畑はどこにあったの?」
「あそこだ」
アルドは、街から少し離れた丘を指さした。
「あそこで父さんと母さんはいつも働いていたのね?」
「ああ、サテルドさんたちは、いつもブルーフェアリーをさわっていたから、指にその香りがしみついていた。イマルダが、おれたちの頭や頬をなでるたびにいい匂いがしたんだ」
「だからあの匂いをかいだとき、あんなにもせつなかったのね。ずっと忘れていたけれど、私にもフラリアの思い出があったんだわ。
ねえアルド、私、ここがどんな街だったのか知りたいの。教えてくれる?」
アルドが昔のフラリアの様子を話しながらゆっくりと飛んでいると、ミラクルも前足をたてかけて、じっと街を見ていた。
やがて陽が高く昇り、フレイが風聴塔に向かう時間が近づいてきた。
一旦洞窟に戻ったアルドたちは、今度は三台のランダムと一緒に風聴塔に向かって飛び始めた。
誰も何もいわない。
風聴塔の前でランダムから降りると、フレイは無言で階段をのぼり、すぐにブルーフェアリーがきざまれた石の上に立とうとした。
そんなフレイを、ばぁばは愛おしそうに抱きしめた。
「ああ、私の大事な赤ちゃん。私は、まだおまえと別れたくないんだ。フレイ、フレイ、おまえはきっともどってきてくれるね」
カンタンが、ズズーッと音をたてて鼻をすすった。
「ちきしょーっ、こんな所にダフネを連れてくるんじゃなかった」
「ダフネじゃなくって、フレイよ」
こういぅたサラダッテに、カンタンはくってかかった。
「おれにとって、あの子はダフネなんだよ。たった一人でこんな所に立つなんてよぉ、まるで人柱じゃないか。
なあダフネ、こんなのはやめて、おれたちと一緒に白フクロウ屋敷に帰ろうぜ」
フレイは首を横にふった。
「フレイ!」
流れる涙を、だれもぬぐおうとしない。
「私はちっとも悲しくないのに、どうしてみんなは泣くの?ねえだいじょうぶだから、そんなに心配しないで」
サラダッテ、カンタン、トンデンじいさん、シラード、ハメド、ブレンドが順々にフレイを抱きしめていった。
アルドが、がっしりとした腕でやさしく包み込んでくれたとき、その耳元で
「アルド、もし私がいなくなったら、ばぁばたちのことお願いね」
とフレイがささやくと、アルドは静かにうなずいた。
「ばぁば」
フレイが柱に寄りかかっていたばぁばに飛びついた。
「ばぁば、ありがとう」
フレイを固く抱きしめ、ばぁばはいつまでもこうしていたいと思った。
けれども、陽が真上にさしかかり、ガラスを通して塔の中に光が入りだしたのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
