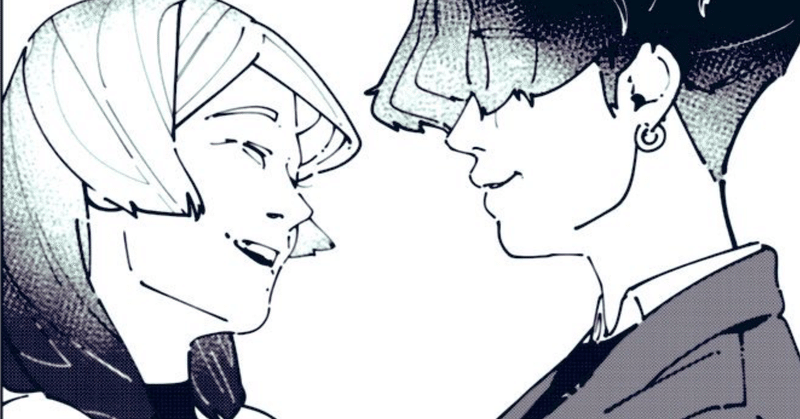
【本編】『tie.acrossstory』
私の理想とする女性とは、人を傷つけても自分が傷ついても、それを吸収できる、優しい女性です。
ほとんどの客は、私-しがないキャバレーの歌手-に言葉を求めていない。
わたしは短い演説を終えると自分のマイクをスタンドから外し、ステージを去ろうとした。
そのとき、ふと振り返った。なんだか、強い視線を感じた。
ほかの歌手より拍手の少ない私のステージは、翌日のポスターで「最後の演説で歌が台無し」と飾られた。
「はぁあ」
私の深い溜息には、疲れと、少しだけ、涙も入っていた。
「イヴ、あなたはほかの店でもあんな演説するの?」
同職であるヨーテに話しかけられる。この店で初対面であるが、このように馴れ馴れしい。
「...まさか。ここで初めてよ。このキャバレー、客のレベルが低いわね。」
私は思ったことを悪意をもってぶつけた。
しかし、ヨーテは嫌な顔ひとつしなかった(笑いもしなかったが)。
「大切な客よ。あんなこと言ったのは、あなたのことが気になるからよ」
「ステージの上の、目も合わない女性に、ああいう物言いは、ここでは許されるのね」
「ねぇ、何をそんなムキになってるの?」
「女性としての尊厳よ!」
私は化粧台に手を付き、音を立てて立ち上がった。
幸いにも香水や化粧道具が倒れることは無かったが、どれも心配そうに私を見上げている。
「ま、謝る機会もないんだし、もういいんじゃない?正直、あなたの行動は理解に苦しむけど、スッキリはしたわ」
「......あなたにいま、謝っとこうか?」
私は初めてヨーテへ暖かな笑顔と、視線を向けた。
涙は引っ込んだが、疲れはまだある。
疲れを癒してくれるのは、やっぱり愛する人なのだろうが。私にはもう何年もいない。
「そうだわ、ハンサムなお客さんから、これ」
「レター?」
「にしては大きくない?」
ヨーテが机の引き出しから出したのは、まるで...
「申込書の大きさじゃない?」
その一言で、私の体温が少し上がった。
しかし、こんなことで舞い上がってるとは思われたくない。机に浅く腰かけ、背筋をしゃんと伸ばし、顎を引いて。
「あぁ、あとで読むわ。」
と視界からそれを外した。
「そ、私もう行くから!じゃ」
ヨーテはこのキャバレーの支配人の腕に自分を絡ませ、笑いながら部屋を出ていった。
笑い声が階段をのぼり、ドレスルームに静寂がおとずれた。
誰もいないことを確認するため、1分ほど鏡の中の部屋を確認する。
ゆっくりとした仕草で封を切り、中身を確認した。
楽譜だ。4枚の、手書きの楽譜。そして、私はこの音符を知っている。
「オーディションかと、騙されましたよ....先生。」
かつて愛した人、そして、今も一番におもってる人。
その名前を本当に久しぶりに口にした。
それだけで、ドキドキした。
その少し前、イヴの歌唱の少し前のホールで、わたしはファイブラインの真っ白な楽譜と向き合っていた。
最近ずっとこんな調子だ。
もうそろそろ描き始めないとまずい。
仕事として書いてる以上、一定リズムで曲を更新したいところではあった。
今日はこの街に来て始めて入るキャバレーで作業していた。
結構うるさい。
うるさいのが嫌なんじゃない。ただ、この五月蝿さは、質の悪いやつだから。
「はぁあ」
こんな時は必ずイヴを思い出す。
わたしが今までで1番愛した人。ずっと想ってる人。
最後には、他の作詞家の男と腕を組んで海外へ行ってしまった。
送れたとしても送れない。どうせ送れないけど。
わたしはどうしても進まない作業に愛想をつかして、メモ代わりに手紙を書き始めた。
「君も覚えてるはずだ。なんでわたしにそれが確信できるか。だって、あの時私たちは、一心同体だったから。」
うん、書き初めにしては大概キモイ!!!
こんなのイヴ本人が受け取ったら悪い意味で笑われてしまう...
なんだか筆がのってきたので、このままイヴへの手紙を書き進めることにした。
「私の中に入ってきそうな距離で、君はわたしを歌った」
作曲家であり、恋人であったわたしの歌を、イヴは積極的に歌った。
なんだか文面がストーカーっぽくなってしまってないか...
「わたしは今、こうして放浪しているが。別に迷子じゃない。」
「君を探してる訳でも、ない」
断じて。
そのとき、後ろから可愛らしい声がした。
振り向くと、胸元を大きく開いた緑髪の少女が、1人で酔っ払っていた。
ここのキャバレーも捨てたもんじゃないな。
「なにか?」
私は気のない返事を返す。もちろん、鼻の下は伸びている。
「あら、隠したの?」
無意識に楽譜-もとい、イヴへの手紙-を右手で隠すと、緑髪の少女もグラスを持たない手でわたしの手を軽くつついた。
なかなかのアルコールの香りが一帯を包んだ。
「お嬢さん、もうその辺に...」
「あなたに声をかけるには、こうするしか無かったの」
「は?」
「勇気をだして、声掛けたの!」
か、かわいい...この子は来店からずっとわたしに声をかけようとして、勇気が出ないからお酒の力を借りて、今この状況になってると言うのか?
かわいい!!
「あの、一緒にお店を出るには、どうしたらいいですか...」
酔っ払ってではなく、恋する乙女の潤んだ瞳で、緑髪の彼女は猫なで声を出した。
わたしも色気のある視線で答える。
「何を言ってるのかわかってる?それって...」
そのときだ。
ステージの上だから、わたしがまさに今、背を向けてるところから、あの声がした。
さらに言えば、私の歌。
体が硬直して、涙が滲んでしまった。
君が私から離れた本当の理由は、男に嫁いだからでも、私に飽きたからでもない。
自由な自分が好きで、自由なわたしが好きだった。
それだけの事。
ゆっくり振り返ると、曲は終わって、客に野次を飛ばされるイヴがいた。
「私の理想とする女性とは、人を傷つけても自分が傷ついても、それを吸収できる、優しい女性です。」
そう言い捨て、ステージを去る彼女の背中を、焦がしてしまうほど見つめていた。
「ね、どうしたら一緒にぬけだせる?」
隣でまだ何か言ってる少女に、私はそっと微笑んで「この曲が書き終わったらね」と額へキスをした。
「今書いてる曲です。あれ以来、どんな歌も君のためのように感じるよ。」
楽譜の最後に添えられたメッセージに、思わず笑みがこぼれる。
先生がまだ私を想ってくれている、歌を書いてくれている。それが本当に嬉しかった。
あなたを捨てて選んだ、歌手の道。
辛いことばかりだけど、まだまだ、頑張れる。
その先で出会えたら、きっと私たちは、もう離れない。
『tie.across story』Fin.
いかがでしたでしょう?
今回は、仕事と恋愛のお話を描きました。
「私の知らない街で、私の曲を歌うんだろう」
そんなポエミーな言葉から始まった『tie.across story』です。
作曲家の凪(先生)と、それを形にする、歌手のイヴ。
1度は恋愛へ発展しましたが、それぞれの道を歩むために離れます。
それでもずっとおもい、愛する。ふとした時に思い出して、二人の子供である曲を口ずさむ。
そういうお話でした。
菓子蔵かる。
今日も一日なんでもない日が素敵でありますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
