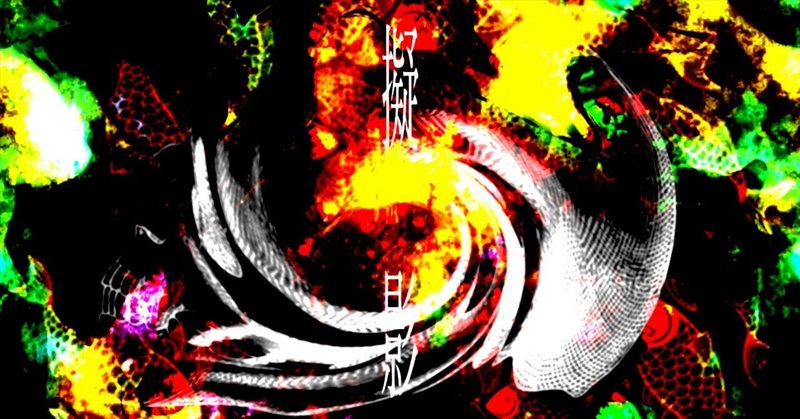
擬影
2024/01/20 17:00
[From] yanagi sawa
[Sub] Re:Re:Re:「この庭から、星へ」
[bit] about… 18,000 over.
擬影
- giei.-
0.
放課後というのはさまざまなロマンスが集まり、その舞台といえば、屋上だ。
少し下手すぎやしないかと女生徒は思うが、高鳴る鼓動は彼女の足を急かす。歩幅が小さい彼女は階段を一段ずつ登るが、今日は二段飛ばしで、三つ編みを揺らす。
扉を開け放ち、待っていたのは金糸のような髪を持つ少年だ。彼は子供の頃から俳優事務所に入っているため校則の厳しい進学校で唯一、髪を染めることも、ピアスをつけることも許されている。
「あの、先輩・・・」
屋上を囲むフェンスの外側に立っている少年が女生徒を見る。
カラーコンタクトだとわかっていても少年に見つめられると女生徒は呼吸を失ってしまう。特別鍛えているような素振りはこの一年間、女生徒が観察し続けてきた中で見受けられなかったが、バレエダンサーの母親の血なのか、やはり直立しているだけで美しく、豹のようなしなやかさがある。
「告白しても無駄だよ。だって僕は君の所有物でも、自慰の道具でもないからね」
少年の手はフェンスを掴んでいる。離せば落下し、最悪死んでしまうだろう。
女生徒は恥ずかしくなりつい、スカートを抑えてしまった。彼女の部屋には隠し撮りした彼の写真が額縁に納められ、彼のために作った祭壇に祀られている。
「じゃあ、どうしたらお側にいられますか」
女生徒にとって彼は神だった。そして彼女は自分のことを神の使いだと思い込んでいる。そうすることで、自分が教室に入った瞬間に静まる教室や、その後に始まるクラスメイトの罵りから自分を保っているのだ。
「きみさ、大喜利って得意?」
「あ、へ?」
女生徒の口から天使らしからぬ、間抜けな、人間みたいな声が漏れる。
「ほら、ぼくさ見ての通り美少年でしょ。勉強もスポーツもできちゃうしさ、生きていく中で困った瞬間なんてないわけ。でもさ、この前バラエティ番組に出て、面皰だらけのオジサンが僕より目立っていたの。その人調べると結構有名なお笑いさんでさ、で、試しに僕もSNSで、そういうのあるじゃん? 大喜利ってやつ? やってみたのよ。そしたら毎日ろくな女の子ともデキずにお家で自分のいじってるような連中の方が遥かに面白くて、だから今すっごい悔しくてさ」
突然のことで女生徒は呆気に取られ、彼女の中にあった理想像がぼろぼろと崩れ始める。
「いや・・・。そんな一気にしゃべらないで」
「なんで? だってお前は僕の側にいたいんだろ? え、待って。人の話に耳を傾けることもできないのに、僕の側にいたいって思ってんの? え、まじ? クソヤバ女じゃーん」
微笑みひとつ浮かべず容赦なく少年は言葉を刺す。
主導権はいつだって彼が握っている。
「じゃあ、お題言うね」
「お、だい」
「今、ここから飛び降りようとしている男子生徒に向けて、彼女が言った衝撃の一言とは?」
女生徒の青い春は桜を待たず散っていく。
大喜利?
私の、私だけの神様はどこへ消えたの?
じゃあなんだったの、この時間は。
それでも彼女は怒りを、虚しさを、少しばかりの期待を込めて、答えを放った。
「ちょ、超絶イケメンだけど、喋ると残念なのなぁぜなぁぜ!」
女生徒は精一杯、流行に乗った。
「その構文、もう古いよ」
少年はフェンスを思い切り押して、後ろ向きのまま飛び降りる。女生徒は自分だけの神を守護しようと走ったが、フェンスに思い切り顔をぶつけ、少年の手を握ることができなかった。
女生徒は哭いた。
道標を失った女生徒はこれから何を頼って、どう生きていけばいいのかわからなくなってしまった。
自分が最期の人になれた安堵と、なってしまった罪悪感が女性との胸中に渦を作る。ごめんなさいと、ただごめんなさいと女生徒は繰り返している。
茜空から嘲笑が聞こえてくる。
女生徒は最初、その声は自らが作り出した幻聴だと思っていたが、紛れもなく誰かの笑い声だった。女生徒はフェンスをよじ登り、少年が立っていた位置と同じ場所で見下ろしてみると、走り高跳び用のマットの上で仰向けになりながら彼は女生徒を指さしていた。
少年も、その取り巻きも、女生徒を嗤い、彼はひっくり返った虫のように四肢をばたつかせている。
「アイツさ、電車で一緒になると必ず僕の向かいに座るのよ。でさ、この前ちょうどその席にジジイがいて、なんかもめててさ、唾撒き散らしながらキャンキャン吠えてたわ。お前の予約席じゃねぇのに」
取り巻きの男の下顎を見上げながら笑っている少年、キヨハルは高校三年生だ。
「キヨくん、この後カラオケ行くでしょ?」
「何、行って欲しいの?」
「おっしゃ! じゃあ今日はオール確定!」
「今日もだろうがタニシ」
そう呼ばれている取り巻きの一人の男子生徒は親から、人との縁を大事にできるようにという願いを込められエニシと名付けられた。
「わりぃわりぃ。そうだわ」
エニシが緊張しながら笑い、キヨハルを起こすと取り巻きの奥でじっと女生徒を見上げていた男子二人が呼ばれる。彼らはマットの端と端を持たされ、引き摺らないように体育倉庫に向かって走り出す。それを二、三人の男女が手を叩きながら笑っていた。
そんな光景を見下ろしながら女生徒は胸が乾いていくのを感じた。
まるで砂浜に打ち寄せる波を眺めるように、眼科の人間の動きがただの景色になっていく。
自分でも驚いてしまうほど、女生徒はキヨハルに飽きていた。
「これでわかったでしょ? もうこの世界ダメダメなんだよ。だから帰ったらわたしたちの新しい推しでもさがそ?」
まるで言い聞かせるように呟いた後、女生徒は帰宅し、家族が寝静ると再び支度をした。
女生徒は深夜2時過ぎに家を出て、自分を揶揄うクラスメイトの家の窓に岩を投げ込んだ。庭からリビングへ通ずる窓に大きなヒビが入って割れた。できた穴から動転している人間たちの悲鳴が聞こえた。
翌日から、彼女は教室で少しだけ息がしやすくなった。
1.
名前には大なり小なり、願いや意味が込められている。だとすれば、彼女、ネズミはどんな意味が込められているのだろう。
漢字は干支に倣い、子の1文字だ。
どんな言葉でもよく調べれば良い捉え方というものは存在するが、誰もがそこまでするほど暇ではない。そのためネズミは幼い頃から迫害を受けた。その影響か、彼女の性格は捻じ曲がってしまった。
ネズミが帰るワンルームには床、コンロの上、冷蔵庫の中すら、いくつものキャンバスが散らばり、部屋の真ん中には孤島のようにイーゼルが屹立している。
事務仕事を終えて帰宅した彼女はメイクを落とすこともなくスツールに腰掛ける。股を開き、振り上げた右足をキャンバスの縁に置くと彼女は鉛筆を手に取る。今はまだ下書きの段階だ。
ネズミは左手の人差し指を噛むのが癖で、人差し指の付け根あたりを何度も噛むためそこには赤黒い歯形がついている。喰み、吸いつきながらネズミは黒鉛で対象の輪郭を模っていく。部屋の隅では除湿機が動いていて、キャンバスに黴が生えないように管理し続ける。
やがて噛んでいた左手の人差し指が蛇のように顎に落ち、鎖骨を渡り、痩せ細って凹凸が顕になった肋を何度も撫でる。
彼女は熱っていた。
行為を終えたネズミはキャンバスから足を外した。スツールから立ち上がって玄関に戻ると放置していた袋からサンドウィッチを掴む。手を洗わず、乱雑に包装を剥いで齧りつき、マヨネーズで汚れた手を舐め取り、唾液はパンツスーツで拭く。そして彼女は再びキャンバスと対峙する。
ネズミは画家ではない。高校の事務員だ。
ネズミにとって人物を描くという行為は捻じ曲げる前段階に過ぎなかった。彼女は描くモチーフが美しければ美しいほど、ソレを捻り、歪ませ、壊すと胸がスッとした。どこにもない自分だけの地平が世界の中に突然現れた気がした。
描く人物は精緻に描けば描くほど、福笑いのように顔面のパーツを散らしたりすると、その日気を削がれた上司の発言や、両親からの婚約者の推薦など、日々の瑣末なストレスが消え失せた。
ネズミは結局、翌朝の四時までキャンバスに右足を乗せ、鉛筆を走らせ続けた。そしてようやく出来上がったデッサンに描かれていたのは、
彼女が通う高校の生徒、キヨハルだった。
彼女は二時間眠り、高校に出勤した。
教室の扉側の列、その最後尾にキヨハルの席はある。彼の周りは受験シーズンの真っ只中で参考書の前で頭を抱える者や、窓際でストレスを友人と緩和している者、それらの雑音から逃れるためにスマホのソーシャルゲームに打ち込む者、時期関係なくうるさい者、様々なクラスメイトがいる。
そんな中で、キヨハルは机に両足を乗せ、座っている椅子を傾けながら親指を忙しなく動かしている。
何度も推敲し、何度も消しては打ち直す。
文字のレイアウトを考え、投稿するタイミングを見計らう。最後にその言葉が見やすいように鉤括弧で囲い、キヨハルは送信をタップした。
「マツケンと2億4千万の瞳」
#新しいマツケンサンバ
RT:5 いいね:78
渾身のネタポストはいつもよりか反響があったものの、つぶやく前に抱いていた期待を遥かに下回る形で萎んだ。教科担任が入ってくるとキヨハルは号令をかける。こうして今日も二限休みが無為に費やされる。
授業中もキヨハルは次のネタポストの内容を考えるためだけに時間を費やす。同時並行で板書だけを書き写しているため、教師には彼が真面目に授業を受けているように見えるが、ノートの罫線が並ぶスペース以外は大喜利の回答で埋まっている。
キヨハルは優秀と称される頭脳を酷使させながら次のネタを考える。だが、執念を燃やすその行為は彼の中でマイブーム程度に過ぎない。あるいは高二病患者か。
放課後、キヨハルは職員室を訪ね、真っ先に顔を上げた副担任の女教師を連れて廊下に出た。
「ドイちゃんさ、うちの事務員でなんか目つき悪い職員知らない?」
「え、知らないよ?」
「そっか。まぁいいや」
「え、できることあるならカオリなんでもするよ?」
彼女とキヨハルは何度か性行為をしている。
何かと健気で便利な彼女との関係は今も継続中だ。
「いや、いいよ。ドイちゃん鈍臭いし」
「そんなことない! カオルはキヨハルの役に立ちたいから」
ドイは多少太っているため、顔は膨らんだ狸みたいだがそれなりに抱き心地が良い。また踏みつけると生温かく、うどんみたいでキヨハルはその感触を気に入っていた。
「そっか。わかったら連絡して」
ドイは苗字が嫌いなため自分のことをカオリと呼ぶ女だ。
「うん、する。すぐするね!」
ドイは有給休暇の申請書をとりに行くついでに事務室に入り早速、あからさまに周りを見渡す。すると不審がって彼女を見た顔の中に一際、痩せ細り不健康そうな顔をした女がいた。
「あんたさ、ちょっと」
ドイはその職員のネームタグを掴んで引っ張っていき、廊下に出す。
「あなたはなんです?」
「いや、カオリに聞くなし」
ドイは困惑するネズミを見窄らしい女だと思いながら電話をかけている。
3コール後、キヨハルが電話に出てドイの心は躍る。彼女は1週間と2日ぶりに褒められ、胸が弾む。
キヨハルの到着を待ちの間、ドイは彼のために今日はペパロニピザを取ろうと思い、そんな妄想をしているとキヨハルが駆けつけてきた。
「やあ、ドイちゃん」
「カオリね、捕まえたよ。ほら、この女でしょ?」
ドイの顔面は熱っている。
「うん。そうそう、コイツ」
ネズミはまだやらなくてはならない雑務がたくさんあった。彼女は常に定時出社、定時退勤を厳守しているため、上司から仕事のできるやつと認められてしまった。そのため他の職員より多く雑務を任されていることが多い。
「今日さ、いっしょに帰ろーよ」
「ああうんうん。」
彼女は一刻も早く仕事に戻りたかった。
だが目の前の女は仕切りにキヨハルへ視線を送り、ネズミが今描いている男はドイの熱を軽々しく振り払っている。
「要件がないなら戻りますが?」
ドイが睨み、キヨハルは皺が寄るネズミ眉間を眺めている。
「あ、ごめん。てかアンタの名前、本当にネズミっていうの?」
「それは今、どうでもいいですよね?」
とネズミが言うと、ドイが噴き出す。
「ねぇ、あんたさっきから態度がなってなくない?」
「態度とは、なんでしょう」
「調子乗ってんね、おばさん」
売られた喧嘩は買ってしまう性格のネズミと、とにかく自分以外の女とキヨハルが話しているところを見ていたくないドイは視線をぶつけ合う。
そこに割って入ることができる男は現状、キヨハルしかいない。
「まぁ、なんでもいいんだけど、僕のこと撮ってるでしょ?」
ネズミの表情が明らかに固まった。
向かいに立つドイは彼女の硬直を目撃した途端に敵意が殺意に変わった。キヨハルはそんな二人の女の胸中を眺めながら耳を穿っている。
「気づいてないと思ってたんだ。アンタもこの前のブスもさ、ほんと馬鹿だよね。それしか見えてないって感じ? ま、悪くない気はするけど、注意力なさすぎじゃん」
今朝出来上がったばかりのデッサンは今まで書いてきた中のどの絵よりも、形が良く、バランスも、陰影の配置も、雰囲気作りも良い。もしかしたら出すべき場所に出せば本当に画家になれるかもしれない、そんなふうに浮かれてしまうほど精緻に描くことができた。
早くこの男を意のままに歪ませたい。
苛立ちを含んだ創作意欲がネズミの中で何度も瞬き、炸裂する。
「ねぇ、ねぇ」
キヨハルがドイの頭頂部を叩く。
「なに? キヨハル」
「ドイちゃんまだいたの? もう帰っていいよ」
笑っているキヨハルの顎の先端をドイは見上げる。
「え? この後、家くるでしょ? カオリ今日早く上がるから一緒にピザ食べよ」
ドイは自分の胸を潔いほどキヨハルに押し当てる。
「嫌だよ。明日CM撮影だし、お前との食事が原因で仕事のクオリティ落としたくない」
「カオリだって明日仕事だよ」
「聞いてねぇよ」
ドイとキヨハルが口喧嘩している間もネズミは何かを呟いている。その声量は蟻の隊列の足音のように小さいが夥しい。
そんな彼女に気づかず、ドイは自分がどれだけ彼を愛しているかを訴えかけ、キヨハルは理解がある男を演じている。
思惑の方向性は三者三様。誰も交わらず、そんな息苦しさの中で最初に離脱したのはドイだった。
「ごめんね。なんかあのオバさん色々大変そうだね。更年期?」
ネズミは俯いている。乾いた唇は経を詠む様にぼそぼそと動く。彼女の意識は部屋の中に帰っていた。今朝の記憶を頼りに架空の線をキャンバスに足していく。部屋の扉は閉めたままだ。
「あのさ、おい」
前髪を掴まれて無理やり顔を上げさせられるが、ネズミはキヨハルの顔を観察しながら、さぁ、どこから歪ませようかと彼女は思案している。
「なぁ、地味女。人が話してる時は相手の顔を見るって教わってないのか?」
ネズミは口を半分開けたまま、恐れることも、怒ることもなく、凝視する。彼女は慎重に彼の綻びを探している。
惚けた顔で見られているキヨハルはまさか自分の顔面が向かいに立つ女の作品にされるとは思っていない。だがキヨハルは、以前、移動教室時に資料を抱えて走っていたネズミとぶつかり、散乱したコピー用紙の裏一面に自分の顔らしきものを見た。
知らない人間が自分の顔を描いている。
そのことに関して、キヨハルはさほど興味を示さない。それらしきことは幾度となくされてきているためもう慣れている。
だが、描かれている自分があまりにも微細で、美しかった。
それゆえ、キヨハルはその女の描く絵の虜になってしまった。
「ま、いいか。僕さ、お前にお願いがあるんだ」
「おねがいとは?」
柱に体を押さえつけられ、前髪を引っ張り上げながらキヨハルはネズミを見る。彼女の瞳はただ埋まっているだけで、そこには怯えも、熱もない。
裕福な家庭で生まれた彼は幼い頃から、両親に連れられさまざまな芸術に触れてきた。最先端から秘蔵の品まで望めば世界中にある大抵の美を間近で見ることができた。そうして培った審美眼を通してでも、彼女の落書きはそう呼称できないほどキヨハルの胸を打った。
「お前さ、僕の遺影描いてよ」
彼は期待していた。
断られるのを。
「もうすぐ死ぬ予定でも?」
キヨハルは毎日のトレーニングもスキンケアも怠らない。
それはどのトップモデルも目指していないと公言している彼が追い求めているのは、考える人や観音菩薩といった彫像の中にある計算され尽くした美しさだからだ。
「ないよ。でも生きていると僕も、お前も、みんなどんどん醜くなっていくだろ。最初からある程度のやつの価値観なんか僕には知る由もないけど、とにかく僕はさ、老いていくのが耐えられないんだ」
「だから遺影ですか」
「僕はもう熟れ始めてるんだ。わかるかなこの感覚。気持ちが悪いんだよ、たまらなく。だから今の僕をお前に僕のままで美しく描いて欲しいんだ。遺影ってそういうものだろ?」
「ええ、まあ。私はただあなたが描ければそれでいいです」
彼女の視線は瞳ではなく、ある一点を見つめている。
ネズミはなぜか悔しそうに見つめている。
今まで接してきた多くの人間のどのタイプにも分類できない新しい生き物が彼の前に立っている。キヨハルは初めて理解できない人間と出会った。
「あ、そう。なら、いいんだけど」
キヨハルはいつの間にか彼女の前髪から手を離し、一歩離れていた。
「僕はキヨハル。そういやお前の名前は?」
「は? さっき言ったでしょ」
「そうか。そうだっけ」
普通の高校生の様に頬をかきながら笑うキヨハルを見て、ネズミは案外、子供だなと思った。彼女はモチーフとしての興味を少し失いながら彼の元を去った。
それからキヨハルはドイの家へ向かった。渡された鍵で中に入るとドイはたらこパスタを貪っていた。彼女の両耳にはイヤホンで塞がれており失恋ソングが爆音で流れている。丸まった背中を眺めながらまるで家畜じゃんかと思いつつもキヨハルは後ろから抱きつく。
たらこパスタは餌にしては美味く、セックスをしている時、彼は天井に貼られたいくもの自分の顔に見られながら腰を振り続けた。目を瞑って集中し、そうして脱力した後、贅肉のベッドに倒れ込むと、ドイは嬉しそうに彼を抱きしめた。
「キヨハル大好き。キヨハルはカオリのものだから。ずっと。ね?」
「うん。僕はカオリちゃんのモノだね」
それからネズミは残業をして遅れを取り戻した。
校舎を出ると目の前の視界に混じっていた雨粒が次第に輪郭を帯び、それが雪だということに気づく。
彼女はコンビニでおでんを買った。セルフサービスで装ったスチレン容器の中には、はんぺんが5枚浮かんでいる。外国人労働者は特にリアクションを取ることなくレジ袋に入れている。
「わたし、ゆきみたのはじめてです」
「ええ、私も今年初めてです」
「きれいですね」
「そうですね」
2.
「あの、服脱いでみでください」
「は、なんでそうなるわけ? ここ学校だから」
「じゃあ、私の家ならいいですか?」
「いやだよ。ネズミの家くさそうだし」
朝方の空き教室で彼と彼女は静かに小競り合いを繰り広げていた。苛立ち混じりの協議の末、彼は上半身だけ裸になることで折り合いをつけた。
背中を冷気がくすぐり、くしゃみをすると三脚の上に立つカメラの奥からネズミが顔を出し覗き込む。正面、右、左、背面と床にあらかじめビニールテープで記しておいた位置に三脚を置き、4枚とも同じ高さで撮る。
「そういえば、ポーズとかいらないわけ? 僕、ほらモデルだし」
「いらないですよ。だって遺影でダブルピースなんてしないでしょ」
ちょっと面白かったことに対して、キヨハルは腹を立てた。
「じゃあ、変顔とか?」
「どうせ口にするならもっと笑えるやつお願いします」
「あのさ、面白いだろ! ほら、笑えよ」
「じゃあ、やってみたらどうです? 写真でも撮りましょうか」
「いいよ! キモ女! ねずみ女!」
ああ、やっぱりガキだなと、彼女はキヨハルに対し、さらにモチーフとしての興味を失いながらも、寄りの画と引きの画も撮り終える。それから彼女はデジタル一眼を三脚から外し、嗅ぎ回るようにさまざまな角度から写真を撮っていく。
接してみるとただの18歳の男子高校生だが、レンズ越しでみるとこうも美しいのかと驚嘆する。ほとんど息をするのも忘れ、ネズミは透き通っているかのように白い彼を撮り納めていく。
撮り終えた時、教室の中で吐いたネズミの息は白く、彼女の額にはわずかに汗が浮かんでいた。
「なに興奮してんの? きっしょ」
「そりゃあ、興奮しますよ。だってあなたは私が見てきた中で一番美しい生き物だから」
ネズミは事も無げにそう言いながらカメラケースにカメラをしまい、三脚を折りたたんでいく。
「あっそ。せいぜいがんばってよ」
キヨハルは制服のボタンを留めながら気になってネズミを見た。彼女はいつの間にか撤収準備を整えていて、立ち上がってぶつぶつと何かを呟いている。
キヨハルはそんなネズミに言った。
「そんなに真剣ならもっとちゃんとやればいいのに」
すると彼女の呟きが止まる。
「誰かの自慰に付き合っていられる程、人間は暇じゃないんですよ」
「じゃあ、俺はなんなんだよ」
「奇特な生き物でしょうか。いや、こんな私に関わっていることを鑑みれば、気の毒な生き物?」
純粋に思考し、悩み、答えを出した彼女を見て、キヨハルは笑ってしまった。遠慮も、忖度も、侮蔑も、憎悪もなく、こんなに純粋に笑ったのは初めてだと思いながらキヨハルは膝を叩いて笑っている。
「ネズミといると退屈しなくていいや」
「あ、そう。ならよかったです」
キヨハルの擬似的な遺影、つまり擬影の製作が始まった。
3.
カリカチュアとは、対象者の性格や特徴を際立たせて表現するために身体部位をあえて誇張して描き、あるいは他のモチーフを絵に組み込むことで完成する人物画のことである。用いられるのは、主に風刺画や漫画であり、児童向けアニメーションのキャラクター造形にも使われる事も多い。
ネズミはこのカリカチュアライズという手法を基本軸として人物画を描いているが、彼女の絵は誇張という域を逸脱している。
彼女の絵は歪んでいた。
また、多くのカリカチュアは風刺画や似顔絵に用いられることが多く、前者は誰かの思想を批判するための絵で、後者は相手の顔の中にある特徴的なパーツを誇張することで本物よりもそれらしく魅せるためのテクニックだ。どちらにも共通しているのは「〜のための絵」ということだ。つまり目的がある。
だが、ネズミは描くことに目的を持たない。あるいは、そう描くこと自体が彼女の目的だ。
ゆえに彼女はストレスを昇華していく過程を、自慰と称したのだ。
「ああもう! ぜんっっぜんたのしくない!」
ワンルームの壁に投げた鉛筆の芯の先端が衝突し、爆散する。
ネズミの住む賃貸マンションの前には国道が通る。いっそのこと外に飛び出し、叫びながら全力疾走してみようかと思うが、彼女は幼い頃から走る姿を飛べない鶏みたいだと従姉妹に言われたことがあるため、やめた。
何度消しゴムを投げては拾ったのだろう。
美しいものを歪ませる。
それだけが唯一の自己表現だと思っているネズミは今、自分がなぜ描いているのか、この線はどこに向かっているのか、この輪郭は何を主張しているのか、全てがわからないまま、写真を握りしめ、ただ我武者羅に手を動かし続けるが、必ず止まる。度に消しゴムはスーパーボールになる。
美しいものを美しいまま描くことは彼女にとって苦痛だった。
キヨハルから擬影の製作を頼まれたのは去年の12月の終わりで、構図決めや、エスキースまでならば年明けを待たずに終わるだろうと、ネズミは頭の中でスケジュールを切っていた。だが、一月が後半に差し掛かろうとも、彼女のビジョンは未だ、スケッチブックから出て行かない。
「あー、できないできない。だいたい、なんで私はこんなクソ真面目に考えてるんだよ。こんなのただの遊びじゃん。テキトーにさ、ぱぱっと描きゃいいじゃん。アイツ別に面白いやつじゃないし、ま、顔は綺麗だけど、ああもう歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたい。歪ませたいのに!」
コンビニでいつも顔を突き合わせる店員にレンジで温めてもらったおでんは玄関に放置しているためすっかり温度と鮮度を失っている。
「あーもうだめ。断ろう! 無理無理! だってそのまま描くなんて性に合わないし!」
翌朝、ネズミは鳴り出す前に目覚ましを止め、さっさと出勤した。
朝方、彼を探したがどこにもいなく、昼休憩時に中庭でカロリーバーを齧っていると取り巻きから抜けてきたキヨハルが彼女の隣に座った。
「顔が灰色だけどネズミさん」
「そんなことはないです」
「そういえばどうですか先生、御進捗の方は」
「いちいち聞かないでください」
「あっそ。ダメなら降りてもいいんだけど?」
家に帰ってきたあと、ネズミはすぐに買ってきたおでんを食べた。よく染み込んだはんぺんは熱すぎて一旦、だし汁の中に戻したりしながら咀嚼する。
「どうして『降りたい』って、言えないんだよ!」
スケッチブックに鉛筆を突き立てたまま、ネズミは約10分間、全く動かず思考も止まっていた。部屋にはスキャンして何枚も複製し、引き千切ってできたキヨハルの顔の切れ端が床を埋めている。
「なんで描けないのよ」
ベッドに放り投げたスマートフォンが振動する。
薄暗い部屋の奥だけが白く光る。
ネズミは床を踏み鳴らしながら歩き、耳に当てた。
「あんたさ、息巻いてた割には大したことないね」
「は?」
「ネズミさ、全然進んでないでしょ?」
「そんなことはありません」
「変な意地を張る暇あるなら、早く描けよ」
深夜3時過ぎ、キヨハルは肉体環境の維持のために普段、この時間は寝ている。さらに彼は電話を取ることはあるが電話をかけることなど滅多にない。それはスランプに陥ったネズミと同じように、キヨハルも焦っていたからだ。
キヨハルは多くの美術品に触れていくうちにモデル業に力を入れるようになった。
彼はスタジオから家に帰ると鏡の前で毎日、ポーズ練習を欠かさず行った。腕の角度も股の開き具合も、目線も、全てに神経を研ぎ澄ませ、また新しいポージングは常に考えるようにした。生活の中のふとした姿勢の変化や、体重移動の際、使えそうなポーズがあればそれを起点としてバリエーションを増やした。
そうしていくうちにストロボが発光する度、違うポージングができるようになり、モデルとしての技量は飛躍的に伸び、海外のプロモーター達を魅了できる肉体を手に入れた彼はマネージャーとともにフランスへ渡った。
キヨハルといえど上には上がいた。
目指すかは別として、自分よりも美しい人間がいるのをキヨハルは芸能生活の中で思い知っていた。海外に出ていけばその上位存在の人口は増える。
そこでキヨハルは脚光を浴びた。
どのモデルよりもまっすぐ歩き、服を着たマネキンとしての役目に徹したのが多くのプロデューサーに評価されたのだ。
キヨハルは大抵のことは二、三回行えば要領をつかんでしまうので、スポーツで勝てども、高校の成績が良くとも、なんの感情も湧かなかった。それは当然だと思っているからだ。
だが、フランスでのショーは彼にとって当然ではなく、挑戦だった。
故に、キヨハルはコレクションが終わった後、ホテルの個室で泣いた。
多くの女子生徒に神と崇められる顔面を、
震わせ、歪ませ、鼻水を垂らしながら彼は涙を流した。
何度も擦り、拭った顔を鏡越しに見たキヨハルはそれでも自分は美しいと思い、体を抱きしめながらまた涙した。
それは初めて自分が生きている理由を手にした気がしたからだ。
一夜明け、瞼を晴らすキヨハルを見て、マネージャーは息を呑んだ。
まず心配したのは襲撃だ。
期間中、会場付近のホテルには各界の著名人が集まる。そのため警備は強化されているが、夜襲にでもあったのかと動揺したのだ。
だが、キヨハルは不自然なほど柔和に微笑んで「少し、散歩がしたいな」と誘った。
マネージャーはコレクションが終われば自分といる理由も無くなるから別行動になるだろうと思い、事前に日帰りマイツアープランを立てていたが、仕方なく彼はそのプランにキヨハルを加えた。
キヨハルはマネージャーの彼に対し、どうして食べ歩きばかりなんだと怒り、教養のない彼を連れて美術館へ無理やり向かわせた。
初めてハンバーグを目にした少年のように、マネージャーはどの作品を見ても頭ごなしに褒めた。語彙はもちろん皆無で、感想も退屈だった。
結局、館内の売店で買ったサンドウィッチを見つけた時一番目を輝かせた彼を見て、呆れているとキヨハルの視界に彫像が目に入った。それは展示されていた作品ではなく、庭園にある噴水の装飾を盛り上げるために作られた彫像だ。
その彫像をなんとなく眺めていた時、彼の中に突然憂いがよぎった。
昨日が人生の最高到達点だったのではないか。
その時、彼の頭に初めて死が浮かんだ。
帰国して彼はいつも通りモデル業をこなしながら学校へ通う。右を見ても、左を見ても、皆同じく退屈な景色で、教室で呼吸をすると腐っていくような感覚があった。
その間にも細胞は絶えず生まれ変わり、繰り返すたびに肉体は衰退へ近づいていく。そんな当たり前が、キヨハルにとっては逃げ出したいほどの恐怖だった。
「私は少し仮眠を取ったら、また製作に戻りますのでもう切ってもいいですか?」
「なぁ、ネズミ、」
「なんです。切りますよ」
「うん。だからネズミ頼むよ。早く僕を、今の僕のまま遺してくれ」
「言われなくともわかってますよ」
「そしたら明日なんて、どうでもよくなる」
散乱したコピー用紙を集めながら彼はずっと描かれた自分と目を合わせ続けているような気がして、指先がうまく動かずプリントが拾えなかった。
その時から彼は自分を遺すのは彼女しかいないと決めていた。
カラオケボックスの個室トイレの便座に座り、キヨハルは過去を振り返っていた。どうでもの先の本音をネズミが聞き出す前にキヨハルは通話を切る。
キヨハルはそれから用も足していないにも関わらず、手を洗い、個室トイレの扉を開ける。同じフロアの端にある大部屋では今日も退屈なクラスメイトが流行りの歌で盛り上がっている。
「他の階にも男子トイレあるだろ。なんでここにきたんだよ」
「あのさ、」
「なに」
ドアを開けるとキヨハルの目の前にはエニシが立っていた。
エニシはなんの躊躇もなく、右手に持っていたマイクを力のままにキヨハルの顔面に振り下ろした。
エニシは自分よりも身長が低く、胸板も薄いキヨハルに罵り続けられていた。その度、彼は胸に劣情を溜め込んだ。エニシはやろうと思えば、いつでもキヨハルを襲えた。それでも逆らわなかったのは彼という存在に緊張し、憧れていたからで、暴力だけでは彼の全ては手に入らないと思っていたからだ。
「ねぇ、キヨ。なんで最近、遊んでくれないんだよ」
だが、限界だった。
どうしても今すぐ、彼を振り向かせたくて、畏怖の対象として自分を植え付けたくて、エニシはキヨハルを殴打し続ける。
エニシの衝動は、性欲は、一撃で終わるはずもなく、腹にまた一発入る。寺の鐘をつくように重い拳が一つ、また一つとキヨハルの肉体を打つ。タートルネックを脱がすとエニシは彼の胸に齧り付く。痛みに短くキヨハルが喘ぐとエニシは一旦、顔引く。エニシの前歯の先から引いた糸がキヨハルの胸につながっている。そしてまた吸い付く。
「キヨ。好きだよ」
再び確認するようにエニシが見上げ、キヨハルが見下ろす。
彼と彼は幼馴染だった。
「今からもっとたくさん殴ってやるからな」
幼い頃からエニシは一度こうしてみたいと思っていた。
キヨハルの瞼はすでに左がわずかに開くだけで右は完全に反応しない。鼻の骨が折れそこから垂れたゲルみたいな血が口の中に入る。鼻の奥には血の澱みが溜まっている。殴られるたびに、頬骨が軋み、頭痛がし、口の端からもだらだらと血が流れる。
痺れているのか、痛いのかも判別できないほど意識が混濁としていき、エニシはただ黙ってキヨハルの顔面を執拗に殴り続ける。
自分の存在意義が意図せぬタイミングで、呼んでもいない人間によって損なわれていく。彼の中で全てが崩壊していく。自殺計画が赤く塗りつぶされていく。
もうどうでもいいかと暴力に搾取に身を委ねた時、キヨハルは強制的に瞼を開かされた。
口腔内に他人の、エニシの、生ぬるい息が吹き込まれる。強烈な嗚咽が痺れと共に身体を競り上がり、胃の内容物が逆流する。
エニシはキヨハルの血だらけの唇に思い切り吸い付いていた。
キヨハルにとってそれはファーストキスだった。
4.
ネズミの部屋の前には一人の女が立っている。前髪が大きく乱れ、サテン生地のパジャマの色はシャンパンゴールドで、その上から分厚いダウンを羽織る。
ドイはネズミの部屋の扉横にあるチャイムをさっきからずっと何度も押し続けている。まるでアラームのように部屋中にチャイムの音が鳴り響き、ネズミは明け方5時過ぎに叩き起こされた。やっと眠りについたところだった。
「開けろクソ女! いるのはわかってんだよ!」
ドイは発狂しながらネズミの部屋の扉を殴り続け、ノブを揺らし続ける。
ネズミはキッチンから持ってきた包丁を両手でしっかり握ってとにかく部屋の扉の前で震えながら構えていた。両膝が震え、切先が大きくぶれ続けている。生まれたばかりの子鹿のように立ちながらネズミは叫ぶ。
「用件はなんです!」
「お前、キヨハルをどこにやった!」
ネズミは彼女の怒号に震えながらも、どうしてこの人はキヨハルさんのことを自分の所有物のように言うんだろうと思った。
絵のモデルとしてしか彼に興味がないネズミは個人的な接触をしていない。そのため通話の切れたキヨハルがその後どこへ行こうとも、何をしてようともわからないのだ。
「知らないです!」
ドイがキヨハルの異変に気づいたのは、泣き喚いて無理やり登録させたGPSアプリがいつもいくカラオケ店にマークが定まったまま、彼の就寝時間である午後11時を過ぎても一向に動かなかったからだ。不審に思ったドイは10回以上電話をかけた。だが繋がらず、居ても立っても居られないドイはダウンを羽織って走った。
すると、たどり着いたカラオケ店の駐車場に警察車両を一台見つけた。警官二人組が受付で店員と何かを話している。確実にキヨハルの身に何かがあったのだとドイは思った。
ドイはキヨハルと血縁関係があるわけでも、婚約者でもない。ただのセックスフレンドだ。
そんな他人に警官が事情をことこまあに説明してくれるはずもなく、ドイは再び走るしかなかった。
まず向かったのはキヨハルの家だ。電気は消えていて、車も全てなかった。ドイは自宅に戻り車を出し、今まで自分が確認してきた人間で所在地がわかるものを手当たり次第に回った。そして、今、彼女はネズミの部屋の前にいた。
「開けろ!」
「いやです!」
「開けないと、あんたが空き教室でキヨハルにしてたこと、全部バラすぞ!」
「それもいやです!」
「じゃあ協力しろ! 地味女!」
「殺さないなら!」
「するわけないだろ! バカ!」
右手で包丁の柄をしっかりと握ったまま、ネズミは恐る恐る左手でロックを解除してドアを開く。するとドイの顔は流した涙でぐちゃぐちゃで、化粧しないと私より不細工だなとネズミは思った。
「そういうあんたはカオリを殺す気なの?」
ネズミはまだ包丁を握っている。目が合い咄嗟に後ろに隠すがもう遅い。
「あっ、ごめんなさい。つい」
「ついって?」
ネズミは事務室長の留守電に「風邪をひきました。休みます」とだけメッセージを残し、マンション前でハザードランプを点滅させている軽ワゴンに乗り込んだ。
ドアを閉めると吐いてしまいそうなほど甘い匂いが充満し、ネズミはすぐに窓を開け呼吸しながら、この車に毎回乗り込んでいるとしたらキヨハルさんはちょっと可哀想だなと思った。
当たり前だが二人に会話はない。
まるでそういう仕事かのように二人は淡々とキヨハルの不在確認をする作業を繰り返していく。
事情を説明し、聞き取りするのは必ずドイだった。
ネズミは最初、手分けして捜索するのかと思っていたが、外で申し訳なさそうに何度も頭を下げるドイの丸い背中をネズミは夕方になっても車内で眺めている。また俯いたままドイが小走りで車内に戻ってくる。
「なによ」
「あの、私いらないですよね?」
「いるの」
「なぜ?」
「なんでもよ!」
捜索はなおも難航した。
日は沈み、ネズミは飽き、ドイも半ば諦め始めていた。ドイがエクセルでまとめた確認リストはついに最後の一件のみとなる。
彼女の名前はアイコ。
キヨハルのふたつ年下の高校一年生で、アイコはキヨハルに片想いを抱いていた。クラス内ではいじめの的にされており、後に彼女は傷害事件を起こしている。精神鑑定を踏まえてた裁判の結果、彼女には執行猶予がつき、保護観察処分となった。
アイコの家は住宅展示場で見るような一軒家で、同行したネズミがチャイムを押すと鍋つかみ用のグローブをつけたままの小綺麗な母親が出てきた。開けた扉の奥からクリームシチューの匂いがする。
母親が階段の手すりに手を置きながら、2階に向かって彼女を呼ぶ。するとすぐにアイコが降りてくる。
ショートカットで目は細い。
五月人形のようなアイコは玄関先に立ち、愛嬌のある声で尋ねる。
「先輩がどうかされたんですか?」
精神鑑定という言葉を目にしたとき、彼女たちはもっと、会話すらできない状態だろうと思ったが、アイコの平然さに、明るさに、僅かばかりの違和感を抱きつつもドイがキヨハルの行方を知らないかと尋ねる。
アイコが首を横にふると前髪が小さな額の上でわずかに揺れた。
「ところで、どこを回られたんです?」
躊躇ったが、ドイは藁をも掴む思いで情報を開示し、すると、なるほど、と興味深げにアイコはリストを覗いていた。
「陸橋の下は行かれました?」
「り? え、なにそれ」
「通学路にある陸橋ですよ。上に線路が通っていて、小川が流れていて、」
「どうして、そこなんですか?」
ネズミが尋ねる。
「そこに先輩がいるかどうかなんて私にはわかりません。ですが、私はあの場所で髪を引っ張り回されたり、執拗に顔を殴られたり、服を脱がされて写真を撮られたりしたんです。うちの高校で誰かが酷い目に遭っているとしたら、そこかもしれません」
アイコの瞳は石が埋まっているのかと見紛うほどなんの光も発さない。
彼女はその瞳の無機質さを保ったまま、小さな唇の上に人差し指を立て、「陸橋で私が暴行を受けていたことはお母さんに内緒ですよ」と微笑んだ。
アイコに見送られ軽ワゴンに乗り込むともう夜になっていた。
車内の緊張と甘ったるい香水の匂いがネズミの体の中で混じる。
たまらず開けた窓から入る外の空気を吸っているうちに陸橋が見えてくる。
スマホのライトで足元を照らしながら言われた通りに陸橋の下へ向かうと、確かに誰かが蹲っていた。
「キヨハルっ・・・!」
ドイは転びながらもキヨハルの元へ駆け寄る。
後ろで小走りで追いついたネズミは足を止め、キヨハルを見下ろした。
ライトで照らすとその白より蒼白した脚がまるで全く別の生き物のようで、青黒い華に覆われている肌は鱗のようで、場違いだと分かりつつもネズミは創作意欲に駆られていた。
ネズミの中でその時、突破した感覚があった。
インスピレーションが展開していく。
どうしてこんな時に、私は、こんな。
「あんた、泣くことあるんだ」
キヨハルの両肩に爪が食い込んでいることに気付いていないドイは振り返り、後ろで啜り泣くネズミを見た。
まるで、逸れていた子供が母親に再会したかのように、幼気な姿をキヨハルも見つめている。
「ごめんなさい。本当に。でもありがとう」
もう2月だった。
ひび割れ、腫れ上がった青紫色の唇がわずかに釣り上がった。
キヨハルの顔はもう元には戻らなかった。
5.
3月の初頭、いつも通り今日も陽が昇る。
乾いたキャンバスにネズミが右足を乗せると、イーゼルが少し後ろへ傾く。
純度の濃い黒の背景の前で佇むのは、
病的に白く透き通った肌を持つ美しい少年の遺影だ。
構図と方向性が決まったネズミは早く、何も進んでいなかった彼女は着想得てから僅か半月で要望通りどこも歪ませず、美しいまま、キヨハルを描ききった。
事務仕事は学校が卒業シーズンへ移行するとともに雑務が山積し、ネズミも例外なく仕事に追われた。それでもネズミは睡眠を限界まで削り、描ききった。そうできたのは混じり気なく描くという行為を受け入れ、そして昇華させてみたかったからだ。
発見後すぐにキヨハルは外科治療を施された。だが隙がなかった彼の顔面には綻びが生まれてしまった。
術後、退院したキヨハルは芸能活動を辞め、その時トップモデルとしての彼は死んだ。それから普通の受験生となった彼はそれなりに勉強し、慶應大学への進学を決めた。
通りかかる誰もが腫れ物に触るようにキヨハルを見るのだろうと、気の毒に思った彼女は自分だけは平然としていようと誓ったが、彼は術後の顔を隠すことなく登校した。ドイとの肉体関係も相変わらず続いているらしく、なぜか彼は今も周りから持て囃されている。
迎えた卒業式の翌日。
ネズミは入居してから始めて隅から隅まで掃除し、展示会場のようにした部屋にキヨハルを招く。
「これが僕か」
「はい」
白無垢の壁に飾られているのはM20号。
彼を描こうと考えた時から、ネズミはキャンバスのサイズをモナリザと同じにしようと決めていた。
「ネズミの家って賃貸でしょ?」
「はい。穴はなんとか埋められますので」
「へぇ」
背景が黒の影響で、より肌の白が際立つ。
少し浮き上がっているのではと思えてしまうほど立体感があり、光と影の位置、顔面のパーツのバランス、絵全体の比率。目に映る全てが計算された美しさの中にある。間違いなくこの人物画はキヨハルの待ち望んでいた代物だ。
「綺麗だね」
「ええ。綺麗なまま描きましたので」
「そっか」
彼が称した通り、紛れもなくネズミの中でも、目の前の人物画は最高傑作だった。仕上げている途中、濁流のように欲望が押し寄せ、苛まれたが、彼女は奥歯を食いしばり筆を動かした。
「メルカリで売ったらいくらだろうね」
だが、その割には描かれた当人の反応は薄い。
「あの、なにか不満でも?」
「いや、完璧だよ。完璧な僕だ」
「そうですか」
自分にとって渾身の一作でも、受け手に渡った時その作品の価値は渡った者の感性に委ねられる。そうでない場合もあるが、彼女の絵は所詮、こんなものなのだろうか。
風に揺れているレースカーテンを見て、足が寒いと感じ、ネズミが部屋の窓を閉めようとした時、俯いた先に水滴を見つけた。その滴はキヨハルの足元にあり、彼女は顔を上げた。
「よかったのかもな、これで」
術後の顔を覆って涙を流すキヨハルの姿は美という執着から解放されたようにも、縋り付いているようにも見える。
「僕さ、ずっと自分の顔を見るのが怖かったんだ」
「どうしてです?」
「美しいからだよ。美しいは目立つし、その割には脆い。だから保ち続けるってのは並大抵のことじゃないんだ。そういうことを鏡を見る度に自覚するんだ。こんなクズだけど美しさに対しては、誠実でいたいと思って生きてきたんだよ」
嗚咽と共に吹き出す。
どこからともなくというやつだ。
「僕はたくさん奪ってきた。でも奪われてきた。なぁ、ネズミ。これからもこういうの続いていくのか?」
「はい。そして私も奪った一人。だからせめて、奪わせてあげます」
彼女は画材道具の箱からカッターナイフを手に取り、再び彼の前に立つ。
「きっとコレをする権利は、すべきなのは、キヨハルさんです」
ずっと絵ばかりと目を合わせていたキヨハルがネズミを見る。彼は手渡されたカッターナイフの柄を握る。すべきと言った割にはネズミの手に力が入っている。
「なにがしたい」
「切り刻むんです。この顔を。過去を」
「本当はネズミがやりたいんだろ?」
彼女は首を横に振り、やっと力を緩めた。
カッターナイフがキヨハルの手に渡る。
「まだ、この絵のタイトル決まっていないんです。『遺影』でもいいのですが、なんかしっくりこなくて、だからこの絵はまだ完成していない。没の絵なんで処理はやらせてあげます」
「随分と上から目線だな」
キヨハルは言い切ると同時に絵に飛びついた。
そして無邪気に、何も考えずに、カッターナイフの先を突き立て、縦に横に裂く。描かれた自らの顔面を、幾度となく撮られ、晒され、他人の玩具に、嫉妬の対象にされ続けてきた顔面をーーー見逃し続けてきた今までの搾取を切り刻んでいく。
「なぁ、ネズミ」
「随分と楽しそうですね」
「どうして僕らはこんなにも傲慢なのかな」
「さあ。ですが、あなたは気にせず好きに生きたらいいと思います」
ネズミは躍動し続けるキヨハルの背中を描きたくなり、最近買い足した正方形のキャンバスを手に取り、イーゼルに立てかけた。キヨハルは制服を脱ぎ捨て、自らの擬影を台無しにしていく。
「芸人にでもなろうかな!」
「そのセンスで?」
「このセンスで!」
「私は美大に通います」
「春から?」
「春から」
スケッチブックの上で黒鉛が踊る。エスキースに描かれたキヨハルの背中は斑模様の鱗に覆われていた。背中の惨状の解釈は彼女なりのユーモアだった。
process.
今回は自作された詩を読んで「その中に描かれている『彼』に出逢いたい」というリクエストでした。(リンクはreference.に貼付)
この詩ざっくりと解説すると、とある女性が想い人を見つめている視点で描かれており、すごいなと思ったのは想い人である彼は成長していくのに対し、想い焦がれる彼女(視点、あるいは主人公)は、口調や描写から察するにどんどんと若返っている。この順光と逆光の交差を一つの詩に入れ込むというのはテクニカルだなぁと思いました。
ですが、それとは別に僕はこう思いました。
「この主人公、だいぶ傲慢だな」と。
よくできているからこそ、一面的な視点に嫌悪感があり、読めば読むほど彼の気持ちはどんなものだったのだろうと、そればかりが気がかりになり、その時なんとなく、他人に心を無自覚に搾取されている主人公が存在証明していくような物語が浮かびました。
なので、この詩のアンチテーゼとして、僕はこの物語を描きました。
気分を害されたのならば、文面上のみとはなりますが謝ります。
ごめんなさい。
でも、書きたかったんで書きました。いえい。
person.
reference.
vs
promotion.
『あなたのためだけに物語書きます』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
