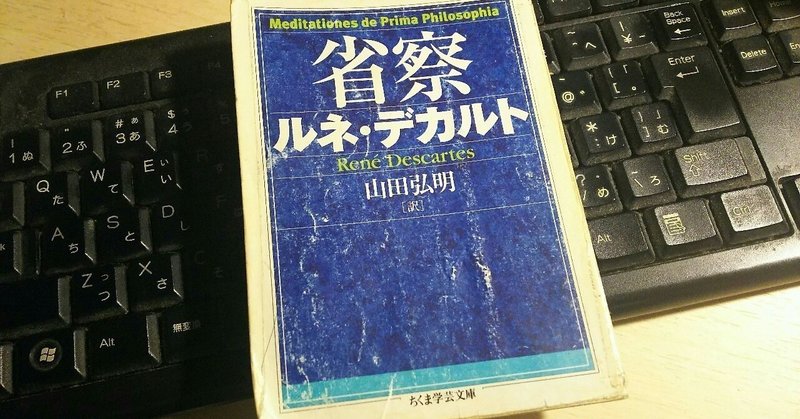
デカルト『省察』「第一省察」要点・解説
デカルトは「近代哲学の祖」?
→デカルトは「心身二元論」によって世界を物理的な対象として見出し、それ以外のものを切り捨てた「近代の悪しき根源」と悪く言われることがしばしば。しかし、その思索そのものをフェアに評価するなら、彼は「個人が真に自由に独立にものを考える」ということ自体を可能にし、そのことによって、人間理解、世界解釈に革命を起こした偉大な思想家であったと言える。
なぜ、デカルトは一切を疑ったのか?
→タレスも「万物の根源」を自らの観察と理性的洞察によって思考した、という点では、「思考とは何か」という根本問題を提起した偉大な哲学者であったと言える。しかし、タレスを含め、古代の哲学者は、あらかじめ自らが自明視している先入観を省察し、それを根こそぎにすることによって哲学を始めたわけではなかった。ところで、デカルトは、科学的な世界観が芽吹き始めていた当時において、一切の権威から独立に思考することを可能にする必要に迫られていた。そのためには、自らが理由なく受け入れてきた常識のすべてを洗い直し、一切を根本から疑うという企てがどうしても必要だった。理由なく受け入れてきた一切を疑うことが可能であって初めて、「自ら自身が思考する」という自由を獲得できるはずだから。このことを企てたのが、彼の主著『省察』であり、「疑いを差し挟みうるものについて」と題された「第一省察」。しかし、「すべてを疑う」という大胆な企ては如何にして可能となるのでだろうか?
如何にして「すべてを疑う」のか?
「すべてを疑う」といっても、あれやこれやのことについて一々疑うのではきりがない。私たちの信念がその上に成り立つ土台をひっくりかえせば、その上にあるものは皆一々疑わずとも疑わしい、と言える。そして、少しでも疑わしいなら、それは確たる根拠によって自ら受け入れた意見ではなく、思考を可能にする拠り所にならないので、デカルトからすれば「疑わしきは偽」である。では、その「土台」とは何か。それは感覚。私たちは「それは見た、聴いた」という感覚への信頼を拠り所に、自らの世界観を築き上げ、日々生きている。この土台が確かなのか、それが「第一省察」では人類史上比類ない仕方で本格的に問われている。
私たちが懲りずに感覚を信じる理由
→「感覚は時折は欺く」ので、感覚は信用できない、とデカルトは「第一省察」で述べている。なるほど、確かに感覚が如何に強力な確かさを印象付けるとしても、たとえば明日、いきなり太陽が西から登ったりすれば、これまで私たちが積み上げてきた世界観は崩れ去ってしまうだろう。あるいは、自分では確かな人生を歩んでいると思い込んでいても、いきなり不幸に見舞われると突然奇妙奇天烈な占い師の祈祷を信じたりするかもしれない。凡人のみならず、無敵のアレクサンダー大王でもこれについては同じことである。しかし、それでも手痛い思いをしながら感覚を信じて生きていくのが私たちの偽らざるありのままの姿というもの。感覚への信頼が時折は揺らぐとは言っても、同じく感覚から汲まれるものでも、それについては全く誤る心配はないと思えるものもあるからである。この情景をデカルトは狂人を引き合いに出しつつ、「この身体全体が私のものであり、私は今ここにいる、そんなことまで疑えば、私は心身喪失者とも思われかねない」と述べている。
夢と現実が無差別⁉
→そう、私たちは薄々感覚が疑わしいと思っても、結局は感覚を信じて生きているし、プライドというものがあって、心身喪失者と思われるほどまでに自らを貶めることはできない。しかし、こうした確信や自己認識には果たして根拠があるのか? ここでデカルトは夢の中の出来事を想起する。夢の中では心身喪失者よりももっと不可解なことを真実と思い込むことが現実にある。そして、その確信は今、この現実を現実と思っている確信とどれほど区別できるだろうか? いくら自明な常識と思っていても、状況によってはその確信だけが根拠ではまさに狂気と紙一重となることはこの議論で充分に示唆されている。そして、このことを真摯に反省するなら感覚を正しいと思う根拠には確たるものが何もないことがはっきりとわかり、デカルトの言葉を借りるなら「私は今夢を見ている」と本気で思いかねないほど。
「私は今夢を見ているとしよう!」
→デカルトは、あたかも舞台役者のように「それならこの現実は夢だとしよう」と提案。しかし、この現実が仮に夢だったとしても、それでも夢を構成している「一般的なもの」は信と見做されていると指摘。ここで、デカルトは「比類なき独創を誇る画家」を引き合いに出しているが、なるほど、画家は新奇な怪物や幻想的な情景を創り出し、現実を相対化しながら自らの独創を誇る。しかし、そのこの現実を一夜の夢と喝破しつつ、比類ない独創を自負する画家といえども、「色」や「形」という枠組みまでを創造することはできない。すると、こうした単純で一般的なものしか扱わない、数学者、幾何学者は何か真実の本性に関わっており、それゆえ欺かれてはいない、と言えるのではないか?
数論や幾何学、論理学の規則も疑わしくなる驚くべき理由とは?
→「2+3=5」。それを別用に考えることは確かにできない。デカルトも真面目に「2+3=8」であり得る可能について検討しているわけでは決してない。しかし、「だからといって、そこを出発点に世界を解釈してよいとか、それが真理だと言いえるわけではないのではないか?」、「私たちが「2+3=5」としてしか思考できないとしても、それを根拠にそれを真であると定めていいのだろうか?」 これがデカルトの懐疑の一つの要点。なぜならば、「2+3=5」は確かにそれ以外に思考しようがないというだけで、決して私がそれを真と定めたわけではないから。そうだとしたら、私には、それを真と定める権限がそもそもないはず。もしも、そういう事柄について真と偽を定める権限がある人がいたとすれば、それは神以外にはあり得ない。したがって、デカルトは次のように問う。「神がもしも欺いていたら、どうするのか?」と。
唯物論者でも、懐疑は免れ得ない⁉
→神が存在するとしても、その存在の何たるか、神が存在するのかしないのかについてさえ、私は確たることが何も言えない。私が無神論者なら、猶更のこと、これについては何も言えずに、それゆえ、それを無根拠に真と見做して、ますます「常に欺かれている」という状況が確からしくなってしまう。結局、「これまで真と見做してきたもののうち、確実な意見は何もない」。
「すべてを疑う」なんてやっぱり不可能? それとも可能?
→こうして、一通り文字通り「すべて」について一通り疑ったことになるはずだが、デカルトはそれだけでは本当にすべてを疑ったとはまだ言えない、と言う。というのも、「これらを疑うよりは真と見做すほうが理に適っていると見做す習慣」がある限り、私は物事を結局正しく認識できる状態には至らないから、と。せっかくこれまで真と見做してきたすべてについて、有力な懐疑理由を手にしたとしても、これまで真と見做してきた習慣ゆえに、「疑うよりは信じたほうがいい」と思ってしまったら、懐疑の企ては実質的には可能ではなく、「真に自律的に思考する、私自身において真理を探究する」という企て自体が不可能になってしまう。そこでデカルトは、自己認識自体を全く逆転させることで、「偽に同意しない自由」と確保しようとする。つまり、私は何かを真だと思うたびに欺かれるような本性だと仮定する。デカルト的に表現すれば、狡知に長けた悪霊が常に私を欺くように設え、その結果実際に常に欺かれるような存在として自己認識を改める。このような自己認識に踏みとどまる限りは「仮に何か真なるものを認識できなくても、少なくても偽には同意しない」という自由は確保できる。こうして、デカルトは「理性的である」ということ、「真にものを考える」という状態を準備したと考えた。
ありがとうございます。メッセージを添えられている場合には必ずお返事致しますが、メッセージのない場合は差支えあるかと思うので返信は控えます。ご了承下さい。
