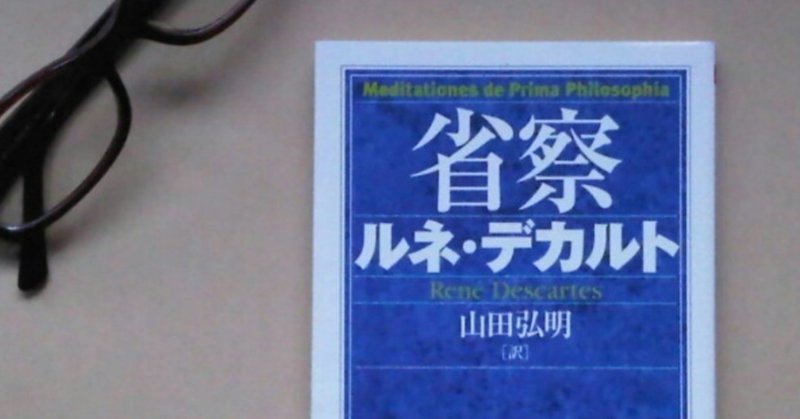
デカルト『省察』「第二省察」要点・解説
デカルトの求めるもの、それは「アルキメデスの点」
→「第二省察」は「第一省察」の懐疑の辿り直しによってはじめられる。そこでまず示されているのは、デカルトが求めているのが「アルキメデスの点」、すなわち、一切の思考の土台であり、出発点だということである。「第一省察」の懐疑の要点は次の点にある。それは、私が今目覚めた目で見ているということについて、あるいは、「2+3=5」といった単純で容易な判断でも、それを別用に考えられないからといってそれが真理であるとか、思考の出発点にしてよいということにはならない、ということである。私は「2+3=5」としてしか思考できないが、「2+3=5」であるということは私が決めたことではない、私はそのことの創始者、創造者ではないからである。すなわち、ここでデカルトは私は「2+3=5」としか思考できないが、だからといってこのことが確実だとか、思考の出発点としてよいのか?ということを問題としている。つまり、これは「2+3=5」が「2+3=8」である可能性を疑っている問いではなく、「2+3=5」の倫理的な意味を問題にした問いである、といえる。このことは「確実な認識とは何か」という理論的なレベルの関心も究極的には倫理的な問題に応えなければならないことを意味している。デカルトは単に知識の形式的な確実性を問題としていない。倫理的なレヴェルにおいても確実な思考の絶対的な出発点(アルキメデスの点)が探求されている。かくして、「私を超えた超越者が私を力の限り悪意で欺くとしたとき、それでも疑い得ない何かが果たして残るのか」、これがデカルトの問いである。逆を言えば、自分を超える創造の深淵を前にして、自らの知性の限界を超えた問いの中で、それでも確実をみなさざるを得ないものは、真理と見做さなければならない、とデカルトは主張しているのだ。なるほど普通、私が認識したからといって、その通り実在しているとは限らない。実際、創造者による欺瞞という設定はこの認識と実在の不一致、つまり、認識が実在を捉えると確信できる根拠を根こそぎにする。つまり、認識と実在の間に必然的な絆を見出すことができないものはすべて「欺く神の懐疑」と「欺瞞者の想定」によって疑われ得る。これは知性が創造の神秘、知性の限界を超えた問いの前に立つ、ということである。しかし、そうであるなら、それゆえ、その懐疑においても確実と見做される認識は「認識したことがその通り実在する」のでなければならない。認識が必然的に実在でなければならない。すなわち、この必然性は、単に認識の上での必然性ではない。つまり、「私がそう思わざるを得ないだけ」にすぎないのではない。「創造者が欺いていようとも私にとって疑い得ない」というのは、「実際に私が思う通りに事柄が在る、創造されている」ということと同じだからである。「創造者の欺瞞」という一見荒唐無稽な設定は、すなわち、この懐疑でも尚且つ「疑い得ない命題」が仮にあるとすれば、その命題に関しては認識が単なる仮説の域を超えて、そのまま実在になる。
私は存在しない?「存在すると思っている」だけ?
→デカルトが求めているものが「アルキメデスの点」なのだとすれば、もはや、疑えい得ないものは何もなさそうだ。たとえば、「私は存在する」。このことは誰もが知っている。敢えて、このことを疑う人はいないだろう。しかし、デカルトは「第二省察」でこのことを疑っている。たとえば、私は一切を「第一省察」においてデカルトが為したようにすべてを有力な懐疑理由に基づいて疑った。それならば、これらの懐疑理由を案出したのが私ならば、私は少なくても何ものかではあるだろう。だが、これらの考えもまた、巧緻な欺瞞者の欺き(現代的にはスーパーコンピューター、ロボットによる操作でもいい)だとしたら、つまり、「私は自分で考えていると思っているけれども、実はそう思い込んで騙されているだけ」なのだとしたら、私もまた無であろう。すなわち、「私は本当に疑っているのか?」「私は存在するのか、無なのか」。このことが「第二省察」で新たに問われているのである。夢遊病者の例はデカルトは引用していないが、およそ私たちが自分で自律的に思考していると思っていても、何ら思考していないということは確かにありそうだ。すると、身体はもちろん、精神も含めて一切は無なのか。私は存在しないのだろうか?
脱線:リアル・マトリックスの恐怖
→デカルトの懐疑を現代的に例えるなら、一昔前に流行った映画『マトリクス』のように自分が主体的に行動していたと思っていた世界が全てコンピューターが見せていた幻影だったという未来話が適当するかもしれない。目覚める度に現実と思うが常に欺かれる。自分で考えていたと思っていたこともコンピューターのプログラムであったことを思い知らされる。これを繰り返したら人はどうなるだろう? 自分が考えていること、存在していることを全く信じられなくなるのではないだろうか? これがただのフィクションとは言い切れないのは、心理学や大脳生理学の進歩によって、「意志の自律性」という虚構は暴かれつつあるということも不吉な傍証であろうし、何よりただ感覚に依拠しているだけの自己確信は危ういということが、想像力を駆使したそれらの想定によって身もふたもなく暴かれてしまうからにほかならない。いずれにしても、実際にリアル・マトリックスを体験したら、人は絶望してしまうだろう。しかし、絶望するのはいったい誰なのか? デカルトの懐疑はこうした問題を連想させる。
私は在る、私は存在する!
→一切を疑う。あえて考えたくもない究極の想定を考え、公正に事態を省察するなら「今私は考えている、存在している」ということさえも疑わしくなってくる。なるほど、私が身体を持つこと、「2+3=5」であると考えていたこと。そうしたことはどれも疑わしい。なぜか。それらは単に、「私は狂人では断じてないという理性的存在者としての自負を持っている」とか「私は2+3=5としか思考できない」ということを示しているにすぎず、実際に理性的存在者であるとか、「2+3=5」であるとかは出てこないからである。では、「今、私は疑っている」ということはどうなのか。それをただ素朴に主張する限りは、それも世迷言でしかないだろう。そうした考えを欺瞞者が吹き込むということはいともたやすいだろうから。それならば、私は無なのだろうか。ここで逆転が起きる。「一切を疑う」というこれまでのプロジェクトが悪霊の欺きだったとしても、というよりも、積極的にそれを悪霊の欺きだと仮定したときに、まさにその時に私が実在していることだけは疑い得ないと自覚しないわけにいかない。こうして、「私は在る、私は実在する」このことは私が精神で思うたびに必然的に真である。これが、デカルトの所謂コギトの発見である。こうしてデカルトは求めていた「アルキメデスの点」を見出す。なぜか。創造の起源まで遡って一切を疑ったからであり、コギトを真として見出す以前には、如何なる事柄も確実ではあり得ないからである。「私が疑っている」ということも確実ではあり得ない。欺瞞者の欺瞞を払拭できない間は何ものについても確信できない。「私が疑っている」という事実は私が自分で意図して疑っていると思うから肯定される事態なのではなく、一切を疑うときに疑う自分自身の存在が逆説的に肯定されてしまうからこそ肯定される事態、言い換えれば私自身が疑っていること、存在していることを疑うことができるからこそ逆説的に肯定される事態なのである。それでは、この逆説的なコギトの発見を支えているものは何か。それかは実際にすべてを疑い抜くときに、コギトはそれ自体で直接に知られるということである。他の知については「欺瞞者による欺瞞」を想定して、疑い得ないようなものは何もない。しかし、「私の実在」だけはどれほどの欺瞞を想定しても、すでに存在していることを自覚してしまっている以上、疑い得ない。すなわち、「実際には考えていないのに考えているように神が思いこませているのではないか」と反問したとき、直ちにこの懐疑が氷解するのは「実際にすべてを疑い抜くときに私自身の実在が直接的な知として自覚されるから以外の何ものでもない。逆にこの直接的な知、自覚という条件を度外視すれば、コギトは命題としては全く空疎な論理性しか有さず、欺く神の懐疑には耐え得ない。たとえば、「疑っているその時、私の存在を疑い得ない」と言っても、それが単にそうした行為が不可能であるという事実性についてだけ述べているのだとしたら、「私は私の存在を疑い得ないように悪しき霊によって創造されているのかもしれない」という疑惑を免れることは到底できないだろう。そうではなく、「私の実在」が現実的な直観として啓示されており、その直観が懐疑によって疑われる諸々の存在についての直観とは成立する次元を異にし、それ自体で真理であることを証明するからこそ、如何なる懐疑をも免れるのである。
考えるってどういうこと?
→「私は在る、私は実在する」このことは、単に「私にとってそう思われるにすぎないだけ」ではなく、私が自分を何ものかと考える限り、その度に必然的に真であること、「存在すると知っていることが、その通り実在すること」であることが証明された。だが、一切を疑った挙句、逆説的に実在が導かれるところの「私」とはいったい何者なのだろうか? デカルトはここで、「実在する私とは何か」と問いを立て、私とは考えるものである、と定義する。しかし、考える、とはどういうことか? たとえば、そこに椅子が在る、と私が考えるなら、それは椅子について何かが語られていると思うかもしれない。しかし、懐疑を経た省察の見地からすれば、私の考えは虚偽でありうる以上、椅子に関しては無を表現している。つまり、私が椅子が存在すると考えるからと言って実際に椅子が在ることは帰結しないし、そのことは表現されていない。「椅子が在ると考える」ということから帰結するのは、椅子の存在ではなく、私の存在である。このように、考えることは私自身の本性を表現すると考える限りは、虚偽ではあり得ない。このことをデカルトは「見ていることは偽だが、見ていると思われることは真である」と言う。「見る」という視覚の働きも、それが対象を捉えていると思い為すなら偽だが、「見る」が思惟の働きとして捉えられる場合には私自身の存在を表現するので真なのである。こうして、思考の働きの中には、疑うこと、理解すること、意志することだけではなく、想像や感覚も含めた精神の活動すべてが含まれることになる。考えるということは、何かについて考えることではなく、むしろ私自身の実在を表現することなのだ、ということがこの議論のポイントである。
脳がなくても考えることができる⁇
→こうしたデカルトの議論に対して、「考える」ということはそもそも身体がなければ生じないのではないか? 思考とは脳内現象ではないか、という最もな疑問が投げかけられるかもしれない。実際、身体が存在しなければ考えるということも可能ではないという事態は医学的にはあり得るだろう。しかし、それでも、身体よりも先に精神がそれ自体として確実に知られるということは動かない。身体の存在を疑って、コギトが最初に確実に知られたからである。ここで、身体の存在によって思考が成立するという話をしてしまうと、懐疑以前に逆戻りしてしまい、確実な道を踏み外すことになる。また、そもそも不確実な身体の知識によって、直接的で確実な知の意味を解き明かすことはできない。こういうわけでデカルトは、自己の何たるかを知るためには、想像力を遠ざけなければならない、という。なるほど、懐疑においては様々な想定を行い、想像力を駆使した。それは偏見を自覚し退けるために有効だった。だが、それ自体として知られる私の存在を想像力によって描き出すことはできない。想像するとは物体の像を描き出すことだからである。精神は何よりもまず、それ自体として知られる、というのがデカルトの主張の眼目である。
私たちはものを実は目で見ていない⁉、目ではなく精神のみによって捉えている⁉
→だが、こうして以前よりは私は自分が何ものであるかを知り始めているとはいえ、相変わらず感覚によって捉えられる物体の方がより判明に知られると思えてしまうのではないだろうか? それ自身によって捉えられる精神よりも、疑わしい物体の方がより判明に認識されると思われてしまうのはなぜか? それそれは、物体が感覚によって直接捉えられると見做されているからだ。そこでデカルトは眼前の蜜蠟を例に、物体が感覚ではなく、精神のみの判断によって捉えられていることを示す。つまり、蜜蠟を火に近づけ、ことごとくその属性が変化しても、同じ蜜蠟が残っていると見做される。変化の無数性を貫いてそう判断しているのはただ精神による判断であって、感覚が直接蜜蠟を捉えるということでもなければ想像によって変化のすべてを通覧したからでもない。私は目で見ていると思っていたものを、ただ、精神のみによって判断していたのである。それならば、物体よりも精神のほうがより判明に知られることは確かである。なぜならば、私が蜜蠟を見ると判断するならば、それ以上に私が実在することが確実に帰結するからである。つまり、物体が感覚ではなく知性によって捉えられているということは、物体を人間精神なくしては現にある通りに認識できないということであり、精神そのものの内に精神についての知を判明にする多くのものが内在していることは明らかなので、わざわざ物体を考察して精神の本性を明らかにしようとする必要がないのである。
以上が「第二省察」の要約です。徹頭徹尾、デカルトは感覚を排除し、知性による洞察のみで「第一の確実な認識」としての「私の実在」、そして、その実在する私の何であるかを究明しています。デカルトが懐疑の遂行の果てに見出したのは、「私の実在」です。その私は、身体でもなく、何らの能力でもなく、ただ、思惟しつつ実在している自覚的存在だということです。これが徹底的な知性的な反省、方法的懐疑によってもたらされた自己認識であり、自覚です。私はおよそ何かについて判断する度ごとに欺かれ得るけれども、その欺かれる最中において自覚的に実在していることだけは現実に知っています。では実在していることが私とは何か。それは「考えるもの」です。しかし、「考える」とは対象を表現することではなくて、逆に自己の存在を表現すると見做されたときに、正しく私の本質を言い当てることができます。かくして、実在という観点からみた私とは大変孤独な存在だということができるでしょう。なぜなら、私が思うことは実は世界を表現しているのではなくて、私自身の存在を表現しているに過ぎないからです。そこで暴かれたのは感覚によって外の世界とつながっていると思い込みながら、実際には自己自身しか見ていない私のありのままの姿です。デカルトが例に挙げているように、窓から眺めている人もひょっとすると自動機械かもしれません。私はその姿形と言動から他者に心があると判断しているけれども、それはただ、そう判断しているにすぎません。この判断が如何に危ういかはAIの登場によって嫌が負うにも自覚を促され今日では現実的な危機となりつつあります。まさしくデカルトが言う通り、感覚は不確実であり、これまで下してきた一切がどれほど薄弱な基礎の上に建てられているか、ということになるでしょう。しかし、一切が不確実であるとしても、その徹底的な自覚を通してまさにその不確実性の中で私が存在していること、生きていることは確実な真理として光り輝いています。私たちは何ものについても移ろいやすい考えを持つに過ぎないのではなく、確実にものを知るということができます。知っていることが単なる思い込みではなく、その通り現実であるという揺るぎのない確信に到達することができます。不確実な現実を現実として捉え、自らの存在が現実を越えて確実性に到達できることも自覚できます。だからこそ、感覚を遠ざけ、この確信の内に留まり、それを心に刻み付けるように、デカルトは勧めるのでしょう。
ありがとうございます。メッセージを添えられている場合には必ずお返事致しますが、メッセージのない場合は差支えあるかと思うので返信は控えます。ご了承下さい。
