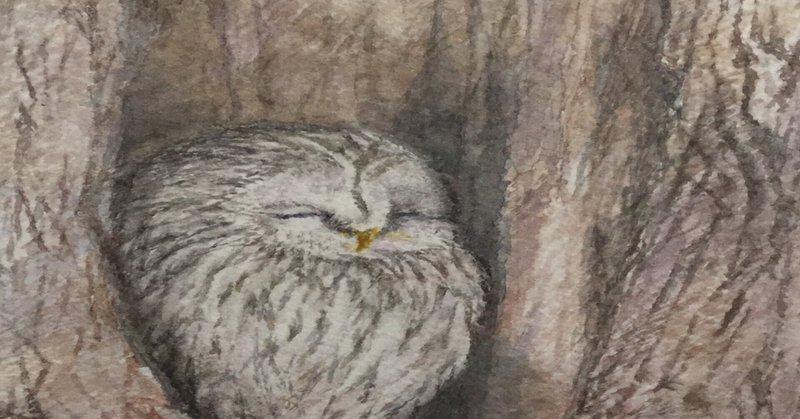
幸田露伴の随筆「災厄に対する畏怖と今後の安心策」
災厄に対する畏怖と今後の安心策
地震に対する恐怖も既に過ぎたし、火事から引き起こされた困難も避難やバラック建てによって段々と緩和されて行き、不逞の輩の行為に対しての人心の畏怖もようやく薄らいだ今日、最早それ等について多くを語る必要は無い。ただこの際に於いて、各人に要望する所のものは、各々その縁ある業務において奮励努力して貰うだけである。
この不幸な大災に際して、人々は普段は予想していない様々な状態に置かれた為に、心の状態もまた何時もとは大いに異なったものとなっている。それは先ず第一に自然の力に対する畏怖である。自然と云うものはどんな時でも同じような力を持っているものと決まっている。地震の有った日も無かった日も同じ力の量に違いないが、その力の場所の変更が大災害を引き起こし、そしてそれに引き続いて各種の災厄を起こし、大いに人々を驚かせたのである。もし自然の力が畏怖すべきものであるならば、天気晴朗で鳥鳴き花笑って居る時でも、畏怖すべきものでなければならない。ただ之に慣れると、恐ろしい自然の力が日々刻々に我に加わっていることも忘れ、自分程豪い者は無いように思うのが人情である。ところが、忽然として地が動き、忽然として水が狂い、続いて火災が起こり、人間の社会組織が破壊される段になると、今更のように自然の力の偉大な事と人間の力の微弱な事を痛切に感じる為に、まるで鳥が驚いて枝から起き、獣が驚いて土に隠れるように、取り付く暇もない天と地の間で、右往左往しウロウロするのが人間の常である。そこで、恐ろしい自然の力に対する免れがたい畏怖心が起きる。畏怖心が起きると同時に此の天地の大異変に対し、何らかの意義があるように感じ出す。そうして、その意義なるものをアレコレと探って、或いは之を神意とし、或いは之を仏の力の現われだとして、そのような人間よりも優れたもの、天地の主宰者と云うようなものに対して、我々はその御心(みこころ)に順うから我々の災厄を少なく仕玉えと願うようになる。これは思うに、今の我々がそう云う場合にはそう云う観念を起こすべきだと認識しているから生じるのでは無く、我々の先祖の先祖のその先祖の遠い遠い人類の昔から受け伝えられているものが現れて、我々が意識しなくてもそう云う念(おもい)を起こすのである。云わば多くの宗教と云うものは、そう云う場合を源に発して流れを続けて居ると云ってもいいような訳で、云わず語らずの間に、我々は祖先の抱いた感情や思想を伝え受けていて、それがそう云う場合に発露するのである。
それなので、一面から云えば、自然に対する解釈も知識も幼稚であった時代の感情や思想に支配されてそう云う感情や思想が復元すると云ってもいい。我々が今日有している知識や判断から云えばそんなことは一笑に付しても善いと云うべきような事である。
けれども、地震や津波が遠く過ぎ去った今日ではそう云う事も云えるが、その当時は我々が近代の教育から得たものよりも、古代から遺伝してきているものの方が、頭の奥底に強く存在していると見えて、誰もが宗教心のような感情を抱かざるを得なかったことは偽りない事実である。そこで善良な人々は多くそう云う場合に、知識や判断の上から当不当を論じるよりも、そのような暇は無いと、咄嗟に生じる感情に動かされて、自分の日々の行為が果して天地の主宰者或いは神、或いは仏と云うようなものの意に沿っていただろうか、いなかったであろうかと反省し、此の恐るべき自然の暴威を神の御叱りとか天の戒めとかのように解釈し、そして、自分が以後、願わくば天地冥々の道理に背かないようにと祈願する心を発したのである。
そう云う場合にそう云う心を持たない者も無いでは無いが、それはよくよくの極悪非道な者で、平生から善悪の判断が混濁していて我儘に振舞うことを善しと信じている輩である。また何パーセントかの人間は、震災を神怒や天罰と考えず、恐れるに足りないと考えらる事も出来ず、畏怖したまま、狼狽したまま、に在るものである。
サテこうなって見ると、そう云う場合に災厄を天罰と感じた人が、一般社会の善良健全な分子であって、此のドサクサに旨い事でもしてやれと云う人間は社会の一番悪い破壊者であり、大部分のいわゆる不善不悪の人間は唯々狼狽してごった返したと云う訳になる。
そこでこれ等を観察すると、たとえ科学的につまらない感情であるにしても、大災厄に際して天を恐れ神を恐れる人は、寧ろ人類の為には喜ぶべき人であって、そう云う人々が多い社会であれば、そう云う社会は醇化して段々よい社会を作り出す素質を持って居ると云える。即ち宗教心のあるものは、よい未来を持つと云う事になる。
ところが、自然の力が平穏に現れている場合は、全く自然の力の偉大さを忘れていて、之を軽んじ、之を侮るようになり、平時に於いて自然に頭を下げるような思想は、意気地の無いもののように思わて来るのも免れない人情である。従って平時に於いては宗教心のある者は薄馬鹿のように見える傾向を生じる。
しかしながら、今回のような大災厄が起きた後では、暫く身に沁みて、各自の心中に宗教的情調が漲る事が自然であろう。此の宗教的情調の存在と云うことは、一般社会にとって決して悪いことでは無い。ただそれが一転して、偶像崇拝や迷信に陥っては、それは野蛮時代への後戻りで、感心したことでは無い。
翻って考えて見ると人間と云うものは、本来理智ばかりに支配されているものではない。従って科学ばかりで何もかも済むと云う訳には行かないものである。此の道理がある為に、宗教心と云うものも必要なものである。これを絶滅して仕舞おうとしたところで、絶滅できるものでは無い、例えば自然に起きる大災厄が無くても、万物生滅の道理で誰もが死と云うものに待たれているのであるから、自分の存亡と云うことに対して或る考えを持たないで済むわけが無いのである。それなので、宗教は何処までも必要である。或いは理知以外に何ものもないと云うように理智が旺盛になるまでは、必要である。
そこで、今回のような事態にあっては、宗教者が大いなる力を持って善い宗教へ人々を導くと云う事は、大きな効用を挙げる時である。又、迷信を吹き込む悪い宗教者もこの際は相当の結果を挙げる時である。であれば、此処で最も注意しなければならない事は、悪い宗教の台頭する事を抑え、善い宗教が働き出すことを求めなければならないと云う事である。そして今の人々の頭に善良な観念を植え付ければ、何代か後の子孫の頭の中の善い種と成って、或る場合には善い芽を出すことになるであろう。そうして宗教の淘汰が行われれば、我々の子孫はより賢い、より正しい、より幸福な生活を送るであろう。
今の時に当って、人々の、特に善良な人々の注意すべきことは、こう云う災厄に際して愚劣な宗教に引き込まれることなく、善良な宗教に引かれるように、そして、賢明で活発な態度で、各々の縁ある業務に努力すると云う事であろう。
(大正十二年十一月)
訳者あとがき
露伴先生は遺伝と云う事を信じて居られたようで、自分の生まれは先祖の結果で、自分の経験が子孫に伝わるので、心して生きろと云われているように感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
