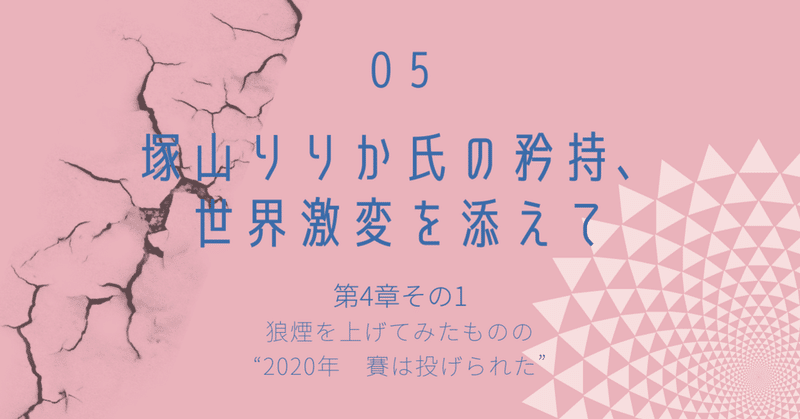
【小説】塚山りりか氏の矜持、世界激変を添えて:第4章その1「狼煙を上げてみたものの」
“2020年 賽は投げられた”
この病院の手術室の感染対策を任されている斉藤が、熊田主任と共に、インターネットで拾い上げて来た各学会の感染対策情報を整理して久しい。
「いやー先生がいて助かるわー。私だけだとこんなに症例報告とか集められないもの」
熊田はにこにこしながら斉藤を労っていた。ここ最近の手術室の急激な変化に、斉藤はまた休みがちになっていたのだ。今は、収まったとはいえ、次の流行の波が来る事を想定して、対策の見直しを行っているところだった。
「はは、お気遣いありがとうございます。僕も熊田さんに手伝っていただいて助かります。休みがちなので…」
恐縮しがちに斉藤は答えた。
さて、りりかが休憩室の隣にある記録室に来た時、2人は書類に埋もれながら仕分け作業をしているところだった。りりかはチラリと書類を見た。
「わー、こんなにあるんですか?げ、英語だ」
「大丈夫ですよ、直接感染対策に関係しているものを仕分けたら、これより少なくなりますから」
と苦笑いしながら斉藤がメガネを直した。するといつの間にかりりかの隣にいた浜崎優がりりかの腕を掴んで口を手元で覆った。なにごとかと思って隣を見るのと、優が「カッコいい!」と声を上げるのは同時だった。
「ええ!先生!メガネ姿カッコいい!やばい!」
普段はコンタクトなんですが、ちょっと、と斉藤は困ったようにまた苦笑いした。その照れ臭そうな様子にも優はますますカッコいい!と連発するのだった。
「イケメンパワー補充~!よし、午後から頑張ろ!ね、りりか!」
「そ、そうだね」
半ば優に引きずられるようにして、りりかが手術場に戻ると、手術を終えた明石が使用済みで血だらけになった器械を片付けるために部屋から出てきたところだった。
2人はお疲れ様です、と声をかけると明石が出てきた部屋に向かった。ちょうど、静男や砂肝が片付けを始めていた。
「あの野郎、準備くらいテメエでやれっての」
静男が不機嫌そうに感染物廃棄用の赤袋に血まみれのドレープを突っ込んでいた。砂肝が、ハイハイと呆れたように相槌を打った。
「砂肝さんは何とも思わないんですか!あの女医、お上品に喋ってオレらに色々言ってくるくせに、全然、実力が伴ってないじゃないですか!」
あの女医、と呼ばれる人物はこの手術室で1人しかいない。ああ、またかとりりかは思った。どうも静男と伊治原京子の相性は悪いようだ。
「それは私たちにはどうにもできないし、する事じゃないわ。そう言っている暇があったら、自分達の腕も磨かないと」
手術室の体制が元に戻り、手術件数が増加していくに従って、静男の伊治原に対する愚痴が聞かれるようになった。また、星や瑠偉も伊治原のことを女医と呼んで、最近ではまったくあけすけに毛嫌いしていた。
「もーどうしてこうなったかなー」
砂肝は静男の敵意剥き出しの態度を持て余しているように呟くが、その実何も困っていないだろう事は、彼女の普段の様子から容易に想像できた。
「はい、はい、掃除して次の準備!」
一難去ってまた一難というか、この感染症騒ぎで明らかになったのが、伊治原は想像以上の問題児だったということだ。
下根が連れてきた人物なので、一癖も二癖もある事は予想していたが、斉藤や星とは全くタイプの違うくせ者だった。
部長権限で、朝令暮改で意見や規則を変えるので、他の麻酔科医たちはその度に振り回されていたし、熊田や看護師たちも例外ではなかった。
それで、また医師応援が再開されて下根がきた時には麻酔科医たちと熊田が訴えるのだった。
「うーん、伊治原先生が逃げるから突っ込んで話せてないんだよね。僕が連れて来たから心苦しいけど、まあ、彼女の性格もあるし、ここはひとつ見守ってくれないかい?」
そう下根に言われると、彼に恩義を感じている面々は仕方がないと溜飲を飲むのであった。そして、下根ならこの状況をどうにかできるに違いないと信じていた。
程なくして、他のグループ病院でクラスターが発生したので、職員各位は行動に注意するようにと通知がされた。
「うわ、また制限とか、応援休止になるのかな?」
りりかはひと通りメールに目を通して呟いた。ニュースでは、世界全体の感染者が1600万人を超えたと報じていた。かくして再び、様々な制限が課されるようになった。
また慌ただしくなったが、斉藤と熊田が近隣病院や各学会報告から集めた情報で作り上げたマニュアルは、改訂された物に差し替えられていた。差し替えられたマニュアルは部署の朝礼で読み合わせをして、スタッフで統一した対応ができるよう図られた。
第4章は少し長めの全3回です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
