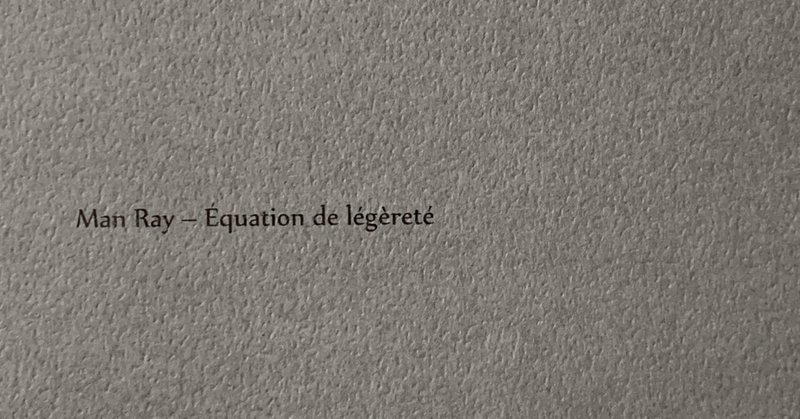
【書籍】マン・レイ 軽さの方程式
シュルレアリストやレイヨグラフなどで知られる巨匠の一人、マン・レイ。彼の芸術家としての「軽さ」とは何であろうか。
マン・レイといえば、昨年クリスティーズ・ニューヨークに出品された《Le Violon d'Ingres》(1924)が写真史上最高額おおよそ16億円で落札されたのは記憶に新しい。
マン・レイといえば、ダダ、シュルレアリスト、レイヨグラフなどで有名ではあるが、果たしてその理解のみで正しいのであろうか。
本書にもよく比較対象として名前が上がっているデュシャン。本書で木水氏はデュシャンとの違いを以下のように指摘している。
デュシャンは芸術ではないものをアートワールドに持ち込むことによって、ある作品がどのように芸術作品として決定されるかを実演してみせた。それに対し、マン・レイは、アートワールドでは芸術作品とされるものをその外に持ち出すことによって、アートワールド自体を相対化してしまうのである。
マン・レイの行為は、アートワールドにおける芸術の制度そのものが解体されてしまう可能性を孕んでいる。
デュシャンが行った「何が芸術になるか」とは真逆の、芸術であった作品がアートワールドの外に出たとき、芸術作品としての価値が解放されることになる。
ハーパース・バザー誌やヴォーグ誌といったモード雑誌に提示していたマン・レイのモード写真は、こうした機能を担っていたのである。
マン・レイがアトリエを開き、ポートレート写真家として活動していたのは金銭的な理由だけではなく、交友関係を難なく築くための免罪符のひとつとして捉えていたそうだ。
写真とは、結局のところ、九割がた機械であり、絵を描くよりはずっと厳密な計算を必要とする。
私は写真(photo)を捨てたわけじゃない。写真術(photographie)という表現を放棄したのだ。
あくまでマン・レイにとって最終成果物である「写真」を獲得するためにカメラなどの機械が存在しているにすぎず、手段が目的化することはないのである。
既存の表現方法から逸脱しうるのはオートマティスムが作用しているときであり、オートマティスムと媒体の軽視は連動している。
シュルレアリストたちは、思考の真の働きを表現するためにオートマティスムを用いる。
マン・レイはシュルレアリストの一人として認知されているが、厳密にはシュルレアリストたちのベクトルとは逆を向いていたのである。
あくまで表現したいイメージや思考を説明するための口実としてシュルレアリスムを「利用」していたのかもしれない。
マン・レイがこだわっていたのは写真特有の表現方法であったと木水は指摘している。
マン・レイは何よりも手段に対する全面的な軽視を望んでいる。そして写真という表現方法を、創造における媒体の軽視そのものと考えるのである。芸術表現において写真を認めるということは、いわば創造における媒体の価値の低下を受け入れることである。
本書で木水はマン・レイの表現方法に対して4つのタイプに分類している。その中で私が気になった点について取り上げる。
「マン・レイは、版型18x4センチの12枚のオリジナル写真を収めた写真集をトリスタン・ツァラの序文とともに『うるわしの湯』というタイトルのもとに出版しようとしている。この写真集は40部刷られ、41部目には斜線の入ったネガプリントがつけられることになっている。
複製芸術の観点から、ネガフィルムにおいて、デュープフィルムを除いたとして、ネガフィルムそのものを破壊(傷付ける)したとき、複製という行為から解放され、厳然たるエディションが担保されることになる。
では、デジタルの場合はどうであろう。元のデータを完全に消し去ったとしたとき、そのエディションは担保されるであろうか。仮にその画像がSNSなどにアップされていた場合、完全に「複製不可能」であることは保証できない。
結局のところ、物質的なフィルム同様に、デジタルもまた貨幣価値と同様に「信用」によって担保されているのではなかろうか。
本書では、名称が異なるのみでこれまで同一視されていたモホリ=ナジのフォトグラム、マン・レイのレイヨグラフについて指摘している。
モホリ=ナジは写真を表現手段として位置付け、「光の造形物」であることを意識している。
すなわち、写真手順の本質的道具はカメラではなく感光層であり、特殊写真的な法則と方法は光の効果に対する膜層の反応からもたらされ、光の効果は個々の材料に影響されて
と言った具合に、フォトグラムについてモホリ=ナジが端的に説明している。
一方、モホリ=ナジはマン・レイのレイヨグラフについて以下のように述べている。
日常的なものがここでは素材の新しい利用を通して謎めいたものになっている
フォトグラムについてモホリ=ナジは以下のように説明している。
文学的な、あるいは連想による隠れた意味や、色彩の効果による視覚的理解に訴えることなく、光の非物質的な放射によってのみ生まれるべきだ
本書では、ドミニク・バケの主張に賛同するように、フランス(パリ)でのモダニズム:マン・レイと、ドイツでモダニズム:モホリ=ナジとに分化されるとしている。
19世紀後半にフランスで配布された「帝国勅令」によって、それまで美術を牛耳っていたアカデミーから国家へとその権利が移された。芸術の自由化が促されたのである。
マン・レイはこの芸術自由戦争に対して、自由を「主題」と「手段」という2つの側面で捉えていたと木水は指摘している。
「教会や国の活動の要因とは見なされなくなった」芸術家は、「大芸術の持つ技法やきまりをすべて放棄」し、「独自の主題」を選び、「個人的な描き方」で描くという。
一方でマン・レイにおいては、技法を捨て個人的に描くことが自由なのではない。『「描くこと」すらも放棄し、もっと自由に創造する(中略)この未知の領域に踏み込んで「手段において自由」であることこそ(p198)』が、誰も到達し得なかったフェーズなのだ。
画家としてキャリアをスタートしたマン・レイであったが、描くことに対して特別な思い入れはなく、自動でイメージが生成される写真にのめり込んでいったのはある意味必然的であったのかもしれない。
表現手段の自由が、画家、芸術家というよりは、何でも屋というイメージを人々に与え、マン・レイの芸術を理解するにあたり少なからず困惑させたのである。
1966年、ロサンゼルス・カウンティ美術館においてアメリカ最大規模のマン・レイ回顧展が催された。この展覧会についてニューヨーク・タイムズ誌に掲載されたフィリップ・レイダーによる批評は非常に辛辣なものであったという。
時はグリーンバーグが提唱する抽象表現主義の全盛期。芸術の中心をアメリカへと企んでいた時期である。レイダーはマン・レイについて「完全にヨーロッパ化したアメリカ人とみなして(p219)」いた。
アメリカ人であったマン・レイは渡仏し、戦火を逃れるために帰国。戦後に再度渡仏した行為は、米仏間で勃発した芸術の主導権争いになぞらえて語りやすい格好のターゲットであったのかもしれない。
当の本人はというと『あたかも分かっていないのはお前たちのほうだといわんばかりに、ダダイストやシュルレアリストの「先駆者」として、ヨーロッパでは「喝采をもって」受け入れたのだと主張するのである(p231)』とあるように、マン・レイにとってはヨーロッパ>アメリカであったのである。
一方で好意的な歴史的評価としては、ダダ、シュルレアリスムが1960年代のアメリカ、ヨーロッパで再評価されたことにある。なかでもその発端となったのはネオ・ダダの芸術運動によるものである。その延長線上にはアメリカが中心となって賑わった「ポップアート」へとつながっていく。
同時期のヨーロッパでは「ヌーヴォー・レアリスム」運動(ネオ・ダダやポップアートのヨーロッパ版)が挙げられるという。
ただし、先に触れたように、この時代においてグリーンバーグの抽象表現主義がアメリカ芸術の中心にあった。ダダ、シュルレアリスム、ネオ・ダダを一切認めなかったグリーンバーグが力を持っていた以上、当時マン・レイがその後に続くポップアートの先駆者として扱われるはずがなかったのだ。
「近作は描いたことがない」(中略)この突拍子もないタイトルは、単に人目を引く冗談ではなく、作品を歴史化から解放し、作品を永久化させるための宣言なのである。
絵画においては、その作品が「オリジナル」である=唯一無二であることが重要であるのに対して、写真のように複製可能な作品について『どれが真正なプリントかという問いは無意味である(p252)』とマン・レイが指摘するように、複製芸術においてはオリジナル性の性質が異なってくる。
少し脱線するが、最近はもっぱら話題に上がらなくなったNFTアートにおいて、「データのオリジナル」や「唯一無二」などが担保できるとしてもてはやされていたが、こうした戦略の根底にはやはり絵画的価値基準がベースとしてある。性質も価値基準も異なるはずなのに、訴求ポイントがそこしかない作品に価値など存在する訳はない。
マン・レイは自身のオリジナルな作品(絵画など)のレプリカを制作している。ただし、完全に真似るのではなく、あえてわずかな差異を残すことによって、レプリカの作品でさえも「オリジナル」な作品として扱われるよう仕向けている。
たとえば『プレゼント』と題された、アイロンに釘が付いた作品は1920、1963、1970、1974年と実に4作も制作されている。
アイロンと釘というモチーフはそのままに、アイロンの型や釘の間隔が異なっている。このとき、作品のオリジナリティの在り方が変容する。
そのようにオリジナルと異なるレプリカを作ることによって、レプリカはオリジナルに従属させられることなくそれ自身がオリジナルとなる。(中略)マン・レイの思惑通りに、私たちはそこで、オリジナルの代わりにオリジナルとは違うレプリカを与えられ、実際レプリカの数だけ、オリジナルが増殖する事態に気づかぬうちに立ち会っているのである。
こうしたオリジナルとレプリカとの差異を見極めようとする者を、マン・レイは「新種のコレクター」と呼んでいたそうだ。
終わりに、木水はマン・レイの作品について以下のように指摘している。
マン・レイが望むことは、鑑賞者が偏見なしに物質として今目の前にある彼の作品と向き合うこと、それによって作品が永続することなのである。
********************
非常に読み応えがあり、多くの気付きが得られた一冊であった。現代アートを語るうえで、必ず押さえておく必要がある重要人物であると感じた。マン・レイ、おそるべし。
よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。
