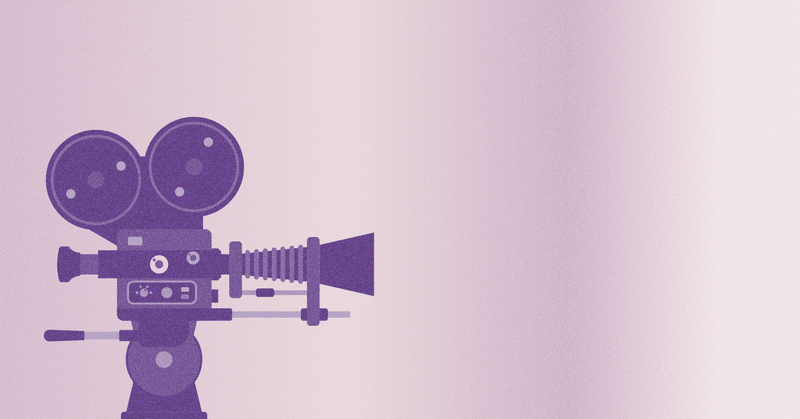
エイゼンシュテインとプロパガンダ映画⑴:モンタージュ
⚠️注意⚠️
ソ連映画について話していますが、現在の国際情勢とは無関係です。
エイゼンシュテインの映画が持つプロパガンダへの適性に関して、「モンタージュ」と「シーン」の二回に分けて考察します。
今回は、エイゼンシュテイン映画の特徴的な技法である「モンタージュ」の機能を見ていこうと思います。
モンタージュとは何か?
これ。映画マニアでもなければ、そもそも「モンタージュ」という用語自体に馴染みがないだろう。
そんなモンタージュという技法は、『映画の教科書』の中で以下のように説明されている。
隣り合う二つのショットがもつもとの二つの意味から、第三の意味を創造する弁証法的過程
第三の意味? 弁証法的過程? …はあ。
ぶっちゃけ、これだけ聞いてもよく分からないと思うので、ここで一つ具体例を出してみよう。
ここに四枚の写真がある。
⑴水で満たされたコップの写真
⑵苦しそうな顔をした人の写真
⑶空のコップの写真
⑷穏やかな顔をした人の写真
それぞれの写真は、あくまでも「水で満たされたコップ」だとか「苦しそうな顔をした人」以上の意味を持たない。
そのため、「人が苦しんでいる理由」なんかを知りたかったら、他の部分で補完するしかないだろう。
写真自体は、話の流れを教えてはくれないのだ。
しかし、これらの写真をひとつなぎにしてみるとどうだろう。
「喉の渇きに苦しんでいた人が、水を飲んで満たされた」という、一つのストーリーが浮かび上がってはこないだろうか?
それも、「人が水を飲んでいる写真」などないにもかかわらず。
あるいは、⑵の写真と⑷の写真の順番を入れ替えてみたらどうだろう。
「この人は水ガブ飲みコンテストに参加させられた」とか、また違うストーリーが考えられるかもしれない(水のガブ飲みはやめよう)。
このように、写真の並べ方次第で、時として全く異なるストーリーができあがってしまう。
これが「モンタージュ」である。
そう聞くと、「一つのストーリーを組み立てるのは、各ショットではなく、むしろモンタージュなのではないか」という気持ちさえ湧いてくるだろう。
実際、今挙げた四枚の写真のような各ショットや各シーンは、互いに衝突させられて新たな意味やストーリーを生むための、単なる記号にすぎない……といった考えもあるくらいだ(これについては次に述べる)。
シーン自体にとりたてて意味がないとは、なかなか衝撃的な考えである。
さて、ここまでで、モンタージュとは何であるのかが大まかに確認できた。
次は、それがエイゼンシュテインの映画の中でどのような役割を果たしたのかについて考えていこうと思う。
エイゼンシュテインにおけるモンタージュ
エイゼンシュテインにとってのモンタージュとは、対立する二つの断片(=シーン)の衝突であった。
…はあ?
いよいよ分からなくなってきた。「なんのこっちゃ」と思ったかもしれないが、安心してほしい。私も「なんのこっちゃ」と思っている。
ただ、この「断片同士の対立」という発想が、ソシュールの言語学からの影響を受けていることは確かだ。
ソシュールの考えの中から、エイゼンシュテインのモンタージュ理論の補足をするために必要な部分だけ抜き出すと、だいたい以下の通りになる。
我々は、「inu」という音を聞いたときに、四足歩行でワンワンと鳴くあの動物(犬)を思い浮かべることができる。
それは、iとnとuという各音素(それ以上分解できない音の最小単位)が互いにぶつかり合っているためである。
試しにこの「n」を「t」に変えてみると、iとt、tとuがぶつかり合うことになるわけだが、そうすると、言葉の意味はどうなるか?
途端に「何時」などと変わってしまうのである。
「i」「n」「t」「u」といった、それぞれの音自体に意味があるのではない。
それらの異なる音のぶつかり合いの中に意味があるのだ。
多分こんな感じで合ってると思う。
ここまで読んだ上で「対立する二つの断片の衝突」と聞くと、少しピンとくるのではないだろうか?
エイゼンシュテインは、「異なる無意味なシーン同士の衝突の中から、一つの意味を取り出すのがモンタージュである」と考えていたのだ。
それでは、エイゼンシュテインがモンタージュを用いて取り出そうとしていた「意味」とは、一体何なのだろう? これを次に考えていきたい。
モンタージュと全体的主題
結論から先に言うと、取り出される「意味」とは、叙事詩的な一つの主題であった。
…What's ? 叙事詩?
何だかまた厳つい単語が出てきたが、ざっくり言うと叙事詩とは、ドラクエとかに出てくる「勇者の物語」のことである。
「勇者」に個別具体的な人格はない。実際にはあるのかもしれないが、少なくとも、それが作中で描かれることはほとんどない。
ちょっと考えてみてほしい。
「勇者」は明るい性格だろうか? それとも、物静かな性格だろうか?
真面目? それとも、実は結構ちゃらんぽらん?
親しみやすい? それとも、クールで近寄りがたい?
「勇者はこういう性格だ」という、確固たるイメージはないのではなかろうか?
なんとなく自分の中で「この作品の勇者キャラはこういう性格だろう」という印象を持つことはあるかもしれない。
しかし、万人が納得するような形で「勇者の人格」が描かれることは少ないのだ。
一方で「勇者の物語」のゴールは分かりやすい。
魔王の打倒や平和の実現といった、世界に関わる壮大で崇高な目的がそれだ。
この点、「叙事詩(=勇者の物語)」とは、個々の人間性や人格を超えて、一つの偉大な目的が達成されるものであるといえる。
エイゼンシュテインは、モンタージュによって、個々人の生を超えた、人々に普遍の主題(=叙事詩的な主題)を提示しようとしたのである。
例えば、『戦艦ポチョムキン』におけるそれは「革命の理想」であった。
「革命の理想」は、個人の感情からはかけ離れた、ソ連国民の共同の意識である。
これを観客自らが能動的に導き出せるよう、方向づけること──それが、エイゼンシュテインにとってのモンタージュの機能であった。
(原典が手元になく、孫引きになってしまい申し訳ないのだが)エイゼンシュテインは、以下のような言葉を残したという。
観客はモンタージュのお蔭で、正確にそれが作者によって実験されたように、映像の現われのダィナミックな過程を実験している
エイゼンシュテインにとっての映画は、映像のダイナミックな現れを通して、観客に能動的な一つの感情的動きを「そそのかす」ものなのだ。
例えば、こんな映像を考えてみよう。
鉄砲を構えた兵士が映り、続いて頽れる女性が映った。
⑴ここに「何の罪もない市民である女性が、腐敗しきった政府軍に撃たれた」というストーリーが生まれる(モンタージュの働き)。
⑵それを見た観客はショックを受けたり、「なんてひどいことをするんだ」という憤りを覚えたりする(実際にその通りかはさておいて、映像を作る側としては間違いなくそのような反応を期待しているだろう)。
⑶そして、「そんなことをする政府は、革命によって打ち倒した方が良い」という一貫した主張へとたどり着く(実際にその通りかはさておいて(ry
こうした一連の流れにおいて、映像は感情へ、感情は一貫して変わらない主張へと移っていく。
観客はその中で、動的かつ能動的に「革命の理想」を称揚するよう、誘導されているといえる。
「鉄砲を構えた兵士」や「頽れる女性」といったシーンに対する解釈は無数にある。
これを、観客に「ショック」や「憤り」といった限られた数の感情を喚起し、彼らをただ一つの主題へと方向づけるような映像に仕立て上げるのがモンタージュである。
モンタージュは、無数の「意味」を特定の方向へと絞り込む働きを持っているのだ。
この点で、モンタージュとは、ロラン・バルトのいうところの
「シニフィエの揺れ動く鎖を(ある一つのイデオロギーに向けて)固定するためのさまざまな技術」(映像の修辞学、21-23ページ。丸括弧の中は引用者注)
の一つであるといえそうだ。
※シニフィエ:「意味されるもの(所記)」の意。記号内容。
ここでは「シーンという記号によって表される意味って本当はいっぱいあるけど、作品に対して変な解釈されたら困るから、作者側である程度意味を絞っちゃうよね」ということ。
バルトって基本何を言っているのかよく分かんないんだけど、なんと第二回にも登場する予定だ。ワーッ!!
以上、エイゼンシュテインがモンタージュによって、「革命の理想」などの叙事詩的な全体的主題を提示しようとしていたことを確認した。
次回予告とか
「マジでシーンには意味ないの?」という問いについて考えていきたい。
それから、今回の内容を踏まえて、エイゼンシュテインの映画が持つプロパガンダへの適性についてまとめていきたい。
何かありましたらコメント欄まで!!
↓次回
今回の参考文献
アンリ・アジェル著、岡田真吉訳『映画の美学』(白水社、1958年)
「音韻論」『世界大百科事典』Japan Knowledge Lib
「音素」『世界大百科事典』Japan Knowledge Lib
「記号」『世界大百科事典』Japan Knowledge Lib
ジェイムズ・モナコ著、岩本憲児他訳『映画の教科書』(フィルムアート社、1993年)
「ソシュール/用語解説」『日本大百科全書』Japan Knowledge Lib
山田和夫『ロシア・ソビエト映画史 ──エイゼンシュテインからソクーロフへ』(キネマ旬報社、1997年)
ロラン・バルト著、蓮實重彦、杉本紀子訳『映像の修辞学』(ちくま学芸文庫、2005年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
