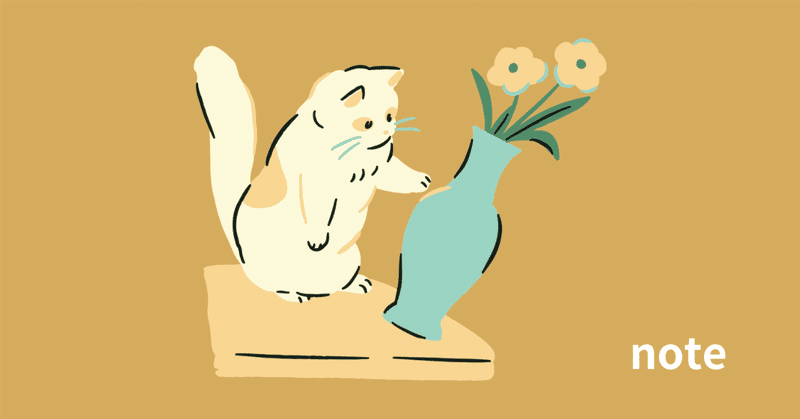
「花瓶の葬式」
花瓶を割った。
その花瓶は僕の友人がまだ若く金もない頃に、それでもどうしようもないほどに魅了されて購入したものである。それから十年以上大事に使っていたその花瓶を、友人は僕の働くBARのカウンターに置いてくれと持ってきた。それは友人がもうその花瓶に飽きたとか、もっと高価でいいものを見つけたからという理由ではない。友人は自分の大事な花瓶と、その想いを僕に託したのだ。そして僕は、その花瓶を割った。
その日は年末で、正月休みに入る前の在庫点検や大掃除をするために店を訪れていた。僕は休み明けにお披露目する正月らしく立派な雲龍松の枝を買い、花瓶に生けることを決めていた。だがいざ花瓶に生けてみると雲龍松の重みで花瓶が安定せず、少し触っただけで花瓶が倒れてしまいそうになる。枝をいくつか切り落とし、花瓶の水をいっぱいにしてなんとか安定を保ったところで、僕は微調整を後回しにして先に掃除をしようと店の窓を開けた。
花瓶は特に異変なく掃除も順調に進んでいた。だがトイレ掃除が終わり、店内の床をシートで拭き掃除している時にそれは突然やってきた。窓枠が「ガンッ!」と大きな音を立てたかと思うと、ものすごい突風が店の中に流れ込んできたのだ。その直後、ちゃんとバランスを保っていたはずの花瓶は、その場で回るようにグラつき始めそのままカウンター下の床に消えていった。
僕は思わず「ふざけんなよ!」と叫んでいた。先ほどから花瓶を割ったと表現しているが、その時の気持ちとしては「割られた」という感覚の方が強かったかもしれない。過失の割合で言うと、松の重さが3で、突風が5、僕の不注意が2という感じではないだろうか。
僕はとりあえずバラバラになった花瓶をほうきで集め取りビニール袋に入れると、すぐにAmazonで新しい花瓶を探した。それは一刻も早く証拠の隠滅を図ろうとした訳ではなく、あくまでも正月明けに花瓶がなければ、完璧な状態で店を開けられないと考えた上での迅速な行動だった。そして偶然にも似た雰囲気の花瓶を見つけたのだ。次に僕は友人にLINEをしようとスマートフォンを手に取ったが、直接謝った方がいいかと思い直し、正月明けの営業まで待つことに決めた。
休み明けの営業が始まると、挨拶がてら沢山のお客さんが顔を見せに来てくれた。友人も後輩などを連れて来てくれたのだが、花瓶の置かれたカウンターの左端ではなく右端の椅子に座ることが多く、花瓶を意識する状態ではなかった。遅くまで飲む友人はいつも最後は一人になり、そのタイミングで僕は友人が気づく前に花瓶の話を切り出そうと思うのだが、気持ちよく酔っ払った友人を前に中々話せずにいた。3回目、4回目と友人が来てくれる間に、それでも言い出せない僕はふとあることに気付いた。
「全然気づかへんやん、もしかしてこのまま気づかへんパターンもあるんかな」
きっと友人はもうあの花瓶を視覚で認識していないのではないかと思った。若かりし頃に恋焦がれた女性がいくら年老いても美しく映り、あの頃と変わらず胸を熱くさせるように、きっとあの花瓶がどういう状態であれ、友人にはあの頃と同じように映っているのではないだろうか。そしてそれは、僕などが干渉していい事柄ではないように思えた。だから僕は、黙っていることを決めた。
しかし審判の日は訪れた。その日は友人が花瓶の真ん前座り、酒を飲んで後輩達との会話を楽しんでいた。そして会話の合間に何気なく花瓶に目を落とした友人は、一度外した視線をものすごい速度でもう一度花瓶に戻した。それは漫画でしか見れないほどの綺麗な二度見で、ギャルのパンティーを見つけた時の亀仙人とほぼ同じだった。それから身を乗り出し、暗がりの中グッと花瓶に顔を近づける友人を僕は目の端で捉えながら、「やばいやばい、めっちゃ花瓶みてる」と酒を作りながら焦っていた。
こうなってはもう仕方ない。僕は友人の反応をいくつか想定して、それに対する答えを思案した。「難波ぁ〜」友人の不自然に高くあげた声が僕の耳にへばりついた。「花瓶どうした?」「カウンターの花瓶変えた?」友人は一体どんな言葉で真相を探ってくるだろうか。
「お前、花瓶割ったん?」
探るどころではなかった。一瞬で全てを理解した友人は、ど真ん中に160キロのストレートを投げ込んできた。完全に射し込まれ、手も足も出せずに僕は「わっ・・割った・・というか・・」そう絞り出すだけで精一杯だった。
その日の友人はいつもより酒を飲み、飲み干す度に「花瓶割った人、お代わり」と呪いの言葉を僕に浴びせ続けた。
それから何日かが経った夜、友人が花瓶のことをエッセイに書いたと言って読ませてくれた。そこには花瓶への想いと、僕の名前が漢字のフルネームで記されていた。そしてそれはその後にエッセイ集にも載せられることとなり、読んだ人から花瓶の話が好きだとよく言われると友人は僕に教えてくれた。
エッセイは花瓶の葬儀へと変わり、皆の言葉は弔いとなって、花瓶と友人の想いが成仏してくれることを切に願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
