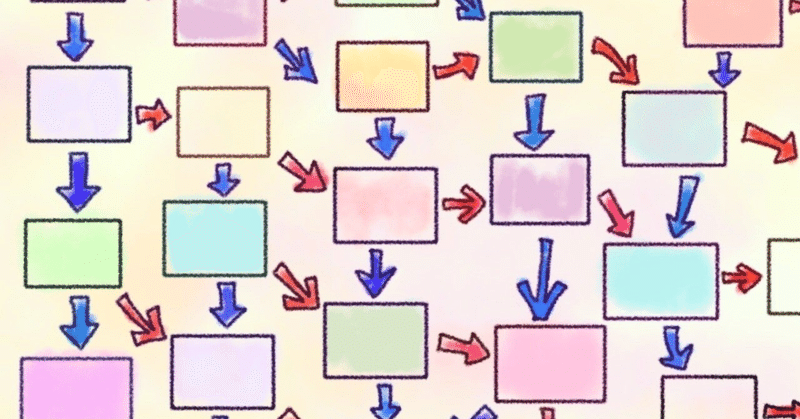
選ぶことこそが我々の武器である(機能と構造について考える④)
引き続き、機能と構造シリーズ第4回目。
第1回は、構造によって機能が規定されるという話。
第2回は、思考実験から、機能が規定されない構造は存在しないという話。
第3回は環境という因子が構造に影響を与え、その関係性はカラダと臓器の関係性とフラクタルになっているという話。
前回は、環境にヒトが振り回されるだけで、ヒトが自身で変えることは不可能なのかという話で終わった。
ある意味、ヒト以外の生物だと環境への影響を大きく受けて、流されてしまうことがあるかもしれない。けども、ヒトと他の生物には大きく違いがある。
その一つとして、脳の発達(特に大脳新皮質)があり、それによって行動に意味づけ、意図することが可能となった。
意図することが出来るということは、ある出来事に対して選択することが出来る。他の生物であれば、闘争もしくは逃走のような本能的な選択しかとることが出来ないが、ヒトは意図的に不快に感じる選択肢でも選ぶことが可能である。「2つの選択肢で迷ったときは楽じゃないほうを選べ」とか、ヒトのわけわからんところの極みみたいな言葉からも、他の生物とは違っていることが窺える。
もちろん選択する際に環境による影響はあるが、それに流されず選択することは可能で、それを意図して選択することがヒトの大きな特徴だ。
今自身に持ちあわせている機能の幅を広げることで、行動の選択肢を新たに増やし、その結果、周囲を変えていくことができる。
「自分が変われば周りが変わる」とよく言われるフレーズがあるが、それはまさしく意思による自身の変革による結果ともいえる。
なので、前回の
環境変化 ⇒ 身体的変化 ⇒ 生理的変化
という流れに意図という要素が入ることで
環境変化 ⇔ 身体的変化 ⇔ 生理的変化
という相互的な関係になっていく。
環境はヒトに影響を与え、ヒトは環境に影響を与える。
つまり、選択することが自身を、ひいては環境を変え得るツールである。
だから、機能と構造の関係は第1回の繰り返しにはなるけども、決して「どうしようもない」という悲しい話ではなくて、「変わることは可能だ!」という前向きな希望の話である。
では、どうやって機能の幅を増やしていくのか。
ここが繋がれば、機能と構造についての大きな道のりに一本、筋が通る気がする。
これはまた次回。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
