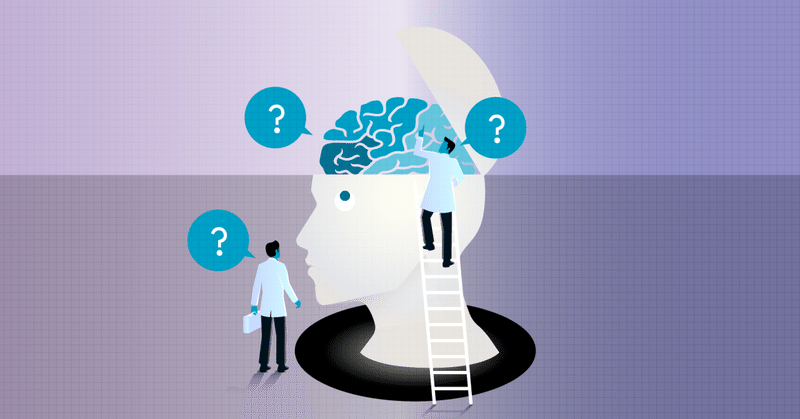
思考は発酵するのか?脳のはたらきから『思考の整理学』を考える。
思考の発酵
「思考 発酵」で反応する諸兄方は、おそらく外山滋比古先生の『思考の生理学』を読んだことがあるだろう。
自己啓発系や○○思考法、ビジネス系の本を読み漁る人なら必ず通る『思考の整理学』
当該の本を詳しく説明するのはレビューを読んでもらうとして、今回話す部分を簡単に説明すると、思考をより良いものに昇華させるための方法として「素材に酵素を入れて寝かせ、発酵させる」というアナロジーを用いて説明していた。
……こういう部分が素材である。ただ、これだけではどうにもならない。ビールをつくるのに、麦がいくらたくさんあっても、それだけではビールはできないと同じことである。
(中略)
このヒント、アイディアがビール作りなら発酵素に当る……それでは、アイディアと素材さえあれば、すぐ発酵するか、ビールができるのか、というと、そうではない。これをしばらくそっとしておく必要がある。
(中略)
頭の中の醸造所で、時間をかける。あまり騒ぎ立ててはいけない。しばらく忘れるのである。“見つめるナベは煮えない”。
これを読んだときに、
「なるほど!そうやって思考を洗練させていくのか!」
と目を輝かせた自分もいれば、
「いやいや、そんな発酵なんておこるわけないっしょ」
と懐疑的になる自分もいた。
最終的には、「そういうこともあるんだろうな、人によっては」
という所で結論は落ち着き、自分は本を閉じた。
そう、こういった思考系の本の類は大抵、人による要素が多く、あてはまる人もいればそうでない人もいる。
「あんたの経験論で話されても困るんだわ」と思うのだが、こういったビジネス書界隈で作られる本は大抵が経験談であるか、どこの引用文献か載せていない「○○の研究によれば」というものが跋扈している地獄のような世界だ。しかし、その中から生まれるキラーワードに目を奪われて、多くの人は財布から何枚もの英世を取り出す羽目になってしまう。
ただし、冒頭から話している思考の発酵。単なる経験論から導かれたn=1の話では終わらず、どうやら脳の働きによって説明できるようだ。
もちろん今回の話は研究によってわかってきたことであって、今後の脳科学の発展によって違ってくる可能性があるので悪しからず。
簡単に説明すると
課題への遂行時に「セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク」が活性化し、課題の中断時に「デフォルト・モード・ネットワーク」へと切り替わったのち、「セイリアンス・ネットワーク」が働き、新たな発想へと昇華、創造される。
………………。

この文章だけだと、自分が大学時代によくネタにされていた意識高い系の会話のようだ。
「来週のアジェンダどうなってんの?」
「言ってる内容は概ねアグリーなんだけど、確実な売り上げをコミットするためにはもっとスキームを練ってこい。アサップで」
………………。

冗談はさておき、一個一個の説明を進めていく。
セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(CEN)
これは、課題を遂行するときに外界へ注意を向ける実行機能としてはたらく。集中モードとも言い換えられる。
夏休みの宿題が残ったまま終盤を迎えたときとか、レポートや論文の提出期限が間近な時がそう(あの頃を思い出すと頭と胃が痛くなる)。
自律神経とともに考えるなら、交感神経が爆上がりしている状態。
脳がどうはたらいているかというと、前頭前野という行動の計画や予定を立てるための領域があるのだが、その中でも背外側前頭前皮質や、頭頂葉における後部頭頂皮質(空間認識)が主となっている。


デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)
これは逆に、外界に注意を向けず、脳内が安静状態のときに活性化、つまりボーっと何もしていない状態のときにはたらく。
何もしていないのにはたらくとは如何に、と思うかもしれないが、外界に対して何も注意が向いていないだけで、自分の内部のことには目を光らせている。
その時には目の前に起こっていることとは関係のない雑念や妄想、空想などを浮かべ、思考をさまよい続ける、いわゆるマインドワンダリングの状態となる。
この間は、常に自分のことをモニターしている状態で、ある意味、自意識まんまんな状態ともいえる。なので、全く関係ないことを考えていても、外界から自分に関わる情報だけは聞き取ることができる(いわゆるカクテルパーティー効果)。
自律神経で考えるなら、背側迷走神経複合体がはたらいている状態(決して凍りつき、虚脱と異なる状態という点は強調しておく)。
脳がどうはたらいているかというと、先ほどと同じ前頭前野でも、運動より情動と結びつきが強く、自己感というものを成立するために重要な眼窩前頭皮質や内側前頭前皮質、前帯状回が機能する。

セイリアンス・ネットワーク
上記のCENとDMNは絶えず行きかっているのだが、そのスイッチ役としてはたらく。
DMNから、明らかな刺激に気付いたら注意を高めてCENへ移行し、
CENから、刺激の元が去ったら(解決したら)DMNへ移行する。
脳がどうはたらいているかというと、多感覚を統合する島皮質の中でも主に右前島皮質が機能する。

以上、3つのネットワークの上澄みを掬って説明したが、読んでいる人の中にはDMNは思考の邪魔になるもの、CENは思考のキモになるもの、と捉えるかもしれない。しかし、上記の2つのどちらかが良くて、どちらかが悪いというわけではない。
ずっと働き続けると交感神経が機能しすぎて休息できないし、ずっと気を散らしていると仕事が進まない。適度に仕事をして適度に休む、メリハリが必要というのは社会人なら痛いほど理解していると思うが、脳も同じことが言える。
収束的思考と拡散的思考、そして発酵
アメリカの心理学者のジョン・ギルフォードが「収束的思考と拡散的思考」という、思考について提唱した概念があり、2つが揃ったときに創造がなされるという。
この収束的思考は集中している状態、つまりCENであり、拡散的思考は考えがぼんやりしている状態、つまりDMNともいえる。
そして、その2つの思考をセイリアンスネットワークによって行き交うことでひらめき、斬新で有用なアイデアが創造される。
これは結局、外山先生の「思考の発酵」で書かれていることとほぼ同義ではないか。
CENは素材をあつめて酵素を入れる
DMNは煮える鍋は見つめずに全く違うことをする
その作業を経て、セイリアンスネットワークとしての発酵が起こる。
これが脳科学的に説明された思考の発酵の原理である。
図にすると以下のとおりである。

さいごに
過去、先人が言ってたことやんってことが近年、科学的に証明されていることが多い。もちろん、俗説にまみれた世の中で、どれもが正しいわけではなく玉石混交となっている。
その中で玉を見つける方法としては、言った人が何を為したか、何をしているか、そこに尽きる。
口先だけの詭弁は誰にだって言える。自分がその例だ。こんだけ文章では雄弁であるが、対面だと途端に口ごもり、立派なことは言えない(もちろんそのために練習をしている)。
なので、キャッチーな内容、キラーワードが出てきたときにはすぐに食いつかずに、「誰が言ったか・何をした人か」をチェックする習慣は大切である。
つまり、ここまで語った自分の発言も、決して正しいと鵜呑みにしてはいけないということだ。
参考文献
種本。この本を読んだらほかの思考本は要らないのではないかくらいのエッセンスが凝縮されている。
種本2。思考の整理学を脳科学的に説明していた、と勝手に解釈した。著者の書いていることは自分よりかは遥かに正確なため、こちらを信用した方がいいと思われる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
