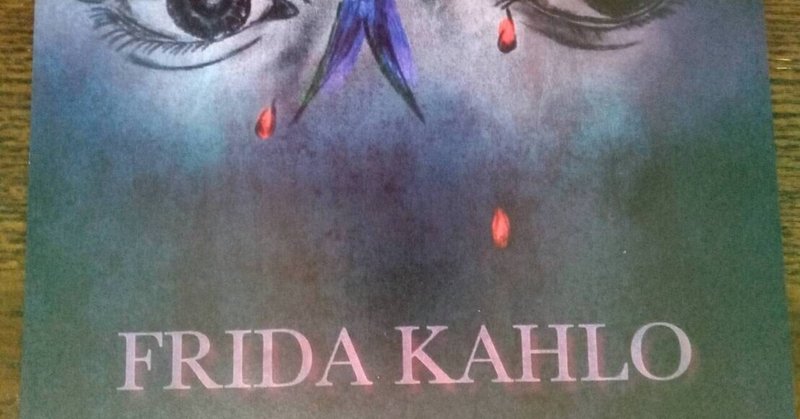
「弔い/フリーダ、おおばあちゃん、私、母、など。」
7月初めの日曜日の日、それは前々から予定されていた、身内に誘われて、とても久々に、ミュージカルの舞台、に出掛ける日だった。
ミュージカルの舞台、というのは、少し警戒している。若い頃、同じように身内に誘われ、かの有名な劇団のミュージカルというのをやおら、都会の真ん中に観に行った。案の定というのか、私は全く性に合わず、なぜだか腹立たしさすら覚え、なんとか耐え忍んで終演後、忌憚のないところでそのような感想を述べたが、家族と全く意見が合わず、なぜか多少なり説教されるモードで喫茶店でお茶など飲んだ覚えがある。
同じ様なシチュエーションといえばそうだが、今回のは少し演目が特殊だった。フリーダ・カーロの生涯を描く、というものだった。母がこの人物の紹介をもうかれこれ30年くらいも前に、女性誌での連載から始めて著作を物してきたので、私にとってもそれはある意味で幼なじみに近い友人のような存在になってしまった。そんなフリーダを舞台にした作品だというから、怖さ半分興味もあり、誘われて行った。
舞台は死の床に横たわりこちらを見つめるフリーダの姿から始まった。あらゆる痛みを受け入れ、自分を見つめ、描き、人生を愛し、晩年増々そこから動けぬ場所として文字通り彼女の世界であった寝床、ベッドの上に、横たわる彼女である。
彼女が死んだ歳、それは今の私と然程変わらない年であり、私も気づけばそんなにも長く生きてきてしまった、とも言えた。
舞台はフリーダの生涯を誠実に辿り、向き合う、意欲的な、とても良く出来た、すばらしい作品だった。それぞれの人物がいきいきと躍動し、フリーダとその生涯に関わった多くの人物たちの魂と相まみえる、そんな奇特な舞台であり、作り上げた俳優、演出の皆さんに敬服した。
ところがそんな舞台の始まる直前、家人からの一報で知ったのは、それまでいつも私の生涯第二の地元で世話になり、近年ではなにかとお世話することも多かった、義理の祖母、おおばあちゃんの死の報せだった。驚いたものの、この2日ほど急に、容態が悪くなっているとの報告は受けていた。
まだ6月の終わりだというのに始まった記録的な猛暑の、終盤の日だった。終わってみると家の前の桜の木の茂る緑も一部立ち枯れていたような、そんなかつてない猛暑が、100歳を目前にもしようという地元で皆に愛された名物ばあちゃんを、あちらに連れて行ってしまった。
フリーダの居るほうに、ばあちゃんも逝ってしまったのか、、そんな呆然とした思いとともに、観始めた舞台だった。
様々なことが頭をよぎり、運命にも似た、自分の人生というもののこともまた、まるでそれが、あたかもフリーダとともに歩んできたものだったのかとでもいうように、フリーダの人生と絡まりながら、自ずと考えに上ったりもするのだった。
終演後、連れの母らにもそのことを伝え、紹介を楽しみにしていたスペイン語関係の方がとても素敵な人生の先輩で、なおかつ大学の先輩でもあったことによろこびながら、ゆっくりもできずに暇乞いをし、その場を後にした。未知の領域である、おおばあちゃんの葬儀等の関係のことがあれこれと待っているはずであった、ところがその夜から私は熱が上がり、なんとコロナ陽性であることがわかったのである。
私はそれで、本来なら中心で動かざるを得なかったであろう、義理の祖母を送る葬儀の諸々の準備等を、すっかり家人はじめ地元の親戚に任せることができてしまったのであり、それはあたかもこの数年、数ヶ月、いちばんのレシーバーという女性、母、嫁としての家にまつわる仕事という、意識化されづらいという意味でアンビバレントな労働に多く時間を割かざるを得なかった、(むろんこれで終わりということでもなく、じっさい回復してみるとまた変わらずそんな日々が続いてもいくのだったが、)私へのあたかも祖母からの贈り物のような気持ちで受け取った(、あるいは冷静に考えると、どちらかというとフリーダから贈られたといえなくもない)、初め熱に浮かされながらも、ある意味で少し不思議なようにも感じた、そんな時間でもあった。
そしてそんな折身体の辛さのなかでこれもあたかも運命であるかのように想うのは、ミュージカルで眼前に体験したばかりの、痛みとともにあったフリーダのその生涯のことでもあった。そしてそれは自然、女の人生、というものに馳せる思いでもあった。
フリーダ、おおばあちゃん、私、母、など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
