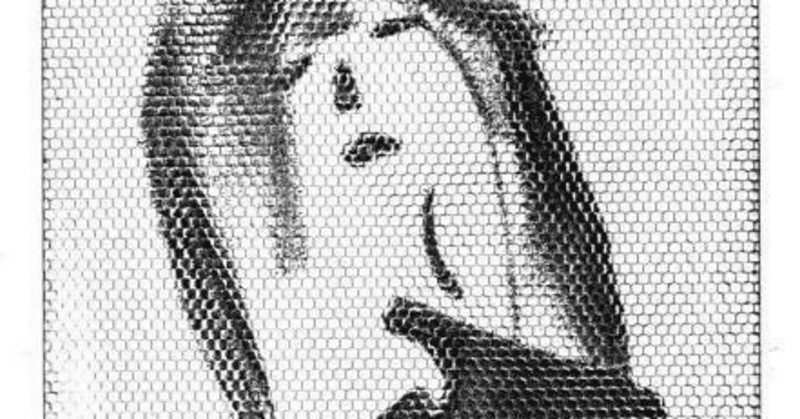
『木になる』(小さなお話)
朝起きると、まず私は歯を磨く。きれいに磨いた歯を鏡で確認し、顔を洗う。保湿液を塗り込み、その上でリップと眉を乗せ、最低限の顔を作る。さて、出来上がり。
「おはようございます」
「ああ。おはようございます。今日も早いですね」
言いながらそっと、棚の高さまで体を屈ませた。そこに在るのはシチューを入れる器よりも、もう少し底が平らで、広い皿。その中には、温い水が三分の一程度入っている。
「あれ? 水、口に合いませんでしたか?」
「いいえ、そんなことは」
彼はそう言うけれど、昨日寝る前に足した分から、あまり減っていないようだ。そっと縁から指を指し入れ、水に浸ける。私の指から小さな波紋が立って、それが彼の肌にも触る。さっと持ち上げた指先を口に運ぶと、少し甘いような味がした。
「そんなものを舐めなくても」
「だって、貴方の苦手な味なら、知っておきたくて」
私はティッシュを一枚引き抜き、舐めた指を丁寧に拭った。丸めたティッシュを屑籠に放り込み、彼にもう一度目線を合わせた。皿に置かれたその首は、元の体にあった時には、あんなに華奢に見えたのに。こうして皿の上にあると、しっかりと大切な頭を支えるための太さを与えられていることが分かる。
今日も朝の光の中で、彼は本当に美しかった。黒髪は瑞々しく、耳に掛けられるくらいに長さは揃えられている。同じ色の眉も、睫毛も、そして眼球の白も、瞳孔の縁取りの色も、素晴らしい彩光を持っていた。私は彼のそれらを満足するまで見つめ、彼の微かに温かな頬に手を添えた。水の中から静かに持ち上げ、私も同じ速さで立ち上がった。生まれてすぐの赤ん坊のような重たさを、愛おしみながら、私は色の抜けてしまった彼の唇に自分の唇を押し当てた。数秒の触れあいを胸に刻み込み、私は整った動きで彼から顔を離した。触れあったのと同じ秒数見つめ合う。微笑みひとつを呑み込み合い、私は彼を元の皿の上へと丁寧に下ろした。
「水、替えましょうか」
「いや、昼まではこのままでいいよ」
「遠慮していませんか?」
「君に? いや、まったく」
「じゃあ、今日のお昼に替える水は、昨日の夜のものじゃなくて、前の水に戻しますね」
「ありがとう。正直に言うと、少し硬くて、吸い上げるのに疲れてしまったんだ」
「言ってくださいね。ちゃんと水を吸収して育ってくれないと、いつまでも庭に植えてあげられませんから」
「そうだね」
朝の光が彼の頬を暖める。今はまだ、カーテン越しの光でなくては肌を焼いてしまうけれど、もう少し経てば、彼の皮膚は変化をはじめる。そして同時に彼の首の切れ目からは、根が伸びはじめるのだ。それは土を掴み、抉ることを求めるだろう。彼のための場所は、もう庭に空けていた。そこに彼の首を埋めたならば、きっと彼に似た、うつしい陰を持つ葉を茂らせる若木に育っていくはずだ。
私は部屋を出る前に、もう一度彼を振り返った。白い皿の上、まるで神様が、魂の変容を行っている最中のような厳かさ、穏やかさで、その首は立っていた。
2023.11.11の文芸会での発表作
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
