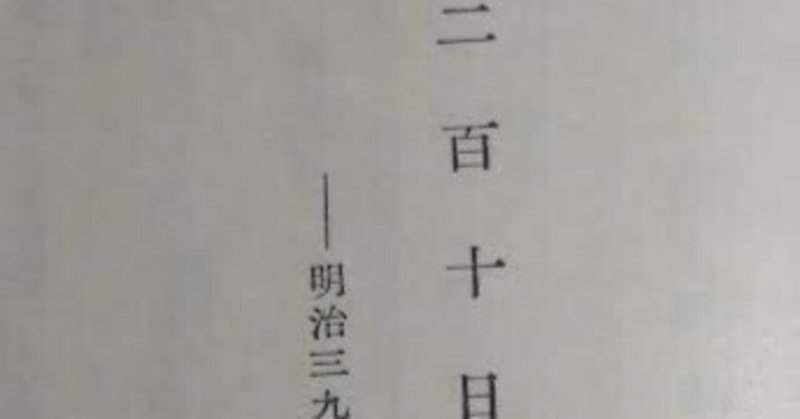
リズムを味わいたい小説―夏目漱石『二百十日』
初めて『二百十日』を読んだのはいつだったろう。私の記憶力の悪さは古くから定評(?)のあるところだが、(一応)漱石愛惜者の私が、初めて読んだ時期をまるで憶えていないとは、よほどこの作品への関心は薄かったということか。
我が家に長い間鎮座していた角川版1953年版の文学全集の『夏目漱石集』には収められていないし、筑摩書房版の1955年版全集にも、『二百十日』は収められていなかったから、家で出会わなかったのは確かである。大学に入ったときにはあらすじがアタマの中に入っていたのだから、高校卒業までには読んでいただろう。となると中学か高校の図書館か。あるいは市の図書館か。記憶の糸を探っていっても全く手繰り寄せることができないでいる。ただ、ぼんやりとだが、読んだ時の活字は割と大きめの、旧漢字であった記憶があるから、おそらくは市の図書館で、岩波版の漱石全集だったのではないか。
『二百十日』を軽視するのは私だけではなく、一般的傾向であるようだ。2016年、私が岩波版漱石全集を購ったとき、手にしたパンフレットに岩波から出版される他の漱石関連の書籍の宣伝もいくつか載っていた。そこに『二百十日』と『野分』が揃って一冊の岩波文庫に収録されて公刊される、これで漱石の小説作品が全て文庫化される、という意味の文言があり、少々驚いた記憶があるからである。漱石作品出版の家元格ともいいうる岩波書店の中で、まだ文庫化されていない小説が2016年まで存在したのである。
『二百十日』を軽視させることになったのは、あらすじの展開なのだろう。実際それは極めて単純である。圭さんと碌さんの二人が、阿蘇山に上ろうとして遭難しかけ、翌日再び挑もうとするところで終わる、それだけの小説である。劇的な展開はどこにもない。『坊ちゃん』のような勧善懲悪な活劇も、『草枕』のような美文調の華麗さも、ここにはない。確かにこれでは省みられにくいのも無理はないのかもしれぬと思える。それでも、その発表から90年たって、めでたく文庫化されたのは、安定の漱石ブランドがあったればこそなのであろう。むしろ昨今の出版事情から鑑みて、よくぞ文庫化してくれたと、思うべきなのかもしれない。
セールス・ポイントがないままでは本は売れないと考えたのか、出版社側は漱石ならではの社会批評感が良く表れた作品とうたっているようだ。しかし出版社の方々には申し訳ないが、そんなことは、今の私にはどうでもいい。私は別の視点から、『二百十日』を楽しんで読み返す。おそらく高校時代以来ずっと読んでこなかった『二百十日』を、今は好んで読み返すのである。
どこに惹かれるか。これまた単純な話である。会話である。圭さんと碌さんの二人の会話。二人の会話のリズムが、心地よいのである。会話の中身ではない。中身にフォーカスすると、それこそ出版社の皆さんのおっしゃる社会批判云々になってくるが、私はそちら方面に食指は動かない。ただひたすら二人の会話の持つリズムの心地よさを楽しんでいる。それはまるで、落語を聞いているようである。いや、これは落語である。漱石は高座に上がって落語を一席ぶつつもりで、この小説を書いたのではないか。漱石の落語好きは広く知られている。彼は自分が咄家になったことを想定し、高座を小説という表現形式に鋳直したのではないか。そしてストーリー展開は二の次、会話のリズムが醸し出す妙味、一種の高揚感を再現しようと実験してみたくなったのではないか。
小説自体の持つ、この高揚感は当時の漱石の、創作することへの意欲の高まりも大いに与っているであろう。小説が発表された1906年の漱石は、東京帝国大学などで教壇に立つことに意欲を減退させ、小説家として一本立ちしたいという欲求を膨らませていた。それが創作意欲を一層刺激する。漱石の妻であった境子の回想によれば、仕事から帰ってくるとたちどころに小説を書き上げてしまったこともあるということで、おそらくこの時期が小説家夏目漱石のピークだったのではないか。
その後の漱石の小説には、こうしたリズム感のある、高揚感を、そして多幸感をそろって醸し出す作品はみられなくなる。多幸感ということならば『三四郎』に軍配が上がるであろうが、リズムの快活さによるナチュラルな高揚感は、『二百十日』ならではの味、である。
そんないつも通りの勝手気ままなことを考えつつ、どうせなら漱石の命日である今日に、この戯言を投稿してやれと思いついたのである。ちなみに、1916年の今日も土曜日であったということである。
