
All's fair in love and war(ダージリン生誕記念17.09.2019)
秋の日の
ヴィオロンの
ためいきの ひたぶるに
身にしみて うら悲し
北の地にて
飲み交わすべし
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.
『ガールズ&パンツァー 劇場版』(ポール・ヴェルレーヌ『秋の歌』より引用)
「熱い紅茶だな」
この夏摘んだばかりのセカンドフラッシュを楽しむ秋の午後。
雑味のないすっきりした、それでいてフルーティーな香りが、過ぎ去ったばかりの夏を呼び起こす。

お茶の葉はとても繊細なものよ。
リーフの数だけそれに適した数値と作法があるの。
誤った数値では時に違う答えを引き出してしまう。
『ローゼン メイデン』1 Phase 3
茶葉が少なかったかな、とラベルを見返しながら、ある薔薇乙女の台詞を思い出す。
ルピシアのレシピでは、カップ一杯に2-3グラムの茶葉。
スプーンひとすくいは、少しだけ少なかったかもしれない。
わかってみればきっと、ほんの少しのことだろう。
しかしどんな時でも、真紅と同じくらい紅茶好きの彼女は一滴たりとも紅茶をこぼしたりはしない。

聖グロリアーナ女学院隊長、ダージリン。
今夜誕生日を迎えるこの英国淑女に、この昼下がり、薔薇の香りのGarden Partyを捧げたい。

冷静な計算の上に立った捨て身の精神
「土壇場を乗り切るのは勇猛さじゃないわ。冷静な計算の上に立った捨て身の精神よ」
『ガールズ&パンツァー』TVシリーズ 第12話「あとには退けない戦いです!」
夏の全国大会決勝戦、大洗vs黒森峰の最終局面を見届けながら言ったこの格言ほど、発言したダージリン自身の性情をよく表した言葉はないだろう。
事実、彼女は基本的に常に冷静だ。
この状況、こちらがこう出た時に相手がどう出るか、計算した上で戦うゆえに、盤上の駒を動かすチェスプレイヤーのように、全体の流れを把握しながら予定行動を落ち着いて遂行することができる。
戦いとは、 つねに二手、三手先を読んで行うものだ。
『機動戦士ガンダム』第2話「ガンダム破壊命令」
某ロボットアニメの赤い服の少佐と同じような性質を、真紅のタンクジャケットを着た金髪の少女も身につけているのだ。
だからこそ、こういう台詞が出てくる。
「どんな走りをしようとも、我が校の戦車は一滴たりとも紅茶をこぼしたりはしないわ」
『ガールズ&パンツァー』第4話「隊長、がんばります!」
余談だが、シャア・アズナブルも一年戦争後半でモビルスーツ搭乗時ノーマルスーツを着るよう部下に言われ、必ず生きて帰ってくるから必要ないと嘯いている。似たもの同士だ。
さて、ダージリンが常に「冷静な計算の上に立っ」て戦闘に望んでいることは説明できたとして、「捨て身の精神」とは何だろう。
例えば、「必要なリスクを取る大胆さ」というのはどうだろうか。
身も蓋もない言い方をすれば、「計算上割に合う損害なら躊躇なく犠牲にして勝ちを得る冷徹さ」にもなるかもしれない。
大洗・知波単連合vs聖グロリアーナ・プラウダ連合の練習試合の最終局面でのあの行動、カチューシャのT-34を盾にみほのIV号の砲撃からフラッグ車である自身を守り、その隙をついて同じくフラッグ車だったみほを撃ち取ったあの判断はその好例だろう。
同じ隊長格であるカチューシャすら、試合に勝つのに必要な損害ならばためらわずに犠牲に供する冷徹さ、この決断力は流石である。
そしてこの「計算上割に合う損害」の判定対象には、ダージリン自身すら含まれている。大局観のある彼女にとっては、彼女自身すらも盤上の駒でしかないのだ。
大洗vs大学選抜の厳しい戦いでダージリンは、冒頭に紹介したヴェルレーヌの詩を使って、大洗と親交のあるライバル校に大洗への助っ人を呼び掛ける。
第二次世界大戦後期のノルマンディー上陸作戦、そしてそれをテーマにした映画『史上最大の作戦』の故事に倣った、戦車女子(と多くのミリオタな視聴者)には確実に通じる洒落た暗号である。
他校生の大洗への大量の「短期転校」をアレンジした影(?)の立役者にも関わらず、ダージリン本人は3中隊に分けた部隊の中隊長を勤めなかったし、自分からその地位を要求もせず、大隊長みほが率いるたんぽぽ中隊の副隊長に甘んじた。
自分よりまほとケイ、そしてみほが適任だと判断したのだろう。
私益や私欲より、「勝てるかどうか」「勝つのに効率的か」を優先したのだ。
そして「冷静な計算の上に立っ」て合理的ならば、彼女は自分自身という駒すら敵前に差し出し、チームを勝利に導くことすら敢えてする。
一滴たりとも紅茶をこぼしたりすることなく。
「みほさん頑張って。戦いは最後の5分間にあるのよ」(『ガールズ&パンツァー 劇場版』)

こう言い残して超重戦車T-28を道連れに戦場に散った時、ダージリンはプラウダ車が「崇拝」するカチューシャを身を挺して守り玉砕した時のような熱狂(あれはあれで感動的な名シーンで、僕だって見る度に涙が止まらないけれど)はきっとなかっただろう。
戦いは非情さ。
『機動戦士ガンダム』第5話「大気圏突入」
宇宙世紀の赤い服の仮面の将校がこう言った時と同じ冷静さで、彼女は最後までティーカップを放さず支えていた。
冷静な計算の上に立った、捨て身の精神で。
騎士道精神/No Side/All is fair in love and war.

ダージリンはたまに「二枚舌」だとか、「英国面に堕ちた」と言われることもあるけれど、個人的には(少なくとも戦場では)彼女なりの「騎士道精神」は貫いていると考えている。
サンダースのレギュレーションスレスレ(というより「非常識」「マナー違反」と言うべきか)の盗聴は論外としても、アンツィオの欺瞞作戦(マカロニ作戦)のようなトリッキーな戦術や、プラウダのような僚車を餌兵にしてキルゾーンに誘い込む作戦を、ダージリンは取っていない。
策士のイメージのある彼女だが、基本的にはあくまで騎士道精神に乗っ取り、正々堂々戦いたい人なのではないか、と思い始めている。
だからこそ、大洗との初めての練習試合の際、「こそこそ作戦」を「安直な囮作戦」と見破りながら、あえてキルゾーンに突入した。そして装甲の厚さを活かした浸透突破で切り抜け、逆包囲にまで追い込んだのだ。
『007 ロシアより愛をこめて』の冒頭部分、犯罪組織スペクターの幹部達がイギリス政府への陰謀を巡らせる場面で、立案者のNo. 5が「罠だと知っているからこそ立ち向かいます。それがイギリス人です」と喝破するシーンがある。
彼の言った通りMI-6とそのエージェントのボンドは、罠だからこそあえて敵勢力(当初敵はスペクターでなくソ連だと考えていたが)のプロットに乗って行動し、敵の手がかりをつかもうとする。
そしてスペクターの思惑に反しすべての罠をくぐり抜け窮地を脱しただけでなく、エサとして用意されたロシアの暗号解読器、その上美人スパイまでちゃっかり手にして一人勝ちするのだ。
古き良き英国紳士と同じ騎士道精神を、ダージリンも持っているのではないか。

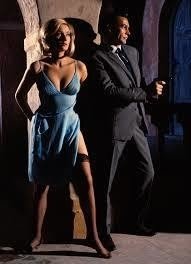

騎士道精神と少し似ているが、ラグビーでいう「ノーサイド」の精神を、継続性のある「制度」「儀礼」「風習」として一番体現しているのは、案外聖グロ、特にダージリンな気もしている。
ノーサイドは、ラグビー(特にラグビーユニオン)において、試合終了のことを指す(英語圏でもかつては「No side」が使われていたが、現在では「Full time」が使われている)。戦い終えたら両軍のサイドが無くなって同じ仲間だという精神に由来する。
『wikipedia』「ノーサイド」最終更新日2019.09.14
個人と個人の間の「情」としてのノーサイドの精神は、もちろん主人公西住みほ(とその周辺)で最も良く体現されている。
黒森峰との決勝戦前、試合準備中のみほのところに先の試合相手、かっての「敵」が皆激励に来るシーンがある。それを見てダージリン自身が言ったことだ。
みほは戦った相手とみんな友達になってしまう、と。
そしてもちろん、大学選抜との廃校を賭けたあの戦い、ダージリンの書いた筋書きとはいえあれだけの元「敵」が助っ人に駆けつけてきたあの戦いは、みほの戦車道が「ノーサイド」であることを証明している。
だがこれは個人間で自然に発生する自然なノーサイド、「情」のノーサイドで、「風習」のノーサイドではない。
極端な話、みほが卒業した後、ノーサイドの精神を大洗に引き継ぐためには、後継者となる誰かが受け継ぐ必要がある。「個人」に依存する精神文化という意味では、継続性が弱いのだ。
アンツィオはどうだろう。
試合後に試合相手と大がかりな宴をするあの姿は確かにノーサイドだ。そして見たところ、アンチョビがスカウトされる前からのアンツィオの伝統だったように見える。継続する風習なのだ。
月並みな言い方になるが、アンツィオにあっては「試合の延長に宴がある」のではなく、「宴の延長に試合がある」のではないか。
あの子(アンチョビ)は楽しい戦車道を以前からやっていた。
しかしそれは勝てない戦車道だった。
優しすぎたのだ。
『リボンの武者』第43話「小諸の死闘・10」単行本11巻p101
僕はラグビーどころかスポーツ自体がからきし駄目だけれど、趣味でサバイバルゲームをたまにするのでそこから類推するに、勝つためにお互い死力を尽くした上で初めて生まれるのが「ノーサイド」の精神ではないか。
その意味では、アンツィオは優しすぎた。
「ノーサイド」のコールの前に、最初から両サイドに分かれてなかったのではないか、というくらい。
そういう意味では、試合自体の緊張感を保ちつつ、個人的な情ではなく風習としてのノーサイドの精神文化が根付いているのは聖グロで、根付いた文化をよくメンテナンスし、より発展させたのがダージリンではないか。
何しろ彼女達は、劇場版の最後であの大学選抜とすら紅茶を酌み交わすという「大人の対応」が出来てしまうのだから。
ノーサイドの精神がなければ、対大学選抜での他校共闘、『リボンの武者』の「大鍋(カルドロン)」のオーガナイズなど出来なかったろう。
策士としてのダージリンの強みは、こういうところにもあるのではないか。
とはいえ、「騎士道精神」も「ノーサイド」も、あくまで「勝利」という「実利」に反しない限りであるのを忘れてはいけない。(ひとつひとつの試合というよりは長期的な、自身や今のチームというよりはより広い範囲の「勝利」「実利」だとは思うけれど)
大洗・知波単連合との練習試合ではみほのIV号に一騎討ちを何度か挑まれているが、挑発に乗っていない。「受けた勝負に逃げている」のだ。
実利を伴わないリスク、「コスパ」の悪いリスクは避けるのも、「冷静な計算の上に立っ」たひとつの判断である。
「こんな格言を知ってる?イギリス人は恋愛と戦争では手段を選ばない」
『ガールズ&パンツァー』第4話「隊長、がんばります!」
「All is fair in love and war. 恋と戦いは、あらゆることが正当化されるのよ」
『ガールズ&パンツァー』第11話「激戦です!」
…やっぱり「二枚舌」かもしれない。
殻を破るための「紅茶仮面」

『リボンの武者』というスピンオフ漫画を、不勉強ながら最近になって読んだ。
かなり攻めた内容だが、個人的には非常に肌触りがいいというか、感性によくフィットする。
名作だと思う。
特にまほとエリカの性格描写、黒森峰と西住姉妹の関係性についての解釈は、自分がうっすら思い描きながら言語化出来ずにいたことをピタッと表現してくれて、「やられた!」と感じたものだ。
あと、戦闘シーンやキャラ同士が対峙するシーンの描き方がなんとなく『蒼天航路』に似ていて、妙に懐かしていい。
『リボンの武者』のダージリンは、アニメ版では見せなかった「素顔」をさらけ出してくれる。
逆説的だが、「紅茶仮面」を被ったその瞬間に。

もうひとりの赤い人、キャスバル坊やは「シャア・アズナブル」という「仮面」を被ることで周囲の監視から解放され自由になり、いつしか仮面だったシャアのほうが「素顔」になり、「クワトロ・バジーナ」、そして「キャスバル・レム・ダイクン」という「仮面(!)」を被るという経緯を辿る。
仮面とパーソナリティーとは、かくも微妙な関係性で繋がっているのだ。
(パーソナリティーの語源はラテン語でpersonaだが、もともとは「仮面」という意味だ)



このスピンオフのダージリンは、なかなかにアグレッシブだ。
だがそれでもダージリンらしさ、英国らしさを失わないのがいい。
「英国が優雅で保守的なのはカードの片面…
型破りで革新的なことをなすのも英国の一面
そのゆりかごが名門私立学校出身者…
そして我が校はその名門私立学校に範をとった学校…」
『リボンの武者』第23話「それぞれの想い」第6巻p118-119
格言好きの彼女は歴史を、「伝統」の意味を正確に理解している。
真に伝統を引き継ぎたいならば、型破りをしなければならない。伝統を壊さなければ、伝統は守れないということを。
そして、そのための追い風が、今まさに吹いている。
「現状の戦車道のルールはとどのつまり戦車道強豪校…
黒森峰やプラウダが絶対的に有利なルールよ…
私たちもその中でなかば諦めていたわ…
伝統や優雅を言い訳にして…
ーでも今は違う
停滞した戦車道に風が吹いたの…
大洗女子が吹かせた風がー
その“風の音”が囁くの
もっと楽しみなさいーと!」
『リボンの武者』第23話「それぞれの想い」第6巻p121-122
そして、「大鍋(カルドロン)」開催。
今や壊して守るべき伝統は戦車道全体にまで拡大する。
「私つねづね思ってましたの
私たち日本人の悪い癖ー
ルールを疑いもせずその枠内のみで努力してしまいがちなことー
ルールでは則るものではなくー
乗っ取り 刷新するものだと思うの
私たちは世界に伍していくのではなくー
世界をここに持ってくるべきなのではないかしら」
『リボンの武者』第32話「佐渡島の戦い」第8巻p158-160

戦車道全体の革新について語りながら、大会が進むに連れ、ダージリンは「彼女自身」の楽しみ、「彼女自身」の戦車道を語り始める。
「聖グロリアーナ隊長」「優雅な戦車乙女」という仮面を、「紅茶仮面」が解放したかのように。
「なんてー楽しいのでしょう
大洗女子が起こした風ー
風に吹かれてやってきた新しい出会い
すべてが繋がったときー
見えたわ 私の戦車道ー
この大鍋(カルドロン)は世界への狼煙
傲然とした挑戦状
貴女がた
戦車で思い切り遊んでみない?
さあ 大人の顔色窺い、いい子ぶるのをやめてー
この遊びに参加したければー
全ての戦車乙女に告げる
ここへーいらっしゃい!」
『リボンの武者』第40話「小諸の死闘・7」第10巻p162-165
ダージリンが求める「革新」とは何か?
大会のCFO(最高財務責任者)のアスパラガス(BC自由学園)はこう語る。
「ダージリンの目的はー
今後の戦車道にいろいろな発展性を持たせることざます
日本戦車道が排除してきたものの復権ー!
「道」とはいえ日本戦車道公式が歩んできた道は競技化への道
とどのつまり敵味方二者間の勝敗を決める遊戯にすぎない
その実表面はそれに反し「乙女のたしなみ」「自己修養」といった美辞麗句を並べ
自己美学の追求を標榜してきた
しかしヨーロッパ系競技では数多のチームによる戦いの中
敵同士が協力し合うというのも魅力のひとつ
競合する他者間での協力と裏切りを
遊戯として経験することー」
『リボンの武者』第41話「小諸の死闘・8」第11巻p25-27
後を引き取り、ダージリン自身が語り出す。
それが私たち日本人には圧倒的に足りないー
だから私たちは世界では勝てない
ではどうする?
答えは簡単
楽しみながら遊べばいい
強襲戦車競技(タンカスロン)を!
『リボンの武者』第41話「小諸の死闘・8」第11巻p28-29
そしてこの理想の究極とは何か?
ダージリンは、いや大会参加者全員がよくわかっている。
それは「彼女」が大学選抜戦で体現した、夢の戦車戦。
敵も友となる楽しい戦車戦
『リボンの武者』第41話「小諸の死闘・8」第11巻p35
西住みほが吹かせた新しい風に、皆乗りたいのだ。
しかし最初の大会だ。
オーガナイザーのダージリンには、やればやるほど課題が山積していく。
掘れば掘るほど、戦車道という競技の抱える矛盾と対峙しなければならない。
戦いの最中、ダージリンはいつになく感情的になり、本音を吐露し、叫び声を挙げる。

戦車道家元が創り出したふたりの化け物
島田流島田愛里寿!
そしてー
西住みほ!
あのふたりがー
伝統戦車道からの回答だとしたらー
私は自分の戦車道を追おうと思う
戦車の楽しさ
みながそれを目指している
この先に私が見ていた何かがある
この先を見たいのにー
もうちょっとでなにかがー
見えるのに!
『リボンの武者』第43話「小諸の死闘・10」第11巻p96-99
泥にはまった戦車を手ずから引き揚げ、泥まみれになりながら叫ぶダージリン。
剥がれた紅茶仮面の下の素顔は、大きな夢を追いかけながら届かずもがく一人の少女。
大粒の涙。
みほさんの戦いを見て私の目標は定まった
私の楽しい戦車道
『リボンの武者』第43話「小諸の死闘・10」第11巻p100
彼女の見つけた戦車道は、まだまだ遠いかもしれない。
しかし彼女は諦めない。
「冷静な計算の上に立った捨て身の精神」で、あらゆる手を使って前に進んでいくだろう。
「イギリス人は恋愛と戦争では手段を選ばない」のだ。
P.S. Bon Voyage!
9月15日、風の強い曇りの午後にダージリンの母港、横浜に僕はいた。
神奈川県民でありながら「川崎都民」と揶揄される身の上で、実は横浜との接点が少ない。
それでもたまに訪れると、長く港町だっただけあって、「異文化交流」の街なのだと感じずにはいられない。


「異文化」というパッケージ商品を移植して、真空パックで販売し享受するというよりは、土着のものと舶来ものが交ざってひとつになっているというか。
日本人にとっても住む場所というより働く場所に特化している都心と比べると、「異文化」が(一過性でなく)「根付いて」呼吸している感じがした。
山下公園にはバラ園があって、こういうところならダージリンは喜んでお茶会をするのかなと夢想した。あいにくバラの季節には少し早く、まだまだ咲いてはいなかったけれど…





バラの薫りを嗅いでいると、汽笛が鳴った。
船が出るのだ。
ダージリンの夢を乗せた船が、明日へと。

Bon Voyage!
自販機で買った缶の紅茶を飲みながら、僕は低く呟いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
