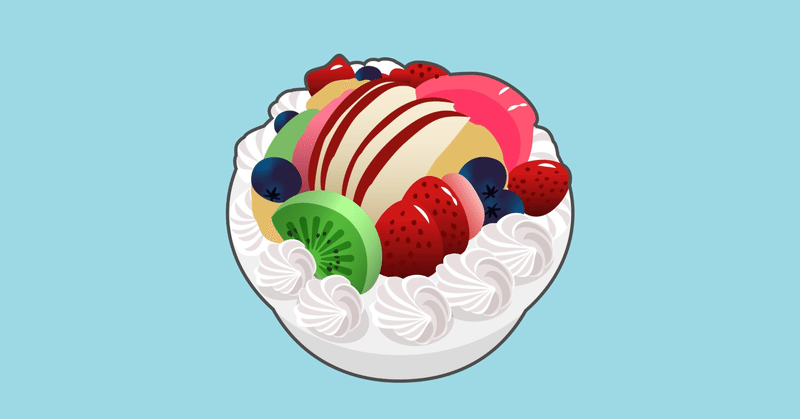
【ショート小説】祝う
最近、両親共々元気がめっきりなくなってきたことが心配だ。
そんな二人はとっても仲が良い。
それだけ長くいるのに、お互い飽きてこないものなのだろうか。
私はというと結婚17年目であるにも関わらず、夫の定年退職後の生活を思い描くだけでうんざりしている。
そんな私たちだが、去年まで二世帯住宅に住んでいた。
私には弟が一人いるのだが、弟は大学進学を機に都会に出てしまい、こちらに戻ってくる気配はない。
私はというと、生まれも育ちもずっとここで、結婚するまでは実家から出たことがないし、当然両親にはここまで育ててもらった恩がある。
しかも物価高で、火の車だった我が家の家計を幾度となく助けてくれた。
これも、一流企業の技術者だった父だったからこそだ。
だから、二人の介護は私がするものと思っていたし、家族たちも理解してくれていたのだが…。
しかし、両親たちは密に自分たちの余生について、真剣に考えていたらしい。
ここから車で3時間ほどの老人ホームを見つけ、さっさと引っ越してしまった。
私に何の相談もなかった。
分かっている。
自分たちの事で子どもたちの手を煩わせまいという親心。
だけど、心の中では意地悪されたような気持ちが広がって、だだっ広い家に一人、取り残されたような切ない気分になっていた。
そんな中、両親の結婚記念日が迫っていた。
何より今年は特別。
結婚して50年、金婚式を迎えるからだ。
この間、二人が住む老人ホームへ行った時の事だ。
二人の様子がなんだかおかしい。
どうしたの?と聞いても、「心配するな!」の1点張り。
心当たりがあるとするならば…。
弟のことではないだろうかと思う。
弟は、今年40になるにも関わらず、未だに花の独身貴族を貫いている。
本人曰く、結婚願望は全くないらしい。
だが両親は、特に母は家庭を持つこともせず、相変わらずフラフラした生活を送っている弟のことが気がかりなようだ。
実際、雑談をしていても、弟のことが出てくると少しずつ顔が曇っていくのがよく分かる。
何とかできないだろうか。
私はリビングに掛かるカレンダーを見つめながら、そんなことを考えていた。
ふとある事実に思い当たる。
私は弟に電話を掛けるべく、スマホのロックを解除した。
結婚記念日当日。
私は弟と一緒に老人ホームにやってきた。
今日の両親は顔色が良く、ホッと胸をなで下ろす。
弟はあまり乗り気ではないらしく、無表情を気取っていながらも言葉の節々がとげとげしい。
母から、結婚しないのか攻撃が発射されるのではないかと、気が気ではないらしい。
事実、母は弟とあまり目を合わせようとしない。
この作戦をきっかけに、少しでも関係が変わってくれたらいいんだけど…。
しばらく他愛のない雑談を交わした後、私はニコニコしながら、あるものをテーブルに載せた。
それは、直径20センチほどのホールケーキで、イチゴと生クリームたっぷりの定番ケーキが箱の中に収められていた。
「父さん、母さん。今日何の日だと思う?」
「そりゃあ、俺たちの結婚記念日だろ?」
「それも正解だけど、もう一つ忘れてない?」
「えっ?他にあったか…?」
眉間に皺を寄せながら考える父を尻目に、私はあるものを袋から出し、いそいそと準備をする。
すると、弟がぶっきらぼうに口を開いた。
「今日は…、俺の誕生日だよ。忘れたのか?」
あーそうだったわね、と呟く母と、あー忘れてたよ、という表情を見せる父。
私は言う。
「せっかくだからさぁ、一緒にお祝いしてくれる?」
二人はこくんと頷いた。
そうして私は、ケーキに刺さっているロウソクに火をつけた。
カーテンを閉め、灯りを消したところで、ハッピーバースデーを皆で歌う。
齢70を過ぎた高齢者と、中年に差し掛かったいい大人が誕生日を祝う場面は、さぞかし滑稽に見えるだろう。
「誕生日おめでとう!我が弟よ」
「おぉ…ありがとう」
さぁ本番はここからだ。
弟が思いっきりロウソクを消した。
火が消えた瞬間、私は部屋の電気を付けた。
「!!!」
両親の顔が驚きに包まれている。
「その…おめでとう。金婚式」
そう言った弟の顔が薄っすら赤くなっている。
ホールケーキの真ん中を見ると、
「金婚式おめでとう」と書かれたチョコプレートが載っている。
弟がロウソクを吹き消したタイミングで、私が置いたのだ。
二人は、驚きと嬉しさが同居した表情を浮かべながらありがとう、と頭を下げた。
その様子に、サプライズは成功したと確信した。
父がポツリと言う。
「俺たち…、まだまだ長生きせんとな。なぁ母さん」
母も頷く。
「それもそうだけど…」
そう言って母は弟を見た。
「今日はあんたが主役よ。誕生日おめでとう」
思いも寄らない言葉を掛けられた弟は、照れ隠しなのかただ頷いただけだ。
それでも、両親と弟の間に流れる空気は今までの中で一番温かく感じた。
帰り道。
私たちは夕日暮れる一本道を、並んで歩いている。
「姉ちゃん」
「何?」
「実はさ、俺言わなきゃいけないことがあって」
弟の顔を見た。
その表情には、何か決意めいたものが浮かんでいる。
「うん、実は…」
私も弟もそれぞれ、ままならない事情を抱えながらも、日々の生活は続いていく。
いつか、今日という日がこれからの希望として、光輝いてくれることを願いながら。
(了)
よろしければサポートを頂けると幸いです。 頂いたサポートは、自分や家族が幸せになれることやものに使わせていただきます。
