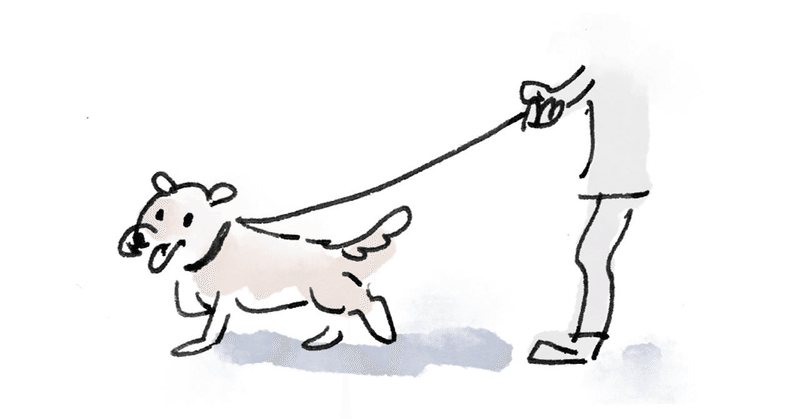
短編小説「モーニングルーティーン」
朝の空気が冷たくなり、日の出が遅くなってきた。夏の終わりと秋の気配を告げる風を顔に受けながら、今日も5時頃に起きてランニングに出掛ける。
家からすぐ近くの公園に行く。家を出て左に曲がればすぐ下り坂に入る。細い道が続く住宅街を抜けると、その先に公園がある。
毎朝この公園で走るのが日課だ。野球場のフェンスの外側と桜並木の間が遊歩道になっていて、そこを走るのだ。これだけ早い時間だと人はほとんどいない。緑の豊かな空間を独り占めすると、辛い早起きの憂鬱さを忘れる。
でも今日はいつもいっしょだったムギがいない。ムギは自分と同じ16歳だった。小さな雑種の犬で毎朝いっしょに走っていた。
この1週間はひどく落ち込んでいた。朝のランニングも1週間ぶりだった。
今日は走る時に下を見ることはほとんどない。前だけを見て走ればいいのだ。いつもはじっくり見られなかった草花の緑が、太陽の光に照らされて輝き始めていた。
まだ、いつもの半分も走っていないのに寂しくなってしまった。そのうち涙が溢れそうになった。
ペットを飼う時から宿命づけられているのだ。いつかは亡くなる。ペットを飼った者にしかわからない乗り越えなければならないハードルなのだ。
「今日はもう帰ろう」
家に帰って洗面所に向かった。冷静になると人は気持ちの整理ができるというが、顔を洗った後に感情が一気に押し寄せてきた。
タオルで顔を拭いても、目の周りがすぐに濡れてしまう。母が洗面所に入ってきたので、顔を背けながら焼てて化粧水を顔につけた。
「あら、走ってきたの?」と母が言うので、「うん。少しだけね。」と私は答えた。
テーブルには朝ごはんが準備されていた。
「いただきます」
冷えた体に味噌汁の温かさが身に沁みた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
