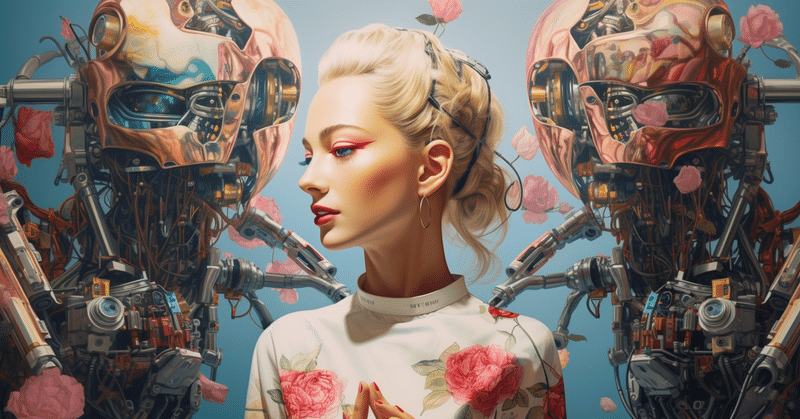
メランコリー・ノスタルジー・ファンタジー #シロクマ文芸部
文化祭の後片付けで夜八時まで学校にいた。
昼の底が朱く吹き抜けた。朱の上が黒冷えした。僕はそれを仰ぎ見てばかりいた。こういう行事は準備してる時が一番楽しいんだよな、と、ため息交じりにかれこれ百二十回くらい唱えた。
家に遊びに来た友達が帰ったあと、それ以前の喧騒から一層静謐さを増す部屋にひとり取り残されて、みんなで食べ散らかしたお菓子の後片付けをする、その何とも言えない胸の空白、虚無感ともいうべき感覚。それとさらに、この祭りのためにかけた時間、絞った脳みそと労力を振り返る、夕暮れの水平線を冷たい海風に吹かれながら見渡すような、目を細めたくなるような感覚、そして微かな後悔。ついに終わったという言葉の中に、物体の後片付けをするという単純作業の傍らに、片付かない感情が居座り腕組みしている。片付かない感情を、一体いくつ胸に畳み込んで、いつの間にか忘れてしまうのだろう。ばねのようにたわんで心にしまわれた感覚を、すうと版画のようにうつして、額に入れて胸中に飾って、青春という題をつけるのだとしたら、それは甚だ馬鹿げている気がする。かといってこの気持ちをどう表出するともわからない。ただ僕はこういうものを扱いかねている。
空のどこかで、よだかの星が鳴いた。鳴き声は慟哭となって夜の底を揺らした。さながら、太陽にもう一度地平から顔を出して、同じ日をもう一度繰り返してほしいとせがむかのように。よだかは別に文化祭には関係ない。僕のこの気持ちとも関係ない。だいたい僕はあの話をあまり好いていない。こんな馬鹿なことを考えるのも、空にかかる夜のせいだろう。
いつもは静かな時計の秒針が、やけに声を張り上げて存在を主張する。僕は壁から時計を下ろして、僕がこれから片づけるべき厚い黒幕でしっかりと包み、教卓の上に置いた。窓の外を覆った夜への贈り物だった。この夜の下に目を閉じたたくさんの生き物の上、星々の虹が静かにかかっている。
風。そしてあなたがねむる数万の夜へわたしはシーツをかける
誰の俳句だったか忘れた。三十秒くらいじっと突っ立って思い出そうとしたが駄目だった。そうだ、今時間はあつあつのトーストに塗ったバターのように引きのばされている。もう一度太陽が昇ったら、時間は再び矢のように過ぎ始める。今だけだ。今だけなんだ、今のこの気持ちは。扱いかねるこの気持ちも、もう一度太陽が昇ったら、強烈な陽光に灼かれて色褪せるだろう。
それに対して何らかの感情が湧いてくるのを待ってみたが駄目だった。文化祭のお開きの時には涙が湧いてくるかと思っていたがそれもなかった。僕はまた、これのために命を捧げるというような勢いで準備した祭りの後片付けをし始めた。
ちょうどその時箒に跨った淑女が窓の外を通り過ぎて、道に迷って泣いていた一匹の白蛇を抱き取った。ちょうどその時碧の目をした猫が夜空に飛び上がって月に足跡を残した。ちょうどその時地中から顔を出したもぐらは、太陽の戦車の燃える明るさに目を瞬いた。この時の僕は、確かにその光景がどこかで繰り広げられていると思った。
僕らの見逃していることの、なんと多いことだろうか。こんなにいっぺんに、たくさんのことが起こっているのに。
僕にはわからない。青春の二文字は呪いのように、僕らの未来を現在に引き換える。こんなにいっぺんに、たくさんのことが起こっているのに、それを僕らは殆ど全部見逃しているのに、ぺったりと視界を版画にして額に入れて、青春の二字を題にあてる。そうしなければ強烈な明日の陽光に灼かれて、すべてが色褪せてしまうんだろう。
僕はただ、生きているだけだ。人生している、だけだ。
文化祭の後片付けで、結局夜八時まで学校にいた。休日の長い眠りが、夜八時の不思議な幻想をすべて洗い流してしまって、次の日に学校に行った僕は、もうすっかり元通りの僕だった。ただ、教卓の上に置かれた黒い包みだけが、文化祭の名残を投げかけた。
了
こちらの企画の参加です。幽霊部員、正体見たり葵さん、珍しく二週連続なのよ。
今までのはあんまり意味はない。ノンセンス。で、こっちは真剣。私、自分の冗談に真っ先に笑っちゃうのを直したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
