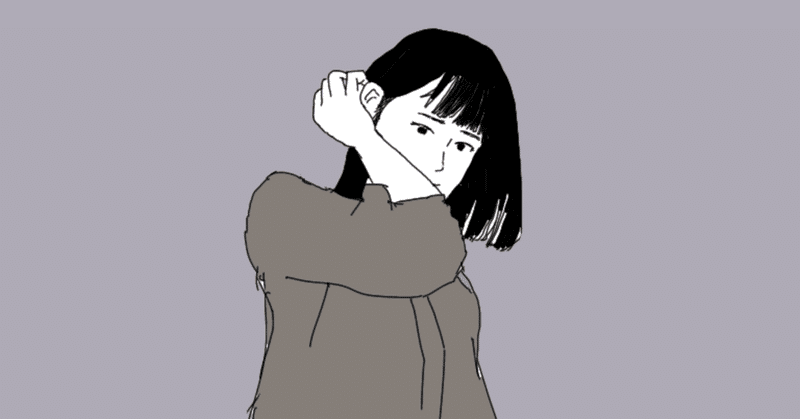
『自傷していたキミと、7年後のボク』
中学2年の時、3回連続で彼女の隣になった。
・・・・・・
彼女の左手首には何本もの”痕跡”があった。
多分、カッターかハサミでやったのだろう。
古そうなのもいくつかあったから、”それ”が始まったのがつい最近ではないことだけが確かだった。
右隣に座っていた僕の視界にはいつもそれがうっすらあった。
彼女はほとんど言葉を発さない。
いつも一緒にいる女子としか話さない。
あとは授業で当てられた時くらいしか声を出さないので、彼女の声をしっかり記憶している人は少ないと思う。
たまに会話しているのを誰かが見ると話題になる、そんなレベルだった。
彼女は「メンヘラ」「病んでる系」だと言われていた。
当時は僕もそう思っていた。
そんなことするやつは、ただの「構ってちゃん」か目立ちたがりなのだろうと。よくないことだが、当時は内心馬鹿にさえしていた。
彼女は学校に来たり、こなかったりで、「最近来ないな」と思っていたら1週間毎日きたり、逆もあった。彼女の仲間によると保健室登校の日もあるらしい。
そんな彼女と話した、数少ない記憶の中で、
とても印象に残っていることがある。
隣の席の僕はよく彼女の休み明けにプリントを渡したり行事の説明をする役割を持っていた。だから僕は彼女の声を実はよく知っていたのだ。
それは多分、昼休みの図書室だった。
その日僕は友人と喧嘩をしてその場に居づらくなり、図書室に逃げ込んだ。
授業以外で図書室に行ったのはこれが最初で最後だった。
そこに彼女がいた。一人で本を読んでいた。
本を読むのもなんだし、だけどまだ時間があるしで、
手持ち無沙汰な僕は彼女に話しかけた。
「何読んでるの」「昼休みはいつもいるの?」
そして、「”それ”はどうしてなの?」と。
聞いた瞬間、やってしまったと思った。
少なくともいい気はしないだろう。
でも彼女は答えてくれた。一瞬困惑の表情を見せたあと、こう言った。
「生きてるって感じがするの」
意味がわからなかった。死にたいんじゃないのか?
少なくとも「生きたい」と思っているやつがすることじゃないだろう。
本当に頭がおかしいのか、僕は混乱してそれ以上そのことについては聞くことができず、「そうなんだ」とだけ返して、「じゃあ午後の授業でね」と、その場を後にした。
午後の授業は美術だった。
ちょうど、彫刻刀を使う作品を作っている最中だった。
僕はこの日のことをよく覚えている。
彫刻刀を見つめては、左手首にあて、彼女の言葉を反芻していた。
そこを切れば血が出る。手首には大きな血管があり、大量失血で死にいたることもある。だから死にたい人はそこを切るのだ。ドラマでそんなシーンを見たことがある。死にたいから、切るのだ。
でも彼女は言った。「生きている感じがする」と。
彼女とはその後何度か会話をしたがよく覚えていない。
その日の印象が強すぎたのと、彼女の印象が僕の記憶の中で薄いのと、どっちもあるだろう。
その時、少なくとも、それから7年間では、彼女の言葉など、ましてや彼女のことなど、これっぽっちも覚えていなかった。
7年後、僕は心の病にかかった。
常に漠然とした不安に襲われ、考えても意味がないようなことを永遠に考えては体が震え、眠ることができず、不安や恐怖に震え続け、疲れ果てた頃に気を失うかのように眠る。そんな日が続き、常に頭の中にモヤがかかっているようで、まともな思考ができなくなった。
外出も困難になり、毎日死にたいと思うようになった。
何をしても楽しさを感じなくなり、そこから徐々に悲しいとか苦しいとか、そういうネガティブな感情さえ薄れてきた。もう、これじゃ自分が存在していること自体怪しいな、とか意味がわからないことを考えだすようになったある日、本当に、なんでかわからないが、ふと思い出した。
「生きてるって感じがするの」
なるほど。無感情で思考が曖昧な僕は搾り出すようにそう、納得した。
彼女は手首を切ることで、自傷による痛みや出血といった痛覚や「苦しい」という自己反応で「生」を感じていたのかもしれない。そう思った。
完全な憶測だが、彼女は当時、今の僕と同じ状況だったかもしれない。
なぜなら、僕も同じことをしようと考えたからだ。
結果的にそこには至らなかったが、彼女のことがなんとなくわかった気がした。
それからさらに1年経って、僕はそこそこ良くなった。
学校にも行けるようになった。感情も、ある。
でも、いまだに「生きること」のしんどさは抜けない。
僕にとって「生」は重すぎる。
死にたいとは思わないが、生きている感じがしない時がある。
平均寿命まであと60年余り、僕にとっては懲役に等しい。ああ、無情だ。
どうせ死ぬのなら、いつでもいいじゃないか。でも、死にたくはない。でも、生きたくもない。でも、何か、何かが欲しい。その、「生きている感じ」があったら、少しは楽になるのだろう。それは楽しいことでもいいし、痛みでもいい。とにかく、死ぬか、生きるか、どっちかにしたい。だからせめて、せめて、マシな方をくれ。
そして、そういう時は決まって彼女の言葉を思い出す。
「生きてるって感じがするの」
彼女、いや、石井さん、わかったよ。
多分、「そういう」ことだったんでしょ。
fin
・・・
2000文字にお付き合いいただき、ありがとうございました。
僕の実体験をベースにちょいちょいフィクション(名前)を混ぜて、自分の生きづらさや、「生」への葛藤を書きました。
決して、自傷行為を推奨したり、自殺を仄めかす意図はありませんし、一切の責任は取れませんのでご了承ください。
私の「生きづらさ」です。
生活費になります。食費。育ち盛りゆえ。。
