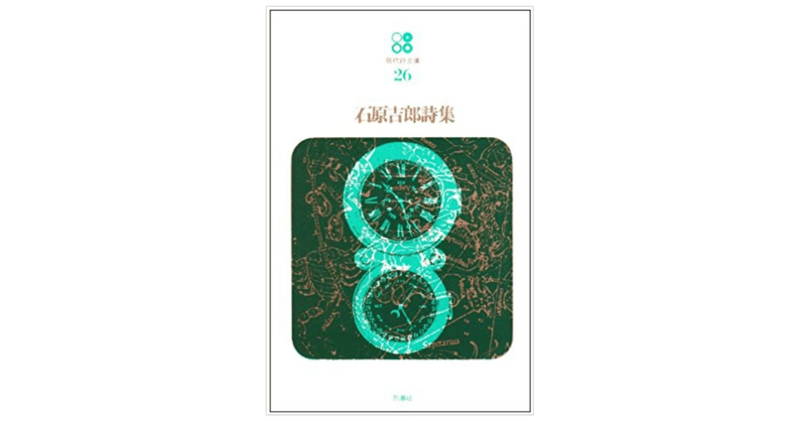
サンチョ・パンサにロシナンテはいない。
『石原吉郎詩集 』(現代詩文庫 第 1期26)
古本屋のワゴンで100円で手に入れたのだが、衝撃を受けている。それを言葉にすることができるのだろうか?すこしづつ整理していく。
ある人のツイートで『シベリア抑留とは何だったのか』が紹介されて興味を持つ。
『石原吉郎詩集』から「サンチョ・パンサの帰郷」を読む。
事実
そこにあるものは
そこにそうして
あるものだ
見ろ
手がある
足がある
うすらわらいさえしている
見たものは
見たといえ
けたたましく
(『石原吉郎詩集』「サンチョ・パンサの帰郷から)
難しい言葉はないものの具体的なものは見えない。想像するしかない。ただ「うすらわらいさえしている」という不気味さは、事実と取っていいのだろうか?事実が作者を逆手に取って笑っているように感じる?
総題の「サンチョ・パンサの帰郷」ということから、詩人はサンチョ・パンサを模している。ドン・キホーテは、日本軍?うすらわらいさえしているのは、事実を突きつける者だろう。
「もしあなたが人間であるなら、私は人間ではない。もし私が人間であるならあなたは人間ではない。」
これは、私の友人が強制収容所で取り調べを受けたさいの、取調官に対する彼の最後の発言である。その後彼は死に、その言葉だけが私のなかに残った。この言葉は挑発でも、抗議でもない。ありのままの事実の承認である。(石原吉郎『石原吉郎詩集』「三つのあとがき」)
その取り調べ室を想像してみる。なんと過酷な言葉だろう。「人間止めますか?」に匹敵する。というか予めに判決は決まっているのだ。カフカの作品のようだ。カフカもサンチョ・パンサに魅せられた作品があった。
それは何もシベリア勾留でもない。その人間であるか、ないかのふるい分けは、この社会でも行われいるような気がする。もしかしたら自分自身でもふるい分けしているのかもしれない。SNS上のログで絶えず問われるもののような気がする。「もしあなたが人間であるなら、私は人間ではない。もし私が人間であるならあなたは人間ではない。」。システム化され白黒だけで判断する二分法的を求める社会。その中間色を無くす。敵か味方か?
石原吉郎の悲劇は、シベリア勾留だけではない。日本に帰郷してからも、もはや死者なのか生者なのかわからないような差別を受けた。抹殺したい記憶。
危機の観念だけでは生活は展開しない。はじめからすでにわかりきっているようなこのりくつを。あらためて思い知るためには、ともかくも一応の行きづまりを必要とする。行きづまる過程は、劇的な場面の中ではなくて。日常のたいくつな空気の中で進行する。進行に気づいた時は、すでに一方の極に達していのだ。(石原吉郎詩集「1960年ノート」より)
石原吉郎の詩よりも日記に衝撃を受けた。それは意識化させては絶望しながら、それでもなお生活し続け生きていかねばならない。ドン・キホーテを背負って。
その重さに耐えられなくなってプロテスタントのキリストに救いを求める。キリストは、ドン・キホーテなのか?
石原吉郎の憤りは、巣鴨プリズンの戦争犯罪人に向けられる。「戦争犯罪人」でもシベリア送りにされた者は、その後の名誉回復もなされぬまま、シベリアが汚点でもあるかのような差別を受けた。一方巣鴨プリズンの犯罪者たちのあるものはアメリカの手先になっていた。そして帰郷するやいなや、親戚からまず「赤」でないかを問われた。さらに精神的な親代わりになるとまで言われた。戦争犯罪人として強制収容所に入れられ、生きてきたことへの虚無感。彼はそれを病いだろうと思っていた。だから精神的な救いを、プロテスタントのキリスト教に求めていく(もともと戦前からのキリスト者だった)。その中でも収まりのつかない言葉が詩となっている。しかし、後にかれは沈黙を選ぶようになった。
さらに読み続けなければならないと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
