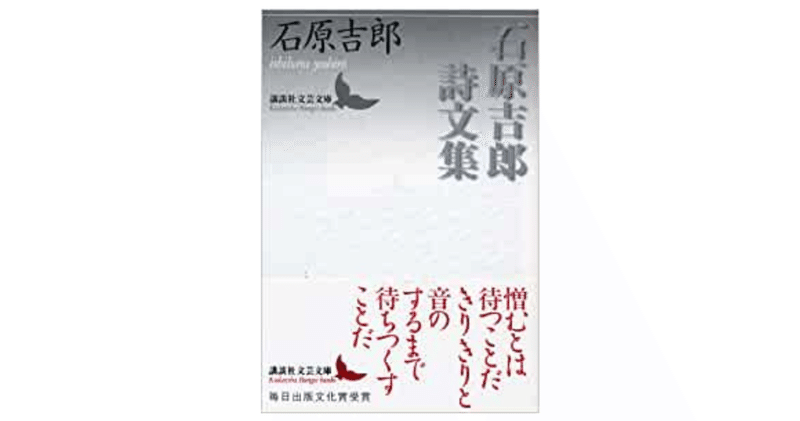
ドン・キホーテに成り損なったサンチョ・パンサ
『石原吉郎詩文集 』(講談社文芸文庫)
憎むとは待つことだ
きりきりと音のするまで
待ちつくすことだ
詩とは「書くまい」とする衝動であり、詩の言葉は、沈黙を語るための言葉、沈黙するための言葉である――敗戦後、8年におよぶ苛酷な労働と飢餓のソ連徒刑体験は、被害者意識や告発をも超克した<沈黙の詩学>をもたらし、失語の一歩手前で踏みとどまろうとする意志は、思索的で静謐な詩の世界に強度を与えた。この単独者の稀有なる魂の軌跡を、詩、批評、ノートの三部構成でたどる。
石原吉郎
海が見たい、と私は切実に思った。私には、わたるべき海があった。そして、その海の最初の渚と私を、三千キロにわたる草原(ステップ)と凍土(ツンドラ)がへだてていた。望郷の想いをその渚へ、私は限らざるをえなかった。(中略)1949年夏カラガンダの刑務所で、号泣に近い思慕を海にかけたとき、海は私にとって、実在する最後の空間であり、その空間が石に変貌したとき、私は石に変貌せざるをえなかったのである。(中略)望郷のあてどをうしなったとき、陸は一挙に遠のき、海のみがその行手に残った。海であることにおいて、それはほとんどひとつの倫理となったのである。――<本文「望郷と海」より>
詩の定義
石原吉郎ほど「詩とは何か」を考え続けた人はいないのではないか?その解答が詩は、「書くまい」だった。アウシュヴィッツ詩人パウル・ツェランに繋がるかもしれない。
詩における言葉はいわば沈黙を語るためのことば、「沈黙するたの」ことばであるといっていい。もっとも耐えがたいものを語ろうとする衝撃が、このような不幸な機能を、ことばに課したと考える。いわば失語の一歩手前でふみとどまろうとする意志が、詩の全体をささえるのである。
詩集『サンチョ・パンサの帰郷』の衝撃。
事実
そこにあるものは
そこにそうして
あるものだ
見ろ
手がある
足がある
うすらわらいさえしている
見たものは
見たといえ
けたたましく
コップを踏みつぶし
ドアをおしあけては
足ばやに消えて行く 無数の
屈辱の背なかのうえへ
ぴったりおかれた
厚い手のひら
どこを逃げていくのだ
やつらが ひとりのこらず
消えてなくなっても
そこにある
そこにそうしてある
罰を忘れられて罪人のように
見ろ
足がある
手がある
そうして
うすわらいまでしている
(『サンチョ・パンサの帰郷』から「事実」)
ある〈共生〉の経験から
石原吉郎の詩は一見やさしい言葉で書かれているように感じる。それは石原吉郎が影響を受けた堀辰雄や立原道造の影響だと思われる。詩のリズムを大切にする詩人は心地好いリズムの中に悪意を潜める。それは人間の本質なのだろうか?
詩よりも石原吉郎がエッセイとも批評ともつかぬ散文によって石原吉郎の詩の解釈となるようだ。いや、解釈をしてはいけないのかもしれない。解釈できない世界があるのだ。そうした問いを我々に突きつける。
それはシベリア抑留という誰もが経験出来ないことなのだ。その世界では弱いものが共生するしか生きていく道はない。何に共生するのか?捕虜とも囚人ともつかぬ人間でないもの。
それは親友である鹿野武一が取調官に放った言葉。
もしあなたが人間であるのなら、私は人間ではない。もし私が人間であるなら、あなたは人間ではない
捕虜(囚人)生活で身体的な危機を乗り越えても、精神的な危機は拭い去れないという。他者に対する不信感と他者を排除して生き延びてきた懺悔と、そこは個人というものが否応なしに剥奪される場なのだ。人間ではない集団の中で生き延びなければ収容所。
〈人間〉はつねに加害者のなかから生まれる。被害者のなかからは生まれない。人間が自己を最終的に加害者として承認する場所は、人間が自己を人間として、ひとつの危機として認識しはじめる場所である。
加害者がシステムに逆らって人間になろうとするとき、しかしシステム全体は人間になるわけではない。人間である孤独と孤立を引き受ける彼は英雄なのだけど除外されるのだ。
そして被害者は死を待つより、その生のシステムに従属しなければならない。人間でなくなるのだ。この逆説を理解することは難しい。それほど衝撃的な言葉なのだ。石原吉郎の詩の衝撃性はそこにあるようだ。
そして彼も日本に帰郷した。植物の感情だという。動物のように意志的なものを持つのではなく、移植されるのだ。そして故国の記憶は、そのままに戦時の日本だった。むしろ考えない人間であるからこそ生き延びたのかもしれなかった。
関係を断ち切られたのは向こう側からだという。あんなにも憧れた日本の故郷。そうして彼も日本で孤独を選ばねばならなかった。
ノート(日記)
日記は(1956年から1958年の日記と1959年から1962年のまでの日記)自己内対話で延々と積み上げては壊すシシュポスの虚無だった。しかし、石原吉郎はそれを認めることが出来ない。だからドストエフスキーを読みキリスト教に帰依したいと願うのだ。だがドストエフスキーの精神を抱えたままキリスト教には帰依できるはずはない。
そこに文学はあった。ただ石原吉郎が選んだのは沈黙としての詩だったのだ。
信仰のユーモアについて。ユーモアと真剣に取り組むことは、けっして滑稽なことではない。ユーモアを「真剣に」扱わなればならないことに深いユーモアがあるのだ。それは「あたたかいユーモア」というような情緒的なものではなく、人生のリアリティというものは、結局ユーモアでしか理解できないということなのだ。
この日記から後藤明生『『笑いの方法 あるいはニコライ・ゴーゴリ』を連想した。ゴーゴリがまさに生き方としての喜劇を描いたのだと後藤明生がいう。ドストエフスキーが言ったように、「われわれは皆ゴーゴリの『外套』から出て来た」のだ。それがカフカの笑いであり、後藤明生の笑いであった。
石原吉郎が詩(韻文)の世界ではなく小説(散文)の世界にいきていたならば、もう少し違う人生を歩めたかもしれない。しかし彼はセルバンテスではなく、ドン・キホーテでもなく従者のサンチョ・パンサを選んだのだ。ゴーゴリやドストエフスキーになろうとどっちみち悲劇だったのかもしれないが。
詩的言語の悲劇性を強く感じる石原吉郎だった。
関連書籍
『石原吉郎詩集 』(現代詩文庫 第 1期26)
郷原宏『岸辺のない海 石原吉郎ノート』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
