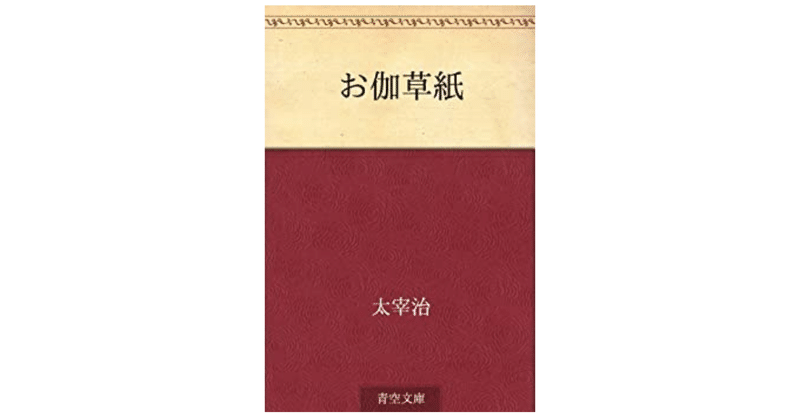
「お伽草子」、同じ阿呆 (あほ) なら踊らにゃ損々
『お伽草子』太宰治
「無頼派」「新戯作派」の破滅型作家を代表する昭和初期の小説家、太宰治の短編小説。初出は「おとぎ草紙」[筑摩書房、1945(昭和20)年]。5歳の女の子のために絵本を読んで聞かせる父は、その胸中におのずから別個の物語が出現する。「瘤取り」「浦島さん」「カチカチ山」「舌切雀」といったお馴染みのおとぎ話が太宰流にアレンジされている。
太宰治が戦時中に防空壕という閉じられた世界(作家としても自由に表現できない検閲があったり日本全体が閉じられていた)で絵本の童話を娘に読み聞かせると体裁を取った語りだが、太宰の想像世界の中で開かれた文学となっている。太宰の傑作短編を自由に想像して楽しもうじゃないか。
『瘤取り』
家族に相手にされず一人で酒を飲んで気を紛らわす爺さん。妻は模範的な家庭の主婦で息子は品行方正な聖人。そんな中で酒を飲んでは酔っ払わなければやっていけない老人。左ほっぺに出来た瘤が慰めというわけだった。孫のように可愛がっている。
『寄生獣』という漫画があったが、あの先駆けだった。普通の人は病気だとして取り除こうとするが放置する。『寄生獣』は本体を乗っ取ろうとするわけだが『瘤取り』は爺さんそのものだから、乗っ取られる心配もない。異物ではなく、身体の一部で愛すべき出っ張りなのだ(ペニスと言ってもいいかもしれない。射精しないペニス。)
その頃の男としては失格な人間なのだが、酒を飲んで酔っ払って鬼たちの間ではヒーローになっている。アングラ的な世界で才能を発揮する人。でも、鬼たちはその宝のような爺さんの瘤を取ってしまう。次に会う約束だと言って。
もう一人の爺さんは質実剛健で戦時に先生と呼ばれるぐらいの爺さんだ。ただ瘤は異物として邪魔な存在なだけであった。彼が「瘤取り」爺さんの話を聞いて鬼の里に出かけ舞を舞うが、どうも鬼たちの気分にそぐわない踊りだった。舞と踊りの違い。一人合点の舞(それも平家物語の鬼退治のような舞)は、鬼たちには恐怖心を起こさせた。同じ文化を共有していないからだ。踊りは共有出来るリズムと歌があったのだろう。鬼たちは逃げ出し、追っかける爺さんに瘤を返した。
『浦島さん』
これは竜宮城の描写がいい。黄桃の実が落ちてきて紫の花が咲き乱れ、それは酒の代わりになって、藻はいろんな味があって(うまい棒か?)それを花の酒に調合するといろんな味のカクテルになる。戦時にこんな夢見たいな世界が描いていたのだ。そして海底の無重力性。
魚の糞で出来た山は真珠の山で、乙姫さんが出迎えると後は勝手に過ごしていいという。無理にもてなしたり料理を強制したりしないで、魚たちは勝手踊って音楽も聴こえてくる。それなのに陸に帰りたくなる。家族がいるからかな。
ギリシア神話の『パンドラの箱』と比較して、煙だけで「希望」も何も残らなかった。ただ300歳という年月だけ。それは乙姫の復讐だろうか。『パンドラの箱』はゼウスの復讐なのである。ただ「希望」が残ったにすぎない。玉手箱は、忘却するだけである。これ以上にない幸福なのか?それから10年も生きるんだよな。310歳にもなれば不幸とか幸福なんて概念はない。
今だったら悪徳ポリスにイジメられる亀を助けたら、麻薬の売人だった亀の元締めの乙姫御殿に案内されて、薬中になって、玉手箱をもらって娑婆に戻って開けたら、どうなるでしょう(想像力が膨らむ)。
実は玉手箱は自爆装置だった。煙と共に上がったのはテロリストとして利用されたジハードの名誉だけでした。でも、それはこの世界では通用しないものでした。無駄死にというやつです。
『カチカチ山』
兎は16歳処女なんだが悪魔のような女だという。狸は37だけど、ホラ吹きで間抜けで馬鹿で色黒。モテない狸が惚れたがために酷い目にあう。でもその前に婆さんを汁にして食っちまったんだっけ。何回も読んでいるはずなんだけど、演劇も見ているはずなのだが詳細なことは忘れている。
狸も兎を見ると幸福感いっぱいで過去は忘れてしまう。これはモテ男太宰としては逆のパターンだけど、そうやって女をイジメて楽しんでいた。だから惚れたら悪いかという狸のセリフ。死んだのは惚れたせい。狸が女が。関係性だから。嫌いというのも脈がないことはない。
河合隼雄の本にも出てきた。本当に嫌なら付き合わない。付き合うといのは何かしら関係性が生じるのだから。サド・マゾの関係で愛と言えるかもしれない。一方的な愛なのだが。狸は死ぬ前にそのことに気づいただけだ。愛なんてこんなもんだ。人生もそれに通じる。兎は16歳にして殺人者になってしまった。愛とは何か知らないうちに。
『桃太郎』
「桃太郎」は書かれていない。そんなことはないのです。書かないことを書いた居合抜きみたいなものです。日本一の「桃太郎」を書かないことを書いて、「桃太郎」を斬ってみせた。桃太郎は書けないというメタフィクションなのです。それを語り手が書いているのを読めばいいのです。「脱構築」された『桃太郎』なのです。
『舌切雀』
これは介護小説だった。40にならないのに自分では身動きできない男。その介護をする女も33歳だった。その介護する女が男を爺さんと呼ぶ。爺さんも婆さんと呼ぶ。そこに一羽の雀(ヘルパーさんだと思う)がやってきて、爺さんと楽しそうに会話している。婆さんが嫉妬して、その雀の舌を抜く(解雇する)。
爺さんは雀に会いたくて、雪の日に外に出る(ボケ老人の迷子のパターンです)。藪の手前で倒れる。
そこで語り手と読者代表が爺さんをどうにかしろとメタフィクションで話の続きを書くようになる。読者代表の娘が案内役となって登場し、お鈴ちゃん(舌切雀)に会わせる。そこで爺さんは久しぶりに会話を楽しんで、お土産も貰う。稲穂なんけど思い出の稲穂。それを婆さんがやっかむ。
婆さんが爺さんの行動を確かめるために行動する。爺さんの虚言癖だと思っていたのだ。また女がいる口実だとも。それで若返って外に出たりして(これは書いてないけど、たぶんそんなことを思った)。それで舌切雀に会いに行く。お土産は大きな箱をもらった。中身は金だったが重すぎて、婆さんは死ぬ。
爺さんはその金で政界に出て大臣になったとさ。それも内助の功の婆さんのお陰で。面白いけどどう思ったらいいんだろう。爺さんの妄想だったとして、婆さんは夢の中で死んだのかな。舌切雀は妄想だ。婆さんは本当に死んだのか?死んだとしたら自殺だよな。介護疲れ。そして、爺さんも夢を見たのかもしれない。自分がこの悪政を変えなきゃと。
舌切雀はヘルパーさんだった。お喋りばかりで仕事はしないから介護会社に解雇された。でも爺さんはその会話が楽しかったのだ。これは、家庭に介護を押し付けた政府が悪い。舌切雀にしても労働条件最悪で低賃金で働かねばならなかった。現代だとこんな感じ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
