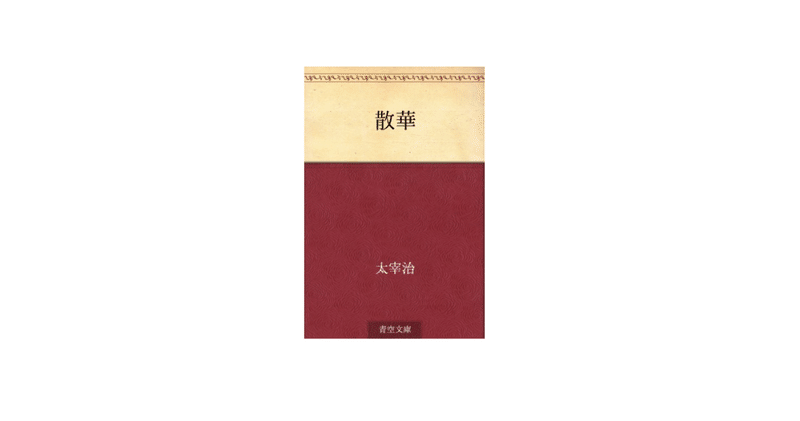
花よ散れ!玉砕ではなく散華として
『散華』太宰治
初出は「新若人」[1944(昭和19)年]。小説を書いていた三井君の病死と詩を書いていた三田君の玉砕という、「私の」二人の若い友人の別れが描かれた作品。一見、時局に迎合したものにも思えるが、時局におもねりつつ巧妙に自身の創作への思いを織り込んでいる。
NHKラジオ:特集番組『高橋源一郎と読む 戦争の向こう側2022』を聞いていたら、太宰治の小説が戦争文学だったという高橋源一郎氏の指摘には納得した。太宰の執筆時期は戦時でほとんどの作家が思うように書けなかったのだが、諧謔と自虐を本領とする太宰は日常を描きながら戦争を描いていた。この日は、その太宰治の三作品の紹介。
『十二月八日』『散華』『惜別』。
『十二月八日』
昭和十六年の十二月八日(太平洋戦争の開戦)の妻の日記を紹介しながら、当時の主婦の様子と作家(太宰か?)の滑稽譚として、面白く読める。その内容はかなり辛辣で銭湯の夜道の街頭が暗いのに、作家は日本精神を持っていれば明るい道が見渡せると言ったが、その顛末は真逆だった。太宰が日常を描きながら戦争を描いていたという代表的作品。
『散華』
今回が初めて読む。太宰の作品は、結構読んでいると思ったが、まだこのような凄い作品があったのだと知った。
「散華」は戦時には「玉砕」と同じ意味に用いられていたという。もともとは仏教用語で、「法要の時などに仏を供養するため花を撒き散らすこと」の意味で、若くして病死で亡くなった三井君を見送る文章を書き上げる。
そして当時は、若くして戦死する事の婉曲表現として「玉砕」では強すぎるので、「散華」を用いたと太宰も説明する。このへんが言葉にこだわる作家性の太宰ならではのおもしろさ。
そして、実際に「玉砕」する「散華」として三田君の手紙と共に紹介する。その三田君が詩を書いていたのでそれを作品集として出そうという先輩詩人(太宰とは親友?)が言い出すので、それならば詩よりも手紙がいいと太宰は思うのだった。それは書くことよりも(太宰に対して)、日本の精神に則る行為としての自決(自身の行為)の正当性を書いているようでもあり、太宰がそれをここで載せることは、彼の手紙をも作品(詩)としての正当性を訴えてくるものだった。
大いなる文学のために、
死んで下さい。
自分も死にます、
この戦争のために。(『散華』太宰治)
その手紙の書き置きが詩であるという未練がそのまま、例えばランボーの手紙のように、響いてくるのだ。なにより、その手紙は、詩よりも詩的な言葉で彩られていたのかもしれない(当時の戦争詩のたぐいは大きな言葉で自我の言葉を消していく)。そして、なにより太宰治はそれを実践してしまうのだ(パロディとしても)。そこに「玉砕」を「散華」に言い換えた意味がある。
『惜別』
敵国の文学者だった魯迅の若き日のエピソードとして、日本人の先生に学んだ魯迅の作品『藤野先生』を紹介しながら、表向きは敵国の文学者魯迅も日本精神に学んだという体裁を取りながら、その内容は魯迅が日本で受けた差別的感情とそれを超えて尊敬し合う子弟愛を描いたもの。
魯迅『藤野先生』では無意識に集団に寄り添ってしまう自己と変革しようとする自我の対立。そこが個人主義的な文学の導きとなっていく。まさにその本歌取りも言える『惜別』は魯迅へのではなく、戦争へ向かう集団意識への「惜別」なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
