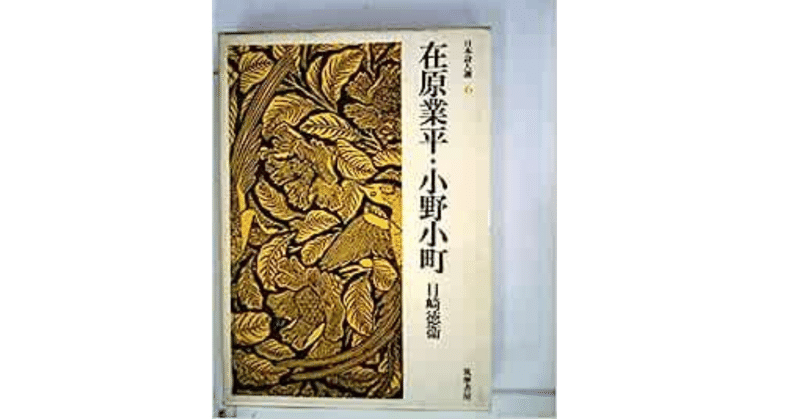
和歌を発展させたスターとアイドル
『在原業平・小野小町』 目崎徳衛(1970年) (日本詩人選〈6〉)
この本は「在原業平」についても「小野小町」についても名著として捉えられていると思うのは(コレクション日本歌人選)の「在原業平」でも「小野小町」でも目崎徳衛のこの本の言葉が引用されていることからもわかる。ただ幾分古い本なので読みにくさはあるし、図書館でないと読むことも出来ないだろうとは思う。
在原業平
『伊勢物語』は在原業平の短歌から創作された二次創作ということだろうか?業平は皇族の息子で恵まれていたが二十歳代で蔵人(天皇の側近)になっていた。しかしその後の十二年間の停滞があり、それが時の権力を握っていた藤原一族の反感を買ったのではないかということだ。そうした日本人の判官びいきによって業平人気は不動のものになり伝説化もされていく。それは斎宮や二条后(高子)との自由恋愛の物語(それはあっさり否定されている)や兄の在原行平の地位的な比較から貴種流離譚を囁かれて『源氏物語』のモデルの一人にもなったのである。
ただ『古今集』以外の『伊勢物語』に掲載されている歌には後の世代が作った歌も多いという。そういう業平像を『古今集』中心に読み解いていくことから恋の達人というよりも人生の折々に詠んだ歌の味わい深さを探っていく(『伊勢物語』では見向きもされなかった中年の業平の歌など)。そうしたことによって業平の歌人としての力量を再評価していく(『伊勢物語』は『伊勢物語』としての面白さがある)。
唐衣着つつなれにしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ
名にしおはばいざ言問はむ都鳥我が思ふ人はありやなしやと
もっとも業平らしいとされる代表作で、この歌の詞書から業平の「東下り」がなにかやんごとなき理由があるのではと『伊勢物語』が書かれた。ただ著者は当時の貴族はふらっと放浪の旅に出るのは珍しいことではなく、まして業平の性格からそういう漂流の旅を好んだのではないかと推測する。
「唐衣」の歌は「折り句」といわれるもので「かきつばた」が歌の中に隠されている。旅の仲間から歌を催促されたので業平の歌による癒やしという解釈である。「かきつばた」にすべて着衣の類語を使い、笑いを取ったのだろうと。業平の和歌のユーモア性はもっと指摘されてもいい。そこに悲劇の「都落ち」を読むよりは臨んでの「東下り」ではなかったのか?ということである。もっとも、都の政治的なことが嫌になったこともあろうが。
世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし
桜花散りかひくもれ老いらくの来むといふなる道まがふがに
同じ桜の歌でも趣が違う。そういうものが業平という歌人の中に存在していたのだ。
さらに代表作と言われる一首も、
ちはやぶる神代も聞かず竜田川唐紅に水くくるとは
は「くくる」は「くくり染め」の意味で業平のサービス精神だという(定家は水を潜ると詠んだ)。紅葉を織物にくくり染めるという奇妙な歌は、皇族の女性たちに大いに受けただろうと想像するのだ。そこには噂の人藤原高子の歌会だったのである。
小野小町
小野小町も後世に語られる伝説の恋歌のアイドルというよりは、当時の女性では珍しく漢文の知識にもあり、まだ新しかった最新の仏教思想にも馴染んでいる知性溢れる女性だったのだ。そんな彼女が普通の男では満足するはずもなく、夢や物語から和歌を作ることが多かった。そこに『古今集』の選者たちのアイドルとなるのだがその人気の反面、鼻持ちならぬ女だと見られることも多かった(アンチも多いのだ)。
そうした小町の伝説は各地にあり、それはアンチが流しただろう玉造小町や卒塔婆小町の創作(デマ)も多いのである(ネット社会を考えれば小町のような男を袖にするアイドルはアンチも多いだろう)実際に確実だと思われる小町は『古今集』とされるが、それも贈答歌として本来ならば独立した歌が並べられれば(何故か坊主が多いが、煩悩を乱す小町というこか?)そのように恋歌として読む方向が決められてくる。それは業平との小町の歌合いがあることからも、『古今集』さえもそういうアンソロジーだったのだ。
また小町は神社に祀られるようになってから念仏仏教の時宗などによって各地に伝えられたようである。それらは巫女や遊女や比丘尼という女性たちの伝承によって「小野お通」として民間伝承されたと柳田國男が述べているのは興味深い。小町神社詣みたいなものだったのか?ますますアイドル歌人だな。
古今的なものについて
正岡子規が『古今集』的な歌を理解しないで直接感情的益荒男ぶりの歌や『万葉集』を持ち上げたのは田舎育ちの子規に季節を巡る繊細さは持ち合わせていなかった(そう著者が書くのだ)。それから日本の詩歌に『古今集』的繊細さは消えて行ったという。芭蕉の季節感を想う気持ちは『古今集』に通じるし、連歌・俳諧は『古今集』に通じる。それは業平や小町のウィット性だし、王朝的な歌と万葉的な歌の通う途上として内に秘めたる(恋)の想いなどが当時の現代人に受けたのである(古今の古は小町や業平の歌だった)。そしてそれを手本として、『古今集』以下和歌が発展していくのだ。以後色好みな業平と小町を生み出すことになるが、その奥底に万人を共感させる「もののあわれや」や季節(人生)の変転があるのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
