
【短編小説】君は、俺が思うほど
友人というには近すぎて、恋人というには遠すぎる――
そんな微妙な距離のままで、臆病な俺は充分だと思っていた……。
いい大人たちの #両片想い の物語。
「天の川は渡れない」
思わず口に出してしまった言葉に、彼女は訝るように俺を見た。
「なによ、いきなり」
まるで不審者を見るような目をこちらに向ける彼女に、少しの苛立ちを覚えて、いつも以上にぶっきらぼうに言い返してしまう。
「どうせ、柄にもないことを、って言いたいんだろ」
「いや、そうじゃなくて、いきなり天の川とか言い出すから驚いたの。しかも渡れないとか、なんとかって……まぁ柄にもないことってのは確かにそうなんだけど」
「あぁ?」
「もう、いい。じゃあね」
むすっとした顔をこちらに向けることなく、彼女はいつものわかれ道を颯爽と歩いていく。
気がつくと、俺の手が彼女の細い腕をつかんでいた。

「どうしたの?」
驚きながらも、気遣うような目で彼女が俺を見つめている。
「悪い、なんでもないんだ」
そう言いながら慌てて彼女の腕から手を離した。そしてもっとマシな言い訳があるだろうと不甲斐ない自分に呆れた。
「なんでもないようには見えないんだけど」
そう言った彼女の瞳の色がグッと濃くなった気がした。
その瞳はまばたきせずに俺をじっと見つめている。たまらずに視線をはずすと、無意識にため息をついていた。
彼女の目は美しい。切れ長の大きい、まるでアーモンドのような形をしたその目は恐ろしいほどに整っている。そしてその奥からのぞく瞳はこれまた恐ろしいほどに澄んでいて、なにもかも見透かされてるような気持ちにさせるのだ。そんな目で見つめられて平気でいられるわけがない。
ため息がふたたび口をついて出た。
思いのほか深くなった吐息に驚いて我に返ると、彼女が俺の顔をのぞき込んでいた。

「ねぇ、やっぱりなにかあるんでしょう?」
俺の目を真っ直ぐ見つめる澄んだ瞳はいつにも増して美しく、ギュッと胸の辺りを締めつける音が耳の奥で響いた。
「君の目はほんとにデカいな」
悩みがあるなら聞く、という彼女の言葉を遮るように言った。茶化すようになにかを言わなければ、身勝手に自分の想いをぶちまけてしまいそうだった。
「ちょっと! なにそれ!?」
さっきまで、不安を浮かべて蒼白くなっていた顔が嘘のように真っ赤になった。そしてぷくっと頬をふくらませ、俺をにらみつけている。
まるで拗ねた子供のような表情があまりに可笑しくて、こらえきれずにクククと小さく笑った。
いきなり笑い出した俺に初めは呆気にとられた様子の彼女だったが、やがてなにもかも俺が酔っているせいだと解釈したらしい。
突然ぐいっと肩をつかまれると、顔と顔が触れそうになるほど近くに引き寄せられた。
「ちょっと、大丈夫? もしかして飲みすぎた?」

そう言いながら俺の背中をさする。
面倒見のいい、彼女らしいその行動がなぜだか可笑しくてふたたび笑った。そして大丈夫だよと告げるようにそっと彼女の腕をなでた。
「お互いそんなに飲んでないだろ」
ジョッキ一杯程度のビールで酔うほど酒は弱くない。
「そうだけど……じゃあ、いったいなんなのよ」
「だから、なんでもないんだ」
こんな答えに彼女が納得しないのはよくわかっている。なにせ長いつき合いだ。長すぎるくらいだ。
けれど彼女が納得してくれそうな言い訳はなにも思いつかなかった。まして本心など言えるはずもない。
「ほんとになんでもないんだ」自分に言い聞かせるようにもう一度、言った。
「そう。わかった」
どうせ問い詰めてもなにも答えないんでしょ、と恨めしそうに見つめる彼女の目が言外に告げていた。
「引き止めて悪かった。気をつけて帰れよ」

そう言いながら彼女に背を向けて歩きだした。
「もう! やっぱり気になる!」
驚いて振り返ると後頭部に手をあてた彼女。かきむしったのか髪が少し乱れている。
「なんだよ。そんなデカい声で」
「誰のせいよ。そもそもあなたが変なこと言い出すからじゃない」
「だから、なんでもないって言っただろ」
思わずぞんざいに言い返して、さすがに言いすぎたかと不安になった。けれど彼女は気に留めた様子もなく、うつむき加減に白くほっそりとした指で唇をなぞっている。
こういうときの彼女はなにか考え事をしている、と長いつき合いからよくわかっていた。
見慣れたはずのその光景が、今日は妙に艶めかしい。
「そうじゃなくて。それはもういいの……いや、よくはないんだけど……今はいい……」
最後の辺りはごにょごにょと口ごもって、声にはなっていなかったが、口の動きでかろうじて読みとれた。
「聞きたいのは天の川! いったいなんで天の川なのよ?」

いきなり彼女が勢いよく顔をあげ、真っ直ぐに俺を見る。
「天の川は、天の川だよ」と言って空を指さす。
彼女が聞きたいのはそんなことではない、とわかっていたが気づかぬふりをした。
「あんたねぇ……ふざけてるでしょ」呆れたように彼女がはぁと息を吐く。
「ふざけるもなにも、天の川は天の川なんだよ」
わざとらしく作った真剣な表情で言うと、いまにもネクタイを締め上げようと彼女がこちらへ手を伸ばしてきた。
俺は苦笑を隠さず、その手をやんわりと押し戻しながら、数時間前の出来事を彼女に話し始めた。
♢
『織姫と彦星ってさ、いわゆるバカップルだよね』
同僚のなんの前触れもないそのひと言に、その場にいた全員の動きが止まった。
ほんのわずかな沈黙のあと、噴き出すような笑い声が昼休みのがらんとしたオフィスに響いた。

突拍子もないその発想に、反論するかのような言葉が口々に飛び交う。といっても皆が皆、こみ上げる笑いと格闘しながらでまともに聞き取れるものは、ほぼない。
俺はといえば、飲んでいたコーヒーを喉にひっかけて涙目になっていた。
『だってそうじゃない? 結婚生活が楽しすぎて仕事なんかそっちのけになってさ、二人で引きこもってたから引き離されたんでしょ。完全なるバカップルじゃない』
からからと笑いながら、けれど、この上なく真剣な表情で彼はつづけた。
まわりの反応をものともせずに、飄々と持論を展開する彼を羨ましいと思った。自分に足りないものを彼のなかに見つけた気がしたからだ。
『でも、仕事どころか普通の生活すら手につかなくなるって、そうはないじゃない? そこまで誰かを好きになれるって、ちょっと羨ましいよね』
♢
「ねぇ、それがなんで『天の川は渡れない』になるのよ?」
話の途中でそう口をはさんだ彼女が、理解できないというように首を振っている。
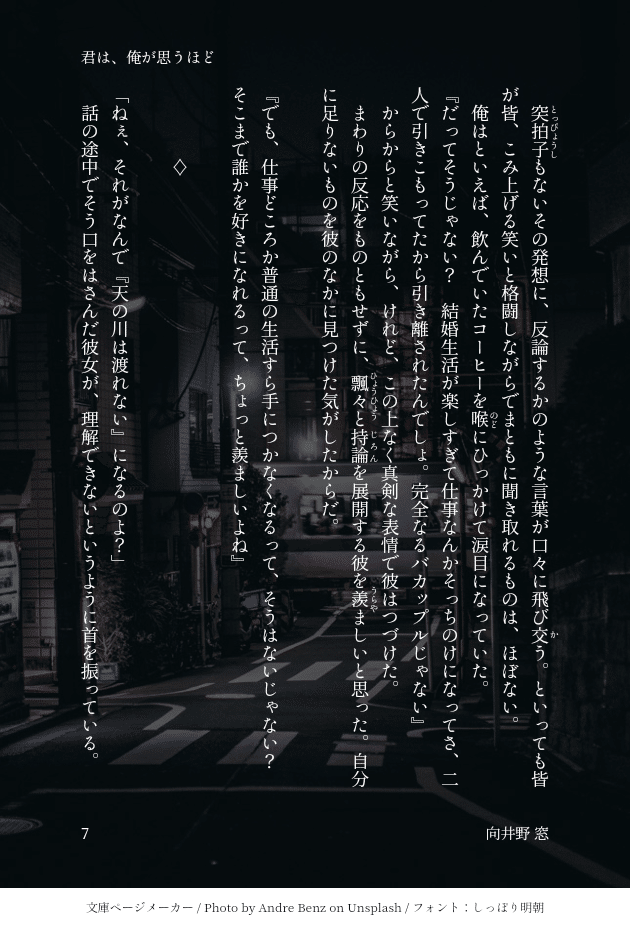
「だから、そこから天の川の話になったんだよ」
「いや、だから“渡れない”ってなんなのよ?」
「渡れないだろ。遥か遠くにある星の集まりなんだから」
ガクッとうなだれた彼女から、くぐもったうなり声が聞こえてくる。
こうもよく表情をくるくると変えられるものだ、と妙に感心してしまう。
感情をストレートに表す彼女は身ぶり手ぶりも大きい。そのよく変わる表情や仕草を見たくて、つい、からかっては彼女を怒らせる。
出会ってから、ずっとそうだった。
そしてそれは、これからも変わることはない、と痛いほどわかっていた。
「だから『なんでもない』って言っただろ」
「じゃあ、どうしてそんな目をしてるのよ?」
そう言って、ゆっくりと顔をあげた彼女の瞳の奥で、強い光が揺らめいている。その揺らめきになぜか胸がざわつく。
「言っておくけど、私、あなたが思ってるほどバカでも鈍感でもないから」
彼女の射すくめるような目に圧倒されて言葉に詰まる。ようやく搾り出した声はひどくかすれて、自分の耳ですら聞き取れないほどだった。

「……君をバカだなんて、思ったことはないよ」
「バカだと思ってなければ『なんでもない』なんて言わないでしょ。そんな目をして……なんでもないわけないじゃない」
いったい俺がどんな目をしてるというのか。
わけがわからず、ただぼんやりと彼女の瞳を見つめるしかなかった。
『僕なら渡らないな。いや、とっくに天の川のほとりから逃げ出してるね。だって、人の気持ちほど当てにならないものってないじゃない?』
離れ離れでずっと待っていられるほど人は強くはない、と言った同僚の声がまだ耳に残る。
俺は天の川は渡れない。渡れないどころか、ほとりへの一歩さえ踏み出せずにいる。
独りよがりに想いをぶつけてしまえば、彼女を傷つけるのではないか。そんな不安に囚われて、前に進むことなんて出来なかった。
なによりも、自分が彼女にふさわしいなんて、とても思えなかった。
「あなたって、ほんとに……でも、そういうとこ嫌いじゃない……ってか、むしろ好き……かな」

はにかむように投げかけられた彼女の言葉が、頭のなかをすり抜けていく。処理能力の限界を超えた俺の頭は、考えることをやめてしまったようだった。
それでも、なんとか彼女の言葉を呑み込むと、ひどく調子のはずれた声が出た。
「あ!?」
「ちょっと、なにその返事! ちゃんと聞いてた? 私、いま一世一代の告白をしたんだけど」
その口調とは裏腹に、彼女の瞳は真剣そのものだ。
「つまり……それは……君が……」
喉の奥がキュっと音をたてて、そのあとの言葉は声にならない。
「私、あなたのこと……好きよ」
はっきりと、けれど静かに彼女が言った。
想像もしていなかった彼女の告白に呼吸が乱れる。軽くめまいがして、もともと緩めていたネクタイをさらに緩めたが、目の前はゆらゆらと揺れたままだった。

「ねぇ、聞いてる? ……って、大丈夫? 顔が真っ青よ」
「ああ、大丈夫。少し酔いが回っただけだ」
「ごめん」
「どうして君が謝るんだ?」
「だって……驚かせた……し……」
肩に掛けたバッグの紐をいじりながらうつむく彼女の首筋に、うっすらと赤みがさしているように見えるのは、きっと気のせいではない。
熱いなにかが、みぞおちの辺りからせり上がってきて、目の前がさらに強く揺れた。
友人というには近すぎて、恋人というには遠すぎる。
そんな微妙な距離が俺には心地よかった。その距離にずっと甘えて、彼女の気持ちを確かめようともしなかった。
拒絶されて、友人という関係すらも失うことがなによりも怖かった。
――俺はなんて身勝手で、愚かだったんだろう。
「な、なに笑ってるのよ!? 人が真剣に……」

「バカだなって思って」
「バ、バカってなによ……」
「そうじゃない。俺だよ、バカなのは」
いまにも泣きだしそうに潤んだ彼女の瞳が、とんでもなく俺を魅了する。
痺れるような感覚が全身に広がって、俺のなかでなにかが弾けた。
気がつくと、俺の手が華奢な彼女の身体を抱き寄せていた。
「もっと早く、こうしてればよかったんだよな」
さらに赤みを増した彼女の首筋にそっと口づけると、甘い香りが鼻孔をくすぐる。
「ま、待って……人が……ねぇ、ここ道のど真ん中!」
「その、道のど真ん中で告白したのは君だろ」
ジタバタとあらがう彼女をさらに強く抱きしめる。ひとたび想いを解き放ってしまえば抑え込むことなんて、俺にはもう出来なかった。
「は、離して……よ」
「嫌だ。離さない」

「い、嫌って!? ちょっと……ほんとに……」
しばらくして彼女の腕がそっと背中に回わされる。
上背がある割に線の細い彼女の身体は、このまま消えてしまうのではないかと不安を煽る。そんな不安を振り払おうと、赤みを帯びたままの彼女の首筋にさっきよりも強く唇を押しあてた。
「天の川って、星屑を集めてつくった光の橋なんですって」
抱きとめられたままの彼女が唐突に言った。
「なんだよ、いきなり」
背中に回していた腕をほどいて、彼女の顔を見る。
「離れ離れになった二つの星がね、どうしても逢いたくて、星屑をすくってお互いの間に橋を掛けたんですって。それも千年もかけて」
「それが天の川になった」
うなずきながら俺を見上げる彼女が、いたずらっ子のような笑みを浮かべている。
「柄にもない、って言いたいんでしょ」

「よく、わかったな」
ニヤリと笑って言った俺の肩めがけて、拳をつくった彼女の腕が伸びてくる。それを直前で受けとめると、握られた拳をほどいてやさしく包んだ。その手は少しひんやりとしていた。
「千年か……気が遠くなるな」
「それだけ想いが強かったのよ。なんとなく……わかる気がする」
伏し目がちに話す彼女の睫毛の長さに目を奪われて、みぞおちから熱いものがふたたびせり上がってくる。その衝動に押し流されそうな自分を、冗談めいた口調でごまかした。
「まさか、千年も待つつもりだったのか!?」
「しょうがないじゃない。誰かさんが、ずーっとグズグズしてたんだから」
彼女の笑顔がたまらなく愛しい。
「健気でしょ? あなたが思うよりずっと繊細なのよ」
「ああ。俺が思うほど、君はせっかちでも、がさつでもなかったんだな」
「ねぇ、こんなにいい女つかまえて、がさつはないんじゃない!?」
「いい女って、それ自分で言うか!?」
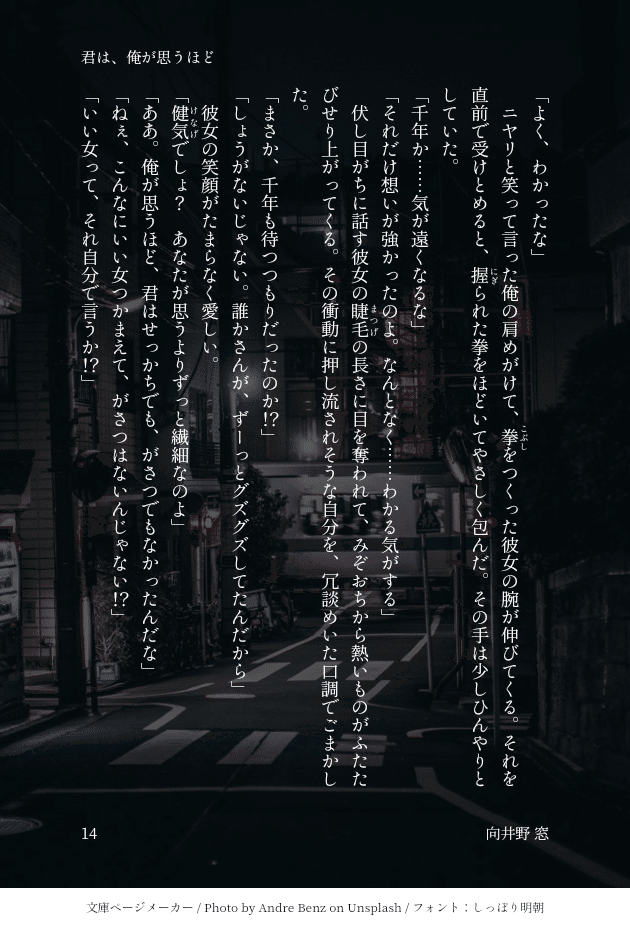
俺たちの笑う声がうす暗い路地に響いた。
いままでとなにひとつ変わらない会話に、自分の臆病さを思い知らされる。
俺が思うほど、彼女は弱くも、臆病でもなかった。むしろ彼女は俺なんかよりよっぽど強くて、その強さに俺が甘えていたんだと気づく。
「俺はほんとに、意気地がなかったんだな」
「え!? いまさら気づいたの?」
「……悪かったな。いまさらで」
心のなかでつぶやいたはずの言葉につっ込みを入れられて、自然と眉間に皺が寄る。彼女の指摘は的を射ているから、なおさらだ。彼女はそんな俺をからかうように、けらけらと笑っている。
「もう、そんなに拗ねないの」と言うと、すかさず俺の両頬をつまんで引っ張る。
「おい、俺は子供じゃないぞ!?」
「子供のほうが、あなたよりよっぽど優柔不断じゃないわよ」
もっともすぎる指摘に言い返す言葉がなくて、相変わらず頬をつまんで遊ぶ彼女のなすがままになった。

「意気地のない、優柔不断な男を好きだなんて、君はいったいどんな趣味してるんだよ」
痛みに耐えられなくなって、まだ頬をいじる彼女の手首をつかんで言った。
「それ、自分で言う?」
「俺が君なら、ごめんだよ。こんなやつ」
子供扱いされてふてくされる自分に居心地の悪さを感じて、彼女の肩越しにぼんやり光る街灯に目を向けた。
「あのね、私はそれでいいの」
彼女が俺の顔を両手で押さえて、むりやりに視線を合わせる。
「意気地がなくて、優柔不断で、人の気持ちとかいろいろ考えすぎて身動きとれなくなっちゃう、そんな“あなた”がいいの」
言った途端に、彼女が自分の顔を両手で覆って下を向く。
「あーあ、言っちゃった」
「なにが『あーあ、言っちゃった』だよ。さっき、盛大に好きって言ってただろ」
“俺がいい”だなんてストレートに告げられて、あまりの気恥ずかしさでまた言葉が荒くなる。
「そ、そうなんだけど……なんか悔しいじゃない……私ばっかりで」

彼女の言うとおり、俺は肝心なことをなにも口にしていない。
――ほんとに、俺はとことんバカだな。
彼女が気持ちよさそうに夜風に当たっている。昼間こそじんわりと汗をかくようになってきたが、夜風はまだまだひんやりとして心地がいい。
「天の川、今年は見られるかなぁ」
街灯の光でよくは見えない星空を見上げて彼女が言う。
その横顔をずっと見ていたい、いままでよりさらに強く思った。
「君が好きだ」
彼女の横顔をこの先もずっと見ていられるように、と心の底から願った。

(了)
Twitterの診断メーカー『あなたに書いてほしい物語』
https://shindanmaker.com/801664 #書き出しと終わり より。
「天の川は渡れない」から始まって「あーあ、言っちゃった」で終わるというお題。
結局、「あーあ、言っちゃった」では終われなかったけれど
✽タイトル画には #SSカードメーカー https://sscard.monokakitools.net/twimeishi.html
本文画像には #文庫ページメーカー (背景つき) https://sscard.monokakitools.net/bunkobg.html
を使用しています。
お気に召しましたら、サポートしていただけると嬉しいです。 いただいたサポートで大好きなミルクティーを飲みたいと思います。
