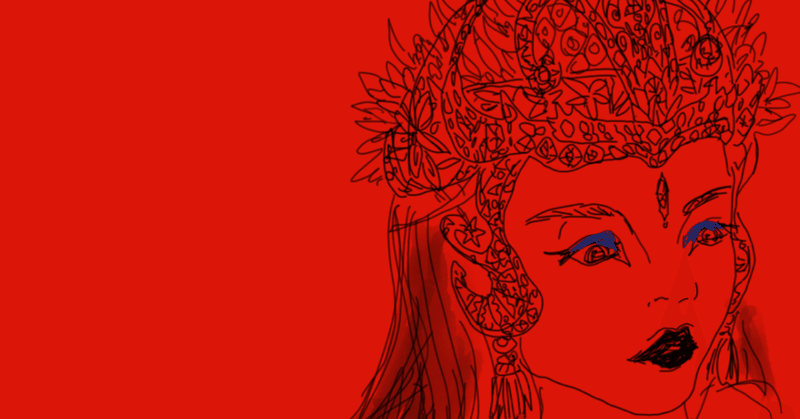
クアラルンプール (短編小説)
「ヴギ」という洋品店が昔あった辺りだろうか。
いつ来ても日暮れているような川のように緩やかに蛇行する商店街の端に、お誂え向きの朽ちた外観の喫茶店ができていた。歴史観光地にある色を抑えたコンビニみたいな揉み手ぶりが鼻についたが、そのついた鼻腔をくすぐる芳醇な珈琲の香りと不思議な店名に惹かれ立ち寄った。
流木をあしらった扉の取手を押し開けるとクラン川の流れは急となり押し寄せ、私は掴んだ流木諸共濁流に飲み込まれてゆく。
夕闇の川辺には褐色の屈強な背が座している。背中の男は原始的な青銅琴、或いは竹琴を激しく打ち鳴らしてガムラン音楽を先導し、訪問者である私を扇動する。
お前は何処から来たのだ、その流木は何処へと流れ着くのだ。夜は暗い。精神が闇へと向かう時、マンゴスチンがアリに集られるのをお前はそこで見ているのか。クアラルンプール。じきスコールが来る。お前今、寝てたのか。ここでは何処まで行っても、流れ着く先は、アリと、スコールだ。
真っ赤な樹脂製の床にこびりついたガムを刮ぎ落としていた店主がこちらを振り返る。
「ああ、いらっしゃい」
立ち上がった店主は確かに色黒のぶ厚い体躯をしてはいるが、Tシャツから覗く弛んだ二の腕やハーフパンツから伸びる太ももの日焼けあとからはクアラルンプールというより近所の市民プールの塩素臭がする。
鄙びた外観を隠れ蓑にした店内は主の嗜好に染められている。ヴィヴィットなピンクの壁紙と無造作に置かれたソテツ。シーリングファンが2時と10時で軋轢音を吐き、透明がかったシアンブルーやバイオレットパープルの角瓶には球状のPickles、こっちで言うところのRakkyoが時間と共に底に沈んでいる。
濁流に飲み込まれたままの私を置いて店主はカウンター内の定位置へと戻ると、人差し指と中指に挟んだ煙草をこちらに見せて少し会釈してから火をつけた。
クアラルンプールはklang Riverとgomback River二つの泥川の交わる地点という意味合いを持つ。かつてのイギリス領であり多くの民族が交わる複雑な香りを今もその街並みや食へと残す。
暮れなずむ商店街を流れ着いた先の、歪んだ異国情緒のある店内でNaci LemakやLaksaといったマレー料理を提供する複雑な喫茶「クアラルンプール」を店主はやろうとしている。
私は珈琲をアイスで注文した。
安っぽいピンクの壁に貼られた「ミーゴレン風焼きそば」の文字が、店の裏路地を抜けるカレーのような匂いの風に剥がれかかっていた。
珈琲はコメダ珈琲みたいだった。
「The Nipplegong」 Macha
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
