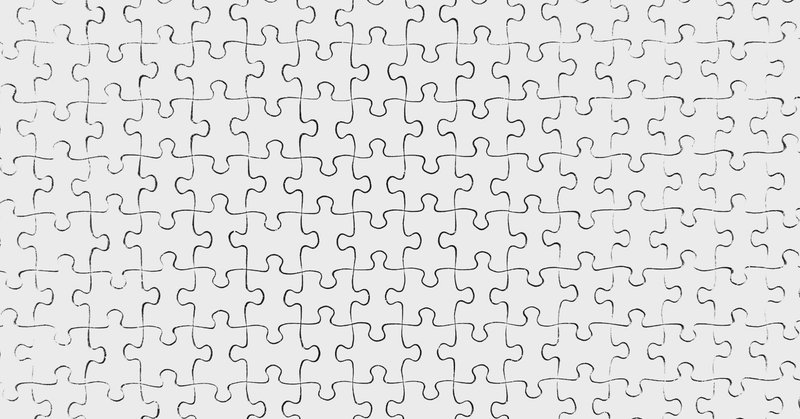
西瓜糖の日々 リチャード・ブローティガン
あのとりとめのない甘みを、煮詰めて煮詰めて煮詰めるとできあがる西瓜糖は、とろんと甘ったるくて、遠くに青い匂いがある。純粋だからこそ、内奥に隠した野性味や凶暴性が垣間見える、混じり気のない西瓜の味。
言葉は透明で、実態がつかめず、淡い匂いと冴え冴えとした空気に包まれたという感触だけが通り過ぎた。
ブローティガンという作家に何かしらの先入観を持っていたのだと思う。最初の数ページでその清澄さを意外に思った。だけど先入観は、すぐに物語へと埋没していった。
社会的で個人的な寓話のように物語は進む。詩のような、小説のような、日記のような。描かれるすべてに意味があるような気がしてくる。あるのかもしれない。でもなくてもいい。
考えは行ったり来たり揺らぐ。
作家が持つイメージや、その生きた時代背景などには関係なく、ここにできあがった世界は、読むその時のその人に沿って姿を変えるだろう。
西瓜糖も、人語を話す人食い虎も、もう渡られなくなった橋も、その時々に人それぞれに意味を持つ何かなのだ。
後味は甘く、すぐに消える。だけどきっと後々も、あの時のあの味は、と懐かしく思い浮かべるだろう。そしてその味を思い出そうと、もう一度この本を開くだろう。
でもその時感じる味は、いま感じているのとは少し違う。読書とはそういうものなのだと何度も気付く。
なぜ今までこの本に出会わなかったのか。我ながら不思議でもったいなかったなと思ったけれど、いま初めて読んだからこそ感じる風味があるのだろうと納得した。
時代遅れなんて言わないよね。時には早いも遅いもない。ただそこにあるのだから、ただそこにいればいい。そして、それを眺めるように、ただ読めばいい。
良い時も悪い時も、気が付けばそこにいる友人が一人いる。
心がいちばんやわい時代に四六時中一緒にいて、互いが互いに食い込んでしまったので、それぞれにそれぞれの形が付いていて、今は離れて、会うことは少なくなっても、その形は時とともに丸みを帯びながら、今も体のどこかに残っている。
そんな感じだなと互いに思っている。
読みながらその友人のことを考えていた。これ読んでって、差し出したい。久しぶりにそう思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
